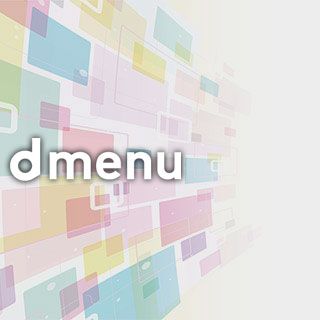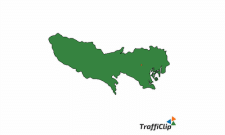ポストコロナ時代に入ったが、世界情勢の不安定化や続く円安など業界を取り巻く環境は刻一刻と変化している。そのような中で、IT企業はどのようなかじ取りをしていくのだろうか。各社の責任者に話を聞いた。前編の記事はこちら。
日本IBMでは、独自の生成AIである「watsonx」(ワトソンエックス)を市場投入するとともに、2024年2月には、大規模言語モデル「Granite」(グラナイト)の日本語版モデルの提供も開始した。エンタープライズに最適化した生成AIとして、今後は業種に特化した日本独自の展開も進めることを、日本IBMの山口明夫社長は明らかにする。
一方、日本IBMは2024年1月30日に東京都港区の「虎ノ門ヒルズステーションタワー」に本社を移転。お客さまやパートナー、社員が輝いて議論できる拠点と位置づける一方、歴代社長としては初めて社長室を廃止した。
インタビューの後編では、日本IBMの山口社長に、生成AIへの取り組みや虎ノ門新本社への移転の狙い、そして、日本IBMの価値共創領域におけるDXの推進やサステナビリティへの対応、人材育成への取り組みなどについても聞いた。
●ITとデータをいかに活用するか 日米の違い
―― 価値共創領域の2つめである「ハイブリッドクラウドやAIなどのテクノロジーを活用したDX」については、どんな成果が上がっていますか。
山口 これは多岐に渡っています。金融/医療/小売/製造など、いろいろな業種において、日本のお客さまのDXの推進を支援していますし、ユニークなところでは、中部国際空港でAI搭載ロボットを活用した空港警備業務の実証実験を行ったり、順天堂大学医学部附属順天堂医院小児医療センターでは、メタバース上で入院患者と面会ができるメタバース面会アプリを共同で開発したり、ボリュメトリックビデオ技術を活用して、名刺上に3Dで自身の小さな分身を表現できるARソリューションを開発したりといった事例もあります。
よくメインフレームとクラウドを比較する議論がありますが、これは対比そのものが間違っています。ITシステムは、オンプレミスとクラウドという利用形態、メインフレームとサーバなどの中小型機というハードウェアによる組み合わせで捉えるべきです。
メインフレームはオンプレミスで利用される場合もあれば、クラウドで利用される場合もあります。また、サーバもオンプレミスで利用される場合があれば、クラウドで利用される場合もあります。この4象限に整理して、何をやりたいか、その際に経済合理性を重視するのか、安定稼働を重視するのか、データのセキュリティを重視するのかといったことを明確にすれば、どこで動かせばいいのかが分かってきます。実現したいことを明確にし、適材適所でシステムを動かすことを理解している企業がDXを成功させています。
―― 日本のDXの取り組みは、米国などに比べて大きく遅れているとの指摘がされてきました。現状はどう判断していますか。
山口 一概に、日本が遅れているということではないと思います。日本の企業においても、先進的な事例がありますし、進んでいる企業はかなり進んでいるというのが実態です。新たなビジネスを創出したいというような明確な姿勢を持ってDXに取り組んでいる企業は、結果を生み出していますね。
しかし何のためにITを使うのか、あるいはDXをやるのかという部分に、フワっとした考え方がある企業の場合、「DXはIT部門の仕事である」ということになりやすく、生産性が少し上昇したというレベルで終わっているケースが目立ちます。
DXはIT部門だけがやる取り組みではなく、経営を巻き込んで行う取り組みです。会社をどう成長させるのかを考えるのは経営にとって当たり前の仕事です。経営の変革を担うツールがたまたまITであるのに過ぎないわけですが、それをIT部門だけがやるものだと勘違いして、IT部門に丸投げしていては、DXは成果につながりません。
また、ITを使えばコストが削減できるとか、生産性が高まると考えて利用する企業と、ITとデータを活用してトップラインを伸ばすビジネスを創出することを目指す企業とでは、ITの活用方法が全く異なります。日本企業は前者が多く、米国企業には後者が多いという実態は感じます。
これはインターネットが登場したときと一緒です。当時の日本企業は、インターネットを使って検索が簡単にできて辞書が不要になるとか、Wikipediaを使えば何でも分かって便利になるといった部分に注目が集まっていましたが、米国企業の場合は、すごいツールが出てきたのだから、これを使って何か新しいビジネスができないかと考える人たちが多くいました。
例え話をすれば、クルマが登場したときに早く移動ができて便利になり、生産性が高まり、今のビジネスを加速できると考えるのが日本の企業であり、クルマの技術を元にトラックやタクシー、バスという新しい形態のクルマを作って、運送業や観光業といった新たなビジネスを創出しようと考えるのが米国企業の姿勢です。日本の企業は、今の延長線上でビジネスの拡大を考えることは得意ですが、これまでにない新たなビジネスを創出するという発想が少ないといえます。
昨今注目を集めている生成AIでも、同じことが起ころうとしています。日本では、生成AIを使って仕事の生産性が上がったとか、稟議書やメールを代わりに書いてもらえるようになったというような話題やニュースが中心です。これは成果としては大切なものなのですが、その一方で新たなビジネスの創出に使ったという事例やニュースが少ないのも事実です。
IBMが開発した生成AIのwatsonxは、企業が使うことを前提に開発したものですが、生産性をあげたり、便利にしたりといったことだけを目的に提供しているのではなく、プラットフォーム化したことでも分かるように、これを使うことで新たなビジネスの創出を支援するという狙いがあります。日本の企業は、たくさんのデータを持ち、そのデータ品質が高いという特徴があります。生成AIを使って、新たなビジネスを創出できる環境が最も整っている国だといえます。
●生成AI「watsonx」と日本語モデル「Granite」で日本企業のDX推進
―― こういった日本企業の意識改革も、日本IBMの役割ですか。
山口 私は、このことばかりを話していますよ(笑)。私自身は、テクノロジーは大好きですが、watsonxのテクノロジーの話はあまりしないので、「山口さん、watsonxはどうなっているの?」なんて聞かれます。watsonxはDXのためのツールの1つでしかありません。私の周囲では経営を変えたり、新たなビジネスを創出するために、新たなテクノロジーを使っていこうというアグレッシブな経営者が増えていることが心強いですね。
その一方で、経営会議では「他社がDXをやっているのに、うちはどうなっているんだ」という議論から始まる事例があるという話も聞きます。DXを経営の課題ではなく、ITの課題だと思っているから、こうした話になるわけです。また、ガバナンスを効かせるべく、新たなテクノロジーの採用に慎重な企業が見受けられますが、「攻めのガバナンス」という考え方も重要だと思っています。
―― IBM独自の生成AIであるwatsonxの強みはどこにありますか。
山口 watsonxは、IBM独自の基盤モデルを活用した生成AI機能を提供する「watsonx.ai」と、データとAIを管理するデータストアの「watsonx.data」、説明可能なAIワークフローを構築し、AIガバナンスを確保する「watsonx.governance」の3つのコンポーネントで構成されています。プラットフォームとして提供することで、最適な大規模言語モデルを利用でき、AI利用時のリスク管理、透明性確保、コンプライアンスにも配慮し、エンタープライズが利用できる生成AIとして提供することが可能になっています。
また、watsonx.dataに蓄積されたさまざまなデータを活用して学習し、watsonx.aiで動作させることができる大規模言語モデルのGraniteを発表しており、日本語性能を向上した「granite-8b-japanese」と呼ばれる日本語版モデルの提供も開始しています。
Graniteは80億パラメータと軽量で、インターネット/学術/コード/法務/財務の5つの領域から得たビジネスに関連するデータセットで学習を行っているのに加えて、IBMがビジネス用途向けにキュレーションしている点が特徴です。
Granite日本語版モデルでは、5000億トークンの日本語/1兆トークンの英語/1000億トークンのコードの合計1兆6000億トークンによる高品質データセットを学習するとともに、「日本語トークナイザー」と呼ぶ、日本語に特化した言語処理を導入したことで、長い日本語の文章を効率的に処理して、より高速な推論を実現しています。
また、好ましくないコンテンツを除去するための綿密な検査や、社内外のモデルとのベンチマーク評価も行っており、watsonx.dataとwatsonx.governanceとの連携によってリスクを軽減し、責任ある形で、モデル出力ができるように設計しています。さらに、テクニカルレポートを通じて技術仕様に関する詳細を公開するなど、Graniteモデルの学習に使用されたデータソースを公開し、透明性を高めることで、AIの適用をより安心して進められるようにしています。エンタープライズグレードの日本語能力を持つ大規模言語モデルだといえます。
今後Graniteをベースにして、日本の市場に合わせた業種特化型の生成AIを提供していく予定です。
これまでのAIは特別な企業や特別な人が作って、特別な人たちが利用するものでしたが、生成AIによって、みんなが作って、みんなで使える世界に入っていくことになります。そういった世界において、安心してAIを使ってもらうために、IBMが発起人となって国際的なコミュニティである「AI Alliance」を設立しました。日本の企業や大学にも参加をしていただいており、今後、さらに参加企業が増加することになるでしょう。AIイノベーションのメリットを誰もが安心して享受できるよう、責任あるAIの実現を推進していきます。
さらに、IBMでは、システム管理やプロジェクト管理、システム運用、障害対応といったところにも生成AIを活用して、やり方を大きく変えていこうと考えています。スキル不足や労働人口不足にも対応できます。
●IT/AI人材育成に注力 グローバル人材を育て新たなイノベーションを
―― その一方で、生成AIは多くの仕事に取って代わるという議論もあります。
山口 それもクルマの場合と、考え方は同じです。クルマはモノを運んだり移動したりという点では、人間の能力をはるかに超えています。しかし、あくまでもツールです。生成AIは、情報の整理や多くの情報を元に思考する能力はありますが、使うのは人であり、人の仕事や判断などをサポートするものです。
大切なのは、そこに倫理が必要だという点です。クルマも交通ルールが守られなければ、事故が多発することになります。生成AIも倫理を守らなければ、大変なことが起きます。IBMが、責任あるAIに対して力を注いでいる理由もそこにあります。既に生成AIは、さまざまな形で使われ始めています。また、多くの大規模言語モデルが作られ始めています。この流れを止めることはできません。
―― 価値共創領域で掲げている「CO2やプラスチック削減などのサステナビリティー・ソリューションの共創」に関する取り組みにはどのようなものがありますか。
山口 カーボンニュートラルや循環型社会への関心が高まる中で、サステナビリティー・ソリューションの共創が増えており、ここでも成果が生まれています。既に三井化学や旭化成、三菱重工と、それぞれに取り組みを進めていますし、2024年1月には、北九州市およびIHIとともに、熱マネジメントによって北九州地域のGX(グリーントランスフォーメーション)を推進する連携協定を締結しました。
2024年にも、いろいろな事例を紹介できると思います。サステナビリティー・ソリューションは、1社でやっても意味がありません。例えば循環型社会の構築においては、製品を生み出して、消費者に届ける「動脈産業」と、不要となった製品を回収して再活用するために処理を行う「静脈産業」との連携が不可欠です。
また、脱炭素においてはサプライチェーン全体での連携が不可避です。特にサステナビリティは、多くの人の価値観を変えなくてはならない領域でもあります。リサイクルされたものは使いたくないという人はまだまだ多いですし、リサイクル素材はコストがかかるという課題も解決にしなくてはなりません。仕組みを大きく変えていくためには、長期的な活動が必要になりますから、その姿勢で取り組んでいきます。
―― 価値共創領域の最後に挙げている「IT/AI人材の育成と活躍の場」についてはどんなことに取り組んでいますか。
山口 全ての価値共創領域において人材が重要です。しかし、ITやAIの人材不足は深刻な課題となっています。デジタル変革を進め、よりよいサービスを提供していくためには、デジタル技術を使いこなすIT人材を育成しなくてはなりません。
当社では、グローバルで展開している官民連携の新たな教育モデルである「P-TECH」や、大学などと一緒になって量子ネイティブな人材育成にも取り組んでいきます。さらに、日本IBM社員に対する教育については、最初はITスキルに関するものから始まりましたが、今では量子やAI、クラウドに加え、リーダーシップや経済安全保障など、幅広いテーマで教育を実施しています。
国際的センスを持った人材をさらに増やしていきたいと思っており、日本IBMの社員を対象にした海外研修も増やそうと思っています。生成AIの浸透などにより、言語の壁が低くなってきます。これは、日本から外に出ていきやすくなるだけでなく、海外から日本に入ってきやすくなることにもつながります。世界の中での経験が必要になり、国際的センスを持ってイノベーションを起こすことが、ますます重要になると思っています。新たなスキルを備え、自分の軸をしっかりと作り上げる必要があり、教育を通じて、そのきっかけの場を作りたいですね。
●箱崎に続き虎ノ門の新本社でも社長室は廃止
―― 2024年1月30日に、東京・虎ノ門の虎ノ門ヒルズステーションタワーに本社を移転しました。この狙いは何ですか。
山口 お客さまやパートナー、社員が輝いて議論できる場所を用意しました。日本中から人が集まりやすいところに拠点を配置し、物理的に集まったり、バーチャルで結んで仕事ができたりする拠点になります。ここから議論やイノベーションが起き、アイデアが生まれるような拠点にしていきたいと考えています。
一方、これまでの本社である箱崎事業所は25フロアのうち15フロアを返却し、今後は上層階の10フロアを利用することになります。また、丸の内の永楽ビルディングのオフィスも継続的に利用できるようにして、虎ノ門新本社を含めた3カ所を都内主要拠点として、社員が働く場所を柔軟に選択できるようにしました。
この他にも、新宿/渋谷/品川などのサテライトオフィスや、時間貸しオフィスによるリモートワークスペース、自宅からの勤務も可能ですから、最も働きやすく結果が出しやすい場所を選び、時間の使い方も考えながら働くことができます。仕事によっては3週間連続で出社した方がいい場合もありますし、2週間自宅にこもった方がパフォーマンスが上がる場合もあります。仕事の内容や仕事のフェーズによって働く場所を自由に選択し、最大限のパフォーマンスを上げてもらうための選択肢を増やしたい。そのための1つの場所が、虎ノ門本社になります。
―― 社長室も、虎ノ門新本社に置くことになりますか。
山口 社長室は、2024年1月31日で廃止しました。虎ノ門本社に社長室を作るという提案は受けたのですが、会社は経営者のものではなく社員のものですから、社長室は作らずに、同時に役員室もなくしました。縦横の壁を排除し、コミュニケーションを活発化したいと考えています。
―― 2024年は日本IBMにとって、どんな1年になりますか。
山口 日本IBMの組織体制を変えて事業ポートフォリオが明確になり、テクノロジーを届けることができる体制も整い、取り組むべき価値共創領域も明確になってきました。足腰がしっかりしてきたともいえます。2024年は、5つの価値共創領域への取り組みをどこまで深められるかがテーマだといえます。
信頼される企業であることをベースに、誠実にビジネスに取り組んでいく姿勢も変わりません。もはや人工(にんく)で行うビジネスモデルだけでは厳しくなるのは明らかです。社会課題が山積している現在、いかにテクノロジーを活用して、社会課題を一緒に解決できるかが鍵になります。そうしたアプローチをすることができる会社になりたいと思っています。