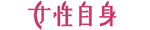「4月から保育園ですか?」
「そのつもりだったけど、2歳で入れようと思ったら、今年は落ちちゃって……。どうしよう」
「うちは0歳枠で何とか入れたんだけど、今度はおなかに2人目がいることがわかって」
「まあ、おめでとうございます!産院はどこですか?」
保育園の話題から地域の産婦人科の評判、はては幼い子供連れ歓迎のランチスポット情報まで、会話は途切れることなく続く。2月最後の水曜日の午前10時過ぎ。神奈川県寒川町の住宅街にある三角屋根の助産院「ママナハウス」に、生後3カ月から1歳10カ月までの赤ちゃんを連れた6人の母親たちが集まっていた。
産前産後のケアに特化したユニークな助産院として知られるママナハウスだが、この日は、離乳食期の赤ちゃんと母親を支援する「赤ちゃん食堂 ままな」の開催日。子ども食堂は全国各地で実施されているが、離乳食まで提供してくれる「赤ちゃん食堂」は希少。その日本第1号こそ、この施設なのだ。月2回の開催で、2歳未満の赤ちゃんには無料で離乳食やミルクが、母親には400円で地元湘南の野菜やサポート企業から届く余剰食材などを使った料理が提供される。
「さあ、みなさん。お話の途中ですが、まずは、赤ちゃんたちのごはんですよ〜」
11時を回ったころ、キッチンから元気な声を発したのが、赤ちゃん食堂の創設者で、ママナハウス代表も務める助産師の菊地愛美さん(37)。自身も4人の子を持つお母さんだ。
「今日も、お野菜は近所の農家さんからです。ああ、ようやく春野菜の季節になったんだなぁと思いながら、真心込めて作りました」
テーブルに並んだ本日の献立は、ハンバーグ、ポテトサラダ、にんじんラペにデザートのみかんヨーグルトまで、栄養バランスだけでなく彩りもバッチリだ。食べやすいようにやわらかくしたふわふわのハンバーグをほおばる赤ちゃんたちから、覚えたての「おいちい」が響きわたると、食堂は笑い声であふれるのだった。
赤ちゃんの食事が終わると、次はお母さんたちの番。大人用のハンバーグに舌鼓を打つ。その間、子供の世話は菊地さんとスタッフらが担う。
食事の間も、ママたちの情報の収集と交換は続いた。菊地さんがその光景を見ながら、
「食の大切さを改めて実感しています。お疲れぎみのママたちが一緒に食卓を囲み『おいしいね』と言い合うなかで打ち解け、いつしか笑顔になっているんです」
厚生労働省の’21年度の統計によると、約10人に1人の母親に“産後うつ”の疑いがあった。それ以前に少子化の問題も深刻だ。くしくも、赤ちゃん食堂が開催されたこの日の朝、新聞各紙の1面に〈出生数最低75万人 8年連続低下〉という見出しが躍った。菊地さんのもとにも、続々と相談が寄せられている。
「ワンオペママたちにとって、何より怖いのは、“寝られない、食べられない、喋れない”という孤独なんです。安心できる出産・子育て環境があれば、少子化問題の解決にもつながるはず。現にうちを利用する人のなかには、2人目を産むお母さんも多いです」
出生数の低下について、菊地さんは「そりゃそうだよな、というのが正直な感想です」と話す。
「みんなの心の奥底にあるのは、将来への不安だと思います。子供ひとり育てるのにもお金がかかるし、老後の年金だって安定して受け取れるのかわからない。これでは、2人目は産めません。産後ケアのデイサービスを使う場合、費用は約1万5千円で自己負担が2千〜5千円程度。誰もが気軽に、とは簡単に言えない金額です。今後は、育休、産後ケア、赤ちゃん食堂などをうまく使い分けていくべきで、そのための具体的な金銭的・人的支援を国や自治体には望みます」
菊地さんはよりたくさんの親子を受け入れるために、「もっと広い場所も欲しい」と話す。 さらに、「手が足りない」というシングルマザーや貧困世帯へ寄付を募ってオムツやミルクを届ける物資支援も充実させたいと考えている。そうした活動の幅を広げるためにも、今後NPO法人化を目指していくという。
ママたちに心安らぐ時間を過ごしてもらうため、菊地さんの奮闘は続く。
【後編】孤独の苦しみに過去の自分重ね…「赤ちゃん食堂」創設者がママたちに手を差し伸べる理由へ続く
離乳食を無料で提供…日本初「赤ちゃん食堂」創設者語る“ワンオペママにとって何より怖いもの”

関連記事
あわせて読む
-

雅子さまが園遊会でバッグから取り出した5、6枚の「猫の写真」 招待客への思いやりを込めた事前準備
AERA dot.4/27(土)9:30
-

横断歩道の91歳女性、教習所の送迎車にはねられ死亡
読売新聞4/27(土)16:02
-

大阪・関西万博ついに参加国を怒らせた! 地盤は脆弱、水はけ悪く、メタンガス噴出も
AERA dot.4/27(土)12:00
-

《宮内庁幹部が告白》「雅子さまは人権侵害を受けてきた」適応障害を発症された本当の理由――2023年読まれた記事
文春オンライン4/27(土)17:00
-

【速報】車同士が正面衝突 5人搬送…男児が意識不明の重体か 長野・生坂村
FNNプライムオンライン4/27(土)17:51
-

田崎史郎氏が衆院3補選「立民3勝」の可能性に言及「自民負ければ岸田さんのもとでの解散は…」
日刊スポーツ4/27(土)9:16
-

〈産休クッキー炎上中〉公園にいるママは「おめでたくていい」「配るくらい自由にさせてほしい」いっぽう丸の内OLは「自慢された気分になる」「配慮が足りない」〈100人の声〉
集英社オンライン4/27(土)11:00
-

【特集】“スーパーマーケット戦国時代”を生き残るのは⁉高品質・低価格は当たり前!『ロピア』『バロー』『オーケー』関東・東海から関西に…進出が相次ぐウラ側に迫る
読売テレビニュース4/27(土)9:00
-

自治体の約4割“消滅の恐れ” 前回調査で“全国ワースト”の村は今【news23】
TBS NEWS DIG4/27(土)15:34
-
-

上地恵栄容疑者、山中で発見の遺体とDNA型一致 事件翌年に死亡か
毎日新聞4/27(土)12:57
-

【写真特集】「園遊会デビュー」の愛子さま 右手で「チョキ!」や「ビックリ」の仕草 クルクル変わる表情の可愛らしさ
AERA dot.4/27(土)9:30
-

「青木ヶ原樹海で自殺したい女性」が改心した理由とは?…“一番の理由”は同行したルポライターが「ある言葉」を言わなかったから
文春オンライン4/27(土)17:00
-

「そのサザエ、捕っても大丈夫?」磯遊びや潮干狩りでも“密漁”に…罰則強化も増え続ける「一般人の検挙」
デイリー新潮4/27(土)10:00
-

逮捕された男の知人2人 空き家に“2時間”滞在し暴行か 那須町の焼損遺体
ABEMA TIMES4/27(土)13:16
-

鈴木宗男氏が「1日で辞職」市井紗耶香の対応を疑問視「それにしても政治が軽くなった」と嘆く
日刊スポーツ4/27(土)9:15
-

三浦瑠麗 夫じゃない男性と腕組みデート、娘同伴で夜遊び報道も…離婚発表前から貫いた“奔放生活”
女性自身4/27(土)11:00
-

東京都で最大震度3の地震 東京都・小笠原村
TBS NEWS DIG4/27(土)17:42
-

都内の空き家に男2人と2時間滞在…暴行受けたか 栃木・那須町2遺体事件
FNNプライムオンライン4/27(土)12:26
-
社会 アクセスランキング
-
1

雅子さまが園遊会でバッグから取り出した5、6枚の「猫の写真」 招待客への思いやりを込めた事前準備
AERA dot.4/27(土)9:30
-
2

横断歩道の91歳女性、教習所の送迎車にはねられ死亡
読売新聞4/27(土)16:02
-
3

大阪・関西万博ついに参加国を怒らせた! 地盤は脆弱、水はけ悪く、メタンガス噴出も
AERA dot.4/27(土)12:00
-
4

《宮内庁幹部が告白》「雅子さまは人権侵害を受けてきた」適応障害を発症された本当の理由――2023年読まれた記事
文春オンライン4/27(土)17:00
-
5

【速報】車同士が正面衝突 5人搬送…男児が意識不明の重体か 長野・生坂村
FNNプライムオンライン4/27(土)17:51
-
6

田崎史郎氏が衆院3補選「立民3勝」の可能性に言及「自民負ければ岸田さんのもとでの解散は…」
日刊スポーツ4/27(土)9:16
-
7

〈産休クッキー炎上中〉公園にいるママは「おめでたくていい」「配るくらい自由にさせてほしい」いっぽう丸の内OLは「自慢された気分になる」「配慮が足りない」〈100人の声〉
集英社オンライン4/27(土)11:00
-
8

【特集】“スーパーマーケット戦国時代”を生き残るのは⁉高品質・低価格は当たり前!『ロピア』『バロー』『オーケー』関東・東海から関西に…進出が相次ぐウラ側に迫る
読売テレビニュース4/27(土)9:00
-
9

自治体の約4割“消滅の恐れ” 前回調査で“全国ワースト”の村は今【news23】
TBS NEWS DIG4/27(土)15:34
-
10

上地恵栄容疑者、山中で発見の遺体とDNA型一致 事件翌年に死亡か
毎日新聞4/27(土)12:57
社会 新着ニュース
-

【天気】連休二日目は全国的に晴れ 関東で今年初の真夏日も
日テレNEWS NNN4/27(土)20:48
-

連休初日、輪島・珠洲で174人がボランティア…夜行バスで駆け付けた男性「明るさ取り戻す助けに」
読売新聞4/27(土)20:43
-

近鉄大阪線で人身事故 一部運転見合わせ
レスキューナウニュース4/27(土)20:40
-

氷川きよしさん活動再開へ=新会社設立、「新しい世界披露」
時事通信4/27(土)20:33
-

母親はその後死亡…親子げんかで突き飛ばすなどした19歳息子を逮捕 千葉・船橋市
日テレNEWS NNN4/27(土)20:22
-

那須2遺体 容疑者、事件当日に指示役と接触か 都内の居酒屋で
毎日新聞4/27(土)20:21
-

丸亀城の城泊、5月1日予約開始 1泊2日で126万5千円
朝日新聞4/27(土)20:19
-

益子陶器市 伝統から新進の作品 ずらり並ぶ
ABEMA TIMES4/27(土)20:16
-

知床沖で小型観光船の訓練 初運航を前に救助支援システム試す
朝日新聞4/27(土)20:15
-

【NNNドキュメント】僕たちの婚姻、認めてくれませんか? 22年間寄り添う男性カップル “同性婚” 婚姻の自由は…
日テレNEWS NNN4/27(土)20:15
総合 アクセスランキング
-
1

大谷翔平7号の裏でまさかの珍光景「面白すぎる」 背後から近付く“敵”に日米爆笑
Full-Count4/27(土)14:44
-
2

雅子さまが園遊会でバッグから取り出した5、6枚の「猫の写真」 招待客への思いやりを込めた事前準備
AERA dot.4/27(土)9:30
-
3

「涙腺ぶっ壊れた」大谷翔平の後を打つ3番フリーマンの母との約束にSNSで感動の嵐
日刊スポーツ4/27(土)10:12
-
4

神田正輝、「旅サラダ」で「松田聖子」に触れる…「昔の奥さん、久留米」
スポーツ報知4/27(土)9:31
-
5

「言葉のプロだろうに」中村仁美 『金スマ』でのまさかの“言い間違い”に疑問続出「そんな言葉あるのか?」
女性自身4/27(土)11:00
-
6

「もはや誰?」35歳の元人気アイドル、劇的イメチェン「えーーー!!」「別人かと」「中学生?」
スポーツ報知4/27(土)16:30
-
7

横断歩道の91歳女性、教習所の送迎車にはねられ死亡
読売新聞4/27(土)16:02
-
8

貴乃花独占W激白「私の相撲人生はあそこから始まった」“同期最大のライバル”曙を悼み、再婚生活で溺愛する新存在「ナナ」の正体を明かす
文春オンライン4/27(土)11:00
-
9

「今井絵理子」参院議員が1ヵ月間「国会を欠席」していた… 事務所に訊ねると返ってきた意外な答え
デイリー新潮4/27(土)11:10
-
10

阪神 逆転勝ちで3&4月の勝ち越し決定 首位がっちりキープ 大竹リーグトップタイ3勝目「私事ですが明日が結婚記念日」甲子園がどよめく
デイリースポーツ4/27(土)17:13
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

「EVO Japan 2024」速報レポート!格ゲー配信者の修行僧さんと巡る「格ゲーマーの“文化祭”」初日の様子をお届け
Walkerplus4/27(土)20:37
-

QPRが早くも「2024-25」新ユニフォームを発表!強豪リーズ撃破で“2部残留確定ユニ”となる
Qoly4/27(土)20:00
-

「長距離で逃げ馬を自由にしてはいけない」を体現した歴史的な大逃げ。イングランディーレと横山典弘騎手の2004年・天皇賞春を振り返る
ウマフリ4/27(土)19:30
-

バンテリンD−C速報まとめ!森下が投げて宇草が柵越えして広島が勝つ、次は5月4日のマツダスタジアムDeNA戦
ひろスポ!4/27(土)18:24
-

“薄緑”がまさかの復活!ボリビア代表、コパ・アメリカでの新ユニフォームを発表 史上最高のおしゃれデザインに
Qoly4/27(土)18:00
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
(C)2024 Kobunsha Co. Ltd. All Rights Reserved.