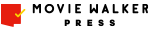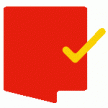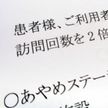映画『渇水』(6月2日公開)の公開直前ティーチインイベントが24日、神楽座にて開催され、主演の生田斗真、共演の門脇麦、監督を務めた高橋正弥、企画プロデュースを担当した白石和彌が登壇し、参加者からのQ&Aに答えた。
原作は1990年に第70回文學界新人賞受賞、第103界芥川賞候補となり注目を浴びた河林満の名篇で、『凶悪』(13)、『死刑にいたる病』(22)の白石監督による初プロデュースする本作では、阪本順治、宮藤官九郎などの監督作品で助監督としてキャリアを重ねてきた高橋が監督を務めている。
冒頭の挨拶で生田は「映画の撮影中はずっと雨。先日のカイブ試写会の日も大雨でした」と振り返り、「この映画のキャンペーンは雨男キャラで行こうと決めていたのに、今日はものすごく晴れてしまいまして…。キャラが崩壊してしまい、これからどう宣伝していいのか分かりません」とユーモラスに挨拶。だからこそ本作を鑑賞した方の力が必要と訴え「お力を貸してください!」と笑顔を見せると、会場は大きな拍手に包まれた。
参加の決め手となったのは脚本のおもしろさだったそう。「日本映画界にとんでもなくおもしろい脚本があるという噂になっていたそうです。その脚本が時を経て自分のところに回ってきました」とニッコリ。台本の中身はもちろん、映画に対する愛情のようなものがふんだんに詰め込まれていたことも参加の決め手になったという。「ただならぬオーラを放っている脚本でした。参加しないときっと公開すると思い、即座に参加を決めました」と出演の経緯を明かした。門脇も出演の決め手は脚本だったと話し、「なんていい本なんだろうと思いました」としみじみ。「これまで何度か一緒に作品をやっている白石監督が『門脇さんで』と言ってくれている。断る理由はなかったです」とハッキリと答えた。
イベントでは高橋監督の人柄が話題に。生田は「雨で撮影がストップしたり、撮影がなかなか思うようにいかない日でさえも高橋監督はずっとうれしそうでした」と指摘。続けて「この映画を撮れているという幸せに満ちあふれていて、一番潤っていらっしゃったのは監督ご自身なのかなと思います。白石監督もおっしゃっていたように人柄に惚れた人が集まって、現場が進んでいたという感覚があります」と大絶賛。
このコメントに高橋監督は「映画を作ることは楽しい作業です。正直、あめでちょっと恨めしいときもあったけれど、映画そのものが中止になったわけじゃないので、次はもっと面白いシーンを撮ろうという気持ちで、ある種励みのようにしていました。そんな気持ちがのったことにより楽しそうに見えたのかもしれません」と説明していた。
白石プロデューサーは作品に高橋監督の人柄、優しさ、根本的に人を信じている感じが映っているとし、「話の内容としては残酷なシーンもあるけれど、人々が必死に生きながらもどこか滑稽で、少しコミカルだったりもします。門脇さんが演じた母親も、残酷だけどなにか理由があるというのが伝わってきます。その一方でこだわって、苦労して撮ったシーンを編集でバッサリ切る割り切りの良さもあるという両面を持っていると思います。僕自身、いろいろと気づきがある映画でした」と笑顔を見せると、生田が「思い出した。何本もタバコを吸って、肺がぶっ壊れそうになりました。(なのにカット)思い切りが良いですよね」と高橋監督の割り切りの良さを表すエピソードも披露した。
■生田が目撃した、女優・門脇麦のオンとオフ
苦労したのは生田演じる水道局員の主人公、岩切俊作の同僚、木田拓次を演じた磯村勇斗と門脇演じる母親が置き去りにした姉妹でアイスを食べるシーンだと振り返る。「磯村くんが食べているアイスに当たりが出るという場面なのですが、縁側で長回しで撮影していて、なかなか一発でうまくいくものではないですね」とニヤニヤ。「磯村くんは食べ切らないといけなかったので、真夏の暑い時期にもかかわらず、震える磯村勇斗を見ることができました。何本もアイスをガリガリ食べて、頭が痛くなりました」と振り返った。
「撮影中にハッとした瞬間はあったか」という質問に「麦ちゃんの登場シーンにはハっとしました」と笑顔。「マニキュアを塗るシーンはなんとも言えない説得力がありました。そこに佇む門脇麦、本物がいるという気がしました。艶かしいキレイさがありました」と話したが、芝居以外での門脇の印象は「誰よりも早く現場を去る女優さんです」と話し、「いままで出会った女優さんのなかで、一番帰るのが早くて(笑)。気づいたらメイクを落とし、私服に着替えて『お疲れ様でした!』と走っていきます。なぜそんなに急ぐのかを聞いたら『1秒でも早く帰りたいんです!』とおっしゃっていました」と明かすと、門脇は早く帰るコツは「段取りをちゃんとつけること」と即答し、「駐車場が遠ければマネージャーさんに頼んで近くまで車を持ってきてもらいます。あとは走りながら脱げるものは脱いでいくのもコツです」と得意げに語り、笑いを誘っていた。
幼い姉妹を家に残して姿を消す母親役を演じた門脇が撮影を振り返り、「高橋監督は姉妹に付きっきりで演出しているので、私にはあまりなにも言ってくれなくて」としょんぼりすると、生田、白石プロデューサーは大笑いし、高橋監督は気まずそうに下を向く。姉妹を演じた役者には台本を渡していなかったため、その場で細かな演出をつける必要があったこと、そしてなにより高橋監督がキャスト陣を信頼し切っていることが大きな理由だった。「いい俳優さんたちにめぐり会えたので、こんな風に演じて欲しいということを現場で感じることがありませんでした」と説明し、「生田さん、門脇さん、お2人の芝居が好きだったというのもあります」と付け加えていた。
本作は16ミリフィルムで撮影されたため、フィルム映画の魅力を問われる場面も。「1ロール8分しか撮影できないフィルム撮影にはフィルムチェンジの時間があります。僕はその待ってる時間がすごく好きで『映画を撮ってるなあ』っていう感じがします」とうっとりとした表情を浮かべ「フィルムでしか刻めない味や香りを体験してほしいと思います」と呼びかけた。門脇は「フィルムというだけでテンションが上がります!」と満面の笑みを見せ、「自分がずっと観てきた60年代、70年代の作品の俳優さんや監督たちもこうやって映画を撮ってきたんだとか、こんなふうにフィルムチェンジの時間を過ごしていたのかと想像するだけですごくうれしくて。スタッフのみなさんもうれしそうなので、こちらもうれしくなります」とフィルム映画への愛を熱く語っていた。
フィルムでの撮影は水の表現や太陽の光には「メリットでした」と微笑んだ高橋監督。「デジタルではクリアすぎるところもあるので、粒子が荒れてちょっとざらついていたりするのが、今回の映画では非常に有効的でした」と胸を張る。「光が当たっていないところは映らないのがフィルムの特徴です。そこに強弱をつけたり、スポットを当てたいところに光を当てるのをずっと(フィルム映画で)学んできました。夜のシーンで岩切や子どもたちにちゃんとフォーカスが当たるというのはメリットでした」と満足といった様子で語った。
最後の挨拶で生田は「心を抉られるようなシーンもたくさんあります。映画を観る前と観た後では世界が少しだけ違って見えるかもしれません。フィルム映画のすばらしさ、長年かけて完成した映画を楽しんでください」と呼びかけイベントを締めくくった。
取材・文/タナカシノブ
※高橋正弥監督の「高」は「はしご高」が正式表記
生田斗真、『渇水』主演即決の決め手は“ただならぬオーラ”を放っている脚本!門脇麦と16ミリフィルム撮影の魅力語る

関連記事
おすすめ情報
MOVIE WALKER PRESSの他の記事もみるあわせて読む
-

羽鳥慎一アナに異変…「ごめんなさいね。風邪っぽい」かすれ気味の声で「モーニングショー」進行
日刊スポーツ5/6(月)9:07
-

“ビリギャル”女優・石川恋(30)がタトゥーだらけのイケオジ経営者(36)と“高級マンション半同棲”「TikTokで大バズり、窪塚洋介似、和製ジョニー・デップ」――2023年読まれた記事
文春オンライン5/6(月)7:00
-

小室哲哉との別れ、母の死、離婚と困難も多かったけど…平成最強の歌姫・安室奈美恵(46)が引退するまで「トップスター」であり続けた理由と音楽的な転機――2023年読まれた記事
文春オンライン5/6(月)7:00
-

やす子の寝顔姿が「圧倒的な子犬感」「赤ちゃんみた〜い」 仕事合間のオフの姿が話題
ENCOUNT5/6(月)9:31
-

松山千春「私はテレビに出てるような二流、三流のコメンテーターとは違いますから」
サンケイスポーツ5/6(月)5:00
-

北川悦吏子氏“生と死”扱うドラマをテレ東で「他局では通らなかった」 渡辺謙は2度オファー断るも「3回目にノックアウト(笑)」
ORICON NEWS5/6(月)6:00
-

「これはアカン」Perfumeあ〜ちゃん、“激ヤセ”自撮りショットにファンから再び心配の声
週刊女性PRIME5/6(月)7:00
-

元ザブングル松尾陽介氏、久々テレビ登場 芸能界辞めたのは芸人叩きが「苦手になって」
デイリースポーツ5/6(月)10:43
-

56歳・原田知世、変わらぬ姿に渡辺謙も賛辞「本当に“時をかける少女”」
ORICON NEWS5/6(月)6:00
-
-

山田裕貴の〝赤いパンイチ姿〟をツッコむ西野七瀬 お笑いコンビさながらの夫婦仲
東スポWEB5/6(月)5:00
-

北斗晶 長男幼なじみの結婚式のためハワイで孫と再会!「ぐーんと大きくなって驚くことばかり!!」
スポニチアネックス5/6(月)6:30
-

朝ドラ「虎に翼」5月7日第27話あらすじ 特高警察から目をつけられていた香淑(ハ・ヨンス)、事情を知り衝撃を受ける寅子(伊藤沙莉)ら
iza!5/6(月)8:15
-

「小さな時から美人だから恐ろしい…」 幼少期から決めポーズ、人気女優の写真が反響
ENCOUNT5/6(月)8:10
-

ダレノガレ明美 家に20個もストックしている意外なもの明かす それでも「すぐなくなる」
スポニチアネックス5/6(月)6:30
-

妻夫木聡、20年ぶり北川悦吏子作品に感慨 熱弁振るう「本当に小さな幸せが…」
ORICON NEWS5/6(月)6:00
-

唐十郎さん死去 宮沢りえと森田剛の交際きっかけも 華麗な人脈誇った
スポニチアネックス5/6(月)5:00
-

「虎に翼」でまさかの司法試験合格者にネットびっくり「できる子だったんかい!」【ネタバレ】
デイリースポーツ5/6(月)9:32
-

笑福亭鶴瓶、TBS前でタクシーにひかれていた 無傷強調も運転手にマネジャーは激怒
ENCOUNT5/6(月)10:07
-
エンタメ アクセスランキング
-
1

羽鳥慎一アナに異変…「ごめんなさいね。風邪っぽい」かすれ気味の声で「モーニングショー」進行
日刊スポーツ5/6(月)9:07
-
2

“ビリギャル”女優・石川恋(30)がタトゥーだらけのイケオジ経営者(36)と“高級マンション半同棲”「TikTokで大バズり、窪塚洋介似、和製ジョニー・デップ」――2023年読まれた記事
文春オンライン5/6(月)7:00
-
3

小室哲哉との別れ、母の死、離婚と困難も多かったけど…平成最強の歌姫・安室奈美恵(46)が引退するまで「トップスター」であり続けた理由と音楽的な転機――2023年読まれた記事
文春オンライン5/6(月)7:00
-
4

やす子の寝顔姿が「圧倒的な子犬感」「赤ちゃんみた〜い」 仕事合間のオフの姿が話題
ENCOUNT5/6(月)9:31
-
5

松山千春「私はテレビに出てるような二流、三流のコメンテーターとは違いますから」
サンケイスポーツ5/6(月)5:00
-
6

北川悦吏子氏“生と死”扱うドラマをテレ東で「他局では通らなかった」 渡辺謙は2度オファー断るも「3回目にノックアウト(笑)」
ORICON NEWS5/6(月)6:00
-
7

「これはアカン」Perfumeあ〜ちゃん、“激ヤセ”自撮りショットにファンから再び心配の声
週刊女性PRIME5/6(月)7:00
-
8

元ザブングル松尾陽介氏、久々テレビ登場 芸能界辞めたのは芸人叩きが「苦手になって」
デイリースポーツ5/6(月)10:43
-
9

56歳・原田知世、変わらぬ姿に渡辺謙も賛辞「本当に“時をかける少女”」
ORICON NEWS5/6(月)6:00
-
10

山田裕貴の〝赤いパンイチ姿〟をツッコむ西野七瀬 お笑いコンビさながらの夫婦仲
東スポWEB5/6(月)5:00
エンタメ 新着ニュース
-

山田邦子、月収1億円をデパートの紙袋で手渡し 人気絶頂期に丸刈り頭の理由を告白
サンケイスポーツ5/6(月)13:01
-

【明日7日の虎に翼】第27話 昭和13年春 思想犯の疑いを掛けられた香淑もとに特高がやってくる
スポニチアネックス5/6(月)13:00
-

みちょぱ スーパー帰りに路線バスを利用「今日は主婦になろうと思って」
スポニチアネックス5/6(月)12:59
-

伊織もえ、野外でビキニ姿を披露! 「お腹周りがちょっとだらしないのがリアルでエロい」「相当有り難み感じる出来」
All About NEWS5/6(月)12:55
-

りんごちゃん 理解が追い付かない変ぼう姿「だれーw」「そのヘアスタイルなのに何で」「ギャップが」
スポーツ報知5/6(月)12:55
-

呂布カルマ GWに来日する外国人観光客を疑問視「リサーチ足りな過ぎるな」
東スポWEB5/6(月)12:53
-

「SEVENTEEN」、ベストアルバムが初動で新記録…トリプルミリオンセラーなるか
WoW!Korea5/6(月)12:52
-

村重杏奈の中学時代の成績表 ハライチ澤部「大谷の打撃成績みたい」とあ然
デイリースポーツ5/6(月)12:51
-

エビ中・低学年メンバーの目標は東京ドーム フォトブック発売で「まだまだ止まらないぞ!」
ENCOUNT5/6(月)12:50
-

新山千春の愛娘、母のマッチングアプリ再婚に「心配でしたね。もう妻がいるかもしれないし…」
サンケイスポーツ5/6(月)12:50
総合 アクセスランキング
-
1

大谷翔平9&10号連発でリーグ「9冠」!難敵ブレーブスを3タテでドジャース貯金「10」
スポーツ報知5/6(月)8:11
-
2

衝撃1試合2HRの大谷翔平が達成した「4/5」にネット騒然 超強力LA打線で「笑える」「意味わからん」「異次元」
THE ANSWER5/6(月)8:06
-
3

「骨が見えるほど、うれしい」 身長155cmで体重26kg 子どもの発症増える“摂食障害” 苦しんだ女性が明かす壮絶な過去
CBCテレビ5/6(月)6:32
-
4

【速報】3歳の娘に暴行か 骨を折る重傷を負わせたとして派遣社員の男(30)逮捕 滋賀・愛荘町
読売テレビニュース5/6(月)8:17
-
5

羽鳥慎一アナに異変…「ごめんなさいね。風邪っぽい」かすれ気味の声で「モーニングショー」進行
日刊スポーツ5/6(月)9:07
-
6

“ビリギャル”女優・石川恋(30)がタトゥーだらけのイケオジ経営者(36)と“高級マンション半同棲”「TikTokで大バズり、窪塚洋介似、和製ジョニー・デップ」――2023年読まれた記事
文春オンライン5/6(月)7:00
-
7

小室哲哉との別れ、母の死、離婚と困難も多かったけど…平成最強の歌姫・安室奈美恵(46)が引退するまで「トップスター」であり続けた理由と音楽的な転機――2023年読まれた記事
文春オンライン5/6(月)7:00
-
8

【速報】「インド洋に大きな弧」上川外相が帰国 強まる中国の進出 アジア・アフリカなど歴訪
FNNプライムオンライン5/6(月)9:25
-
9

ピクニックなのに「お弁当忘れちゃった♡」渋々【ママ友】に分けてあげると → とんでもない仕打ちが!?
ftn-fashion trend news-5/6(月)7:01
-
10

やす子の寝顔姿が「圧倒的な子犬感」「赤ちゃんみた〜い」 仕事合間のオフの姿が話題
ENCOUNT5/6(月)9:31
いまトピランキング
 いまトピランキングの続きを見る
いまトピランキングの続きを見る
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

今季絶望から電撃復帰した前田大然を感動させたセルティックファン5万人の大喝采が熱い!
Qoly5/6(月)13:00
-

車内でスヤスヤ眠る1歳弟 いきなりリサイタルを始めた兄の歌声に…→露骨な表情が可愛すぎ!
ほ・とせなNEWS5/6(月)12:30
-

アーセナルがプレミアリーグで優勝する可能性は20%…槙野智章が予想する
Qoly5/6(月)12:30
-

パリス・ヒルトンの義兄、45歳でプロサッカー選手デビューしたワケ 57歳カズと同じリーグ
Qoly5/6(月)12:00
-

「5時に夢中!」マツコ&若林の生ワイド 初夏の今おすすめ車中泊旅を調査!
TOKYO MX+(プラス)5/6(月)11:55
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) MOVIE WALKER Co., Ltd.