賃金上昇が物価高に追い付かない中、消費を刺激するため、岸田政権が打ち出した目玉施策「定額減税」が6月から始まります。所得税3万円と住民税1万円、合わせて4万円が減税されますが、減税額やタイミングなど、人によって大きく異なる仕組みとなっています。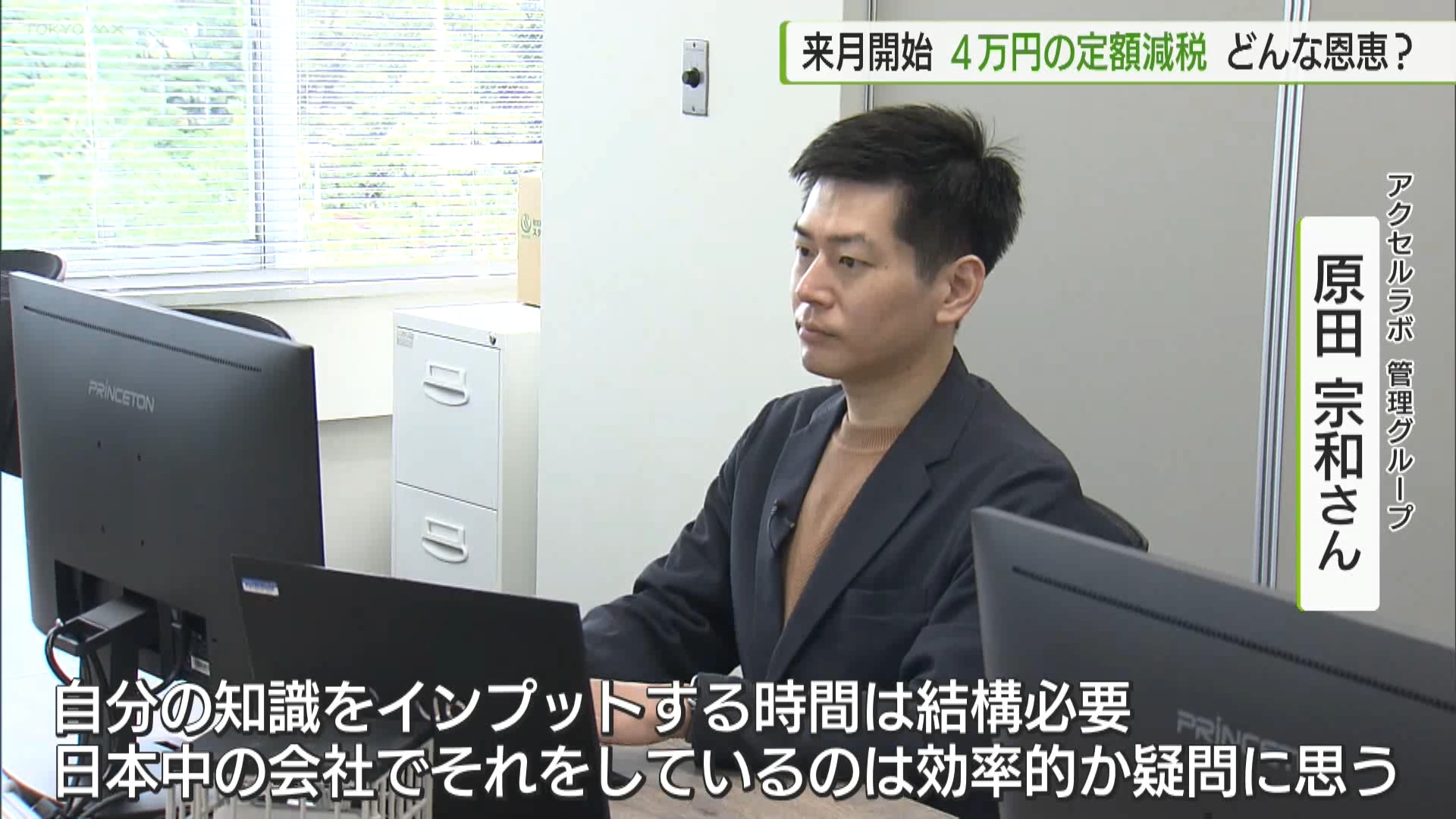
まず、定額減税の対象者となるのは、会社員や個人事業主、そして年金受給者など年収2000万円以下の納税者とその扶養家族です。年収2000万円以上の人や非課税世帯は定額減税の対象には含まれません。ただ、非課税世帯については1世帯当たり7万円などが給付されます。
対象者についてですが、扶養家族の有無によって減税額が変わってきます。扶養家族がいない場合は所得税と住民税合わせて4万円ですが、扶養家族がいる場合は1人当たり4万円となるため、例えば扶養家族が3人いる場合、所得税12万円、住民税4万円の合わせて16万円の減税となります。
では、どのように減税されるのでしょうか。まず、会社員の場合、6月以降に支給される給与から減税となります。例えば月2万円の所得税を払っていた場合、扶養家族がいない人は6月は全て減税され、2万円が給料から天引きされず、その分、手取りが増えることになります。そして7月は減税分が1万円残っていますので、天引きされる所得税は1万円となり、8月以降は従来に戻ります。扶養家族が3人いる場合は本人分を含めて所得税が12万円減税されるので、6月から11月分まで天引きされず、12月から天引きされることになります。なお、減税額が引き切れない分が出た場合は、給付されるということです。
この所得税の減税について、岸田総理は「減税の恩恵を実感いただくことが重要だ」として、政府は5月21日、企業に対して減税額を給与明細に記載することを義務付ける考えを示しました。ただ、企業の事務負担が増えることが課題となっていて、現場からは疑問の声も上がっています。
新宿区にある、家電などを遠隔操作できるアプリなどを提供する70人規模の企業「アクセルラボ」では、人事担当者が「準備のための業務が増えた」と話します。
管理担当・原田さん:「6月給与から始まるので、そこからは質問をいっぱい受けるだろうと思っている。税務署から来るパンフレットを見たり、給与計算ソフトから送られてくるセミナーを見て勉強したりしている。自分の知識をインプットする時間は結構必要だと思う。日本中の会社でそれをしているというのは効率的なのかなと疑問に思う。恐らく今年1回きりだと思われるので、そのためだけに非常に大きな労力がかかっていると思う」
この会社では会計ソフトを使用しているため、計算の手間は省けているということですが、3人で担っている経理や人事の業務は増えているといいます。
続いて、会社員以外の所得税減税の仕組みを見ていきます。年金受給者については会社員と同じく6月からで、支払われる年金から順次減税されます。一方、個人事業主については2通りあり、1つは「今年分の確定申告」で、もう1つは「7月の第1期予定納税額で減税」となり、恩恵を受ける時期が異なる仕組みとなっています。
一方、1万円減税される「住民税」については、本来の今年の住民税から1人当たり1万円を引いた金額を、11カ月にわたって均等に徴収される形となります。6月は一律で“徴収されず”、7月から減税された住民税を支払うことになりますが、年金受給者については10月以降となり、今年生まれた子どもについては「対象外」となります。
物価高が続く中、国民の軽減負担を目的とした政策ですが、こうしたお金が絡む政策を政府が行う時は詐欺行為も増えます。十分ご注意ください。


















































