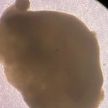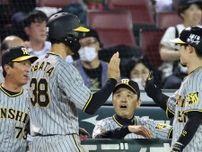【メジャーリーグ通信】
2023年に始まったピッチクロックに対する大リーグ選手会(MLBPA)の態度は一貫して否定的であり、大リーグ機構に改善を強く求めている。
確かに、シェーン・ビーバー(ガーディアンズ)、スペンサー・ストライダー(ブレーブス)、投手としての大谷翔平(ドジャース)ら、球界を代表する投手が昨季から今季にかけて相次いで肘や肩をケガしたり、トミー・ジョン手術を受けたりする状況は、従来と異なる。
この間に起きた投手に関する大きな変化といえば、ピッチクロックの導入である。
ピッチクロックによって、投手が球を受け取ってから投げるまでの時間が厳密に計測されるようになったものの、投球に求められる動作が短縮されるわけではない。そのため、これまでよりも短い時間で一連の動きをスタートしなければならない。息つく間もなく投げることで体への負担が増し、結果として投手のケガが増えているというのがMLBPA側の批判の趣旨である。こうした見方は大谷も「間違いなく負担が増えている」と指摘し、肯定している。
一方、機構側の見解は異なる。機構が強調するのは、ピッチクロックの導入により、昨季の試合時間は1985年以来の平均2時間40分と前年に比べて24分短縮された点である。そして、投手のケガとピッチクロックの導入とが関係することを示す証拠はなく、むしろアマチュア時代に肘などの既往歴のある選手が増加したことが背景にあるとしている。
機構がピッチクロックを導入した理由の一つに、投球間隔を短くすることで試合の展開を速くし、視聴者の関心をつなぎとめる狙いがある。視聴者の限られた時間を他のプロスポーツ中継やオンラインゲーム、テレビ番組や映画などのオンライン配信と奪い合う現在、「野球の中継は冗長」という印象は視聴者の野球離れをもたらし、球界にとって重要な収入源である放映権料に影響を与えかねない。
何より、MLBPAが反対するということは、今後の労使交渉の材料になることを示唆する。すなわち、MLBPAが導入を拒むのはサラリーキャップ制や国際ドラフトであるから、機構や経営者はピッチクロックの緩和を条件にこれらの制度の導入を迫るのは、有効な戦略となる。
それだけに両者の駆け引きは今後も激しいものとならざるを得ないのである。
(鈴村裕輔/野球文化学会会長・名城大准教授)