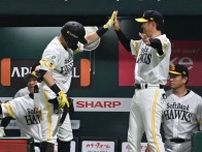1月7日に行われた全国高校ラグビー決勝戦は、史上希に見るロースコアの決着となった。
試合は春の選抜を制した神奈川の桐蔭学園が昨季王者・東福岡を3点差で振り切った。ファイナルスコアは8−5。過去3年間の優勝チームはすべて30点以上をあげていたことから見ても、異例といっていいロースコアだった。この大会、決勝で両チームとも1桁得点で決着したのは1987年度の第67回大会、秋田工が9−4で相模台工を破って以来36年ぶり。
当時はまだトライが4点の時代であり、使われていたのは皮製のボールで、元号は昭和だった。トライが5点になった1993年以降では初めてだ。
歴史的なロースコアとなった原因は両チームの「堅守」だ。単純なタックル力・技術だけではない。一度タックルしてもすぐに起き上がって次の相手アタックに備え、素早く防御陣形を整える勤勉さ、危険なスペースを察知して埋め、複数選手が役割を分担して遂行するコミュニケーション能力。それを連続するフィットネス。すべてがハイレベルだった。
ディフェンスが際立ったのは、アタックもまたハイレベルだったからだ。
試合開始のキックオフは東福岡が蹴った。決勝のようなビッグゲームではひとつの得点がモノを言う。自陣深くの危険なエリアからは速やかにキックで脱出し、得点を狙える敵陣へと陣地を進めるのが得策。それは3カ月前まで多くのファンの目を釘付けにしたワールドカップでも実証されたセオリーだ。
キックを使わずボールを“運ぶ”ことを選んだ桐蔭
しかし、自陣深くで相手キックオフを捕球した桐蔭学園はキックによる陣地回復を狙わず、自陣深いところからアタックを始めた。細かいパスを繋ぎ、相手ディフェンスに当たっては着実にボールをリサイクルしてじわじわと前進。
そのアタックは1分半、実に11フェイズに及んだ。最後は相手陣10m線まで進んだところでノットリリースザボールの反則で終わったが、徹底して攻め続けるという覚悟を表明するアタックだった。実際、桐蔭学園はこのアタックを皮切りに、前後半の60分で10フェイズを超える連続アタックを6度もみせた。
スコアが動いたのは前半12分。桐蔭学園がこの試合で最長となった23フェイズまで攻撃を継続したところで東福岡が密集で反則を犯し、桐蔭学園FB吉田晃己がPGを成功。
3点を先制すると、24分には再び相手ゴール前へ。ここでは相手ゴール前10mで東福岡DFにターンオーバーされるが、そこからのアタックで東福岡SO井上晴生が落球。これを拾った桐蔭学園WTB田中健想がそのまま右中間インゴールに飛び込んだ。桐蔭学園から見れば意図的なアタックであげたトライではなかったが、徹底した地上戦で圧力をかけ続けたことが相手のゴール前でのミスを呼んだ形だ。
徹底的なアタック――言うは易しいが実行は困難なその策を桐蔭学園が遂行できた原点は、1年前の屈辱にある。
全国の切符を逃した昨年の屈辱
2022年11月20日、ニッパツ三ツ沢で行われた神奈川県予選決勝で桐蔭学園は東海大相模に13−14の1点差で敗戦。花園大会への連続出場が「7」でストップした。2019、2020年度には全国大会2連覇を飾るなど全国のトップに君臨していた濃紺のジャージーが、全国の舞台を逃した。
その日、桐蔭学園の部員たちは学校に戻るとすぐにミーティングを行い、負けた原因を徹底して話し合った。先発15人中9人を占めた2年生以下の選手たちは自分たちの覚悟が足りなかったことと向き合い、1年2カ月後の全国大会決勝まで勝ち続けることを誓った。12月には自分たちの出場しない花園を視察し、翌年の勝利への決意を確かめ合った。
翌年に向けて高めたのは思いだけではなかった。新チームを早く始動できた分、時間はあった。その時間をチームは基礎スキルのレベルアップに使った。パスを投げ、捕る。ラグビーでは当たり前の、小学生でもやるような練習メニューだ。
「こんなことから? と言われるようなことからやりました」と藤原秀之監督は苦笑する。
とりわけ徹底したのは捕球だ。片手でパスを捕る。それも左右にぶれたパスや地面に落ちそうな低いパスを捕る。その繰り返しで培った高い基礎スキルが、花園での徹底継続ラグビーを支えた。6度にわたった10フェイズを超える連続攻撃は、相手の反則で終わったのが2度、味方の反則あるいは相手のターンオーバーで終わったのが3度、味方のノックオンつまり捕球ミスで終わったのはわずか1度だけ。地面に落ちそうな低いパスも難なく捕球し、強い姿勢で相手タックルに向かって行った。
とはいえ、連続攻撃がそのまま勝利に直結したわけではない。60分であげたトライは相手のミスであげた1本だけ。ラグビーでは攻撃側が防御側よりも体力を消耗する。
実際、後半の半ばからは桐蔭学園のフィフティーンが明らかに消耗し、東福岡が運動量で圧倒。後半16分に東福岡がNO8高比良(恭介)主将の突破からCTB神拓実がトライしたあとも東福岡は桐蔭学園ゴール前へ殺到、逆転トライ寸前まで攻め立てた。紙一重の勝利だった。
結果だけを見れば、キックを有効に使っていれば、もっと効率的に戦えたのに――そんな見方もできるだろう。
だが、桐蔭学園はそれを選ばなかった。
「昨日のミーティングで、選手たちが腹を決めてくれました」と藤原監督は話す。
「昨年のチャンピオンである東福岡に対してどう戦うのがいいか、話し合いは長くかかったけど、花園の決勝ですから、普通の戦い方では勝てない。最後は『自分たちはどうしたいか』。1年間、さんざん練習してきたことを出そうと腹を決めてやりきってくれました」
城央祐主将も明かす。
「自分たちは誰も花園を知らない。だから、ここで試合をするというのはどんなことか、試合をしているところを想像しながら、出られなかった悔しさを忘れずに1年間やってきた。練習では、ひとつひとつのメニューを最後まで全力でやりきることにしていたので、その習慣がついていて、最後までやりきれたんだと思います」
かつてのようなスター選手は不在でも…
メンバーには高校日本代表候補がズラリ並ぶ。とはいえ、初優勝を飾った2010年度の松島幸太朗や竹中祥、小倉順平、初の単独優勝を飾った2019年度の伊藤大祐、連覇を飾った2020年度の佐藤健次、青木恵斗、矢崎由高のような、世代トップクラスのスター選手は見当たらない。
他校が目を見張るようなスーパープレーでトライをあげるわけでもない。だが今季の桐蔭学園は、NO8城を筆頭に、派手さはなくとも強く実直なプレーをひたすら反復して勝利した。その原点には1年前の悔しさがあった。
「苦しかったと思います。でも、どんなに苦しいことも笑って乗り越えてきた城たち58期の選手たちは素晴らしかった。桐蔭の新しい歴史を作ってくれた」
史上希に見るロースコア決着の陰には、そんな物語があった。
文=大友信彦
photograph by JIJI PRESS