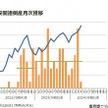年始の箱根駅伝で、青学大に敗れこそしたものの戦前は“一強”とまで言われ、圧倒的な優勝候補だった駒大。その評判の裏にあったのは、分厚い選手層だ。有力ランナーが多いほど、実力者でも檜舞台を逃すケースは増えていく。その熾烈な戦いの裏では、一体なにが起こっていたのだろうか。大学最後の箱根路を「逃した」選手が語る、大学駅伝のリアルとは。(全2回の1回目/2回目につづく)
天然のパーマが、風になびくほど伸びている。
4年前、鳴り物入りのルーキーとして、坊主頭で名門駒澤大陸上部の門をくぐった白鳥哲汰も、この春で大学を卒業する。学生生活を振り返る声は、心なしか沈みがちに聞こえた。
「正直、完全燃焼とはいかなかったですし、やり残した感も大きい。満足したとは言えないですね」
本人がそう語るように、順風満帆な4年間ではなかった。下級生の頃、箱根駅伝には2度出場したが、いずれも区間二桁と不本意な成績に終わっている。ケガや体調不良に苦しみ、高校時代のようなインパクトのある走りはできなかった。
走れなかった最後の箱根路
もっとも悔いが残るとすれば、今年の箱根駅伝を走れなかったことだろう。ひと月近くが経っても、白鳥はまだ悔しさが拭いきれないと話す。
「引きずってますね。切り替えたいと思っていても、うまく切り替えられない。最後の箱根を走れず、まさか11月の上尾(シティ)ハーフ(マラソン)が学生ラストランになるとは思っていなかったので……」
4年生で臨む最後の箱根で、白鳥は1区にエントリーされていた。しかし、当日変更が前提の区間配置で、走る見込みは端からなかった。言葉は悪いが、当て馬である。大学生活の最後をこんな風に締めくくることになるとは、あの時点では想像もしていなかったことだろう。
白鳥の名が広く陸上界で知れ渡ったのは、高校2年の頃だった。長距離ランナーの憧れである都大路(全国高校駅伝)で、エース区間の1区を走って区間賞を獲得。早熟な才能が注目を集めた。
卒業時にはもちろん複数の大学から勧誘の声がかかったが、白鳥はこんな理由で駒大を選んだ。
「箱根駅伝も目指していた大会の一つではあるんですけど、その時から将来はマラソンをしたいという思いが強くて。自分たちが入る頃にはまだ中村匠吾さん(現富士通)がこっちで練習していて、MGCに出場する卒業生の方も多かった。それで駒澤大でやりたいなって。あとは総監督の熱意ですね」
現在は総監督として一部選手の指導をする大八木弘明氏から、白鳥は熱心に口説かれた。
いざ大学に入ると、そこは想像以上に多くの才能が集まる場所だった。1つ上の先輩に田澤廉がいて、同級生には鈴木芽吹や花尾恭輔らがいた。白鳥たちの代はその頃、こんな誓いを立てたという。
「まだ三冠とまでは言ってなかったと思いますけど、4年生になったときには絶対に箱根で優勝したいねって。これだけのメンバーが揃ったので、みんなできると思ってました」
入部当初は練習の質の高さに驚き、夏合宿でも思うように距離が踏めなかったと言うが、才能はやはり非凡だった。秋になると徐々に調子が上向きとなり、11月の競技会で5000mの自己ベストを更新、12月の10000m記録会でも28分14秒86の好タイムを叩き出し、同級生の中で一目置かれる存在となった。
1年目から箱根メンバーに抜擢も、本人の胸中は…?
1年生ながら、白鳥は箱根駅伝の1区に抜擢される。エントリーされていたのは4年生だったが、当日変更で憧れの舞台に立ったのだ。
「でも、結果的に15位と振るわない成績だったので、チームは優勝しましたけど、自分的には悔しさしか残らなかったです」
区間15位とはいえ、トップとは47秒差。チームが13年振りの総合優勝を勝ち取ったこともあり、端から見れば白鳥は大学で順調なスタートを切ったように思えた。
だが、本人はこの頃から思うようにいかないもどかしさを感じていたという。
「ほんと暑さが苦手で、夏になると練習にもついていけなくなって。逆に涼しくなると走れるようになるので、2年目も箱根のメンバーには選んでもらえたんですけど、1年を通して練習ができていないのでうまくはまらなかった。けっこう課題が残りました」
2年連続で箱根駅伝を走ったが、2年目も7区で区間10位と満足のいく結果ではなかった。
夏に右足を疲労骨折し、しっかりと距離を積めなかった影響もあったのだろう。箱根後の徳之島合宿で、白鳥はまた同じ箇所を痛めてしまう。振り返ればこのケガが、大きなつまずきの要因となった。
他の同級生が頭角を現す中、3年生になった白鳥は徐々に存在感を失っていく。2度目の疲労骨折を発端にした不調は、そこから1年近くに及んだ。
「気づいたら……眠れなくなっていた」
「最初は疲労かなと思っていたんですけど、大きな病院でレントゲンを撮ってもらったらやっぱり折れてて、かなり長期で離脱したんです。練習に復帰してからもボロボロで、精神的にもまいってしまって。気づいたら……眠れなくなっていました」
気分的な浮き沈みが激しくなり、練習への意欲も湧いてこない。そんな自分が許せずに、精神的に追い込んでしまう。完全な悪循環だった。
外傷と違い、心の不調は本人以外にはわかりにくい。
伝わりにくいからこそ、周囲に打ち明けることなく自身で抱え込んでしまったのだろう。
「精神的な理由で『練習できません』っていうのは自分でも言いたくなくて。だから、誰にも言わずに病院へ行って、先生にも『(チームには)言わないで』と頼んでいました。それこそずっと足を引っ張ってきて、これ以上足手まといになりたくないという思いがあったので」
仲の良い部員にも苦しみは打ち明けず、思うように走れない日々が続いた。白鳥は一度実家に帰り、両親にこんな思いを伝えている。
「(部を)辞めたいじゃないですけど、走ってもこんな中途半端な状態なら、陸上をこれ以上続ける意味はあるのかなって。そんなことばかり四六時中考えていて。でも、両親に打ち明けたことで少し気持ちがラクになりました」
心の問題はふとしたことが切っ掛けで良くなることがある。これを機に徐々に体調が戻り始め、3年目が終わろうとする昨年3月には本格的に練習復帰を果たした。
ポイント練習ができるまでに回復すると、藤田敦史新監督からこう声をかけられたという。
「『お前は練習さえ積めれば駅伝を走れるから』って。まだ指導者に見捨てられてないんだってことがわかりましたし、そこから調子も上がってきました。(鈴木)芽吹とかも『駅伝を一緒に走ろう』と言ってくれて、チームメイトが支えてくれましたね」
大学のラストシーズン、白鳥は5月の関東インカレで5000mのメンバーに選ばれ、久しぶりに公式戦を走った。結果は14位だったが、ここでも復調の切っ掛けをつかんだ。
「両親が見に来てくれていたんですけど、走り終えた後に、なんか母親が泣いていて。ここまで戻せて良かったじゃんということだったんでしょうけど、その姿を見てまた気持ちが入ったというか。このままじゃ終われないって思いました」
翌月には5000mの記録会で1年生以来の自己ベストを更新。懸念の夏も、継続をテーマに乗り切った。強度を落としても中断なくやりきることで、結果的に例年以上の距離を積めたという。
捲土重来を期した4年目の駅伝シーズン
秋になれば駅伝シーズンが幕を開けるが、出雲駅伝はメンバー外、全日本駅伝はメンバー入りを果たすも不出場に終わった。だが、白鳥に焦りはなかった。
「この1年は本当に練習の一つひとつが身になっている感覚があって、力がついてきているなっていう実感をもてたのは4年目にして初めてでした。正直、全日本には出たかったですけど、直前のポイント練習を1本外したので納得せざるを得なかった。
『まだ箱根がある』っていうのが心のセーフティーネットになっていて、そこには絶対合わせる気でいました。全日本後の上尾ハーフが箱根の大きな選考になるというのはわかっていたので、そこで結果を出すことに気持ちを切り替えてましたね」
駒大は出雲と全日本を連覇。だが、箱根のメンバー選考はいったんフラットにして考える、と藤田監督は明言していた。控えに甘んじていた選手にとっては、11月19日の上尾ハーフこそがアピールできる最大にして最後のチャンスだった。
白鳥は期する思いでレースに臨んだ。
<後編につづく>
文=小堀隆司
photograph by Yuki Suenaga