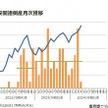「シンデレラボーヤ」
2月25日の大阪マラソンで優勝した國學院大・平林清澄につけられたニックネームだ。
この日、平林の走りはまさにシンデレラストーリーの主人公のようだった。2分58秒のペースを刻む先頭集団で安定した走りを見せ、32km過ぎの起伏を利用してスパート。初マラソンだったためギャンブル性の高い仕掛けにも思えたが、昨秋のMGCを制してパリ五輪内定の小山直城、2時間4分台の自己ベストを持つキッサ(ウガンダ)らを振り切り、そのまま優勝テープを切ったのだ。
優勝タイム、2時間6分18秒。これは初マラソン日本最高記録かつ学生日本新記録であり、21歳以下としてはアフリカ勢以外で初めて2時間7分を切ったことになった。
レース後、タイムについて平林はこう振り返っている。
「後ろに海外の選手がついてきているのは怖かったけど、気にしたらダメだと思って、自分がいけるところで仕掛けようと思っていました。勝負に徹した中でタイムがついてきて率直にうれしい。(42.195kmという)未知な領域は楽しみだった。最後は1km、1kmが長く感じたけど、正直楽しかったです」
パリ五輪の設定記録は突破できなかったものの、誰もが苦しいマラソンを「楽しかった」と振り返るコメントは、國學院大の前田康弘監督の命名通りマラソン界の「シンデレラ」にふさわしいものだろう。
シンデレラの「靴」の正体は…?
シンデレラの物語では、忘れてきた「ガラスの靴」が鍵になるが、21歳のボーヤの足元も他の選手とは違う。
今回の大阪マラソンで着用したのがadidasの「アディゼロ タクミ セン9」だ。これは箱根駅伝やマラソンレースでお馴染みの「厚底シューズ」とは少し異なる。
多くの選手が着用しているのが、NIKEのアルファフライやヴェイパーフライ、ASICSのメタスピードシリーズ、adidasのアディオス プロだ。これらはソールの厚さが世界陸連の規定「40mm以下」をぎりぎり下回る厚いミッドソールを備え、カーボンプレートが搭載されたものだ。エリウド・キプチョゲ(ケニア)ら世界トップ選手もこれを履いている。
だが、平林の選んだタクミ センはそれよりも薄く、最新の「10」でみると厚さは「ヒール:33 mm/前足部:27 mm」となっており、約1cm薄い。
一般的には厚い方が反発力に優れており、第100回箱根駅伝でタクミ センを選んだのは平林を含めて9名と、選手全体をみてもアディダス着用者の中でも明らかに少数派だ。しかも、平林は箱根でも今回の大阪マラソン最新モデルの「10」ではなく一つ前の「9」を選んでいる。
「厚底を使っちゃうと、もう自分の力じゃないというか」
以前の取材で、平林は周囲とは違うシューズ選択の理由を教えてくれたことがある。そこにはトップランナーならではのこだわりがあった。
「厚底ってすごくクッションがありますよね。地面にバンッてついたときに、最初にアウトソール(靴底)がパンッてついて、ミッドソールのクッションが潰れるじゃないですか。バキュンッて。潰れた部分がガンッて跳ね返って地面から離れるんですけど、そこの時間差が嫌なんですよ。潰れて、反発するまでにタイムラグがあるのが気になってしまう。
それに厚底だと、接地の時に足の回りが遅くなるんです。ガーンッて跳ねはするんですけど、回転が遅くなって走りの動きがゆったりになってしまう。僕の強みは『軽さ』とか、『回し』なので、ちょっと合わないんです。それに厚底を使っちゃうと、もう自分の力じゃないというか……僕は大きな反発というよりも、自分の足を使って走りたいんです」
高校時代の平林はトラックもロードもすべてASICSの薄底シューズの定番である「ソーティーマジック」で走っていた。周囲が厚底シューズを履いても手を伸ばそうと思ったことはなかったというが、高校時代から今に至るまで自分の走りの「強み」を正確に理解し、それを活かせるシューズを選んできたということだろう。
そこに登場したのが今回の「ガラスの靴」だった。
「もうちょっとミッドソールを分厚くしてくれないかなって、ずっと言っていたんですよ。そうしたらタクミ センが出てきて、これはいけると思った。柔らかすぎず、硬すぎず、クッション感も僕の走りにちょうどいい。地面を掴む感覚も残っていて、なおかつほどよい反発感もあるので、リズムが崩れないんです。いまはすべての距離のレースでこれを履いてます」
キプチョゲら世界トップ選手のフォームを観察しているという平林。自分にはケニア人選手のように厚底シューズを「押し込んで」、その「反発をコントロールする」だけの筋力が不足していることは認めつつも、シューズに対する哲学はぶらさないと宣言していた。
「僕自身、靴に合わせる練習をしたくないんです。ウエイトをしたり、靴を履くための補強みたいなものが出てきていますよね。でも、僕はそれをやりたくない。自分に合うシューズで、自分の動きをするからこそ、しっかり走れると思うんですよね。それを厚底に“合わせ”に行っちゃったら、自分の良さが崩れだすのかなと」
今回の大阪マラソンの走りを受け、青山学院大の原晋監督も「平林君は接地のタッチが軽い。本当に軽やかに走りますね」(スポーツ報知)とコメントしていたが、体重の軽さと回転するような走りが生む独特の推進力こそが平林の持ち味だ。その相棒が“厚すぎない厚底シューズ”であり、シンデレラボーヤの「ガラスの靴」である。
前田監督「箱根駅伝101回大会では優勝を狙う」
では、なぜ前田監督はシンデレラ「ボーイ」ではなく「ボーヤ」と名付けたのだろうか。1月下旬に行ったインタビューで、前田監督は次回の箱根駅伝で優勝を目指すこと、そしてチームの新主将にもなった平林を紐づけてこう語っていた。
「ずいぶん前から次回の箱根駅伝101回大会では優勝を狙うと公言してきました。平林や山本歩夢らが最上級生になり、青山学院や駒澤大学に肩を並べ、競り勝つためのピースが揃うと思ってきたからです」
一方で、そのためには駅伝シーズンだけでなく、2月、3月からロードでライバルチームに強さを見せていかなければならないと思っているという。
「私の解釈としては、箱根駅伝とマラソン強化は明確に結びついています。だからこそ、競技力とその背中で後輩たちの手本になっている平林の大阪マラソンは、個人だけでなくチームにとって大事なんです。今年は國學院大学として平林を先頭にして戦っていき、青山学院や駒澤に正攻法でバシッとあたっていきたいです」
監督が語る平林の「成長の余地」
エースに全幅の信頼を置く指揮官だが、平林のことを語る時は、いつも笑顔で留保をつける。それが、駅伝などで逆さに被っている白いキャップのことだったり、お調子者の側面があるというエピソードだったりする。
今回の取材で、前田監督が平林の「成長の余地」と語っていたのは言葉についてだ。
「饒舌なんですけど、自分の思いを言語化するのは苦手というか。どうしても思いが先走ってしまうので、本当のニュアンスと違う捉え方をされ、誤解されちゃうことがある。キャプテンとして上に立つのなら、言い方、話し方を気をつけなさいという話はしています。誤解されると後輩が距離をとってしまうから、一度、立ち止まって考えてから発言してもいいんじゃないか、ということですね」
言葉のまっすぐさ、強さは平林の長所でもある。ツッコミどころも人間的な魅力になる。
それがわかっているからこそ前田監督はキャプテンを任せているのだし、今回のニックネームも優等生的なニュアンスのある「ボーイ」ではなく、どこか響きに愛嬌のある「ボーヤ」としたのだろう。
平林清澄、21歳。國學院大学のキャプテンで、エース。日本マラソンのシンデレラボーヤの名前は歴史に刻まれた。
文=涌井健策(Number編集部)
photograph by JIJI PRESS