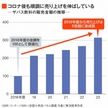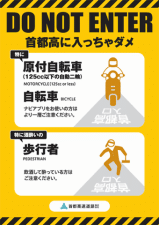マエストロが振るタクトのように、優雅かつ繊細、そして力強いフォーム。プロ4年目、今季入団した横浜DeNAベイスターズで、“野球の芸術作品”と呼ばれるアンダースローを武器に存在感を示している中川颯は、晴れやかな表情で言うのだ。
「育ってきた街で野球ができることはすごく幸せなことだと思って、毎日を噛みしめながら過ごしています」
じつはもう野球を辞めようと…
神奈川県横浜市出身。地元の名門である桐光学園高校でプレーをすると、立教大学へ進学。2020年のドラフト会議でオリックス・バファローズに4位指名され入団するのだが、所属した3年間で一軍登板をしたのはルーキーイヤーの1回きり。2年目は肩の不調により登板機会に恵まれず、シーズン終了後に育成契約になると、3年目は支配下復帰することは叶わず、オリックスを自由契約となり退団している。ハードラックな3年間だった。
「退団後、じつはもう野球を辞めようかとも思っていたんです……」
普段は朗らかで優しい表情が印象的な中川の眉間に皺がよる。当時のことを脳裏で反芻しているようだった。
この数年のオリックスといえば、連覇を重ねている黄金時代の真っ只中。“投手王国”と呼ばれるピッチャー陣の層は厚く、中川にとって大きな壁となった。とくに3年目はウエスタン・リーグで中継ぎとして21試合を投げ防御率1.38、WHIP(1イニングで何人の走者を許したか)は0.67という好成績を挙げていても、一軍から声が掛かることはなかった。見上げても光が射してこないファーム生活は骨身に染みた。
「自分の実力不足といえばそれまでですが、ファームにずっといるとメンタル的につらくて、モチベーションを保つのが難しかったというのは正直ありました。いいピッチングをして抑えていても、チーム状況もあって上から呼んでもらえない。どうしたら上がれるのか、そんなことばかり考えてしまって……」
一緒にやらないか
実力の世界とはいえ、置かれた環境や出会う人間、タイミングなどによってプロ野球選手の運命は大きく揺らぐ。中川は抗うことのできない渦の中にいるように翻弄され、心が焼き切れる寸前まで落ちていった。
自由契約となり、好きな野球を手放すことを呆然と考えていたある日、携帯が鳴った。出るとDeNAのスカウト部スカウティングディレクターの河原隆一(現・プロスカウティングディレクター)だった。
「一緒にやらないか」
単刀直入に河原ディレクターは言った。その言葉を聞いたとき、消えかけていた心の炎が音を立て爆ぜた。中川にとって地元球団であるベイスターズは、幼少期に憧れをもって見つめていたチームだ。家族と一緒に応援をしに横浜スタジアムへ足しげく通い、少年野球で使っていたグローブは石井琢朗モデルだった。
かつての夢が叶うんだ
「じつは小学生のときにベイスターズジュニアの試験に落ちていて、あのユニフォームで野球ができるんだと思ったら信じられなかったし、かつての夢が叶うんだって。誤解を恐れずに言えば、このチームで終われるのならば本望だって」
生気の宿る目で中川は言った。また条件は育成契約ではなく支配下登録選手であり、これも大きなモチベーションになった。この吉報には、ベイスターズの前身のホエールズ時代からのファンである祖父をはじめ家族も大いに喜んだ。まだ新たなスタート地点に立ったに過ぎなかったが、中川は、自分を見捨てなかった野球の神様に感謝をした。
環境が変われば戦力になる
獲得を決めた河原ディレクターは、次のように中川を評価している。
「オリックス時代から動向に注目していた地元出身の投手でしたし、アンダースローはうちのチームはもちろん、セ・リーグにもいないタイプ。昨年のファームでの成績も良かったこともあり、環境が変われば戦力になると見込み獲得しました。課題はありますが、コントロールもよくストライク先行のピッチングもできるので、新天地でぜひ力を発揮してもらいたいですね」
投手王国オリックスでの経験
いよいよ始まるDeNAでの日々。改めて振り返れば苦しいことの多かったオリックス時代ではあったが、得たものも大きかったと中川は語る。
「応援してくれたファンの方々やチームメイトには感謝しかありません。やっぱり投手王国と言われるだけあってレベルは高かったし、とくに同級生の山本由伸や、同期入団の山下舜平大といった結果を残している選手は一番練習をしているんです。彼らが練習をしていることで、引っ張られるように周りも練習をするし、本当にいいお手本というか、仲間には恵まれましたね」
かつてのライバルが友として助ける
1月31日、宜野湾キャンプ前日に、中川はチームに初合流した。「人見知りなので……」と、最初はドキドキしたというが、そんなときに声を掛けてくれたのが同学年の投手である石川達也だった。地元出身の石川は横浜高校から法政大学へ進んでおり、中川とはライバル関係にあったが、その一方で古くからの友人だった。
「達也がチームの人たちにいろいろと繋げてくれて、本当に助かりましたね」
持つべきものは友である。そしてDeNAの雰囲気は、噂通り明るく、元気で、優しかった。初めてのキャッチボールは、石川と仲のいい宮城滝太が相手をしてくれた。晴れて横浜ブルーのユニフォームを身にまとった中川は、主力や若手と交じって汗を流し、沖縄の抜けるような高い空の下で好きな野球に没頭した。
ここが、わたしの生きる場所――。
「後悔なく、ただシンプルに野球ができればいい。そしてチームに拾って頂いた恩返しがしたい。本当にそれだけですね」
実感のこもった様子で、中川は言った。
数字に出ない部分を大切にしている
キャンプ地のブルペンで投手たちは横並びでピッチングをするのだが、その中にあってアンダースローの中川は、やはり異質な空気を放っていた。球史を振り返ってもアンダースローの投手は希少であり、そのノウハウやメソッドは極めて少ないわけだが、中川はピッチングにおいてどこに重きを置いているのだろうか。
「僕はあまりデータや球速を重視するのではなく、数字に出ない部分を大切にしています。例えばフォームでタイミングを外すなど、数値化できないところにこだわっていますね」
ストレートとツーシーム(シンカー)の球速は130キロ台、さらに120キロ台のスライダーと100キロ台のカーブとチェンジアップが持ち球となる。これらを上手く組み合わせながらピッチングを構成する。
「球速だけ見たら他のピッチャーに比べて遅いですし、それをどうやって速く見せることができるか。一球一球のタイミングを変えたり、あくまでも自分の感覚でしかないんですが、バッターを惑わすっていうんですかね。速球で抑えるピッチャーも格好いいとは思いますが、僕は例えば和田毅選手(ソフトバンク)のように、“技”を駆使して抑えているピッチャーに魅力を感じるんです」
大学時代対戦した牧の証言「打てたためしがない」
そう言うと中川は、張りのある声で続けた。
「“臨機応変なピッチャー”になることが理想です。環境や相手バッターに左右されるのではなく、自分が適宜対応していく柔軟性のあるピッチャーになりたいですね」
タイミングやボールの出どころ、そして駆け引き。さらに地面からフッと這い上がってくる独特な軌道。中央大学時代に中川と対戦経験のある同学年の牧秀悟は、その球筋について感嘆しながら次のように証言する。
「何度も対戦しているんですけど、打てたためしがなかった。とにかくあの軌道が本当に打ちづらいんですよ。これからシーズンが始まりますけど、対戦相手も苦戦すると思いますね」
牧ほどのバッターが唸る、魅惑のピッチング。ここまでオープン戦では2試合マウンドに立ち、いずれの登板も4イニングを投げ、被安打2、無失点と結果を残している。中川は「一軍で投げられるのであれば先発、中継ぎどちらでも構いません」と言うが、首脳陣の起用傾向を見るかぎり先発の可能性が高そうだ。
27球で終わらすイメージ
懸念があるとすれば体力面だろう。中川はプロ入りしてからリリーフでしか登板しておらず、果たして長いイニングを稼ぐことに不安はないのだろうか。そう問うと、中川は考える間もなく、すぐさま自分の考えを口にした。
「僕としてはバッターが自分のスタイルに慣れてしまうのが一番怖いので、若いカウントで打たせることをテーマに取り組んでいます。中継ぎであれば全部三振を取るぐらいの気持ちなんですけど、先発ならばなるべく球数が少ない方がいい。以前、同じアンダースローの牧田和久さん(現・ソフトバンクコーチ)が『1試合27個三振を取るのではなく、27球で終わらすイメージ』とおっしゃっていて、その感覚でピッチングができれば、長いイニングでも投げることができると思います」
コントロールもよく、緩急自在にゾーン内で勝負できる術もある。そのピッチングスタイルから消耗が激しいとおぼしきアンダースローではあるが、さらに心技体を練り上げることができれば、十分勝負できるはずだ。過去3年間で一軍登板が一度しかない投手に対して過度の期待は禁物だが、その冷静で利発な考えや表情を見ていると、やってくれるのではないかと思ってしまう。
キャンプ中に同級生会
新たな環境、憧れのチーム。中川がDeNAに入団して心強かったのは、前出の牧や石川のように同学年の選手が多かったことだ。他にも山本祐大、入江大生、知野直人、京山将弥、育成では村川凪、堀岡隼人らがいる。
「キャンプのとき、宜野湾組のメンバーで同級生会を開いてくれて、すごく楽しかったんです。本当に同世代はいい刺激を受けますし、みんなで頑張っていきたいなって」
彼らが生まれた1998年といえば、偶然にもベイスターズが38年ぶりにリーグ優勝と日本一を達成したメモリアルイヤーだ。だが、あれから約26年、歓喜の時は残念ながらまだ訪れてはいない。
今季からキャプテンになった牧を中心とした98年世代が大活躍をして、再び栄冠を掴む――。新たな使者としてチームに現れた中川と話していると、そんなドラマチックなシナリオを、ふと考えてしまうのだ。
「ベイスターズがリーグ優勝したのは10月8日なんですけど、僕の誕生日は2日後の10月10日なんです。予定日は8日だったんですけどね」
そう言うと中川は笑った。つくづく縁の深い選手だなと思わずにはいられない。
こういった場で野球ができるは、本当に幸せ
また多くのDeNAファンも中川の入団をとても喜んでいる。惜しくも甲子園には届かなかったが、かつてハマスタで躍動した桐光学園のアンダースローを、野球王国・神奈川県の野球ファンはしっかりと覚えている。6日にハマスタで開催されたロッテ戦で、中川はマウンドから桐光学園のタオルを振っているファンの姿を見かけたという。
「すごく嬉しかったし、こういった場で野球ができるのは、本当に幸せなことです」
しみじみとした様子で、中川はつぶやいた。
一度は終わりかけた野球人生。しかし運命は流転し、中川にとって一番思い入れのある場所とチームで再びチャンスは訪れた。
「いい意味で、メンタル的にも割り切ってプレーできているので、さっきも言ったように球団に恩返しできるよう、1試合でも多く優勝に貢献したいですね」
ハマのサブマリンは、果たして敬愛する球団の歴史に名を刻むことができるか。迷いなく、心を燃焼させる日々を過ごせることを願ってやまない。
文=石塚隆
photograph by JIJI PRESS