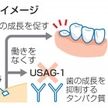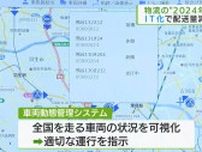古馬を相手に安田記念で3着に入り、武豊に「来年は全部持っていかれる」と予感させた“マル外の怪物”――名手たちがこぞって「世代ナンバーワン」と認めた逸材は、なぜ出口のないトンネルに迷い込んでしまったのか。長く競馬界を見つめる筆者が、ファンに鮮烈な印象を残した「消えた天才」の蹄跡を振り返る。(全2回の2回目/前編へ)
「能力だけならあの馬が世代ナンバーワンだろう」
1997年の春、田原成貴、横山典弘、蛯名正義、四位洋文といった騎手の座談会で、自然と1頭の旧4歳馬の話になった。
「距離適性などを抜きにして、能力だけならあの馬が世代ナンバーワンだろう」
そう見解が一致した。
後日、それを武豊に伝えたら「ぼくもそう思います」と頷き、「それだけに、路線の重なるシーキングザパールで負かしたいですね」と加えた。
トップジョッキーたちが認めた世代のトップホースとは――。
芦毛の外国産馬、スピードワールドである。
6馬身差の圧勝…圧巻だった京成杯
アメリカで生まれたスピードワールドは、市川不動産の所有馬となり、美浦の小西一男調教師が管理することになった。
デビューは1996年10月12日、東京芝1400mの旧3歳新馬戦。的場均を背に、4馬身差で圧勝。橋本広喜が騎乗した2戦目の府中3歳ステークスは5着に終わるも、的場に手綱が戻ると、ひいらぎ賞(500万下)、1997年初戦の京成杯、3月のクロッカスステークスと、すべて完勝で3連勝をやってのける。
なかでも圧巻だったのは京成杯だ。大外10番枠から1馬身ほど遅れたスタートを切り、徐々にリカバーして中団の外につけた。3、4コーナーを回りながら差を詰め、先頭に並びかけて直線へ。的場が鞭を右手に持ち替え、軽く促しただけで加速し、最後は流すようにして2着を6馬身突き放した。1頭だけ古馬がまじっているのではないかと思うほどの強さだった。
当時は外国産馬の出走できるレースが限られており、年明け3戦目として「マル外(外国産馬)のダービー」と言われていたNHKマイルCを目ざしていたが、捻挫のため回避。
ターゲットを歴戦の古馬が相手となる安田記念に切り替えた。主戦の的場がオークスで落馬負傷したため、田原成貴を鞍上に迎えることになった。
武豊の予感「来年は全部これに持っていかれるな」
田原が美浦に駆けつけて行われた1週前追い切りも話題になった。その年の皐月賞を勝った大西直宏のサニーブライアンと併せ馬をしたのだが、スピードワールドが並びかけて行かず、単走のような形になってしまった。サニーブライアンにとって、これはダービー当該週の重要な追い切りだった。大西は田原が追いついてくるのを待っていたのだが、田原は最後まで動かなかった。
大西は田原より3期下(デビューは2年遅いだけ)だ。「田原さんは感覚で乗る人だし、大先輩なので何も言えなかった」とのちに語ったが、追い切り直後、田原は大西に「お前の馬、すごく具合がいいな」と言ったのだという。結局、ブライアンはその週の土曜日にも大西が跨って稽古をつけ、翌日のダービーを勝って二冠馬となった。混戦クラシックを制した二冠馬と、同世代の「消えた天才」には、こうした縁があったのだ。
安田記念で、スピードワールドは、タイキブリザード、タイキフォーチュンという2頭の先輩外国産馬に次ぐ3番人気に支持された。古馬より4kg軽い54kgの斤量とはいえ、一頓挫あっての実戦だったにもかかわらず、これだけ高く評価されていたのだ。
スピードワールドは遅れ気味にゲートを出て後方を進む。直線入口でも先頭から7、8馬身離れた後方3、4番手だったが、馬群を割って伸び、勝ったタイキブリザードから2馬身弱遅れた3着となった。まさに負けて強しの内容で、上がり3ハロン34秒3はメンバー最速だった。
アメリカ調教馬アマジックマンで4着になった武は、スピードワールドの走りを近くで見て、「来年の短・中距離は全部これに持っていかれるな」と思ったという。
武豊を背にまさかの惨敗…狂い出した歯車
秋初戦の毎日王冠では的場が騎乗し、バブルガムフェローの3着。
そして、次走のマイルチャンピオンシップでは、この馬をライバルとしてずっと警戒していた武が騎乗することになった。「ユタカ人気」も手伝い、単勝3.3倍の1番人気。2年連続最優秀短距離馬となる、同い年のタイキシャトルを2番人気に押し退けての支持であった。しかし、結果は、勝ったタイキシャトルから大きく離された12着。再度武が騎乗したクリスマスステークスは4着と、相手が弱くなっても勝てなかった。
その後、翌1998年のオーロカップで柴田善臣が乗って2着、1999年の関屋記念で的場が騎乗して3着と、馬券圏内には2度入っただけで、旧7歳時の2000年11月19日のオーロカップで11着に敗れたのを最後に現役を引退、種牡馬となった。
種牡馬としては、地方競馬の重賞勝ち馬を数頭出すにとどまった。
種牡馬引退後は功労馬としてスピードファームで過ごし、2022年8月10日、28歳で世を去った。第2、第3の「馬生」も生き抜いたすえの大往生であった。
“主戦騎手の怪我”が不振のきっかけに?
本稿を読みながら「この馬も的場だったのか」と思った方は少なからずいるはずだ。
なぜ「この馬も」なのかというと、1990年に最優秀3歳牡馬となったリンドシェーバー、1990年代の終わりに活躍したグラスワンダーとエルコンドルパサー、そして、芝・ダートの二刀流で成功したアグネスデジタルといった外国産馬(それも競馬史に残る強豪)にも、的場が騎乗していたからだ。「的場均」といえばライスシャワーを思い浮かべる人が大多数かもしれないが、強いマル外の背でターフを沸かせた名手でもあったのだ。
それにしても、と思う。この「消えた天才」シリーズで前に取り上げたモノポライザーも、シルバーステートも、不振に陥ったり、路線に乗り損ねたりするきっかけに、自身の故障のみならず、主戦騎手の怪我も影響したように見受けられる。新たな鞍上がどんな名手であっても、特に若駒のときは、ちょっとしたリズムの変化がキャリア全体に響いてしまうほど、サラブレッドというのはデリケートな生き物なのだろう。
<「オーシャンエイプス編」とあわせてお読みください>
文=島田明宏
photograph by Sankei Shimbun