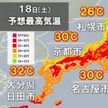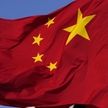政府が4月29日付で発表した春の叙勲で、タイガー・ジェット・シンが旭日双光章に選ばれた。
タイガー・ジェット・シンといえば、“インドの狂える虎”の異名を持ち、1973年の初来日以来、アントニオ猪木の敵役などで長年にわたり悪のかぎりを尽くしてきたヒールレスラーの代表格。しかしリングを降りれば、在住するカナダのトロントでさまざまな事業を展開する企業家であり、’80年代から子供や医療機関に対する慈善活動を続けてきた慈善家としても知られている。
東日本大震災の際は被災した子供たちへ義援金を送るなどの支援活動を行い、2021年2月には長年にわたる日本との友好親善への貢献が評価され、主宰する慈善団体「タイガー・ジェット・シン財団」は在トロント総領事から表彰も受けている。今回の旭日双光章も「スポーツを通じた日本・カナダ間の友好親善・相互理解の促進に寄与」したことを理由に受章したものだ。
タイガー・ジェット・シンが、猪木の闘魂に火をつけた
「ヒールは人格者が多い」とは、プロレス界で昔からよく言われることだが、タイガー・ジェット・シンは、まさにその筆頭と言えるだろう。
そしてレスラーとしてもプロフェッショナルであり、アントニオ猪木との抗争はまだ弱小団体だった初期の新日本プロレスが人気団体になるきっかけともなった。元・新日本プロレス営業本部長で、猪木vsモハメド・アリなど数々の大一番を実現させ“過激な仕掛け人”と呼ばれた新間寿は「猪木の闘魂の導火線に火をつけ、新日本プロレスの人気を爆発させたのがタイガー・ジェット・シンですよ!」と断言している。
アントニオ猪木が’72年3月に新日本プロレスを旗揚げした際、当時のプロレス団体の生命線ともいえる外国人レスラーの招聘ルートは、既存の日本プロレスと国際プロレスに完全に握られており、テレビ局のバックアップもない、苦しい船出だった。当時のことを新間はこう振り返る。
「新日プロの旗揚げ当初は、本当に大変でしたよ。とにかくお金もないし、レギュラーのテレビ放送もないという、ないないづくし。あるのは、レスラーと社員のやる気だけだったね。とくに困ったのが、外国人レスラーの招聘ですよ。なんとか猪木の師匠格であるカール・ゴッチの協力こそ取り付けたものの、その他はドランゴ兄弟にブルックリン・キッド、インカ・ペルアーノなど、誰も知らない2流、3流レスラーばかりだった。いくら宣伝カーを走らせて、街角にポスターを貼りまくっても切符なんて売れやしない。とにかく最初の1年は借金ばかりがかさんでいく状態だったね」
「俺だって頭が痛いよ」猪木の苦悩
その猪木・新日本から遅れること半年、’72年10月に日本プロレスから独立したライバルのジャイアント馬場が全日本プロレスを設立。こちらは最初からプロレス中継の老舗である日本テレビの全面バックアップを受け、世界最大のプロモーター連帯組織であったNWAからのレスラー招聘を独占することにも成功。スタートから完全に“メジャー”であった。
「私がNWAの総会に初めて出たとき、アメリカのプロモーターの馬場さんに対する信頼度というのを、嫌というほど痛感させられましたよ。アメリカのレスラー招聘ルートの98%は、すでに馬場さんが押さえていた。だから、無名外人ばかりだった新日プロに比べ、馬場さんの全日プロは最初から凄かったじゃない。もうマディソン・スクエア・ガーデンがそのまま移ってきたような豪華メンバーだったからね。だから馬場さんの全日プロは豪華客船のファーストクラスでの船出であり、対する猪木・新日プロは丸太のいかだのようなもの。いつ沈没してもおかしくなかったんですよ」
旗揚げ当初の新日本プロレスは、猪木の当時の妻である倍賞美津子が宣伝カーに乗り込みウグイス嬢までやるなど、必死の営業活動を続けたが客足は一向に伸びなかった。やはり日本人vs外国人の対決が主流だった当時のプロレス界において、魅力的な外国人レスラーの存在は必要不可欠なものだったのだ。
「だから私は猪木さんに何度も言いましたよ。『社長、外人なんとかならないですか?』と。すると『新間、俺だって頭が痛いよ』なんて言って、猪木さんも困り果てていたね」
そんなときに新間が知人から紹介されたのが、タイガー・ジェット・シンだった。
「あるとき、リキさん(力道山)の古い友人で貿易の仕事をしていた人物に『インドに凄いレスラーがいる、そいつを呼ばないか?』と持ちかけられたんですよ。写真を見せてもらったら、ターバンを巻いて、ヒゲをたくわえたハンサムなレスラーが写っていた。もともとインドのプロレスラーというのは、戦前にグレート・ガマという伝説的なレスラーがいたり、さらに力道山と名勝負を繰り広げたダラ・シンなんかもいて、神秘的な魅力を持っていたので、『これは、イケるんじゃないか』と思ったんだよね」
サーベル片手に大暴れ「何事か!」警察に苦情電話も
こうしてタイガー・ジェット・シンは、73年5月に初来日する。
「いざ来てみると、シンは想像以上の男だったね。まず身長、体格、ルックス、すべて非の打ち所がなかった。そして試合をしてみたら凄いのなんの。技といったらパンチと蹴りくらいしか使わないんだけど、サーベル片手に大暴れしてね。あまりの暴れっぷりに、例えば名古屋で試合があったときなんかは、愛知県警に電話がいっちゃうんだよ。『タイガー・ジェット・シンのサーベルを取り締まらないとは何事か!』っていうね(笑)。
だから私自身、警察に呼ばれて、サーベルの実物を持って説明に行ったこともありますよ。あのサーベルの剣先は丸まっていて刺さらないようにはしてあるんだけど、警察は『新間さん、観客の安全のために、剣先を包帯みたいなものでぐるぐる巻きにして、タンポ槍(練習用に先端をゴムや綿を入れた布で包んだ槍)みたいにしてくれ』なんて言われてね。しょうがないから、言われたとおりにしたんだけど、いざ試合になったら、シンはすぐそんなものは取っちゃって、また大暴れしていたね」
こうして話題が話題を呼び、タイガー・ジェット・シン効果で新日本プロレスの興行人気は上昇。さらにちょうど坂口征二が入団し、NET(現在のテレビ朝日)での念願のテレビ放送がスタートしたこともあり、猪木vsシンの興行人気は一気に火がついた。
この猪木vsシンの大ヒット要因は、シンの暴れっぷりだけでなく、猪木の変貌ぶりにもあった。それまで猪木は、カール・ゴッチの流れを汲む正統派の戦いを売りにしていたが、シンとの喧嘩ファイトで、“怒りの猪木”という新たな魅力が爆発。また正義vs悪の勧善懲悪という日本人が最も好む分かりやすい図式もあり、猪木ファンが急増することとなったのだ。
「だからシンのヒールとしての暴れっぷりも凄かったし、そのシンの攻撃をすべて受けられるだけの身体を作り上げた猪木も凄かった。そういう意味では、タイガー・ジェット・シンが猪木の力と魅力を引き出したとも言えるし、猪木がいたからこそ、シンは日本でトップレスラーになることができた。あの二人だからこそ、あれだけの抗争に発展したのだと思いますよ」
「シンは誰だろうが本気で襲ってくるからね」
事実、猪木とシンの抗争は、それまでのプロレスの乱闘の常識を超える迫力に満ちていた。シンの反則は日に日にエスカレート。それに対し猪木の反撃も激しさを増し、ついには’74年6月の大阪大会で、猪木がアームブリーカーを連発して、シンの“腕折り”にまで発展する。
「やっぱり、なんとかジャイアント馬場さんを上回りたい猪木さんと、なんとか日本でのし上がりたいシンという両者の強烈なハングリー精神が、試合をより激しいものとし、観客を惹き付けていったんだろうね。本当に猪木さんとシンの試合のときは、我々、会社の背広組もマスコミも震え上がっていたくらいだから。シンなんて、お客の前では記者だろうが誰だろうが本気で襲ってくるからね。タイガー・ジェット・シンという男は、普段はジェントルマンなんだけど、あのコスチュームを身につけた瞬間、身も心も“狂える虎”になれる男だったね」
シンの暴れっぷりというのは、試合の興奮で見境がなくなってしまうわけではなく、もちろんプロ意識の現れでもあった。
「地方巡業に行ったとき、NETの放送がない地域なんかに行くと、観客が300人なんていうところもあった。そんなとき、レスラーはみんな手を抜いて、試合も早く終わらせようとするんだけど、シンは違ったね。『こういうときこそ、今日来た観客がまた来たいと思うように、徹底的にやらなきゃいけないんだ』って。場外を暴れ回って、試合が終わったあと、さらに10分も15分も乱闘してたりしたからね」
シンのヒールとしてのプロ意識は徹底しており、70〜80年代はファンに対して記念写真やサインはおろか、笑顔を見せることすら一切なく、目が合った人間は誰でも襲うという“狂人”ぶりを完璧に演じていた。しかし、その素顔は大変な紳士であり、慈善家であることが明らかにされている。
「ヒールとは、自己を犠牲にできる人格者たち」
「ヒールというのは、みんな人格者ですよ。自分が悪となり、ベビーフェイスの魅力を引き立てるという、自己を犠牲にできる人たちだからね。シンなんかその最たる人ですよ。本国に帰ると彼は様々な慈善活動を行なっていて、恵まれない子供たちのためにおもちゃを贈る活動をしたり、タイガー・ジェット・シンの名前が付いた学校も建てているからね。一度、カナダにある彼の自宅に招かれたことがあるんだけど、地元の名士で凄かったよ」
シンは東日本大震災が起きてすぐ「タイガー・ジェット・シン基金」を立ち上げ、日本の国旗を連想させる赤と白のリストバンドを5ドルで売り出し、収益のすべてを義援金として寄付。さらに『タイガー・フェスタ』という震災復興チャリティプロレス興行も開催し、その収益も義援金として寄付している。
「そんなタイガー・ジェット・シンが、リングに上がれば悪のかぎりを尽くすわけだからね。プロレスは底が知れないよ、奥が深い。しかし、いまはシンのような本物のヒールがいなくなってしまったね。見た目だけシンや上田馬之助さんに似せたヤツはいるけど、形だけ似せても、覚悟と心が伴わなきゃどうにもならないだろう。シンや上田さんは、私生活をすべて隠して、プロとしての仕事を全うしたわけだからね。ヒールなら、ファンが5メートル以内に近づけないようなレスラーになれ! 怖くて目も合わせられないくらいになれ! と言いたいね」
コロナ禍以降、集客低迷からの復活を目指している今の日本のプロレス界。タイガー・ジェット・シンのような真のヒールが必要とされているのかもしれない。
文=堀江ガンツ
photograph by AFLO