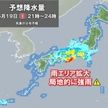壮絶な叩き合いのすえ、日本の人馬が世界の頂に、あと一歩のところまで迫った。
アメリカ競馬の最高峰、第150回ケンタッキーダービー(5月4日=日本時間5日、チャーチルダウンズ・ダート2000m、3歳GI)で、坂井瑠星が騎乗するフォーエバーヤング(牡、父リアルスティール、栗東・矢作芳人厩舎)が僅差の3着と健闘。ゴール前では日本馬初の快挙達成か、と思われた惜敗であった。
もう1頭の日本馬、テーオーパスワードも5着と好走した。
大接戦に敗れた矢作師「ただひと言、悔しいです」
20頭立ての11番枠から遅れ気味のスタートを切ったフォーエバーヤングは中団馬群の後ろに待機。3、4コーナーで外から進出し、外のシエラレオーネと馬体を併せて猛然と末脚を伸ばした。直線でシエラレオーネに何度も馬体をぶつけられながらも、先に抜け出したミスティックダンとの差を詰める。内のミスティックダン、真ん中のフォーエバーヤング、外のシエラレオーネの3頭が横並びになったところがゴールだった。
勝ったのはミスティックダン。鼻差の2着がシエラレオーネ。さらに鼻差の3着がフォーエバーヤングという大接戦だった。
フォーエバーヤングを管理する矢作芳人調教師は「ただひと言、悔しいです」と声を絞り出すように振り返った。
「馬は素晴らしかったです。すごくよく頑張ってくれました。本当に、日本の馬はまったく慣れないような環境のなか、これだけ走れる彼には頭が下がります。ただ、あそこまで行ったんで、勝ちたかったです。この経験は今後に生かさなければいけないし、間違いなく生きてくると思います。世界一の馬になれるよう、一緒に歩んでいきたいですね」
日本の人馬が挑んだ「スポーツで最も偉大な2分間」
2021年、矢作師が管理したラヴズオンリーユーがブリーダーズカップ(BC)フィリー&メアターフ、マルシュロレーヌがBCディスタフを制し、世界中に日本馬の強さを見せつけた。
日本で「競馬の祭典」というと日本ダービーだが、アメリカの「競馬の祭典」は、ひとつの競馬場で2日間にわたっていくつものカテゴリーのGIが開催されるBCである。素晴らしく華やかなレースだが、しかし、1984年創設と歴史は浅い。
それに対してケンタッキーダービーは今年で150回目を迎える伝統の頂上決戦で、「スポーツで最も偉大な2分間」とも言われているアメリカ競馬の牙城だ。日本馬で初めて参戦したのは1995年のスキーキャプテンで、武豊を背に14着。これまでの最高着順は、2019年マスターフェンサー、2023年デルマソトガケの6着だった。
日本人騎手では、2016年にラニで臨んだ武豊の9着が最高着順だったが、今年、坂井瑠星と、5着に入ったテーオーパスワードの木村和士(北米を拠点に騎乗)が更新した。
生産頭数は日本の倍以上…アメリカ競馬のスケール
アメリカは世界最大のサラブレッド生産国で、日本の倍以上の生産頭数を誇る。競馬場はすべて左回りで、コース幅が広く取れて観客に近い外側のメイントラックはダートである。日本のダートが「砂」なのに対し、アメリカのダートは「土」に近く、雨が降ると田んぼのようにぬかるむが、そのかわり、クッションがよく、日本の芝に近いほど速い時計が出ることもある。
いささか乱暴な言い方になるが、アメリカンフットボールやインディカーレースを見てわかるように、アメリカのスポーツのスタート地点は「アンチヨーロッパ」が基本で、自分の国でやる限り、ほかのどの国にも負けない形を編み出す。そして、MLB(メジャーリーグベースボール)もそうであるように、アメリカ国内の王者であっても「ワールドチャンピオン」と称する。
競馬も、芝がメインのヨーロッパの馬に負けないよう、先述したように、メイントラックをダートにしたわけで、その最高峰がケンタッキーダービーである。
1971年にベネズエラ調教馬のキャノネロが勝っており、これが唯一の外国調教馬による優勝だが、この馬はアメリカ産なので、アメリカのホースマンは「外国にやられた」という感覚ではないかもしれない。
私は1990年の夏に初めてアメリカの競馬場(アーリントン国際競馬場=当時の名称)に行き、洗い場につながずに馬を洗ったり、狭い厩舎内の通路で曳き運動をしたり、放馬しても「ポニー」と呼ばれる大型馬に乗った関係者が馬体を寄せて簡単につかまえたりするシーンを見て衝撃を受けた。女性の調教助手が馬房で横になった馬に添い寝して歌っているかと思えば、どの騎手も凄まじいアクションで追いながら馬を真っ直ぐ走らせている。
当時は、岡部幸雄氏や、武豊が向こうの条件戦を勝つだけで「世界のオカベ」「世界のユタカ」と報じられた。そんなふうに見上げる高みにあったアメリカ競馬の頂上決戦で日本の人馬が激戦を繰りひろげ、負けたら国内のレースと同じように悔しがるシーンを見て、日本の競馬はここまで来たのだな、と隔世の感ではないが、嬉しくなった。
坂井瑠星の騎乗も“ワールドクラス”だった
前述したスキーキャプテンも、1998年に日本調教馬として海外GI初制覇を果たしたシーキングザパールもアメリカ産馬だった。
ところが、フォーエバーヤングは、父リアルスティールの日本産馬(ノーザンファーム生産)で、馬主がサイバーエージェント代表の藤田晋氏という、純然たる「チームジャパン」である。リアルスティールの父はディープインパクトで、その父はケンタッキーダービーを勝ったサンデーサイレンスだから、サンデーの血が母国で爆発したとも言える。日本のホースマンもファンも、「世界最高峰」というと、フランスの凱旋門賞ばかりを思い浮かべがちだが、生産界をあげてサンデーの血を熟成しているうちに、いつの間にか、「もうひとつの最高峰」であるアメリカのダートの頂上に近づいていたのかもしれない。
私は、かつて3頭の日本馬が2着になった凱旋門賞より、ケンタッキーダービーのほうが日本馬から遠いタイトルだと思っていたのだが、認識を改めるべきなのか。
それにしても、自身が管理したリアルスティールの産駒で、弟子の坂井瑠星を主戦とし、前走のUAEダービーまで5戦全勝でここに来た「世界のヤハギ」の手腕には感服するばかりだ。
「勝てなかったことは本当に悔しいです。まだ負けていなかった馬で負けてしまいましたけど、この馬の背中にふさわしいジョッキーにならなければいけないと思います」
そう話した坂井の騎乗も見事だった。勝負所で、もうひと呼吸動くのが早かったら最後の伸びが鈍っただろうし、遅くなっていたら他馬に先に行かれてもっと外を回らされることになったかもしれない。
直線では、外のシエラレオーネに押し込まれ、ぶつけられてもバランスを崩さず追いつづけた。そのまま押圧されるのではなく、鞭を右から左に持ち替え、押し返しながら真っ直ぐ走らせた騎乗は、間違いなくワールドクラスのそれだった。
シエラレオーネ鞍上の動きは“妨害”だったのか
ゴール前で、シエラレオーネの鞍上のタイラー・ガファリオンが、鞭を持った左手でフォーエバーヤングを押したように見えた。あれは、自分の馬が内に刺さるのを、手綱だけでは矯正し切れず、距離を取ろうと思わず手が伸びたのではないか。ガファリオンとしては、横並びになった3頭のなかで自分の馬の脚色が一番よかったので、できることなら両手で追いつづけたかったはずだ。坂井の動きを妨害しようとしたわけではないように、私には見えた。
フォーエバーヤングにとっては、外のシエラレオーネも伸びていたから一緒に追い込めた部分もあったが、ぶつけられたロスはゼロではなかった。間違いないのは、坂井がフォーエバーヤングを真っ直ぐ走らせるために、でき得る最善の騎乗をした、ということだ。
昨年、坂井は、同じ矢作厩舎のコンティノアールでこのレースに出るはずだったが、左後肢の歩様の乱れが回復せず、レース前々日に出走取消となる悔しさを味わった。
今年のケンタッキーダービー惜敗は、1999年の凱旋門賞で「勝ちに等しい」と言われたエルコンドルパサーの2着、2012年の凱旋門賞で圧勝かと思われながら最後に差されたオルフェーヴルの2着と並び、語り継がれる「世界戦での惜敗」となるのではないか。
名勝負であったことは確かだが、 願わくは、次に見られる世界での名勝負では、日本馬が先頭でゴールしてほしい。
頂のすぐ近くまで来たチームジャパンの今後に注目したい。
文=島田明宏
photograph by Getty Images