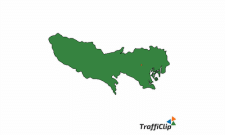ウィンブルドン女子ダブルスで頂点に立った伝説的テニスプレーヤー・旧姓沢松和子氏の伴侶である吉田宗弘氏が、千葉県柏市に創設した吉田記念テニス研修センター(TTC)。この施設から、齋田悟司、国枝慎吾ら、車いすテニスのレジェンドたちが羽ばたいていった。そのきっかけとなったのが、1985年に福岡県飯塚市でスタートした「飯塚国際車いすテニス大会」。世界への登竜門となった同大会の精神は時代を越えて、今も受け継がれている。
(文=内田暁、写真=Getty Images)
オーストリアの国立スキー学校で受けた刺激
現在、吉田記念テニス研修センター(TTC)の代表理事を務める吉田好彦氏には、父の宗弘氏から聞かせてもらった、忘れがたい体験談がある。
まるで子どもの頃に読み聞かせてもらったお気に入りのおとぎ話を語るように、好彦氏はよどみなく、“半世紀ほど前の出来事”を述懐した。
「父の話では、TTCのような施設を作ろうと思った原体験の一つに、オーストリアの国立スキー学校で受けた衝撃があるようなんです。
1970年前後だと思うのですが、スキーが好きだった父は、オーストリアのスキー学校に通っていたんです。最初はちゃんとした生徒というよりは、もぐりこんで授業を聞いていた、いわゆる“耳学問”だったようですが。
その時に父が最初に受けた授業が、病院の見学だったそうです。スキーのインストラクターには、普段は理学療法士として働いている人も多かったからでしょう。その授業でいきなり切断手術の様子などを見て、父はかなり衝撃を受けたと言っていました。
同時に、リハビリをしている人たちが社会復帰に前向きで、明るく、その様子にも驚いたそうです。若い女性が義足をつけて、おしゃれして出かけたりして。当時の日本はまだまだ、障がいを負った人は家で静かにしている、という風潮だったので、その違いにも衝撃を受けたそうなんですね。過去にそういうのを見ていた経緯があるので、父の頭の中には、スポーツはそういうことにお役に立てるという、強い思いがあったんでしょうね」。
時流に合致したTTCの理念
この時の原体験が撒かれた種なら、萌芽の時が、1986年の飯塚国際車いすテニス大会観戦だろう。
「飯塚の大会に両親が招待された時、僕も一緒に行ってました。そこで父は東京近郊の選手たちから『練習する場所がなかなかないんです』と聞き、『だったらうちのクラブに来て良いよ』と言っていたんです。
実際に車いすの選手たちが千葉に来て練習もするようになった時に、父は『自由に使ってもらって構わないよ。ただ、自分でできることは自分でやってね』と、車いすの方たちを特別扱いしなかった。準備や片づけなども他の方々と同じようにさせ、ダメなものはダメだと言った。
その代わりに、『施設で使い勝手の悪いところは言ってもらいたい、改善すべきところを教えてほしい』と父はたずねたんです。彼らからは、いろんなことを教わりました。ちょっとした段差が車いすの方には大変なこと。お手洗いの扉にしても、内開きだと車いすの方は中に入ると扉が閉められない。そういう車いす利用者の方たちの意見も取り入れて、今のTTCの施設を作っていったんです」。
かくして、1990年に千葉県柏市でオープンしたバリアフリーなテニスセンターの評判は、人から人の口を伝い、全国の車いすテニスプレーヤーの間に広まったのだろう。1992年のバルセロナ・パラリンピックに車いすテニスが加わるなど、時流との合致もあった。
一方で、日本人選手の世界への挑戦という面では、まだ厳しい戦いが続いていた。1994年に、世界の上位8選手による“車いすテニスマスターズ”がNECを冠スポンサーとして発足するが、90年台は男女ともに、日本人の出場選手は存在しない。
ただ90年台の最後の年、まるで新時代への扉を開くかのように、一人の選手が、“車いすテニスで生きていく”覚悟を固める。それが、1996年のアトランタ・パラリンピックに出場し、今なお現役で活躍し“レジェンド”と呼ばれる、齋田悟司である。
齋田悟司が開いた新時代の扉
「やっぱり国際ステージでのパイオニアといえば、齋田さんです」と、吉田好彦さんは明言した。
「父は、車いすテニス選手がアスリートとして認められる環境を作ろうとしていましたが、そのなかで大きかったのが、齋田さんですね。齋田さんは三重県のご出身で、四日市の市役所にお勤めになっていたんです。そこから、もうもう一念発起! 車いすテニスに専念すべく、市役所を退職して、うち(TTC)に来たんです」
まだ日本ではパラリンピックの存在すら、広く認識されていない時代。車いす競技で身を立てている選手は、世界的に見てもそこまで多くはなかっただろう。
吉田さんの記憶としても、市役所という安定した職場を辞する齋田を、周囲はとても心配したという。それでもTTC理事長の宗弘氏は、齋田の全面的な支援を約束した。千葉市の車いすメーカーが、社員選手として齋田を採用したことも、大きな後押しとなる。周囲の制止の声を振り切って、齋田は三重県から千葉県に移り、TTCで本格的にテニスに打ち込みはじめた。1999年春のことである。
前述した、日本車いすテニス協会の前田惠理会長にとって、飯塚国際車いすテニス大会の男子シングルスを日本人選手が制することは、一つの悲願だった。
大会創設から17年後、ついにその願いが叶う。実現してくれたのは、他でもない齋田。2002年の第18回大会にて、男子シングルスのトロフィーを掲げた。
その2年後のアテネ・パラリンピックで、齋田はダブルスで金メダルをつかみ取る。この時のパートナーが、当時20歳の国枝慎吾さん。2人は、日ごろ同じTTCで腕を磨く、いわば同門である。
国枝さんにとっても、このアテネでのダブルス金メダルは、キャリアにおける一つのブースターとなった。2年後の2006年、国枝さんは飯塚国際車いすテニス大会を初制覇。そのさらに2年後には、北京パラリンピックで、シングルス金メダルも獲得する。国枝さんが大学職員の席を辞し、車いすテニス選手として日本初のプロ転向を宣言したのは、翌2009年のことだった。
「車いすテニスをスポーツとして見てほしい」
「飯塚国際車いすテニス大会は、僕と同じ歳だと思うんですよ」と、40歳を迎えた国枝さんは、感慨深げに言う。国枝さんが生まれたのは1984年。同大会が正規の国際大会として開かれたのは1985年だが、その前年にスタートアップ大会が開催されているので、両者はまさに“同期”だと言える。
前田会長はその40年の歴史の中で、大会の発展をつぶさに見聞し肌身で感得してきた。ただそれは、大会そのものの変化や拡張というよりは、周囲の人々や社会の変容であり、成長と言えるかもしれない。
齋田の初優勝や、国枝さん、そして女子の上地結衣らの活躍により、徐々に大会の知名度や観客も増した。2021年の東京パラリンピック以降は、特に選手たちの知名度の急上昇を感じたという。
ただ前田さんにとって忘れられないのは、それより以前の、ある出来事だ。
「地元に飯塚高校という、甲子園にも出るような野球の強豪校があるんですね。その野球部の生徒たちたちを、大会に招待したことがあったんです。ちょうど北京パラリンピックの翌年だったのかな。私も客席で国枝さんの試合を見ながら、隣にいた生徒さんに『あの選手は、北京パラリンピックの金メダリストよ。国枝さんが見られて、いいタイミングで来たね』って言ったんです。そうしたらその生徒さんが、国枝さんのプレーを見て『かっこいい!』って言ったんですよ。17歳くらいの野球をやっている子が、『かっこいい、俺、あれ(競技用車いす)に乗ってみたい!』って。その時ね、もう涙が出ました。
それまでは大会を見にきてくれた方も、大概『かわいそかねー』とかね、『不自由しよんしゃろ、でもよう頑張っとるね』と言っていて、そういう言葉を私はずっと聞いてきた。それがこの時、高校生が『かっこいい、俺もやりたい』って。この時にはもう、『きたー! これが聞きたかった』って涙出ましたよね」。
それは前田さんが燃やし続けてきた、「車いすテニスをスポーツとして見てほしい、選手をアスリートとして見てもらいたい」の願いが、これ以上にない形で結実した瞬間だった。
レガシーではなく、受け継がれるトーチとして
コロナ禍による中断を経て、4年ぶりに海外選手も参戦して開催された、2023年4月の飯塚国際車いすテニス大会——。男子シングルス決勝戦が始まる前から、スタンドで席取りをする観客たちは、「いよいよだね!」と試合開始を待ちわびた。
最終的に単複を制した16歳(優勝当時)の小田凱人が会場内を移動すると、ボールキッズの間から歓声が沸き、小田は観客や子どもたちに取り囲まれた。なお小田が初めて飯塚の大会会場を訪れたのは、12歳の時。まだ公式戦には出られなかったが、突出した才能と情熱で、大会関係者たちに鮮烈な印象を残したという。
そのような光景を見やりながら、前田さんは、しみじみと言う。
「TTCの吉田理事長と奥様の和子さんは、何度も飯塚にお見えになっているんです。大会の発起人とも言える麻生(泰)さんが第2回大会にお二人をご招待していなかったら、私は、こんにちの日本の車いすテニスの発展は、ここまで来ていないんじゃないかと思います」。
かつて車いすテニス選手の練習拠点といえば、九州かTTCが中心だった。だが現在、世界2位の小田は愛知県出身で、今も地元を拠点とする。29歳で最高位世界1位、現2位の上地も、長く地元の兵庫県で腕を磨いた。
39年前に飯塚市で誕生した、車いすテニスの国際大会。その精神は“レガシー=遺産”ではなく、今なお熱を帯びるトーチとして、人から人へと受け継がれ、各地に燃え広がっている。
<了>