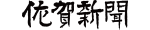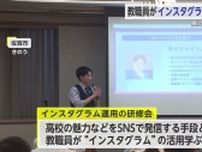第三章「真夜中に鳴く」(12)
――え。じゃあ、もしや……。
「サケちゃん。ひょっとして、さっきからスタジオでニャアニャア聞こえるのって、ニャンタが鳴いてるのかな!?」
アンジェリカも同じことを考えていた。
「ひょっとしなくても、そういう話の流れですよね……」
「なんかワクワクするね!」
「そうですか!?」
引きつった顔の昇太に、少女は「うんうん」と頷いた。
「だってあたしも猫好きだしさ! 知ってる? 猫好きに悪い人はいないんだからね。きっと幽霊もそうだよ」
アンジェリカは思い切りドヤ顔をして見せた。
「幽霊猫のニャンタも絶対可愛(かわい)いと思うよ、声も可愛いし。見えないけど」
僕は生きてる猫が好きです――と昇太は思うのだった。
『ところで、アンジェリカさんのラジオは、霊界でもよく聴こえます』
「あ、霊界なのね。ていうか、天国と地獄と霊界の違いってなんなのかな、よく分かんないけど。ええと、メッセージの続きは、続きは……」
『僕はラジオを持ってないんですけど、この番組は、空から音が降ってくるような感じで聴こえてくるんです』
「へええ。空から音が降って来るって、素敵(てすき)な表現! 徘徊霊さんは、なかなか詩人だねえ」
少女が心の底から感じ入ったように頷く。
昇太は「詩人じゃなくて、死人ですけどね!」と突っ込もうと思ったが、何となく不謹慎な気がして止(や)めた。三秒後に「やっぱ言えば良かったかな」と後悔したが、時すでに遅し。気の利いたトークには瞬発力が必要で、生放送では、逡巡(しゅんじゅん)は禁物だ。
逆に、練りに練ったネタは大抵空振りしてしまうものだし、その最たる例が今夜のぎこちないオープニングトークである。
そもそも着地点が定まった『予定調和』なトークは、ディレクター陽一が本来、最も嫌うところだった。
――ていうか俺、こんなオカルト現象の真っ最中に、トークのテクニックを考えているなんて、ちょっと異常な心理状態なのかも――と考えるのは、昇太の中の冷静な部分だった。
『という訳で最後になりますが、結構、幽霊でこの番組聴いてる人って多いと思いますよ。生きてる人の間でも、人気出るといいですね!』
まるで合いの手のように、猫の声が暗闇から「にゃあ」と聞こえた。
「ほっとけ!」と、アンジェがすかさず突っ込んだ。