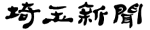秩父地域の食卓に欠かせない漬物「しゃくしな漬」。歯切れのよいシャキシャキとした食感があり、かむほどにうまみが広がる。適度なしょっぱさとあめ色の艶が食欲をそそる。酸っぱくなった古漬けは油で炒め、しょうゆや鷹(たか)の爪で味付けしても絶品。まさに最強の“飯の友”だ。
秩父地方の伝統野菜、しゃくし菜の正式名称は「雪白体菜(せっぱくたいさい)」。葉の形が「飯じゃくし(しゃもじ)」に似ていることから、秩父ではこう呼ばれている。
「この辺の土壌は硬く、ダイコンが育ちにくい。その代わり、それほど根を張らないしゃくし菜を育て、冬の保存食としてどこの家でも漬物にしたものだ」と石川漬物(埼玉県小鹿野町)社長の石川雅章(56)は言う。以前は、各家庭でしゃくし菜を大きな樽(たる)で漬け込むのが晩秋の風物詩だった。
「しゃくしな漬」を最初に商品化したのは石川漬物の先代社長で父の幸次(84)だ。幸次は都内の漬物会社で働いた後、1963年に独立。秩父や長野などから野菜を買い付け、樽漬け(塩漬け)したものを市場に卸した。
当時は各家庭で漬物を漬けるのが当たり前の時代。赤字が続き、売れ残った大量の漬物は廃棄せざるを得なかった。「子どもの頃、ごみ処分場に捨てに行く父親について行ってね」。漬物だけでは生計を立てられず、幸次はトラック運転手などをして家族を養った。
転機は、69年の西武秩父線の開通だ。西武秩父駅の売店の担当者が、秩父の土産物として「しゃくしな漬」に目をつけた。売り場では小さな樽に入れて販売していたが、丈のあるしゃくし菜を縦長の袋パックに詰めたアイデアも客の心を捉えた。
しゃくし菜の収穫は10月末から始まる。昨年、石川漬物では約300トンのしゃくし菜を契約農家やJAちちぶ(秩父市)から買い付け、仕込みを行った。根元に土やごみが残らないよう洗浄を繰り返し、半月ほど下漬けをして、乳酸発酵を促す本漬けに進む。発酵しすぎると変色しやすく酸味も強くなるが、長年の試行錯誤で幸次が編み出した技術により、風味と色はそのままに品質を一定に保つことができるようになり、通年出荷が可能となった。
県内外にファンが多いが、販路を大きく広げる考えはないという。「どこでも売っている全国区の商品にしたいとは思わない。地元に根差しながら、目の行き届く範囲で丁寧に作ることのほうが大事」。“秩父の味”を真摯(しんし)に守る。(敬称略)
■県内土産の人気上位
しゃくし菜はチンゲンサイを大きくしたような形で、背丈が約50〜80センチほどに育つ。明治初期に中国から伝わったとされ、昭和初期まで国内各地で生産されていた。しかし、ハクサイの生産が広まるにつれて姿を消し、秩父地方など一部地域が産地として残った。
秩父地方の農家では8月下旬〜9月上旬に種をまき、10月末〜12月初旬に収穫。収量も見込めるため、農閑期の農家にとっても格好の野菜だ。しゃくし菜の漬物はご飯の副菜としてでなく、刻んでおやきのあんや、お茶漬け、ピザやギョーザに入れるなど、洋風や中華とも相性が良い。
JAちちぶ(秩父市)では昨年、26軒の契約農家から、しゃくし菜約120トンを集荷。そのうちの約半分を皆野農産物加工センターで「ちちぶ菜漬」などに加工して販売している。地元の婦人会や青果店が製造したものも道の駅などに並ぶ。石川漬物でも小鹿野町の黄金カボスを使った「しゃくしな漬」を4月に限定販売、地場産品とのコラボ商品を開発している。
県物産観光協会によると、物産観光館「そぴあ」(さいたま市大宮区)の2023年3月〜24年3月26日の総合売上額で「しゃくしな漬」は4位。毎年上位にランキングされる人気商品という。
西武線で広がった“秩父の味” 風土が生んだ伝統野菜の漬物「しゃくしな漬」 ファン増えても地元で地道に

スゴ得でもっと読む
スゴ得とは?関連記事
おすすめ情報
埼玉新聞の他の記事もみるあわせて読む
-

米どころ 奥州市で田植え始まる 本格的な農作業シーズン到来<岩手県>
岩手めんこいテレビ4/30(火)18:45
-

「雪の下で春を待つから甘くて美味しいのかな」毎朝5時過ぎから畑へ アスパラガスの収穫が最盛期
SBC信越放送4/30(火)18:09
-

家族連れがリゾート施設で田植えに挑戦!米が食べられるようになるまでの工程を体験「お米の学校」
とちテレニュース4/30(火)17:42
-

半数近くの家倒壊し2人死亡…輪島市門前町の高根尾地区で小学生が“希望の田植え” 子供達の元気な声響く
石川テレビ ニュース4/30(火)17:25
-

高校キムチ部『全国漬物グランプリ優勝』『大手メーカーと商品化』の次は…なんと書籍発売! これまでの“奇跡と軌跡”をたどる
MBSニュース4/30(火)17:05
-

黄金色の果肉 マンゴー5000個“鈴なり”さつま町で収穫祭 鹿児島
南日本放送4/30(火)16:04
-

暑い日に食べたい!アイスクリーム万博 あいぱく おすすめ商品3選
テレビユー福島4/30(火)15:30
-

【2024年版】お菓子以外の北海道土産27選!甘いものが苦手な人に喜ばれるお土産
北海道Likers4/30(火)14:00
-

秋田で「いぶりがっこ」ドレッシング 「刻みいぶりがっこ」入り
みんなの経済新聞ネットワーク4/30(火)12:34
-
-

玉ねぎ丸ごとごはんにドン!? 新玉ねぎだからこそ叶う、ワイルド&繊細な“旬メニュー”とは
ラジトピ ラジオ関西トピックス4/30(火)11:55
-

経済変動・伝染病等対策資金 貸付限度額を1000万円に引き上げ 宮崎県
宮崎ニュースUMK4/30(火)11:54
-

懐かしいふるさとの味…物産館で人気の「漬物」「梅干し」が消える…かも? 法改正で製造基準が厳格化 個人出荷に高いハードル
南日本新聞4/30(火)11:32
-

衆院長崎3区補選で当選 山田勝彦さん 「政治改革へ自覚と責任」【インタビュー】
長崎新聞4/30(火)11:00
-

平均年齢70歳以上! 西日本有数のごぼうの産地で誕生した、幻の「ごぼまん」って?
edit Oita エディット大分4/30(火)10:29
-

【復興臨時支局・飯舘村編】アルストロメリア出荷本格化 福島県飯舘村の誇り鮮やか
福島民報4/30(火)10:14
-

いつも新商品に出会える♪身体に優しいパン屋さん 大蔵谷駅近くにあるパン屋さん「ぶれっふる」のパンでお腹も心も満たされました 明石市
Kiss PRESS4/30(火)8:00
-

和倉温泉 活気取り戻せ 能登ミルク再開 地物ジェラート復活へ一歩
中日新聞Web4/30(火)5:05
-

伊勢の子ら、初穂曳に備え田植え
中日新聞Web4/30(火)5:05
-
関東甲信越の主要なニュース
埼玉 アクセスランキング
-
1

懲戒処分…アダルトビデオに出演した消防士 匿名の情報提供あり、写真も添付され発覚 友人に勧められた26歳、5回も出演…報酬は計25万円だった
埼玉新聞4/30(火)14:56
-
2

<高校野球>埼玉県大会、きょうベスト8決定へ 聖望学園と坂戸以外のシード勢が勝ち上がる 活躍の各投手ら期待 きょう4球場で8試合、注目カードや見どころは
埼玉新聞4/30(火)9:31
-
3

イオンの巨大モールに、子が生まれ夫婦で訪れ… 都心派だったのに「妻の価値観が変わった」と夫驚き、その理由は?
まいどなニュース4/30(火)8:20
-
4

【速報】「自転車とともに人が倒れている」30代男性が死亡 ひき逃げか さいたま市
テレ朝news4/30(火)16:05
-
5

お花畑でパチリ 4匹の犬さんの表情に個性あふれる「幸せ写真」に「ほわほわするんやぁ」
まいどなニュース4/30(火)16:30
-
6

大相撲に〝ショータイム〟誕生、先代親方の寺尾さん命名「翔大夢」 大谷翔平にまつわる言葉「名前に負けないような相撲を」
夕刊フジ4/30(火)13:16
-
7

埼玉東部の私立高校6校、合同説明会で一斉に集う 花咲徳栄、開智未来、獨協埼玉、叡明、春日部共栄、昌平が参加 受験生や保護者ら大勢、個別相談ブースに長蛇の列
埼玉新聞4/30(火)13:22
-
8

春日部の個人宅のバラ、今年も一般公開 世界観表現するアートも制作
みんなの経済新聞ネットワーク4/30(火)12:32
-
9

夫婦でウオーキング中、路上に動けぬ高齢女性 救助、通報に感謝状
毎日新聞4/30(火)12:30
-
10

外国人とみられる男性が暴行受け死亡 男が逃走中で刃物所持の可能性も…殺人容疑も視野に行方追う 埼玉・川口市
TBS NEWS DIG4/30(火)14:04
地域 新着ニュース
-

リニア新幹線工事 ボーリング調査を5月中に再開 JR東海社長会見
LOOK4/30(火)19:25
-
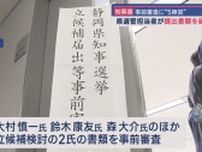
静岡県知事選 立候補の届け出に必要な書類の事前審査行われる 立候補表明の3陣営以外に、2人が出席
LOOK4/30(火)19:23
-

アプリインストール後「暗号資産の運用について教えてあげる」の電話を信用 570万円詐取される
あいテレビ4/30(火)19:22
-

静岡市長 特定の候補は支援しない考え示す 「相談しやすいのは大村氏」だが… 静岡県知事選
LOOK4/30(火)19:20
-

女子大の構内で繁殖のサンショウウオ…実は「新種」だった!その生態に迫る〈仙台市〉
仙台放送NEWS4/30(火)19:18
-

公明党は自主投票 静岡県知事選 衆院3補選自民党全敗は「知事選にも影響が…」
LOOK4/30(火)19:16
-

大谷翔平選手 5試合ぶりマルチヒット 8回にはタイムリーも ドジャースの勝利に貢献
岩手めんこいテレビ4/30(火)19:15
-

東北電力が過去最高益で3年ぶりの黒字 電気料金値下げについては「検討する」
仙台放送NEWS4/30(火)19:14
-

【中継】ゴールデンウイークの東北道 菅生パーキングエリアの様子は 「ハイウェイめし甲子園」2位のメニューを実食
tbc東北放送4/30(火)19:14
-
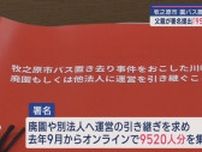
園児がバスに置き去り死亡事件 遺族がこども園の廃園など求める署名提出 静岡・牧之原市
LOOK4/30(火)19:13
総合 アクセスランキング
-
1

火野正平、腰痛悪化 「こころ旅」春ロケは中止発表 ネットは「寂しいけど」「ご自愛を」心配の声続々
デイリースポーツ4/30(火)14:50
-
2

大谷初球ゲッツーで上がる「またかよ」の声に反論「これは真ん中のピッチだ」 米記者が3連投
THE ANSWER4/30(火)12:43
-
3

“15年間フルーツしか食べない人物”に起きた驚きの変化。「ラーメンもお菓子も食べたいとは思わない」
日刊SPA!4/30(火)8:52
-
4

ド軍、衝撃の「0/44」 18年6454日ぶり珍事に日米騒然「クレイジーだな」
Full-Count4/30(火)14:25
-
5

関口メンディーがLDH退社を発表 グループも脱退 今後は独立し個人で活動「新しい挑戦を」コメント全文
スポニチアネックス4/30(火)18:01
-
6

ひろゆきが日本での納税額を公表 井川意高氏ら「納めてから言え」の声にアンサー
東スポWEB4/30(火)11:41
-
7

詩画作家の星野富弘さん死去 78歳 手足の自由失い、口に筆をくわえ創作
上毛新聞4/30(火)14:55
-
8

《半同棲愛の証拠写真》「お忍びで一緒にライブに…」キンプリ髙橋海人(24)が有村架純(30)に‟ベタ惚れ”の理由「関係を隠し切れなかった」――2023年読まれた記事
文春オンライン4/30(火)10:00
-
9

博多大吉、NHK鈴木奈穂子アナに「世界的権威を小走りで呼びつけるんじゃない」
サンケイスポーツ4/30(火)9:43
-
10

市毛良枝「90歳を過ぎた車椅子の母とオレゴン旅行へ。声も発しなくなっていた母の表情は、オレゴンで生き生きと別人のように変わっていった」
婦人公論.jp4/30(火)12:31
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

【現地取材】名古屋DF三國ケネディエブスは浦和に惜敗も「センターバックの僕が中心になって」と成長を誓う
Qoly4/30(火)19:00
-

ときわ台・中板橋で愛される喫茶店&カフェの人気スイーツ4選 〜黒猫スイーツ散歩 ときわ台・中板橋編まとめ〜
さんたつ by 散歩の達人4/30(火)18:28
-

カリアリが歴史的「島民の革命」を表現した限定ユニフォームを発表 ピクセルアートの“ぼかしデザイン”
Qoly4/30(火)18:00
-

伊右衛門が最新スポット「ハラカド」と“濃い”コラボ展を開催!クールなポートレート撮影体験もできる
Walkerplus4/30(火)17:30
-

清澄白河の老舗ガラス工場の3代目が、深川とともに愛してやまない焼き鳥屋『APOLLO』
さんたつ by 散歩の達人4/30(火)17:00
特集
地域選択
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
COPYRIGHT(c) The Saitama Shimbun. All Rights Reserved.