「人間関係ですべてが決まる」「成功体験から抜け出せない」「恥と面子のため方向転換ができない」…太平洋戦争史を振り返ると、日本人特有の“戦い方”が敗因となったと思われる事例は非常に多い。この国が今なお抱え込む「失敗の本質」を深堀りした『太平洋戦争史に学ぶ日本人の戦い方』より一部を抜粋、再編集してお届けする。
「皇軍無敵」に「一撃必殺」。日本軍を敗北に至らせた四文字熟語が持つ“魔力”(5月4日9時公開予定)
日本軍“史上最悪の作戦”インパールの惨敗を招いた「恥の意識」と「各司令部の面目」(5月5日9時公開予定)
「すこし勝ちすぎでは」とおどけた日本の指導層

国の記念日や祝祭日に合わせて大きな作戦を敢行するということは、どの国でもよく見られる。たとえば第一章で述べた英海軍によるイタリア軍港のタラント空襲は、もともと昭和15(1940)年の10月21日に決行するはずだった。ところが空母の故障のためやむなく11月11日に延期された。
では、当初に予定された10月21日とはなんの日かと思いきや、それは文化2(1805)年のトラファルガー海戦の記念日だった。英海軍がジブラルタル海峡付近でフランス・スペイン連合艦隊に大勝した一戦だ。その日に今度はイタリア海軍を痛撃しようとしたとは、いかにもホレーショ・ネルソン提督を頭首と仰ぐロイヤル・ネイビーらしい話だ。
日本でも太平洋戦争の開戦にあたり、明治節(明治天皇誕生日。11月3日)、紀元節(神武天皇の即位日とされる。2月11日)、陸軍記念日(奉天会戦勝利の日。3月10日)、天長節(昭和天皇誕生日。4月29日)を節目として作戦計画が立案されたことはよく知られている。
祝祭日通りに事が運べばだれも苦労しないよと笑う人もいて、なかなかうまい表現だと感心した人もいた。いずれにしても英米相手の戦争なのだから、そう楽には勝てないだろうとする空気が支配的だったはずだ。
ところがふたを開けてみると、強気の予測以上の結果となった。開戦が当初の予定より一ヵ月遅れの昭和16(1941)年12月8日になったにもかかわらず、シンガポール占領は翌17(1942)年2月15日、ラングーン(現ヤンゴン)占領は3月8日、インドネシアのオランダ軍降伏は3月9日だった。
フィリピンの米軍は予想に反してマニラ一帯での決戦を回避し、バターン半島の要塞に立て籠もったため、ここでの作戦終了は昭和17年5月初頭までずれ込んだが、ほかはまったく順調だった。
これにもっとも驚いたのは当の日本の指導層で、「すこし勝ちすぎでは」と口にしておどける余裕すら見せていた。昭和15年9月に日独伊三国同盟が締結された時、「これから日本はどうなるのか」といたく心痛していたという海軍の長老たちもハワイ攻撃や南方進攻作戦の成功を見て、「若い者もよくやっている、これで帝国海軍の行く末は安泰だ」とご満悦だった。
「勝者は学習せず、敗者は学習する」

しかし意外なことだが、下級将校として日露戦争を体験した陸軍の長老のなかには、緒戦の勝利を見ながら将来を懸念する人がかなりいたという。陸軍の武器体系は基本的に日露戦争当時のままで、どうにも心もとない。各級指揮官の能力についても、数年にわたり大陸戦線で中国相手の非正規な作戦を続けてきたためか、低下の一途をたどっているように思われる。
日露戦争当時の動員率(全人口に対する徴集率)は2パーセント程度だったが、この動員率があがれば当然、兵員の質は低下する。それらに対する施策が見当たらないと指摘されていた。
ところがこれまた日本軍の特色の一つだが、どんな大物の実力者でも現役を去れば「ただの人」になり、ほとんど発言力がなくなる。後輩になにを言っても聞き流されるばかりか、現役将官から面と向かって「近代的作戦用兵を知らない人は黙っていてください」と言われるのも珍しくない世界だった(小磯国昭『葛山鴻爪』中央公論事業出版、1963年)。
日本は緒戦の勝利に眩惑陶酔し、それがなぜもたらされたのかを分析することを怠った。まさに「勝者は学習せず、敗者は学習する」との警句通りとなった。西部太平洋からインド洋の東部までを迅速に席巻した日本海軍の勝因は、ハードとソフト両面での奇襲によるものだった。正規空母のすべてを投入した機動部隊の運用法、零戦に代表される航空機の優勢、そして練達した搭乗員の技量、このセットで押しまくった結果の勝利だ。
そんな奇襲の心理的な効果が薄れ、敗者の敵が機動部隊の運用法を学んだらどうなるのか。こちらは航空機の搭乗員や整備員の補充が遅れているのに対して、敵は自動車に慣れた青年が多いから、すぐにも搭乗員や整備員を育成できる。航空機に関する技術も欧米のほうが進んでいる。
陸軍の勝因はごく簡単なことで、相手が弱すぎたということにつきる。フィリピンには米兵とフィリピン兵が半分ずつの割合で、合計4万2000人のいわゆる米比軍が展開していた。これはコンスタビュラリー、すなわち警備隊・警察軍の一種といったもので、昭和19(1944)年に予定されていたフィリピン独立までのつなぎの武力集団であって、正規軍ではない。インドネシアには、一部がオランダ本国兵からなる7万人の軍隊があったが、これもあくまで軽装備な植民地の警備軍だ。
日本にとっての不吉な前兆
かなり手強いと思われたのがマレー半島からシンガポールに展開している英軍だった。戦前の見積によると、英本国兵1万1000人、インド兵3万〜3万5000人、オーストラリア兵2万〜2万5000人、マレー兵若干の合計7万人程度とされていた。
しかし、戦意が高いのは英本国兵だけだろうし、そもそもはこれもまた植民地軍なのだから、国軍最精鋭との定評がある第五師団(広島)、近衛師団、そして第一八師団(久留米)からなる第二五軍が向かえば、シンガポールの早期奪取は可能とされた。
そこで第二五軍は、当初配属された第五六師団(久留米)を隣接する第一五軍に差しだすという余裕を見せた。ところが、開戦時の英軍は四個師団と六個旅団を基幹とする12万人の規模にまで増強されていた。攻略後にこれを知っただれもが背筋が寒くなったことだろう。

第二五軍司令官だった山下奉文中将(高知、陸士一八期、歩兵)は、のちに「敵を軽く見ていたことが図に当たったまでのこと」と苦笑いしていたという(沖修二『至誠通天 山下奉文』秋田書店、一九六八年)。
ともかく、半年足らずで南方資源地帯を制圧したのだから、帝国陸海軍の快挙と酔い痴れるのも無理はないが、緒戦から日本にとって不吉な前兆もあった。ウェーク島攻略戦の苦戦だ。ここはハワイとグアムのほぼ中間で、アメリカは昭和14(1939)年からここに軍事施設を設営しだし、日米開戦時には建設作業員1000人、および警備の海兵隊500人ほどが駐屯していた。アメリカの領土を占領すること自体に意義があるし、ここに哨戒基地を張りだすことにも大きな意味があるとの理由から攻略することとなった。
戦訓から学ばなかった日本軍
開戦3日後の12月11日、第四艦隊はウェーク島に上陸を試みたが、反撃に遭って駆逐艦二隻を失って敗退した。各地から捷報が届くなか、ウェーク島攻略は第四艦隊の面目の問題となった。12月22日、増強された第四艦隊は空母二隻、重巡洋艦四隻、潜水艦七隻をもってウェーク島を包囲、攻略必成を期した。そして哨戒艇二隻をあえて座礁させて上陸するという奇策を講じて、ようやく同島を占領することができた。

ウェーク島攻略戦では第一次と第二次を合わせ、日本軍は戦死者467人を出し、駆逐艦二隻、哨戒艇二隻、さらに衝突事故で潜水艦一隻を失った。一方、米軍の戦死者は122人と記録されている。この二次にわたるウェーク島攻略戦はさまざま貴重な戦訓を残したが、それを学ばなかったことが日本軍の命取りとなった。
最大の戦訓は、少数であっても敵航空機がいる飛行場のそばに上陸しようとするのは、自殺行為に等しいということだ。すぐに燃料や弾薬を補給してまた飛び上がってくる敵機には手を焼く。たとえ攻撃手段が銃撃だけの戦闘機であっても、それが艦艇に搭載している魚雷や爆雷に命中すれば、駆逐艦などは爆沈する。そして同じパターンの作戦を繰り返すと損害が大きくなることも大事な戦訓だったはずだが、これを日本軍がどれほど心に留めたかは甚だ疑問だ。
そしてなにより、米海兵隊は精強であると認識を新たにするよい機会だった。しかし、来援の望みもない絶海の孤島で、最後まで優勢な敵に火力戦闘を挑んだこの海兵隊の実態を知ろうという姿勢が日本軍にはまったく見られない。これは手強い連中だという認識があれば、ガダルカナル戦での対応の仕方もまた別な形になったはずだ。
文/藤井非三四 写真/shutterstock
「皇軍無敵」に「一撃必殺」。日本軍を敗北に至らせた四文字熟語が持つ“魔力”(5月4日9時公開予定)
日本軍“史上最悪の作戦”インパールの惨敗を招いた「恥の意識」と「各司令部の面目」(5月5日9時公開予定)
太平洋戦争史に学ぶ 日本人の戦い方
藤井 非三四
1,056円(税込)
新書判/272ページ
ISBN: 978-4-08-721262-4
負けるには理由がある
この国が今なお抱え込む「失敗の本質」を深掘りした日本人組織論の決定版!
【推薦コメント】
あの戦争において、大日本帝国がいかにして失敗のスパイラルに陥って行ったかを克明に描き出している。
あの戦争をやってしまった日本社会の実質は、何も変わっていない。
────白井聡氏(政治学者・『国体論 菊と星条旗』『武器としての「資本論」』)
【おもな内容】
太平洋戦争史を振り返れば、日本人特有の「戦い方」が敗因となったと思われる事例は極めて多い。
人間関係で全てが決まる。
成功体験から抜け出せず、同じ戦い方を仕掛け続ける。
恥と面子のために方針転換ができず泥沼にはまり込む。
想定外に弱く、奇襲されると動揺して浮き足立つ。
このような特徴は今日の会社や学校などの組織でも、よく見られる光景ではないだろうか。
本書は改めて太平洋戦争を詳細に見直し、日本軍の「戦い方」を子細に分析する。
日本人の組織ならではの特徴、そしてそこから学ぶ教訓とは。
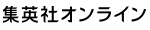















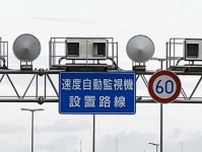





















































































































![[連載・馬主は語る]試合終了(シーズン3-8)](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33089.jpg)





