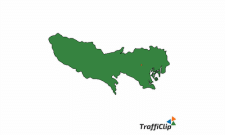前後編の2回に分けて紹介するのは、アスリートの怪我予防などに役立てられるソフトウェアを開発・提供するスポーツテック企業。スポーツとテクノロジーを掛け合わせると、どんな未来が見えてくるのか。多面的な課題の解決へ、取り組みの幅を広げていくビジョンとは――。
――◆――◆――
日本代表が天と地を引っくり返そうとしている。
「ショットだ! ショット!」
橋口寛は無我夢中で叫んでいた。深夜のスポーツバーは興奮のるつぼと化している。ひょっとしたら、ひょっとする。その場に居合わせた客たちは、ひとり残らず、大詰めを迎えた試合中継に釘付けとなり、どよめき、固唾を呑む。
日本代表は究極の選択を迫られていた。確実に引き分けられる道を選ぶか、大きなリスクを取り、ワールドカップ優勝歴を持つ大国を倒しにいくか――。
やがて訪れたのは、感情を制御しているネジというネジが全部弾け飛ぶ、強烈きわまりない忘我の瞬間だ。橋口が共同創業者となったスタートアップ企業の運命は、あの瞬間に決まったのだろう。
スポーツテックのフラッグシップを打ち立て、大きく成長していくその企業が掲げる壮大なビジョンとは? サッカーを含めたスポーツが、今よりはるかに活かされている新しい世界を、誰もがポテンシャルを発揮できる未来を、どのように作っていこうとしているのだろうか。
◇
アスリートのコンディションを可視化するソフトウェア「ONE TAP SPORTS」(ワンタップスポーツ)は、いわば“極限予見ソフト”として開発された出自を持つ。橋口が共同代表取締役を務める株式会社ユーフォリアに、その開発を打診してきたのが日本ラグビー協会だ。
詳しく事情を聞くと、2019年に自国で開催するW杯に向けて、並外れて高強度のトレーニングを、並外れた長期間に渡って繰り返す日本代表の新ヘッドコーチを招聘した。就いては選手たちが怪我をせず、ギリギリまで追い込めるように日々のコンディションを把握し、故障のリスクが高まればアラートを発する、それこそ“極限”を見極めるためのソフトウェアを必要としていると言う。
高強度のトレーニングとは、はたしてどの程度のものなのか。橋口が目の当たりにしたのは、衝撃的な光景だった。
大学ラグビーのあるスタープレーヤーが、練習生の扱いで、日本代表合宿に初めて招集された初日のことだ。橋口は過去に観戦した大学ラグビーの試合で、その選手が躍動している姿をはっきりと覚えていた。秩父宮ラグビー場のそれこそ2万人の観衆全員が、その選手の一挙一動を目で追い続けるような、人気と実力を兼ね備えた逸材だ。橋口も目を奪われたひとりだった。
日本代表合宿の初日にも、その選手は有望株の雰囲気を醸し出していた。元気よく自己紹介すると、元気よくフィールドへ飛び出していく。その選手が所属している大学のラグビー部も厳しい練習で知られている。
ところが――。大学ラグビーのあのスターが、瞬く間に嘔吐しはじめたのだ。頑張れ、頑張れと周囲の選手たちに励まされながら、食べたものを戻し、また戻す。高強度のトレーニングをすでに重ねていたジャパンでは、とてもではないが即戦力たりえない。その事実が明らかになるまで、時間はさほどかからなかった。
“極限予見ソフト”の開発を橋口たちが正式に依頼されたのは、2012年の11月。翌13年4月の菅平合宿から運用を始めたいと言う。
橋口たちに白羽の矢が立ったのは、ターンアラウンドと呼ばれる企業再生のコンサルティングを得意としていたからだ。ITを活用し、企業が苦境に陥っている理由を可視化する。事業のパフォーマンスを数値化し、早期に異常を検知して、アラートを鳴らす。
一見遠く離れた領域にも思えるスポーツと企業再生だが、リスク管理の方法としては共通した構造を持っている。
日本代表の合言葉は「Beat the Boks」。ラグビーの世界ではスプリングボクスの愛称で通り、W杯で優勝2回(当時)の南アフリカを、つまりはボクスを倒すと誓い合う非常に高い目標だ。
南アフリカと激突するのは、2015年にイングランドで開催されるW杯の初戦。早くから照準をその15年9月19日に合わせていた。
並外れた強度のトレーニングを、並外れた頻度で続けるヘッドコーチの要求は、予想以上に並外れていた。選手のコンディションを管理する、世界的に超一流のS&C(ストレングス&コンディショニング)コーチたちが漏らす悲鳴は、橋口たちにも聞こえてくる。
極限予見ソフトで支援して、彼らの負担を少しでも減らしたい。しかし、突貫で最初の合宿に間に合わせたソフトウェアは、アップデートを重ねた現在の最新型とは比べるまでもなく、原始的なプロダクトだった。
それでもアジャイルと呼ばれる、スピード最優先でダメ出しを前提とする開発方式により、機能を少しずつ追加し、アラートの精度を上げていく。やがて橋口たちは、日本代表と共同で開発したと言っていいソフトウェアの価値に手応えを感じるようになり、並外れた取り組みを支える黒子としての強い自覚も持つようになっていた。
だからこそ、南アフリカ戦の最後の一瞬まで、橋口は恐怖の感情を払いのけられなかった。
「Beat the Boks」
本当にそんなことが可能なのだろうか。当時の日本代表がW杯で残していた通算成績は、24戦して1勝2分21敗だ。21敗のなかには、ファンの心を抉るような惨敗も含まれている。
1995年6月4日のニュージーランド戦。オールブラックスの愛称が「最強」の代名詞ともなっているラグビー大国ではあるが、それにしてもここまでの大差をつけられるとは。深夜のリビングルームで、17−145の最終スコアを伝えるTV中継が流れるなか、橋口は魂が抜けたような放心状態に陥っていた。オールブラックスにも匹敵するスプリングボクスを倒すなど、本当に可能なのだろうか……。
【PHOTO】名場面がずらり!厳選写真で振り返る“Jリーグ30年史”!
2015年9月19日。日本時間の深夜に始まった南アフリカ戦のTV中継は、ジャパンの大健闘を伝えていた。先制し、逆転され、逆転し、また逆転される。ダブルタックルやリロードといった徹底して突き詰めた戦術を、日本代表は愚直に遂行できている。それもこれも反吐(へど)が出るほど高強度の合宿を、嫌になるほど繰り返してきた賜物だ。
10−12と2点のビハインドでハーフタイムを迎えた瞬間、スポーツバーの橋口は大きく息をつき、一緒に観戦していた仲間たちと興奮を分かち合う。あの南アフリカと互角に渡り合っている。凄いことが起きている。もうひとりの共同創業者である宮田誠も、うんうんと頷いている。
2008年に橋口が宮田と共同でユーフォリアを設立したのは、大きな志を持っていたからだ。世の中のために、未来のために、良いものを生み出したい。具体的なプロダクトやサービスはまだなく、種火だけがメラメラと燃えていた。
社会に大きなインパクトをもたらせる何かを、どうすれば生み出せるのか。橋口は「何をやるか」ではなく「誰とやるか」で、インパクトの大きさが変わるのではないかと考えていた。最も大事なのは大志を分かち合える、逆境に立たされた時には躊躇なくお互いに背中を預け合える仲間ではないか。
宮田との邂逅(かいこう)は2005年。俺たちは何のために生きているのか。譲れない大切な価値観は何か。これからの人生をどう生きていきたいか。魂をぶつけ合い、確かめ合うような時間を重ね、ふたりで事業を起こしたのが2008年のことだった。
ユーフォリアはラグビー日本代表と出会った創業4年目に、スポーツとテクノロジーを掛け合わせるスポーツテック企業としての第一歩を踏み出し、怪我のリスクを見極めるためのソフトウェアの開発が進むにつれて「何をやるか」が定められていく。「良いもの」へとふたりを導いてくれた日本代表が、W杯の大舞台であのボクスを苦しめている。
真価を問われる後半が始まった。不安は最後の20分。岩のような大男たちと激しくぶつかり合うダメージの蓄積で疲弊してしまえば、相手の思うつぼにはまる。試合が終わるまで当たり負けせず、走り抜けるか。極限を追求するためのソフトウェアは、はたして役に立てたのか――。
決戦はいよいよクライマックスを迎える。スコアは29−32で日本の3点ビハインド。しかしほぼ正面からのペナルティキックを選択すれば、間違いなく決まる。あの南アフリカと確実に引き分けられる。
「ショットだ! ショット!」
引き分けでも十分凄い。そう思いながら橋口が反射的に叫んだその時、同じ叫び声をエディーさんも上げていたと知ったのは試合後のことだ。エディー・ジョーンズ。並外れた強度のトレーニングを、並外れた期間に渡って繰り返させた日本代表のヘッドコーチだ。
ボクスを倒せという例の合言葉は、部外者から多くの失笑を買っていた。そんなことが可能なはずはない。しかし、日本代表のヘッドコーチは本気だった。2013年7月13日の大演説を橋口は間近で聞いている。場所は大阪だった。
日本ラグビー界のトップコーチ90名ほどが、エディー・ジョーンズの話を聞いていた。サッカーであれば、S級ライセンスを持つ著名な監督たちの集まりだ。登壇したエディー・ジョーンズは怒っていた。
君たちは本気で勝ちたいのか。本気で勝ちたいなら、変わらなければいけない。世界とのギャップは、どんどん大きくなっている。今、変わらなければ、20年後、日本のラグビーは死んでいる。
会場の最前列に腰掛けていた橋口は、慌ててペンを走らせる。今では想像もつかないが、当時は日本のラグビー界でストレングス&コンディショニングに本腰を入れているチームは少なかった。みんなで意識を合わせて、フィジカルのスタンダードを上げていかない限り、未来はない。
そう訴えるエディーさんの目は潤み、声は時々かすれ、震えもしていた。40分ほど続いた独演会が終わり、橋口はホテルの自室に戻ると、自分の殴り書きを忘れないように清書した。
今、読み返してみても、魂が震えるような言葉が並んでいる。橋口が共同創業者となったユーフォリアの企業としてのあり方にも、強い影響を及ぼした出来事だ。高い目標を設定し、どれだけ笑われようと、そこへ向かって突き進む。エディーさんが変えようとしていたのは、日本ラグビー界の、あるいは単純に日本の「常識」だった。
南アフリカとの死闘が幕切れを迎えようとしている。究極の選択を迫られた日本の選手たちが迷わずに選んだのは、大きなリスクを取るほうの道。敵陣深くでスクラムを組み、トライを狙う。
トライが決まれば、常識を覆すジャパンの取り組みを完成させる画竜点睛(がりょうてんせい)となる。しかし、ターンオーバーを許した瞬間に試合は終わり、例の合言葉も砕け散る。
最後の数十秒は、スローモーションの夢を見ているようだった。NHKのアナウンサーが「行けえ! 行けえ!」と絶叫し、日本代表が左奥に逆転のトライを決めた時、橋口は人目も憚らず、泣いていた。
あそこまで無防備に我を忘れて、滂沱(ぼうだ)の涙を流したことがあっただろうか。宮田も泣いている。エディージャパンのこの快挙は、極限を追求するために極限を予見するソフトウェアを開発した彼らの歴史的勝利でもあったのだ。
人は一人ひとり全員違う。アスリートの怪我を未然に防ぐ取り組みでは、その全員違うという個別性の壁を乗り越えていかなければならない。
30人の選手が所属しているサッカーチームであれば、コンディションの異変に注意を払うアスレチックトレーナーやフィジカルコーチは、異なる身体と異なるメンタルを持つ30人一人ひとりと個別に向き合わなければならない。
対面のヒアリングや紙のノートに記録といったアナログな管理手法では時間がどれだけあっても足りない。向き合う選手の数が増えれば、それだけ怪我の予兆を見落とすリスクも高くなる。
トレーナーやコーチから、コンディション管理の手間暇を劇的に減らせるのがテクノロジーだ。橋口たちが提供しているワンタップスポーツを活用すれば、30人それぞれの心身の状態をはるかに容易に並行して把握できるようになり、異変やその兆しに気づきやすくなる。
ワンタップスポーツを利用するアスリートは毎日、その日の疲労度、筋肉の張りや痛み、感じているストレスのレベル、睡眠の質、栄養の質といった主観値を入力する。スマホを使えば、1分もかからずに全ての情報を入力できる。
他方では客観値となるデータも蓄積していく。GPSに加えて、身体装着型と非装着型がどちらも増えている様々なセンシングデバイスを組み合わせて活用すれば、身体組成や心拍変動などの各種バイタルデータを半自動的に記録していける。
主観と客観の両面から心身の状態を把握し、怪我のリスクが高まれば、コンディション管理者にアラートが届く。人は一人ひとり全員違う。我慢強い人もいて、痛みに過敏な人もいる。好調だと言って譲らないアスリートの異変が、客観データから掴めることもある。客観値に異常はなくても、主観的な違和感が怪我の防止に繋がることもある。
極限予見ソフトとして開発を依頼されたワンタップスポーツの汎用化の可能性に、橋口たちは少しずつ目覚めていった。ラグビー以外の競技でも、サッカーのような集団スポーツから各種の個人競技まで、幅広く活用してもらえるのではないか。用途も怪我の防止に限らず、コンディションの維持やピーキング、パフォーマンスの最大化へと広げていける。
カテゴリーもトップオブトップの代表レベルやプロスポーツだけでなく、育成年代や部活動での健全な成長支援にも活かせるだろう。競技ごとのピラミッドの裾野でも、もっと言えばスポーツとは距離を置く人たちの健康管理にも、役立ててもらえるに違いない――。
スポーツ史上最大の大番狂わせとも評された南アフリカ戦のインパクト、それゆえの説得力たるや、絶大なものだった。ワンタップスポーツのユーザーは右肩上がりに増え続け、いまや26競技の日本代表が利用する。Jリーグは47クラブ、プロ野球は6チーム、BリーグはB1・B2の全クラブへと広がった。部活動などの学生スポーツまで合わせると71競技、1700以上のチームが活用しているという(2022年11月現在)。
競技別ではサッカーのユーザーが最も多い。エディージャパンを参考にしてレベルの高い取り組みを続けているのが、ブラインドサッカーの日本代表だ。プロフットボーラーでは、ヴィッセル神戸の酒井高徳が早くからワンタップスポーツを熱心に活用している。このあたりの話には後編で触れることになるだろう。
アスリートであれ、アスリート以外であれ、人を氷山に見立てれば、心身に異変をきたす予兆のほとんどは水面下に隠れている。水面下の予兆を可視化するワンタップスポーツのユーザーが増え、多様化していくに連れて、コンディション管理以前の様々な問題に直面するようになったと、橋口は打ち明ける。
多面的な課題の解決に向けて、ユーフォリアはすでに取り組みの幅を広げているという。橋口の話はこう続く。
「スポーツには大きな価値があります。ただし、その価値を最大化していくには、逆説的ですが、スポーツの外側に意識を向けて、外側でもスポーツの価値を顕在化させていかなければなりません」
後編ではサッカーの話を中心に、橋口たちが見据える未来へ、どう近づいていこうとしているか、詳しく紹介したい。(文中敬称略)
取材・文●手嶋真彦(スポーツライター)
※サッカーダイジェスト2023年1月12日号から転載
怪我の予防からポテンシャルの最大化へ。スポーツテック企業が見据える未来と課題【日本サッカー・マイノリティリポート】
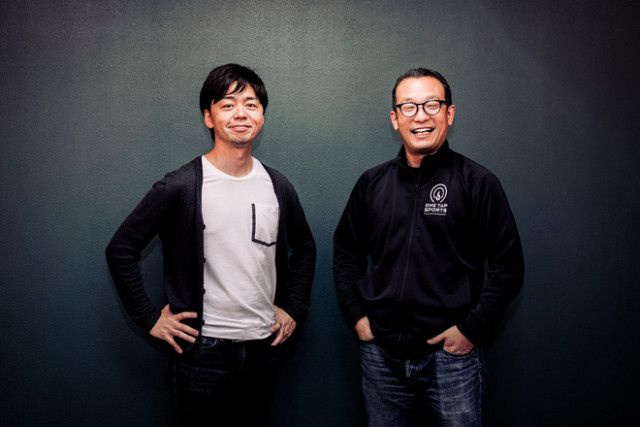
関連記事
あわせて読む
-

DeNA・関根が誹謗中傷被害 巨人戦の死球判定巡り「嘘はつきません」「どんなのが来ているか理解してもらえたら」
デイリースポーツ4/26(金)23:52
-

「深くお詫び申し上げます」40年ぶりに五輪出場を逃した“大惨事”を受けて韓国サッカー協会が異例の公式謝罪!「失敗を二度と繰り返さない」
SOCCER DIGEST Web4/26(金)19:44
-

前回王者サウジがU-23アジア杯8強敗退 退場MFはペットボトル蹴り上げ…警告計7枚の荒れ試合
FOOTBALL ZONE4/27(土)1:14
-

「カタールは審判が支配下だと思っていたのか?」U-23日本代表エースを襲った“腹部への飛び蹴り”に海外ファンも衝撃…「レッドカードは当然」「意図的に見える」
ABEMA TIMES4/26(金)21:00
-

他球団の現役選手もため息 ベッツ、大谷、フリーマンのMVPトリオは「全然違う」「不調でも…」
THE ANSWER4/26(金)21:33
-

【バレー】リオ五輪正セッター宮下遥、今季限りで引退 史上最年少15歳2カ月でVリーグデビュー
日刊スポーツ4/26(金)19:23
-

【巨人】まさか8回に6失点の逆転負け…ドラ1西舘勇陽が11試合目で初失点&初黒星…DeNA度会の満塁弾がとどめ
スポーツ報知4/26(金)20:35
-

ウズベキスタンが10人のサウジアラビア撃破、インドネシアとパリ五輪出場を懸けて準決勝で激突【AFC U-23アジアカップ】
超ワールドサッカー4/27(土)1:14
-

大谷翔平はお茶目ポーズ トロントへ向かう様子が話題に MLB公式は騒動絡める「今回は乗っている」
デイリースポーツ4/26(金)18:58
-
-

阪神がヤクルトに敗れて連勝ストップ 木浪が悪夢の3失策…持ち前の堅守崩れる
スポニチアネックス4/26(金)21:30
-

石井一久は頭蓋骨骨折の大惨事…山本由伸の顔面強襲169キロ弾丸ライナー好捕をド軍OB絶賛
日刊スポーツ4/26(金)19:30
-

DeNA・度会隆輝、ダメ押し満塁弾ですぐ引っ込めたガッツポーズにネット反応「ヤベって顔したのをおばちゃんは見逃しません」
中日スポーツ4/26(金)20:58
-

DeNA 満塁弾で涙の度会 お立ち台でも瞳が潤む「打てずに申し訳なかった」「全力で必死こいてやりました」
デイリースポーツ4/26(金)20:54
-

天国か地獄のパリ五輪予選!なのに…アジア4位のプレーオフ会場は驚きの「クレールフォンテーヌ」
Qoly4/26(金)22:15
-

ドジャース・由伸 直撃ライナー“マトリックス捕り”で2勝目もつかんだ
スポニチアネックス4/27(土)1:30
-

ドジャース・大谷、母校に錦 花巻東グラウンドに雄星との「同時2桁勝利達成記念モニュメント」
スポニチアネックス4/27(土)1:30
-

ドジャース・大谷が守った!試合前にレフトで軽快守備練習 ロバーツ監督「9月に様子見る」
スポニチアネックス4/27(土)1:30
-

上沢直之、悩んだRソックス入り 「早くメジャーで投げるため」優先度低かったレイズと別れ
スポニチアネックス4/27(土)1:30
-
スポーツ アクセスランキング
-
1

DeNA・関根が誹謗中傷被害 巨人戦の死球判定巡り「嘘はつきません」「どんなのが来ているか理解してもらえたら」
デイリースポーツ4/26(金)23:52
-
2

「深くお詫び申し上げます」40年ぶりに五輪出場を逃した“大惨事”を受けて韓国サッカー協会が異例の公式謝罪!「失敗を二度と繰り返さない」
SOCCER DIGEST Web4/26(金)19:44
-
3

前回王者サウジがU-23アジア杯8強敗退 退場MFはペットボトル蹴り上げ…警告計7枚の荒れ試合
FOOTBALL ZONE4/27(土)1:14
-
4

「カタールは審判が支配下だと思っていたのか?」U-23日本代表エースを襲った“腹部への飛び蹴り”に海外ファンも衝撃…「レッドカードは当然」「意図的に見える」
ABEMA TIMES4/26(金)21:00
-
5

他球団の現役選手もため息 ベッツ、大谷、フリーマンのMVPトリオは「全然違う」「不調でも…」
THE ANSWER4/26(金)21:33
-
6

【バレー】リオ五輪正セッター宮下遥、今季限りで引退 史上最年少15歳2カ月でVリーグデビュー
日刊スポーツ4/26(金)19:23
-
7

【巨人】まさか8回に6失点の逆転負け…ドラ1西舘勇陽が11試合目で初失点&初黒星…DeNA度会の満塁弾がとどめ
スポーツ報知4/26(金)20:35
-
8

ウズベキスタンが10人のサウジアラビア撃破、インドネシアとパリ五輪出場を懸けて準決勝で激突【AFC U-23アジアカップ】
超ワールドサッカー4/27(土)1:14
-
9

大谷翔平はお茶目ポーズ トロントへ向かう様子が話題に MLB公式は騒動絡める「今回は乗っている」
デイリースポーツ4/26(金)18:58
-
10

阪神がヤクルトに敗れて連勝ストップ 木浪が悪夢の3失策…持ち前の堅守崩れる
スポニチアネックス4/26(金)21:30
スポーツ 新着ニュース
-

蛭田みな美 大会コース記録1時間半で更新 「情があって替えられなかった」相棒交換で首位発進
スポニチアネックス4/27(土)4:05
-

大谷翔平、移籍先の最終候補だった因縁のトロントで「2番・DH」 待ち受けるのはブーイングか歓声か
スポーツ報知4/27(土)4:01
-

三笘所属のブライトン 今夏開催の日本ツアーで東京Vとの親善試合を調整 鹿島との対戦は内定
スポニチアネックス4/27(土)4:00
-

幡地隆寛 睡魔に負けず猛チャージで暫定19位に浮上 トラウマ乗り越え「ここで賞金を稼ぎたい」
スポニチアネックス4/27(土)4:00
-

“怪物感ある”U−23・内野航太郎 完全アウェーも批判の声も黙らせた「“うるせえな”と思っていた」
スポニチアネックス4/27(土)3:00
-

決勝弾のU−23・細谷 柏Jユース時代からの積み重ねが大一番で結実「やり続けるしかないと思っていた」
スポニチアネックス4/27(土)3:00
-

U−23・大岩監督 采配的中で4得点白星演出「課題を反省して準決勝へ準備したい」
スポニチアネックス4/27(土)3:00
-

ソシエダ久保建英、古巣マドリー戦で3試合ぶりに先発に復帰! 昨季に続いて恩返し弾なるか
SOCCER DIGEST Web4/27(土)2:51
-

韓国「ドーハの悲劇」で五輪連続出場が9でストップ 監督&FW退場響いた 敵将は元韓国監督の因縁
スポニチアネックス4/27(土)2:45
-

渋野日向子「やばいっすね、イライラする」30パットと苦しみ99位と出遅れ 自らに怒り
スポニチアネックス4/27(土)2:30
総合 アクセスランキング
-
1

19年前の殺人 指名手配の男の死亡確認 なぜ今 容疑者特定に?
TBS NEWS DIG4/27(土)0:21
-
2

氷川きよしが長良プロダクションから独立 活動再開を示唆「自分らしく歌い続けていきたい」
東スポWEB4/27(土)1:28
-
3

三鷹市殺人事件で重要指名手配の上地恵栄容疑者、事件後間もなく死亡していたと判明
産経新聞4/26(金)20:45
-
4

「いつもと味が違う」給食の牛乳で腹痛などの体調不良600人超える 仙台市内の小学では水筒持参で対応 宮城
tbc東北放送4/26(金)18:05
-
5

YOSHIKI過労で倒れ入院 所属事務所が発表 予定していた撮影は急きょキャンセル
日刊スポーツ4/26(金)17:29
-
6

DeNA・関根が誹謗中傷被害 巨人戦の死球判定巡り「嘘はつきません」「どんなのが来ているか理解してもらえたら」
デイリースポーツ4/26(金)23:52
-
7

三菱商事、ケンタッキーフライドチキン運営会社の全株を米投資ファンドに売却へ
読売新聞4/26(金)23:30
-
8

「深くお詫び申し上げます」40年ぶりに五輪出場を逃した“大惨事”を受けて韓国サッカー協会が異例の公式謝罪!「失敗を二度と繰り返さない」
SOCCER DIGEST Web4/26(金)19:44
-
9

三浦瑠麗氏 離婚を発表「先日、夫婦を卒業しました。友人になりました」 今後も「三浦姓」で活動へ
スポニチアネックス4/26(金)18:07
-
10

「ムスコは元気か?」サウナ室内で“不適切行為”が横行し、鹿児島の人気ヘルスセンターが閉店「夫婦で来店したのに夫が男湯でこっそり…」「厳しく注意喚起の張り紙をしたらクレームが殺到」
集英社オンライン4/26(金)21:39
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

東京サマーランドがゴールデンウイーク企画 一部の屋外プールを営業
みんなの経済新聞ネットワーク4/26(金)22:16
-

天国か地獄のパリ五輪予選!なのに…アジア4位のプレーオフ会場は驚きの「クレールフォンテーヌ」
Qoly4/26(金)22:15
-

ズラリと並ぶ「人が住まない家々」巡り秘密を暴け ダブルの意味で「家さがし」できる謎解きイベントが楽しそう
Jタウンネット4/26(金)21:00
-

Jリーグクラブチャンピオンシップ、「2023→2024」で最も能力が上がった選手TOP5
Qoly4/26(金)21:00
-

「バター食べ比べ」って、そんなに味の違いある?→ありました 「渋谷バターまつり」で衝撃体験
Jタウンネット4/26(金)20:43
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
(c)Nippon Sports Kikaku Publishing inc. All rights reserved.