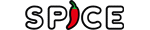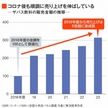2019年の初演を経て4年ぶりの再演となった本公演。女性の地位向上のために闘った人々の姿を描いた物語である一方、決してそこに留まらず、“人間讃歌”という大きなメッセージも色濃く感じられる作品へと深化していた。
物語の舞台は急速に産業革命が進んでいった19世紀半ばのアメリカ。それは女性が仕事に就くことがまだ珍しかった時代でもある。工業都市として栄えた街ローウェルには、夢を抱いて紡績工場で働くたくさんのファクトリーガールズがいた。主人公サラもそのひとりだ。彼女は貧しい家庭を支えるために、大きなバッグを抱え単身でローウェルにやってきた。新しい街に着いたばかりで希望に満ち溢れたサラの笑顔は、工場の実態を前に消え去ることになる。

サラが目にしたのは、まともな休憩時間もなく朝から晩まで機械のように働くファクトリーガールズ。お給料をもらうため、解雇されないため、無理をしてでもしたたかに働く彼女たちにサラは衝撃を受ける。ハリエットの存在も彼女に大きな影響を与えた。ガールズの寄稿集「ローウェル・オウファリング」の編集者であるハリエットとの出会いをきっかけに、サラは文章を書く楽しさを知り、ライターとしての才能を開花させていく。


強い友情で結ばれたファクトリーガールズは、時に衝突し、時に励まし合いながら、それぞれの夢を胸に未来へ想いを馳せて働き続けた。ところが工場の労働環境は悪くなるばかり。労働者への不当な扱いに対して声を上げ、真正面から権力に立ち向かおうとするサラ。必死に築き上げてきた場所を守りながら、争いではない方法での解決を望むハリエット。“女性の地位向上”という同じ目的を持つ2人の運命は、残酷にもすれ違っていく――


幕開けの瞬間から重厚なギターサウンドが響き渡り、本作が闘いの物語であることを予感させる。実話を元に生み出されたこの物語は、全26曲のエネルギッシュなロックサウンドに乗って紡がれていく。「機械のように」や「ストライキ」の場面など、ファクトリーガールズがスカートを翻しながら激しく体を揺らしてグルーヴ感満載で歌い上げる様は、観る者の気持ちを高揚させる。本作のテーマと音楽は密接に結びついており、それ故に作品全体に説得力が生まれているように感じた。

物語の主軸となるのは、サラ・バグリーとハリエット・ファーリーという、実在の人物をモデルとした2人の登場人物だ。

柚希礼音は、持ち前の素直さと明るさでファクトリーガールズから信頼を得て、ゆくゆくは労働争議のリーダーとなってペンを手に闘うサラを力強く演じた。ローウェルに来たばかりの頃は世間知らずだったサラだが、工場で身をもって現実を知り、疑問を呈して果敢に権力に挑む姿は実に頼もしい。かと思えば、突然踊り出してしまうような天真爛漫さを持つ愛らしい人物でもある。柚希のまっすぐな芝居とサラのひたむきさとが舞台上でピッタリと重なり合う瞬間が幾度もあり、その度に心が震えた。


サラと親友になるが、彼女とは異なる方法でファクトリーガールズを守ろうと奮闘する孤高の女性、ハリエット・ファーリーを演じたのはソニンだ。知的で常に冷静で、決して感情には走らない。ファクトリーガールズや女性の権利を守りたいと願うものの、工場の裏に潜む政治に巻き込まれ身動きができず葛藤する。そうして押さえ続けてきた感情が爆発する瞬間の迫真の演技は鬼気迫るものがある。ソニンは、初演時よりもさらに人間味を増した新しいハリエットの人物像を見事に作り上げていた。


工場で働くファクトリーガールズも、一人ひとりが個性的な魅力を放っている。
実咲凜音が演じるアビゲイルは、常に優しい眼差しでみんなを見守る縁の下の力持ち。いざというときの頼もしい言葉が、彼女の持つ芯の強さを感じさせる。いつも空気を和ませてくれるかわいらしい少女ルーシー・ラーコムを演じたのは、清水くるみ。何をするにも一生懸命で、クルクルと変わる表情からは目が離せない。本作初参加の平野綾は、玉の輿を狙うおしゃれ好きなマーシャを活き活きと演じていた。「オシャレをしたい」のナンバーで見せる、かわいらしさと腹黒さのコントラストが秀逸だ。


他にもヘプサべス(松原凜子)、グレイディーズ(谷口ゆうな)、フローリア(能條愛未)など、ファクトリーガールズは誰しもが悩みを抱えながら、けれど希望を捨てず懸命に闘った。たとえ同じ作業服を着ていても、スカートの柄、ブラウスのデザイン、髪型など衣装やヘアメイクの細部が異なっており、それらからも各々のキャラクターを感じ取ることができる。ぜひチェックしてみてほしい。
工場を取り仕切るオーナーのアボット・ローレンスを演じたのは、原田優一。一癖も二癖もあるアクの強い立ち居振る舞いで鮮烈な印象を残していった。アボットと共に表と裏の顔を巧みに使い分ける州議会議員のウィリアム・スクーラーを演じたのは、戸井勝海。権力の象徴でもあるヒール役として存在し、渋みのある芝居で作品に重みを与えていた。

スクーラーの甥で政治家を目指す若き青年ベンジャミン・カーティスを演じた水田航生は、舞台上に爽やかな風を吹かせる。ハリエットに自身の夢を語る場面では、まるで少年のように純粋な瞳を輝かせていた。労働新聞の編集長で移民でもあるシェイマスを演じたのは寺西拓人。本作では持ち前の爽やかさを封印し、複雑な背景を持ちながら権力と闘う勇ましい青年として、芯のある芝居で魅せてくれた。



工場の寮母でルーシーの母でもあるラーコム夫人と、本作のストーリーテラーとして40年後のオールド・ルーシーという2役を華麗に行き来していたのは、春風ひとみだ。ラーコム夫人では女手一つで娘を育て上げた包容力のある母を演じ、オールド・ルーシーでは若かりし頃のルーシーを彷彿とさせる茶目っ気を垣間見せながら、舞台と客席とを繋ぐ大役をさらりとこなしていた。

ペンを手に権力に立ち向かったファクトリーガールズの物語は、決して過去のものではない。彼女たちの行動は現在へと繋がり、闘いは今もなお続いている。ファクトリーガールズが望んでいたのは、人が人として生きる権利なのだ。
本作ではペンは武器として描かれているが、ペンは人と人との理解を深めるための道具にもなり得る。立場の異なる者同士が、文章を通して互いのことを知り歩み寄ることができれば、いつか闘いを終えることができるのかもしれない。

上演時間は1幕85分、休憩20分、2幕75分の約3時間。東京公演は6月13日(火)まで東京国際フォーラム ホールCにて、その後は福岡公演、大阪公演へと続き、7月2日(日)に大千秋楽を迎える予定だ。
取材・文・撮影 = 松村 蘭(らんねえ)