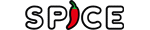ヴァイオリニストの島田真千子が、2024年5月15日(水)にあいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホールで、ピアノの広瀬悦子とともにリサイタルを行う。大阪でのリサイタルは2020年、2022年に続き3回目。サイトウキネン・オーケストラや水戸室内管弦楽団などで演奏するほか、地元の名古屋でセントラル愛知交響楽団のソロコンサートマスターで務めてきた。近年は大阪在住であり、いずみシンフォニエッタ大阪のメンバーとしても活躍している。リサイタルに向けての心境をたっぷりと聞いた、オフィシャルインタビューをお届けする。
ーー名古屋のご出身なんですね。大阪の暮らしはいかがですか?
私は名古屋生まれで、姉が大学でこっちに来ていたぐらいで、大阪にはずっと縁がなかったんです。まさか住むとは思っていませんでした。家族の転勤で実際に住んでみたら、むしろ東京よりも身近な感覚がしました。自分が先入観で思っていた大阪は違うんだだなと思って(笑)。20年ぐらい前、PAC(兵庫芸術文化センター管弦楽団)ができた頃に客演で何度か来ることもあったんですが、その時代とはずいぶんと街の印象が違うように感じます。今は仕事から帰ってきて阪堺電車が走る風景を見るとホッとします。
ーーこれまでもピアノの広瀬悦子さんとのデュオでリサイタルを開催されてきましたね。
2020年がデビュー20年の節目の年だったんですが、その時のリサイタル以来、悦子さんとご一緒してきました。彼女との出会いは小学生の頃で、いつも全日本学生音楽コンクールにお互いが出ていたんですが、なかなか話をする機会はありませんでした。デビューした頃に名古屋のしらかわホールで「名古屋出身の若手同士」として共演しましたが、初めて一緒に弾いたのも同じような時期で、NHKの収録番組でのアンコールだったのをよく覚えています。「カルメンが弾きたい」って言って、オペラとは意外だなぁと思いました。それで2005年に、しらかわホールのバースデー・コンサートでチェロの古川展生さんも加わってブラームスの《ピアノ三重奏曲第1番》を弾いたんです。一音目から普通の音色じゃなくて、そのブラームスが本当に素晴らしかったからお願いしました。名古屋の宗次ホールで楽器を貸与いただいている関係があって、2020年から毎年リサイタルをさせていただいています。大阪では2020年と2022年に、今回と同じザ・フェニックスホールで開くことができました。

島田真千子(ヴァイオリン)&広瀬悦子(ピアノ)
ーー今回の曲目についてですが。
悦子さんは「クロイツェル・ソナタ」を弾きたい、じゃあ私はブラームスの1番のソナタということで、この2曲を軸にプログラムを組みました。実は私の場合はいつも曲目にその時々の世相と自分とが反映されることになるんです。最初にポーリーヌ・ヴィアルドの《ヴァイオリン・ソナチネ イ短調》を弾きますが、ヴィアルドは歌手としても活躍していて、ブラームスの《アルト・ラプソディ》の初演で独唱を務めました。同時代を生きたというつながりに加えて、調性にも意味があります。世の中が混沌とする中で、暗く悲しい気持ちなんですが、その先に希望を見出したいと考えました。ヴィアルドがイ短調で「クロイツェル・ソナタ」がイ長調、さらにバッハがト短調でブラームスがト長調です。「暗闇から光へ」というのがコンセプトなんですが、最後は救いでありたいし、音楽はやはり希望であって欲しい。ベートーヴェンもブラームスも長調とはいっても、単に開放的な明るさがあるだけではない音楽です。それも今弾きたかった理由です。
ーーボリュームたっぷりですね。
意外にそんなことないんですよ。バッハ、ベートーヴェン、ブラームスを並べてみると、共通する部分もあるんですが、演奏する上で気持ちの入れ方が全然違うんです。その中でもブラームスの書かれ方は人間的であって、19世紀後半という時代の影響もあるんですが、深い気持ちが伴わないと弾くことができないんです。一方で「クロイツェル・ソナタ」は確かに大きなソナタなんですが、音楽の素材としてはそんなに重いものではなくて、バッハに近い音楽だということを感じているんです。
ーーバッハの音楽には深い思い入れをお持ちですね。
留学から帰ってきた時にバッハの無伴奏ソナタとパルティータの6曲には取り組みたいと思って、ひとつのリサイタルで1曲ずつ取り上げて、最後に全6曲を弾いたんです。大阪では今回初めて無伴奏曲を入れました。コロナ禍のときに、もう一回バッハをやり直したいと思って、修辞学的なものも含め、音が持っている意味合いを改めて勉強して、それを音にしてみたいと考えています。自分にとって新たな発見だったのは、そうした観点からとらえると「クロイツェル・ソナタ」はバッハと並べた時に、音の並べ方の語法に則って同じようにやってみると、とても弾きやすかったんです。ベートーヴェンにもまだこの時代の書き方が盛り込まれているんだと感じました。ブラームスでさえもそういった部分があります。ベートーヴェンもブラームスもかなりバッハを研究して、影響を受けている部分があります。難しいと思ってきたフレーズが、こんなに自然に弾けるんだなと思えました。
ーーブラームスについてはいかがですか。
ブラームスは彼が二十歳代に活動していたデトモルトで私が学んだこともあって、とても大事な作曲家であり、自然で身近に感じられる存在です。この第1番のソナタについては、親密でプライベートなラブレターのように感じます。孤独であっても優しい愛情が込められていて、温かさもある。ブラームスって、ズバッと言わないんですよね、「でもね、でもね……」って。冒頭はバッハやベートーヴェンに通じているんだけれども、しばらくして、いったんメロディが出てきたらロマン派の響きがあらわれます。この部分から音楽を変えることで、より自然に演奏することができるように思っています。第2楽章が葬送行進曲風で、クララ・シューマンの亡くなった子供のことを思って書かれたと言われていますが、私自身もここ数年は近しい人が亡くなられることが続いています。
最近では、小澤征爾先生が亡くなられて、そして小澤さんのパーソナルマネージャーをされていた志賀佳子さんも亡くなられました。そんな時にそっと寄り添えるのがバッハであり、ブラームスだなと思います。ブラームスの室内楽曲にはこれまでほとんどの作品に取り組んできましたが、ブラームスって何なのというといところに当時は達していなかったように思います。年齢を重ねることで経験を積んで、ようやくつかむことができてきた。だからこそ何年かを経て、改めて取り組みたいという気持ちになります。他の作曲家の作品でもそうなんですが、最近は「自分が弾きたい。聴かせたい」というところから「その作品に触れたい。この曲は何を語っているのだろう」というところが大事になってきました。
取材・文:小味渕彦之