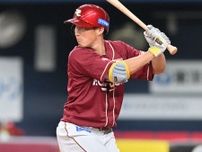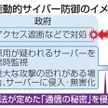連載「斎藤佑樹、野球の旅〜ハンカチ王子の告白」第52回
プロ8年目の2018年、斎藤佑樹は30歳になった。20代最後のマウンドとなったのは、4月7日の東京ドーム。マリーンズ打線をノーヒットに抑えていたのにもかかわらず、8つの四死球を与えてピンチを招き、勝利投手の権利を手にする直前の4回ツーアウトで交代させられてしまった。

練習中に笑顔を見せる斎藤佑樹 photo by Sankei Visual
【失敗を解釈してしまう】
あれは勝つことを難しく考えてしまった試合でした。勝っていい試合だったと思いますし、失敗を恐れずにスイスイ投げていたら何でもなかったはずです。スライダーを真ん中に投げて、真っすぐをピュンと投げて、深く考え過ぎないタイプのピッチングを平然とすればそれでよかったんです。
でも結果がほしくて、打たれたくないからとつい深読みをしてしまい、きわどいところ、きわどいところを突いて、結局は歩かせてしまう。僕にありがちなパターンです。アウトコース低めからボールになるツーシーム、インコースのひざ元からボールになるカットボール......いやいや、そんなところへ投げなくても、真ん中に投げれば勝手に左右へ散らばると考えることができていたはずでした。
頭ではわかっていても、なかなかできないのは、打たれた恐怖心があるからなんでしょうね。ストライクを投げられれば、そこから僕のマインドもいい方へ向かっていくと思うんです。それができない悪循環......勝つことって、難しいんだなと思い知らされる日々でした。
じゃあ、勝つことの何が難しいのかと訊かれると、そこは技術だけが理由じゃないと思うんです。いま思えば"失敗を解釈してしまう"ということが、足かせになっていたんじゃないかと思っています。
僕は甲子園で勝つまでの18年、失敗を失敗と思っていませんでした。失敗も成功するためのひとつのジャンプ台だと思っていましたし、失敗を気にしなかった。深く考えなかったんです。だから、あんまり失敗を覚えていないんでしょうね。
その後の12年は、いろんなことを失敗と感じるようになっていました。おそらく甲子園の優勝があったから、そこに届かないものは全部が失敗だと思うようになったのかもしれません。
むしろそれまでとは真逆で、なぜ失敗したんだろうと考えてしまいました。ただ、それは決してネガティブな意味ではなく、失敗をちゃんと解釈しようと思えるようになった、ということでもあります。失敗を一つひとつ解釈して、前に進もうと思っていました。それが、打たれた恐怖心を抱くことにつながってしまったのかな。
失敗を解釈しないでやってきた18歳までは、アスリートとしてはすごくよかったのかもしれないし、感性を大事にしていればそれでよかったのかもしれません。でも人として考えたとき、失敗を解釈できなければ何も後に残らないと思ったのが30歳の頃でした。
もし18歳のままの僕が、そのまま人前に出続けていたら、すごく恥ずかしかったと思います。いろんな失敗を経て、それを解釈しようとしたからこそ、少しだけ人間的な成長につながったのかなと、そう思っています。
【30歳になって気づいたこと】
4月の東京ドームで勝てず、次のチャンスは30歳になった直後(6月12日)の交流戦、札幌ドームのタイガース戦でした。この日はホームランを2本打たれて(?山俊、中谷将大)、4回(7失点)で交代......結局、この年はここで終わってしまいました(10月にリリーフで1イニング投げて、一軍では3試合、0勝1敗、防御率7.27)。
思えば30歳になってからは、周りからの評価のされ方には違いを感じていたような気がします。30歳だからこうしたほうがいい、30歳だからどうあるべきだ、みたいな......ただ当時の僕は20代初めの頃にイメージしていた30歳の自分を追い抜いたような感じを持っていました。
同じ世代の友だちからは、「30歳ってもっと大人だと思っていた」というような話をよく聞いたんですが、僕は自分が想像していた30歳のイメージを、ちょっとだけ追い抜いた気がしていました。
それは、ようやく自分のなかでいろんなものがハッキリと見えてきたからなのかもしれません。自分が野球をやっている意味とか、自分がなぜ野球をやってきたのか、なぜこんなに野球が好きなのかとか......そういうことを答えるときにも、それまでの僕はいちいちこだわっていたんです。要は、カッコつけていたんでしょうね(笑)。
そういうのってめんどくさいなって思うようになったのが、30歳になった頃でした。たとえば自分が野球をやっている意味を考えたとき、それは周りの人のためだ、なんてザックリと思っていたんです。でも、それって結局、僕が楽しいからだったんですよね。
じゃあ、僕が楽しいと感じるのは何なのか......そこはぐるっとひと回りして、やっぱり僕が野球をやると喜んでくれる人がいて、そういう人の笑顔とか喜ぶ姿を見ることなんです。子どもの頃、野球を始めた時の感情と一緒で、両親に褒めてもらいたいとか、そういう想いが楽しさの原点でした。
小学生の頃、三振取って、ホームラン打ったら、お父さんもお母さんも喜んでくれましたし、チームメイトの父兄のみなさんも喜んでくれました。中学生になったら仲のいい友だちとか、学校のみんなも応援に来て、僕の野球で喜んでくれるのを肌で感じていました。高校に入って、2年生の秋、日大三高に勝った時は学年で応援に来てくれて、全員が喜んでくれました。あの時はたまらなく楽しかった......僕はずっと、その時のように自分が投げて、勝って、応援してくれた人たちがスタンディングオベーションで迎えてくれる瞬間をイメージしていたのかもしれません。
要は、選手として今のマウンドで戦っている僕だけではなくて、僕の日常や試合を迎えるまでの姿勢とか生き方とか、そういうものに共感してくれた人たちが集まって、「よくやった」と思ってもらいたかったんです。
まず自分が全力で集中して楽しんで、周りを楽しくさせる。それを見ている人たちがいつしか心が躍る......僕がもともとの「人が喜ぶ顔を見たい」というスタイルで野球をやれていれば、もうちょっといいピッチングができたのかもしれません。
けれど、勝ちたいとか、防御率とか勝ち星とか、プロ野球選手として評価されなければいけない。ただ純粋に目の前のバッターを抑えて、そこからすべてが始まる。それを見て喜んでくれる人がいるはずだと考えられれば、楽しく、のびのびと野球ができたかもしれないと思います。
【この投げ方ってマー君と同じだな】
30歳になった時、プロ野球選手として、応援してくれている人たちに喜んでもらうためには何をしなくちゃいけないのか、ということをやっと考えるようになったのかな......。
その発想はピッチングにもつながっていきます。何かにこだわるのがいいというわけじゃない。フォームでも、こうじゃないといけないというこだわりは捨てていいのかなと思ったりもしました。
プロで8年、いろんな人にいろんなことを教えていただいて知識も増えましたし、野球をするうえでのテクニカルなこと、身体のことも勉強できたと思います。ただ、そういうものを得たことによって、自分が持っていた本能に近い感覚がちょっとぼやけたのかなとも思います。
だから、本能に任せてみようと思ってつくったイメージは、まず足を高く上げて、そこから何もアクションを起こさずにスーッと前へ落ちて行くだけ。そのとき、踏み込んだ左足でピタッと止まったら右腕が自然と振られる感じ。そうすると目線はブレないし、コントロールも安定する。
アクションをつけようとすればするほど、力んでしまって、ブレるし、安定もしない。そのくせスピードが出るかといったら、思うほど出ないんです。ああ、なるほど、こういう感覚なのかと思ったとき、ふと「この投げ方ってマー君(田中将大)と同じだな」と思いました。アクションをつけず、ストンと力を抜くだけで腕が振られている感じが、まさにマー君だったんです。「そうか、マー君はこの道のずーっと先を行っているのか。よし、じゃあ、僕もこの道を行ってみよう」と思いました。だからあの時期、ヤンキースのマー君のYouTubeをずいぶん見ていましたね。
* * * * *
2019年、ファイターズの栗山英樹監督はメジャーの野球から新たな発想を得ていた。オープナーとかブルペンデーと呼ばれる戦術をチームに取り入れようとしたのである。先発に5イニングを期待するのではなく、頭からの短いイニングを託す。打順の一回り、3回までを抑える力があることは斎藤もたびたび示してきた。新たな役割を託されることでチームに貢献できるかもしれない──斎藤はそんなプロ9年目を迎えようとしていた。
次回へ続く
斎藤佑樹(さいとう・ゆうき)/1988年6月6日、群馬県生まれ。早稲田実高では3年時に春夏連続して甲子園に出場。夏は決勝で駒大苫小牧との延長15回引き分け再試合の末に優勝。「ハンカチ王子」として一世を風靡する。高校卒業後は早稲田大に進学し、通算31勝をマーク。10年ドラフト1位で日本ハムに入団。1年目から6勝をマークし、2年目には開幕投手を任される。その後はたび重なるケガに悩まされ本来の投球ができず、21年に現役引退を発表。現在は「株式会社 斎藤佑樹」の代表取締役社長として野球の未来づくりを中心に精力的に活動している
著者:石田雄太●文 text by Ishida Yuta