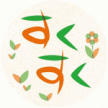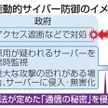7カ月の育休を取り、節分の日に2人の子どもと遊ぶ元山悠希さん=愛知県北名古屋市の自宅で(本人提供)
「育休職場応援手当」最大で10万円
「新生児から首が据わってハイハイができるようになって、少しずつ成長していく。そんな姿を間近で見ることができて、幸せだった」
損保大手の三井住友海上火災保険(東京)の名古屋損害サポート部で働く元山悠希さん(40)は、昨年7月に第2子の長男が生まれた後、7カ月の育休を取得した。同社は昨年、男女問わず社員が育休を取ると、同僚に一時金を払う「育休職場応援手当」を創設。職場の規模や育休期間などに応じ、1人あたり3000〜最大10万円で、7月から支給を始めた。
元山さんは2022年に長女が生まれた際にも、1カ月の育休を取得。「ようやく育児のリズムがつかめてきたときに仕事復帰となった」。年子で2人目が生まれ、育児の負担が大きくなるため、より長期間、育休を取ることを決めた。
妻(36)は生後間もない長男の授乳に追われており、1歳すぎの長女の離乳食作りや遊び相手などをすべて担った。2人の育児は想像以上に大変で、夜泣き対応で妻とともに寝不足に悩まされた。
男性の取得を義務化、さらに後押し
フリーランスで働く妻は、産後3カ月から徐々に仕事を再開。元山さんは妻の仕事時間を確保するため、週5回は子ども2人を連れて近くの子育て支援センターに通った。
子育ては毎日同じことの繰り返し。子どもたちはもちろんかわいいが、ずっと一緒にいて自分の時間が取れないつらさも味わった。「子育ての喜びと大変さの両方を理解することができた。妻と一緒に乗り越えたことで夫婦仲も深まった」と笑顔を見せた。
人事部の担当者によると、同社はすでに男性社員の1カ月の育休取得を義務化するなど、子育て支援に力を入れてきた。「1カ月を超える長期の取得を促すために、職場全体で出産、育児を祝う制度として同僚への手当を考えた」という。
国も「同僚手当」への助成を拡充
ほかに大和ハウス子会社の大和リース(大阪市)は、育休の取得期間によって減額される賞与分を原資として、それを同僚に振り分ける「サンキューペイ制度」を新設。昨冬の賞与から分配を始めた。
国も仕事と育児の両立支援として、同様の取り組みを後押しする。育休を取った社員の同僚に手当を支給する中小企業に対し、1月から助成金を大幅に拡充している。
産後パパ育休創設も、まだ不十分
厚生労働省によると、2022年度の育休取得率は女性80%に対し、男性は17%だった。取得期間も、男性は過半数が2週間未満(2021年度)と、女性と比べて圧倒的に短い。
パーソル総合研究所が昨年1〜2月、子どものいない20〜40代の男性約350人に聞いた調査では、約7割が子どもが生まれたら育休を取りたいと回答した。ただ、取得する上で気になることは、「同僚に迷惑がかかる」が最多の39%だった(複数回答)。
日本総研上席主任研究員の藤波匠さん(58)は、「産後パパ育休」の創設などにより、男性の育休取得率は上がっているが、まだ不十分だと指摘。「長期に休める人員配置や休業中の金銭的な支援など、さらなる取り組みが必要だ」と指摘する。
関連記事
おすすめ情報
東京すくすくの他の記事もみるあわせて読む
-

賃貸の入居、年齢を理由に断られないのは60代まで。専門家が教える、終の棲家を探すときのポイント。取り壊しの有無、病院への交通アクセスなど
婦人公論.jp5/1(水)12:30
-

結婚生活で最重要<お金の価値観>を見抜く方法とは…1300組以上を結婚に導いた婚活スペシャリストが考える「結婚の5つの条件」
婦人公論.jp5/1(水)12:00
-

<部屋はスッキリ>が気持ちいいと頭ではわかっているけど…「片付けられない」に隠された2つの理由を公認心理師が解き明かす
婦人公論.jp5/1(水)12:00
-

減胎手術という選択肢も…「3人を同時に失うのも、誰かを失うのも絶対に嫌だ」命懸けで挑んだ3つ子出産【多胎育児体験談】
たまひよONLINE5/1(水)11:55
-

最新「外国人の人口増加率が高い都道府県」ランキング! 同率2位「秋田県」「宮崎県」、1位は?
All About NEWS5/1(水)11:50
-

腰痛持ちがこぞって買いに来る機能性クッションの実力とは…ハンズ新宿店に聞いた
日刊ゲンダイ ヘルスケア5/1(水)9:26
-
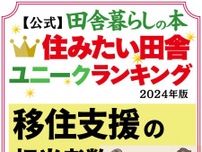
【田舎暮らし徹底解明】移住支援を行う担当者の数が多い自治体はどこ? 【公式】2024年版「ユニーク自治体ランキング」
田舎暮らしの本Web5/1(水)6:00
-

PTAに入らないと不利益はある?非会員の子どものケガ・事故は“対象外”か? PTA保険Q&A
All About4/30(火)21:50
-

【感染症アラート・本格的な流行】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(溶連菌感染症)、咽頭結膜熱など4つ
感染症・予防接種ナビ4/30(火)13:51
-
-

医師の立場からみた、生活の質を保つために必要な体の機能4つとは?自分の優先順位を決めることで、超高齢化社会の医療費に備える
婦人公論.jp4/30(火)12:30
-

認知症の主な4つの種類とは?特徴と原因を解説
婦人公論.jp4/30(火)12:30
-

年齢を重ねると婚活が難しくなるのは必然?1300組以上を結婚に導いた婚活スペシャリスト「まず正しく知るべきは<自分の婚活市場価値>」
婦人公論.jp4/30(火)12:30
-

自信を失う“ほめ方”とは...多くの人がやっている、実績だけ見た自己評価
PHPオンライン4/30(火)12:00
-

知り合いが「親が亡くなったのに預貯金を引き出せない」と言っていました。私の親も高齢なので心配です。生前からなにか対策できることはありますか?
ファイナンシャルフィールド4/30(火)10:10
-

来年2人目を出産予定です。夫に1年間育休を取ってほしいのですが、育休手当だけで生活できるか不安です。現実的に難しいのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド4/30(火)10:00
-

【山形県知事・吉村美栄子】第2回「母子家庭の経験から全国のシングルママ、パパを支援したいと」
ママスタセレクト4/30(火)10:00
-

小中不登校30万人、ひきこもり146万人…ともに過去最多を更新中【「不登校」「ひきこもり」を考える】
日刊ゲンダイ ヘルスケア4/30(火)9:26
-

「熟年離婚」を回避するために40、50代夫婦がいますぐ始めるべきこと
サンキュ!4/30(火)7:52
-
生活術 アクセスランキング
-
1

【SNSで話題】出産時の「会陰切開」なぜ必要? 医師が明かした命に関わる“切実”な理由
女性自身5/1(水)6:00
-
2

妻が怖い。このまま死んでいくのはむなしい…80代男性患者が涙ながらに訴えた【老親・家族 在宅での看取り方】
日刊ゲンダイ ヘルスケア5/1(水)9:26
-
3

【ちくわが最強】チーズに大葉に梅…旨すぎてセンター張れる!ちくわのおかずレシピ3選
ハフポスト日本版5/1(水)8:00
-
4

ゲーセン「大量閉店」の背後にある本質的な変容 「千円でだらだら」若者の消費欲を満たせてない
東洋経済オンライン5/1(水)13:00
-
5

シングルマザーの幼馴染もいつも通り助けすぎる夫…その距離感って普通なの? <ヒーローになりたい夫 5話>【うちのダメ夫】
ウーマンエキサイト5/1(水)12:00
-
6

【3COINS】ちょっとした手土産にもピッタリ!パッケージもかわいいおやつを紹介
サンキュ!5/1(水)12:20
-
7

知ってる?豆腐を“アレ”で焼くと旨みが格段にアップ!コスパも最強の豆腐ステーキ3選
ハフポスト日本版5/1(水)6:00
-
8

三世代で楽しめる小田原で大人気の「寿司ビストロ」。元旅行代理店の筆者が推すその魅力とは?
婦人公論.jp5/1(水)12:30
-
9

賃貸の入居、年齢を理由に断られないのは60代まで。専門家が教える、終の棲家を探すときのポイント。取り壊しの有無、病院への交通アクセスなど
婦人公論.jp5/1(水)12:30
-
10

結婚生活で最重要<お金の価値観>を見抜く方法とは…1300組以上を結婚に導いた婚活スペシャリストが考える「結婚の5つの条件」
婦人公論.jp5/1(水)12:00
生活術 新着ニュース
-

オレンジジュースが飲めなくなる? 不作と価格高騰でメド立たず…販売休止相次ぐ異常事態
日刊ゲンダイDIGITAL5/1(水)15:03
-

シン・ワインプロジェクト始動 山梨大、学生が栽培から醸造まで
共同通信5/1(水)14:58
-

ベイスターズ効果でテレビ売り上げ好調 スポンサー2シーズン目のハイセンスが「大画面テレビ DAY」
オーヴォ [OVO]5/1(水)14:57
-

滋賀振興にビックリマン 特産とキャラの限定シール
共同通信5/1(水)14:47
-

「判断や解決方法、適切でなかった」 私立中いじめ、滋賀県の調査委が報告書
産経新聞5/1(水)14:47
-

【ライジングゼファーフクオカ】5/3〜 B1昇格へのプレーオフ! 3選手に聞いた
ファンファン福岡5/1(水)14:15
-

農耕文明を破壊する「狼」と恐れられた集団の正体 漫画「宗像教授世界篇」(第2回)狼の星座 前編
東洋経済オンライン5/1(水)14:00
-

ジョージア大使、松屋にポーランド風ハンバーグ登場で心配「国際情勢に影響しかねない熾烈な戦いになりそう」
iza!5/1(水)13:55
-

hit住宅展示場「RKBラジオ公開生放送イベント」を開催!<PR>
ファンファン福岡5/1(水)13:46
-

<そろそろ世代交代>みんなのお財布に福沢諭吉は何人いる?野口英世や紫式部もいる?
ママスタセレクト5/1(水)13:25
総合 アクセスランキング
-
1

真美子夫人も共同オーナーに? 大谷「25億円別荘購入」の次は女子プロバスケチーム買収か
日刊ゲンダイDIGITAL5/1(水)9:26
-
2

元Kis-My-Ft2“辞めジャニ”北山宏光の大誤算…ソロコンサートのチケットが売れない!
日刊ゲンダイDIGITAL5/1(水)9:26
-
3

長渕剛の“ラブコール”に松本人志ファン拒絶反応 性加害告発めぐる対応「男らしくない」と痛烈
日刊ゲンダイDIGITAL5/1(水)9:26
-
4

突然…「ゴールド免許」剥奪? 無事故・無違反で「ブルー免許」強制格下げ、なぜ? 忘れちゃいけないコトとは
くるまのニュース5/1(水)9:10
-
5

卒業の関口メンディーに「正直怒ってます」 中務裕太が複雑胸中「これからの活動で僕を納得させて」
ENCOUNT5/1(水)13:39
-
6

藤森慎吾、ラジオで結婚を生報告 お相手は一般女性「思わず今しゃべりたくなっちゃって」
ORICON NEWS5/1(水)9:14
-
7

出川が走ると大渋滞発生…テレ東「充電させてもらえませんか?」は以前から問題視されていた!
東スポWEB5/1(水)5:00
-
8

米ESPN 水原一平容疑者が大谷翔平から盗んだ金をカジノ経由で賭け屋に流出させていたと報道
スポニチアネックス5/1(水)9:32
-
9

キムタクの「静香の誕生祝いSNS」は事務所移籍のシグナルか
デイリー新潮5/1(水)11:11
-
10

LDH退所の関口メンディー、決断理由は「母」との約束「日本と世界の架け橋になってほしい」
ENCOUNT5/1(水)13:26
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-

40年ぶり五輪出場逃した韓国選手謝罪 「韓国人両親にこだわるのは世界の潮流にそぐわない」と韓国紙は二重国籍選手の解禁提案
Qoly5/1(水)15:00
-

秋山翔吾先頭打者アーチ、天敵、村上頌樹の第1投をライトスタンドへ、結果的にはそれが完投勝利を許すことになろうとは…
ひろスポ!5/1(水)13:22
-

48歳になったベッカムの腹筋がこちら 元柔道家がパーソナルトレーナー
Qoly5/1(水)13:00
-

3歳娘が見せるパパとの結婚指輪 ママの結婚指輪を見せたときの反応に「パパさん嬉しすぎるでしょ」「パパメロメロ間違いなし」の声
ほ・とせなNEWS5/1(水)12:30
-

宮本恒靖JFA会長、8大会連続の五輪出場に「イラクとの準決勝ではチームは生き物だと改めて感じた」
Qoly5/1(水)12:30
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
(C) 2024 The Chunichi Shimbun