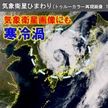古馬最高の栄誉を懸けて争われる天皇賞(春)は、国内最長距離のGⅠ。受け継がれし長い歴史と伝統、さらに高い格式を誇り、数あるビッグレースの中でも存在感は別格。また、ゴールデンウィークの開幕を飾るレースで華やかさもあり、西日本でおこなわれるGⅠの中で最も盛り上がるレースといっても過言ではない。
そんな天皇賞(春)のスタートラインに立ったのは17頭(ヒンドゥタイムズが出走取消)で、5頭が単勝10倍を切ったもののオッズは2頭の一騎打ちムード。最終的に、票数の差でテーオーロイヤルが1番人気に推された。
2022年の当レースで3着に好走したテーオーロイヤルは、その後、骨折による長期休養を余儀なくされるも、復帰してからは4戦2勝2着1回の成績。とりわけ、近2走はダイヤモンドS、阪神大賞典と3000m以上の重賞を連勝中で、6歳ながら勢いと充実度ではメンバー中ナンバーワンといえる。
また、前走阪神大賞典1着馬は、過去10年で[3-2-2-2/9]。このレースと非常に相性が良く、鞍上の菱田裕二騎手とともに悲願のGⅠ制覇がかかっていた。
僅かの差でこれに続いたのがドゥレッツァ。デビューからの7戦すべてで3着内を確保しているドゥレッツァは、休養をはさみながらも条件戦を着実に勝ち上がり、重賞初挑戦となった菊花賞で5連勝を達成。皐月賞馬とダービー馬をまとめて撃破し、ビッグタイトルを手中に収めた。
前走の金鯱賞で連勝は止まったものの、楽々と2着を確保。そして、菊花賞馬もまた天皇賞(春)に強く、2018年から2022年の菊花賞馬5頭中3頭が天皇賞(春)を勝利(2020年の菊花賞馬コントレイルは不出走)しており、2つ目のビッグタイトル獲得が期待されていた。
そして、2頭からやや離れた3番人気となったのが牝馬サリエラ。5歳馬ながら僅かキャリア8戦のサリエラは、過去5年で天皇賞(春)を4勝しているディープインパクトの産駒。負傷療養中のルメール騎手から乗り替わりとなるものの、新たにコンビを組むのは「平成の盾男」こと武豊騎手。さらに、1枠1番の絶好枠を引いた。
牝馬の天皇賞(春)制覇は70年間途絶えているものの、鞍上や枠順などお膳立てはこれ以上なく整い、大舞台での重賞初制覇とGⅠ初制覇が懸かっていた。
以下、復活を期すダービー馬のタスティエーラ。2走前の日経新春杯で重賞初制覇を成し遂げたブローザホーンの順で人気は続いた。
レース概況
ゲートが開くとほぼ出遅れはなく、チャックネイトが僅かに好スタート。鞍上の鮫島克駿騎手が手綱を押し、いく構えをみせるも、ディープボンドの幸英明騎手も負けじと押して、マテンロウレオもこの争いに参戦。最終的にマテンロウレオが先手を切った。
これら3頭とは対照的に、馬なりで先行したドゥレッツァが2番手につけ、ディープボンドを挟んだ4番手を、テーオーロイヤルと出遅れを挽回したサヴォーナが併走。その後ろにサリエラが位置して、上位人気3頭が先行集団を形成した。
一方、4番人気タスティエーラは、中団やや後ろの10番手に位置。5番人気ブローザホーンは、そこから1馬身半差の12番手を追走していた。
1周目のスタンド前に入り、1000m通過は59秒7の平均ペース。この時点で、逃げるマテンロウレオはリードを6馬身に広げており、最後方メイショウブレゲまでは20馬身以上の差。多頭数の長距離戦らしく、かなり縦長の隊列となった。
続いて、1コーナーに入るとディープボンドが単独2番手となり、ドゥレッツァは3番手を追走。その後、向正面に入って2000mを2分1秒7(この1000mは1分2秒0)で通過し、続いて坂の上りに差し掛かると2番手以下が差を詰め、頂上でマテンロウレオのリードは1馬身に縮まった。
そして、坂の下りに入ると、馬群の外を持ったままで進むテーオーロイヤルとは対照的に、ドゥレッツァ鞍上の戸崎圭太騎手が激しく手綱を動かすも、反応なく4コーナーで後退。同じくサリエラも後退した一方で、前はマテンロウレオを交わしたディープボンドが単独先頭に立ち、レースはそのまま直線勝負を迎えた。
直線に入ると、ようやく追い出しはじめたテーオーロイヤルがディープボンドに並びかけ、残り300mで先頭。後続との差を、徐々に広げ始めた。
焦点は2着争いとなり、粘るディープボンドにブローザホーンとスマートファントムが襲いかかり、ゴール寸前でブローザホーンが2番手に上がるも、既にセーフティーリードを取っていたテーオーロイヤルが1着でゴールイン。2馬身差2着にブローザホーンが続き、1/2馬身差3着にディープボンドが入った。
良馬場の勝ちタイムは3分14秒2。長期休養から復帰5戦目のテーオーロイヤルが、重賞3連勝でデビュー13年目の菱田騎手とともにGⅠ初制覇。開業23年目の岡田稲男調教師も、JRAのGⅠは初制覇となった。

各馬短評
1着 テーオーロイヤル
終始楽な手応えで、4コーナーでもほぼ馬なり。直線、ディープボンドに並ぶところでようやく追い出されると、最終的に2着とは2馬身差だったとはいえ着差以上の強さ。これまでGⅠを勝っていないのが嘘のような横綱相撲だった。
1年前の2月に右後肢の寛骨を骨折し長期の休養を余儀なくされるも、復帰後は5戦3勝2着1回の成績。むしろ、休養が成長を促したような充実ぶりである。
今回も含め、勝利した重賞はすべて3000m以上で、ステイヤーの中のステイヤーといってもいい馬。今後は豪国のメルボルンCを目標にするそうで、もちろんそこも楽しみではあるが、有馬記念に出走してきた際も注目したい。

2着 ブローザホーン
メンバー最速となる上がり3ハロン34秒6の末脚でスマートファントムとともに追込み、2着を確保した。
道悪で再三好走していたものの、好時計で勝った日経新春杯や今回の内容を見る限り、メンバーレベルが上がる重賞では、良馬場でこそ実力を発揮できているようにも思える。
こちらはまだ5歳で、母オートクレールは6歳秋にオープンに昇級した晩成タイプ。早くも、来年の天皇賞が楽しみになった。
3着 ディープボンド
前走、3000m以上のレースで初めて掲示板を外し(阪神大賞典7着)、さすがに厳しいと思ったファンは少なくなかったはず(筆者もその一人です)。しかし、直線入口であわやの場面を演出。念願のビッグタイトル獲得はならなかったものの、ついに獲得賞金は7億円を超えた。
この馬の頑張りには頭が下がる思いで、同一GⅠ5年連続3着内という前人未踏の記録を樹立するか。期待が高まる。
レース総評
3200mを1000mずつに区切ると、最初の1000m通過が59秒7で、以下、1分2秒0、1分0秒5。そして、最後の1ハロンが12秒0=3分14秒2。通常、3000m以上のレースでは、真ん中の1000mでガクッとペースが落ちることが多いが、今回はそういったことがなく、11秒台のラップが計7度。一方で13秒台のラップは一度もなく、厳しい流れとなった。
そんな流れを、終始先団に位置しながら直線余裕を持って抜け出したテーオーロイヤルとディープボンドのスタミナは尋常ではなく、とりわけテーオーロイヤルは長距離界の王者。ステイヤーの中のステイヤーといえる。
そのテーオーロイヤルは父がリオンディーズで、産駒初のGⅠ制覇。一方、2着ブローザホーンの父はエピファネイアで、同馬はリオンディーズの半兄。名牝シーザリオを母に持つ点と激しい気性の持ち主であること以外、タイプはやや異なる。
というのも、リオンディーズの父はキングカメハメハで、キングカメハメハ系種牡馬のセールスポイントといえば、母系の特徴を引き出しやすいこと。そのため、テーオーロイヤルは父リオンディーズよりも母父マンハッタンカフェ(現役時に天皇賞(春)、菊花賞、有馬記念を勝利)の特徴を色濃く受け継いでいる。
マンハッタンカフェは近年、母の父として大ブレイク。テーオーロイヤル以外にも、同馬の半兄メイショウハリオは帝王賞連覇などGⅠ級を3勝し、テーオーロイヤルと同じ小笹公也オーナー所有のテーオーケインズもダートGⅠを3勝。
さらに、今回も出走したダービー馬タスティエーラや、2月のフェブラリーSを制したペプチドナイル。先日のマイラーズCを制したソウルラッシュなど、重賞ウイナーをあげだせばキリがないほどで、2023年のブルードメアサイアーランキングでは、ディープインパクト、キングカメハメハに次ぐ堂々の3位。2024年も、4月21日終了時点で3位につけている。
また、京都でおこなわれた天皇賞(春)を、ミスタープロスペクター系種牡馬の産駒が勝利するのは初めてで、連対も2011年2着のエイシンフラッシュ以来13年ぶり。サンデーサイレンス系種牡馬の独壇場だったこのレースも、今後、好走する血統は変わっていくのかもしれない。
一方、今回も含め18戦中14戦でテーオーロイヤルの鞍上を任されてきたのが、デビュー13年目の菱田裕二騎手。2004年の天皇賞(春)でジョッキーになることを志した少年が20年後、同じ舞台で夢を叶えるというのは、まさに人間ドラマそのもの。実家も京都競馬場からほど近くだそうで、勝利騎手インタビューの前に、観客席にいた父の壽男さんと握手を交わしたシーンは感動的だった。
そして、テーオーロイヤルを管理する岡田稲男調教師は、菱田騎手の師匠。菱田騎手は、デビュー以来ずっと岡田厩舎の所属ジョッキーで、デビュー10年以上の騎手がフリーにならず、一貫して同じ厩舎に所属しているのは非常に珍しいケースといえる。
GⅠになると、いともたやすく外国人騎手やリーディングの上位騎手に乗り替わってしまう現代競馬において、その流れと逆行するように師匠と愛弟子が二人三脚で掴んだ待望のビッグタイトル。二人が手にしたのは、古馬最高の栄誉よりもさらに価値あるものだった。

写真:RINOT
著者:齋藤 翔人











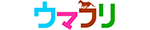
![[重賞回顧]師弟で掴んだ王者の称号。長期休養を乗り越えたテーオーロイヤルが古馬最高の栄誉を獲得!〜2024年・天皇賞(春)〜](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/umafuri/m_umafuri-33150.png)