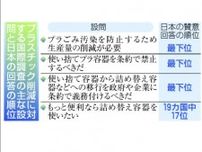戦後から1970年代に至るまで、日本における労働組合運動は活発であった。そこには功罪があり、組合活動が衰退したことには一定程度の必然性はあった。けれども組合が衰退することで、労働者の権利を代表する仕組みも壊れてしまったというのは事実だ。やがて1990年以降の経済衰退が延々と続く中では、豊かさを国民全体で享受するなどということは、大昔のファンタジーとして人々の記憶から消え去ってしまった。
経済の衰退が進むにつれて、労働力は改めて安く買い叩かれるようになり、非正規雇用が進んだり、新卒の処遇が停滞するなど労働者の権利は著しく損なわれた。にもかかわらず、組合活動を含めた労働者の権利というのは忘れられたままである。そんな中で、ストライキという光景を日本では見かけることが極めて少なくなっている。
例えば、2023年8月31日に東京池袋などの西武百貨店では、従業員による一斉ストが行われたが、百貨店業界ではストライキは61年ぶりなのだそうだ。ただし、このストというのはファンドなどによる買収が確定した中でのストであり、意味合いとしては限定的なものだ。世論は「百貨店ビジネスの灯を消すな」という組合員の声に同情はしても、それで業績が回復するわけではなく、いくらストを打っても、そこに時代の流れを反転させる力はない。
 英国のアマゾン倉庫で働く人によるストライキ。外国では、労働者が声を上げている(ロイター/アフロ)
英国のアマゾン倉庫で働く人によるストライキ。外国では、労働者が声を上げている(ロイター/アフロ)24年に入ると、3月に長崎でアマゾンの配達員がストを行った。アマゾンの商品を扱うフリーランスの配達員によるストライキは全国で初めてとのことだが、同社の労働条件については、かなり以前から問題が指摘されており、遅すぎたぐらいである。米国や欧州では、すでにアマゾン関連のストなどの労働争議は行われており、今まで黙っていたことは「労働者が声を上げない」日本を物語っているものと感じられる。
日本の労働組合が縮小していった理由
では、60年代から70年代にかけての昔のような「冷戦型対立」の中での組合活動に戻せば良いのかというと、そうではない。例えば、この時代のヨーロッパでは、各業種でストライキが頻発した。経済合理性を認めず、権利主張ばかりする労働組合は、企業あるいは国全体の経済が不振であることを無視して、過激なストライキを繰り返した。
その結果、国の経済は衰退し、全員が不幸になった。社会民主主義を掲げた労働党がバランス感覚を失った英国は、まさにそのために「英国病」に陥ったと言えるだろう。