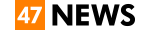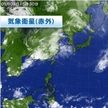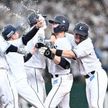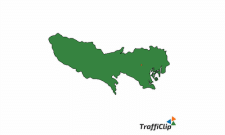東京・渋谷のスクランブル交差点近くから都心のオアシス、代々木公園に通じる緩やかな坂道。この「渋谷公園通り」はファッションとカルチャーの発信地として、バブル経済期には流行感度の高い若者であふれかえった。この街の表情を作ったのは、かつて流通業界で一時代を築いたセゾングループ。総帥だった故堤清二氏は作家辻井喬の顔を持つ二刀流の企業家として知られ、「西武百貨店」や「パルコ」といったグループ各社は堤氏が唱えた「モノを売るんじゃない」との哲学を具現化した。
消費はインターネット通販全盛時代になり、再開発が進む渋谷駅周辺では商業施設を備えた高層ビルの建設が相次ぐ。消費のスタイルや人の流れが大きく変わった今、渋谷公園通りはどんな姿の街を目指しているのか。(共同通信=小林まりえ、三好寛子)
▽堤氏の一言を読み解いて実行
百貨店大手そごう・西武で社長を務めた松本隆氏によると、堤氏が渋谷での開発構想を掲げた当時、西武百貨店は米ロサンゼルス進出が失敗に終わり、経営危機にひんしていた。道玄坂地区ぐらいにしか店舗はなかったが、これから発展しそうな街と見込んだ。松本氏は、堤氏から薫陶を受けた経験を著書「発想は、メタファーで。」にまとめている。
渋谷はもともと東京急行電鉄(現在の東急)のいわゆる城下町だ。1社だけでは活性化できないと東急側も理解を示し、西武の出店計画が動き出した。映画館が閉鎖するとの情報をつかんで、渋谷区役所や代々木公園に通じるその跡地に決定した。井の頭通りを挟んで2棟にまたがる建物で、1968年に西武渋谷店が開業した。
堤氏が最初に示したコンセプトは「若者」だった。西武百貨店の仕事のスタイルは、堤氏が方向性を一言で表現し、部下たちがそれを読み解いて実行に移すというもの。西武渋谷店の場合は「アート」と「ファッション」がキーワードになった。
▽まねをしてもトップにはなれない
西武渋谷店は旧来の百貨店のフロア構造にとらわれなかった。呉服店を源流とする三越や高島屋、伊勢丹のまねをしてもトップにはなれないと判断したためだ。松本氏によると、当時は家具や食器、玩具が多くを占めるのが主流だったが、西武渋谷店は衣料品の売り場を大きくした。若者向けのファッションを展開した草分けとされ、今や百貨店の売り場のスタンダードになっている。
アートの分野も、名画や古典美術は呉服店が源流の百貨店で十分な品ぞろえがあった。そこで西武渋谷店は、ファッションを「モード」、アートを「アバンギャルド」というキーワードに置き換えた。
有名だったのは中2階のフロア全体を使って展開した「カプセル」という売り場だ。新進気鋭のデザイナーだった故山本寛斎氏や故三宅一生氏らを集め、透明なカプセル状のショーケースの中にハンガーに掛かった洋服を陳列するなど特徴的な見せ方で最先端のファッションを演出した。
▽バブル崩壊でグループは解体へ
松本氏は堤氏のすごみを「じつにモノが売れた時代に、モノが持つ意味を考えなければ売れないと力説したことだ」と語る。ファッションショーを企画し、ショーに行くための洋服を売る。「コトを起こしてモノを売る」という手法を確立した。堤氏は文化人と交流し、その中から事業のヒントを得て社員に投げかけていた。最も受け止めていたのは外部のクリエーターで、糸井重里氏の「おいしい生活」といった時代を映すキャッチコピーも生まれた。
堤氏は新しいことを作りあげることが大好きだったが、同時に飽きっぽく、収益に結びつけていくことにも興味がなかったという。バブルを謳歌したセゾングループは多額の負債が重荷となって経営不振に陥り、解体に向かった。松本氏は「バブルの熱狂から冷めるのとともに、世の中を変えていかなきゃいけないんだという頑張りを忘れてしまった」と感じる。
業界の雄だった百貨店の構造変化がそれを端的に表している。全国の百貨店売上高はバブルが崩壊した1991年に付けた約9兆7千億円のピークから、2023年には約5兆4千億円まで減った。店舗数も268から180になった。アパレルメーカーが商品を自由に並べ、売れた分を百貨店側に支払う取引方式が主流になり、百貨店はどこも金太郎あめのような売り場になった。
▽流行発信地の輝きが薄れ、地元は危機感
西武渋谷店とともに渋谷公園通りを象徴してきたのが1973年に開業した渋谷パルコだ。パルコはイタリア語で公園の意味。後にパルコの社長を務めた故増田通二氏は米国のストリートやアベニューに若者が集まっているのを見て、演劇やアートといったカルチャーで人が行き交う拠点を目指した。坂道の名称も「区役所通り」から「公園通り」に変えた。
地元である渋谷公園通商店街振興組合の川原惠理事長は、渋谷パルコによって「公園通りの存在が大きくなった」と振り返る。1988年にはライブハウス「クラブクアトロ」も併設された。
だが2000年代に入り、「ユニクロ」をはじめとしたファストファッションが台頭。ファッション誌が取り上げるスタイルが画一的に支持される時代は終わり、消費は多様化、細分化した。公園通りは最先端の流行発信地としての輝きが薄れ、川原さんは街が廃れてしまうのではないかとの危機感を持つ。
▽混沌が生み出す面白さに活路
ITなどスタートアップ(新興企業)の誘致などにより、街を訪れる人が変化しているが、パルコの川瀬賢二社長は「型にはまったスタイルではなく、何でも受け入れて面白がる土壌があることに変わりはない」と分析する。
渋谷パルコは老朽化のため2016年に一時閉店。ビルを建て替えて2019年に再びオープンした。引き続き劇場やギャラリーを設け、舞台公演や企画展を開催している。ゲームやキャラクターといったサブカルチャーに特化したフロアには、国内初の任天堂直営ショップを誘致。ファッションのフロアでは女性向け、男性向けといった前提にとらわれない商品陳列を展開する。飲食店が集まるフロアにあえてギャラリーやレコードショップを配置し、意図せずに文化に触れてもらう仕掛けもしている。
ビルの外側には10階から地上へつながるらせん階段があり、多くのベンチが置かれている。晴れた日には若者や家族連れがベンチに座り、おしゃべりする姿が見られる。渋谷パルコの建物の中に入らなくても仲間と集えるようにしたという。
川瀬氏は「クリーニング店の隣にバーが、青果店の隣にライブハウスがある。街とは本来そういうものだ」と語る。混沌とした空間が生み出す面白さに、渋谷公園通りは活路を見いだそうとしている。