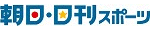「近江のなれずし製造技術」が国の登録無形民俗文化財に登録されて1年。その代表である滋賀県の郷土料理「ふなずし」の材料、ニゴロブナ漁が最盛期を迎えた。毎年ふなずしを自ら漬ける三日月大造知事が、今年は初めてニゴロブナ漁に挑むというので同行した。
2日、琵琶湖に浮かぶ唯一の有人島である沖島(近江八幡市)。夫婦で55年にわたり漁を営む冨田善久さん(74)と敏美さん(69)の船に三日月知事が乗り込んだ。冨田さんが5日前に仕掛けていた刺し網のポイントは西に約5キロ進んだ沖合。水深76メートルにカーテンのように仕掛けた網を引っ張り上げると、琵琶湖の固有種ニゴロブナが引っかかっていた。
三日月知事は、丁寧に網から外す作業に集中した。細かい刺し網を破らないように、フナを傷つけないように。取るのは卵を持ったメスだけ。「うろこと腹を触っただけでわかる」と、長年の経験で瞬時に選別していく冨田さん。「違う、これはオスや」と冨田さんに指導を受けながらえり分け、オスと幼魚を湖に帰した。
この日は約1時間半の漁で、10キロと大漁だった。
沖島漁港に戻り、フナの下処理も三日月知事は体験した。漁師の指導を受けながら、新鮮なうちに魚のうろこを取り、魚の腹を切らずにエラから内臓や浮袋を取り出す「つぼ抜き」にも挑戦。その後、エラから塩を入れてたるに塩漬けするふなずしの「塩切り」をした。知事は「漬け上がるのが楽しみ。毎朝散歩前にたるに『おはよう』と声をかけてたたいて慈しんで待ちたい」と話した。
知事就任翌年から毎年夏、沖島漁業協同組合でふなずしの飯漬けに挑戦しているが、漁に出るのは初めて。「重労働で漁師のご苦労がわかった。代々していただいているから今がある。知恵が詰まった固有の食文化としてふなずしを大事に継いでいかなければならない」
ふなずしは、3〜4月にかけて漁に出て取れたニゴロブナを約3カ月間塩漬けする。梅雨明けの土用の丑(うし)のころ、たるから出してご飯と共に再びたるに漬けて発酵させる。完成するのは12月。年末年始のハレの日の「ごちそう」として振る舞われるまで約8カ月間かかる「究極のスローフード」だ。
伝統の食に欠かせないニゴロブナはかつて、漁獲量が激減した。1965年ごろには約500トンあったが、97年には18トンまで落ち込んだ。
なんとか増やそうと、稚魚の放流や産卵場所となる湖岸のヨシ帯の造成を実施。こういった漁業関係者らの努力で近年、漁獲量は回復傾向にある。今月1日から、県や県漁連、漁業者らによる「資源管理協定」がスタート。ニゴロブナを「とにかく増やす」段階から、資源を守りながら適正な数を取る段階に入る。
ただ、必ずしも順調ではない。沖島のニゴロブナは昨年の3分の1ほどしか取れていないという。冨田さんは「いつものポイントに魚がいない。18から漁師をしているが、経験が通用しない」とこぼす。
今年1月には琵琶湖のアユの漁獲量が、平年の約3%にとどまり記録的な不漁となった。沖島漁業協同組合の奥村繁組合長(76)は「猛暑や渇水などの気候変動に魚がついていけず、その動きに漁師がついていけていない。琵琶湖の恵みやふなずしの文化に触れてもらうためには、琵琶湖全体が健全でいる必要がある」と話す。三日月知事は「関係者と知恵を集めて対策をとっていきたい」と話している。(林利香)