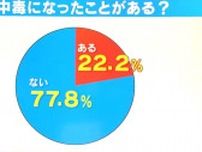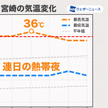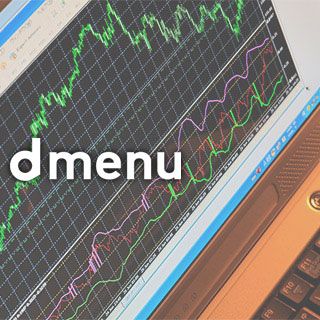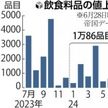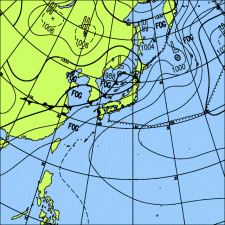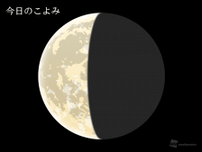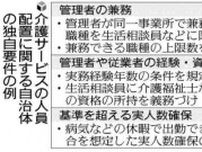〈 「それね、アレが入ってるんだよ」“薬物依存の母”が小学生の娘に飲ませたクスリとは…おおたわ史絵が明かす母親の“恐ろしい記憶” 〉から続く
医師としてだけでなく、タレント・コメンテーターとしても活躍している、おおたわ史絵さん。実は彼女は、母親に対して「いっそ死んでくれ」と願うほど、母娘関係に苦しんだ過去を持つ。
おおたわさんは、いったいどのような母親のもとで育ち、子ども時代からどんな苦悩を抱えていたのか。ここでは、おおたわさんの著書『 母を捨てるということ 』(朝日文庫)より一部を抜粋して紹介する。(全2回の2回目/ 1回目 から続く)

写真はイメージです ©アフロ
◆◆◆
用法用量を無視して注射を乱用
わたしが高校生の頃には、母の注射はほぼ連日常習の状態になっていた。この時点ではすでに父にもわたしにも頼らず、自分自身で打っていた。
オピオイドは通常の生活を送るひとならばまず生涯に一度も使う機会のない薬物なのだから、これは本来の使用頻度や用量をはるかに超えた紛うことなき〈乱用〉の状態だ。
乱用とは正しい目的以外の使用、正しい用法用量を無視した使用のことを指す言葉。依存症に陥る前段階として必ずこの状態を経るものだ。
初めのうちこそは、そのたびに父親に痛みを訴え一回分ずつ注射をもらっていたのだが、この頃になると、
「パパ、そろそろなくなるよ。持ってきておいてね」
と、まるでペットボトルの水の買い置きが切れたくらいのテンションで会話がなされるような異様な状況になっていた。
注射器を何度か使いまわすように
もちろん父は、それをよしとしていたわけではない。
「本当に痛いとき以外は使うもんじゃないんだよ」
困り顔で時に優しく、時に厳しく諭した。だが、そのたびに母はヘソを曲げて、家庭内の雰囲気が悪くなった。だから結局は渋々と薬を渡してしまっていた。
これはアルコール依存症の患者が、家族から酒をとがめられると逆ギレするのとまったく同じだ。家族は言い合いに疲れて、泣く泣く酒を買い与えるのである。
薬の頻度がより一段と増えてくると、そのうち注射器をいちいち新しいものに取り換えるのも面倒になったらしく、何度か使いまわすようになった。
もちろん医療の現場では、使いまわしなど不潔極まりない行為はあり得ない話だが、薬物乱用者の間では日常茶飯事だ。