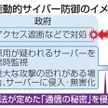オーディションに送られてきたテープを聴き、松田聖子の才能を感じ取った音楽プロデューサーの若松宗雄さんは、早速彼女に連絡を取ろうとする。
同僚によると、父親と学校が強硬に芸能界入りに反対しているということだった。また、実は同僚らスタッフは若松さんほどには、彼女に魅力を感じていなかったようだ。興奮気味の若松さんに対して、反応は薄かった。ここには若松さん自身のキャリアの浅さも関係していたのかもしれない。
それでも若松さんは、自らの感覚を信じて、福岡県に住む彼女のもとに電話をかける。
(若松宗雄著『松田聖子の誕生』をもとに再構成しました。前中後編の中編です。前編では、若松さんが衝撃を受けたオーディションテープについて紹介されています)。
***
「はい蒲池です。法子です」
私は息をつき、先ほどからじっと電話を見つめていた。福岡県在住の蒲池法子に連絡を取るためである。同僚からの賛同がなければ、自分の感覚を信じて一人で動くしかない。孤独な道のりとなるだろう。だが、そもそも他人の評価や意見ほどいい加減なものはないのだ。潮目が変われば黒も白になる。いちいち気にする必要などない。いいじゃないか一人でも。自分が自分を信じてやらなくてどうする。こうなってくると、もはや新人発掘というより生き方の問題であった。
発信音を数回待つ。はたして電話口の向こうに出たのは聖子本人であった。
「はい蒲池です。法子です」
瞬間、さざ波に洗われるように私の気持ちは軽くなり迷いが消えていった。受話器の向こうに、明るくハキハキとした歌声そのままの真っ直ぐな存在があったからだ。
「よかったら一度、CBS・ソニーの福岡営業所に来てみませんか?」
私の言葉に彼女は明るい声で「はい!」と答えた。善は急げ。まずは会ってみよう。数日後、私は東京の自宅から羽田に向かい福岡へ飛ぶと、当時天神の一角にあったCBS・ソニーの福岡営業所に直行した。平日の夕方だったと記憶している。
紺色のワンピースで
そして彼女は現れた。高校が終わってからすぐに着替えて福岡営業所まで駆けつけてくれたという。このとき着ていたのが紺のワンピース。今も脳裏にはっきりと焼き付いているが、清楚な出立ちが非常によかった。横には彼女をやさしく見守る母・一子さんの姿があり、一目で大切に育てられてきた良家の子女であることがわかった。
聞けば子供の頃から服が好きで、特別な日には紺の服を着ることが多かったという。のちのち私も聖子自身も、このときの服装のことを語ることが多かったが、よく聖子は、あのとき紺のワンピースを着ていたから若松さんにスカウトしてもらうことができたと話していた。
確かにそうだったかもしれない。デビュー後に「聖子ちゃんカット」という愛称で親しまれた髪型こそしていなかったが、ふわりと髪をサイドに流し、愛らしい表情に加えて知性と品の良さを持ち合わせていることも瞬時に見てとれた。
営業所の隅にある打ち合わせテーブルで、私と聖子と母親はしばらく話をしていた。歌のこと、学校のこと、将来の夢。するとタイミングよく、レコード店回りを終えたスタッフが数名戻ってきた。「ミスセブンティーンの九州大会で優勝した子なんだよ」と私が話すと、彼らも興味津々でテーブルの周りに集まってきてくれた。
「そうしたら法子さん、何か歌ってもらってもいいですか?」
数名ではあったがスタッフも揃ったし、丁度いいとばかりにお願いする私の言葉に小さく頷く彼女。オーディションのテープは既に何度も繰り返し聴いていたが、生の歌はこれが初めてだった。こちらの高なる胸中を知ってか知らずか、聖子は照れつつもおもむろに歌い始めた。営業所に備え付けられたオーディオから流れてきたのは、意外にも渡辺真知子の『迷い道』だった。

「現在・過去・未来、あの人に逢ったなら〜」
CBS・ソニーのヒット曲がセットされた伴奏音源からのセレクトだったが、『気まぐれヴィーナス』とは全く違うニューミュージック系の曲をのびのびと歌う姿は、既に「松田聖子」の片鱗を見せていた。緊張もしていたと思う。16歳の少女だ。オーディションこそ受けていたが、人前で歌うことは、ほとんどなかっただろう。しかしその歌声は実に素晴らしかった。その上とてつもないエネルギーを秘めており、早くも私のプロデューサーとしての勘は確信へと変わりつつあった。
「この子はスターになるぞ!」
何より生の声量に驚かされた。マイクは要らないじゃないか。言葉の最後に残る母音の響きや声質の良さ、高音の心地よさ、中音域の深み。その後次々に開花していく彼女のヴォーカリストとして才能を、既にこの時点で十二分に感じさせてくれた。未完成な部分ですら、これからの進化を予感させ、私はすぐに彼女と母親にその場でこう告げていた。
「私はCBS・ソニーで制作の一部門を任されています。私の一存でデビューすると言えばできます。ぜひ法子さんを歌手としてデビューさせてください!!」
ところが歓喜の表情を浮かべる彼女の横で、母親は微妙に顔を曇らせている。聞けばこの日は歌手のコンサートに行くと言って、父親には内緒で福岡の営業所まで来たのだという。ミスセブンティーンの九州大会で優勝した日も、実は持ち帰った花束は床下に隠し、父親に告白したのは数日後。しかも話が終わらぬうちに父親は烈火のごとく怒り始め、「何を考えているんだ! 芸能界など絶対に許さん!!」と怒鳴り、言えば言うほど態度を硬化させていったという。高校も、芸能活動は一切禁止していた。
父親の蒲池孜さんは当時、大牟田の社会保険事務所に勤める国家公務員で、近くに住む伯父一家も病院を経営しており、兄は大学職員。蒲池家は実にお堅い家柄であった。およそ芸能には関係がない環境で、もしもあのまま行っていたら聖子は蒲池法子のまま「松田聖子」という芸名に出会うこともなく、ミッション系の名門女子校を卒業後、大学に通い、全く別の道を歩んでいたかもしれない。
しかし彼女は歌が好きだった。
厳格な父
大きな壁は、娘を強い愛情で見守る父親の頑固さであった。確かに当時の芸能ニュースは、多少鮮烈な部分が強かった気もする。一般の方からしてみれば過剰に反応してしまうのは仕方ないことだったかもしれない。
しかしそれを鑑みても聖子の父親は実に堅かった。聞けば、聖子を子供のころから随分と可愛がっていたという。ときには車で学校の近くまで送っては日々の出来事を聞き相談に乗る。たまに聖子が帰り道に甘い物が食べたいと言えば、小遣いとして100円玉を数枚こっそり渡すようなこともあったそうだ。一方で礼儀や作法、生き方に厳しく、けっして人に迷惑をかけるようなことをしてはいけないと厳格に育てていた。
この時点でこそ、たまたまデビューへの障壁という形になってはいたが、松田聖子の真っ直ぐな性格と素直な感性を築いたのは、間違いなくご両親の深い愛情だったのだ。
結局、CBS・ソニーの福岡営業所で聖子と母親に会った日は、そのまま具体的な話になることはなく彼女たちを見送っている。
父親の許可はそのうちきっとすぐに下りるだろうと思っていたのだ。私が「ちゃんとお父さんに話して許しをもらわなくちゃダメだよ」と伝えると、聖子は「はい。わかりました!」としっかりした口調で答えていた。
***
しかし、父の意思は固かった。若松さんも直接交渉をしたが、「(芸能界入りを)許すつもりは一切ありません」の一点張り。連絡を繰り返すと、「君もしつこいな。ダメと言ったらダメなんだ!!」。娘と父の考えは一向にかみ合わず、しまいに父はテレビの歌番組を見せないように押し入れにテレビを隠してしまう始末だったという。
しかし、そんなある日、意外にも父親から若松さんに電話がかかってくる。そこまで言うのなら、一度直接会って話したい、という。
そして運命の話し合いが行われることとなるのだ。後編では聖子の父と若松さんとの対面、交渉決裂から急転直下、芸能界入りまでを描く。
※『松田聖子の誕生』から一部抜粋、再構成。
若松宗雄(わかまつ・むねお)
1940(昭和15)年生まれ。音楽プロデューサー。CBS・ソニーに在籍、一本のカセットテープから松田聖子を発掘した。80年代後期までのシングルとアルバムを全てプロデュース。ソニー・ミュージックアーティスツ社長、会長を経てエスプロレコーズ代表。『松田聖子の誕生』が初の著書。
デイリー新潮編集部