福岡県に住む16歳の蒲池法子、のちの松田聖子がオーディションに送ったテープから才能を感じ、芸能界デビューを進めようとした音楽プロデューサーの若松宗雄さんの前に立ちはだかったのは、彼女の父親だった。何度もアプローチして、ようやく直接話を聞いてもらうことになったのだが――。後編では、それでも首を縦に振らなかった父が、デビューを許すまでのドラマを見てみよう。
(若松宗雄著『松田聖子の誕生』をもとに再構成。前中後編記事の後編。前中編では奇跡の歌声に出会った興奮と、家族の猛反対とが紹介されています)
***

父親と対面したが……
ホテルに到着すると、聖子の父親がフロントの前に立っているのがすぐにわかった。公務員らしくきちんとした装いのスーツで、もちろんこちらもスーツ。父親はすらりとした背格好で髪は後ろにきっちりと撫でつけ、誠実かつ堅実な人柄がすぐに伝わってきた。そうか、聖子は、母親の優しい顔立ちと父親の品格をバランスよく受け継いだのだな。重苦しい空気の中でもどこか冷静にそんなことを思いながら、深々と初対面の挨拶を交わしたのを覚えている。それから父親の仕事の話を聞きながら、私も音楽業界における自分の夢を熱く語った。同時に営業時代からずっと誠実に仕事をしてきた話なども交えて、自分が浮わついた人間ではないことを知ってもらおうと努めた。しかし父親は終始厳しい表情のままだ。珍しく私も緊張し、やたらと喉が渇いたのを記憶している。
思えば西鉄グランドホテルは、当時九州でも一番格式のあるホテルだった。1969年築で帝国ホテルを意識して作ったとも言われる趣のある建築は、父親としてもそれなりに考えての会合場所だったのかもしれない。高い天井と豪華なシャンデリア。声が空中へと吸い込まれ、ともすれば自分を卑小に感じてしまいそうなロビーのソファー席で、私は心を込めて真剣に話し続けた。
なんとかここで許可をもらわねば、と熱がこもる。もちろんそれぞれの人柄を知れば少なからず会話は弾む。短い時間ではあったが、少しずつ父親が心を開き、節々で私の話に頷いてくれるようになっていった気もした。しかし、私が「お嬢さんには素晴らしい才能がある。ぜひデビューさせたいと考えています」と何度言おうとも、一向に「わかりました」という言葉がその口から発せられることはなかった。
2時間近く話しただろうか。ふと気がつくと時刻は夕方になっていた。すると心なしか笑顔になった父親から、「若松さん、飯でも食うか?」と夕食の誘いがあった。延々と話し続けて声を嗄らし始めた私の様子を見て取ったのだろうか。あるいは腹の虫が鳴り響く音が聞こえていたのかもしれない。近所のレストランに場所を移すと、少しだけ砕けた雰囲気の中、私は夕食をご馳走になった。
私は思った。もしかしたら思いが通じたのではないだろうか。少なくとも門前払いではなく、真剣に対峙してくださったようにも感じた。ただし、「わざわざ東京から来てくれてありがとう」という労いはあっても、「わかった」という一言は最後まで聞けずじまい。それでも私は少しの可能性を信じて帰路に就いた。数年後に聞いたところによれば、聖子の父親はこのとき「絶対にわかったと言ってはいかん」と心の中で抗(あらが)っていたという。
まずは私という人間を知ってもらうことはできた。しかし、まだまだ道のりは遠かったのだ。
砕け散った期待
次の日私は、昨日のお礼も兼ねてすぐに蒲池家に電話をかけている。だが、返ってきた言葉はNOであった。しかも昨夜少しだけ近づけたと思った距離は再び大きくひき離され、父親からは直々に、きっちり釘を刺す言葉までいただいてしまったのだ。
「若松さん、どうか今後は娘にも妻にも直接電話はしないでくれ。私が家族の責任者だ。何かあったら私を通して、勝手に娘や家内に話さないでほしい」
そうなると私も「わかりました」と返答するしかない。父親はその日、聖子にも厳格な口調で「もう、このことはきっぱり忘れなさい」と話していたという。そう、わずかな期待は砕け散り、いきなり聖子との連絡の道が断たれてしまったのである。
やはり無理か。なす術なしとはまさにこのこと。さすがの私もそれなりに落ち込んだ。しかし、こんなときは考えるだけ無駄だ。仕方がない。一旦全てを忘れて、まずはしっかり眠ること。考えても何も変わらないときは休むのが一番なのだ。
すると、流れに身を任せたのが良かったのか、ほどなくして、まさに吉報とも呼ぶべき手紙が私の元へ届くのである。希望の糸はまだ繋がっていたのだ。

「私は絶対に歌手になりたいのです」
1978年秋。市ヶ谷のCBS・ソニー本社ビルからは、お堀端の並木の紅葉が見える季節になっていた。私は他の仕事に追われつつも福岡の少女・蒲池法子のことが頭から離れずにいた。そんなある日、彼女から一通の手紙が送られてきたのだ。
私の机の上にある手紙には「蒲池法子」という名前がくっきりと記され、1978年11月1日の消印が押されていた。可愛いらしい丸文字でしたためられていたが、しっかりした筆圧からは夢への揺るぎない気持ちが強く伝わってきた。そこには要約するとこんな感じのことが書かれていた。
私は絶対に歌手になりたいのです。父は反対していますが、私の気持ちをいつか必ず理解してくれるはずです。とにかくあらゆる努力をしますので、これからも私自身の気持ちは変わりません。私にもう一度チャンスをください。どうかよろしくお願いいたします。
その書面に私は改めて感激し、ホッとしていた。正直に言えば実はこのまま本当に連絡が取れなくなるのではないかと思っていたのだ。なんとかなると自分に言い聞かせつつも裏腹に時間だけは過ぎていく。そこへ届いた決意の封書。歌手になりたいという素直な気持ちが、改めて一文字一文字から熱く伝わってきた。
考えてみれば、聖子も気持ちの抑えようがなかったのかもしれない。福岡の営業所でレコード会社のプロデューサーである私に会ったこと。そこで色々な夢について語り、歌を歌ったこと。しかもその場ですぐに「あなたをデビューさせたい。私は責任者です」と熱い口調で言われたこと。その後一瞬ではあったが、東京で芸能事務所の方に挨拶をしたこと。全てが揺るぎない事実であり、16歳の少女には心の拠り所だったに違いない。しかも、父親にきっぱり忘れろと言われれば言われるほど、痛みが情熱に変わっていく。おそらく私が渡した名刺を大切に机の中にしまい、必死の思いでこの市ヶ谷の住所を書き記し、ポストへ投函したのだろう。
実はその後、彼女が歌手になるために上京してくるまでの間に、私は聖子から6通の手紙をもらっている。手紙には、読めばどの時期に何が起きていたか克明にわかるほど、その都度その都度の気持ちが熱くしたためられている。それだけでも松田聖子という人間の「想い」の強さと、真っ直ぐな人間性を理解していただけるはずだ。私はそれらをいまも持ち続けている。捨てられない、捨てられるはずがない。なぜならそこには松田聖子の原点とも言うべき情熱が綴られているからだ。
のちに、どんなに忙しいときも笑顔をたやさず、深夜のレコーディングでも弱音を吐かずに取り組んでいたあの強さは、全てこのときの手紙に込められていた。そう思うと手放すことなどできなかった。
女性スタッフに頼んで電話
彼女から手紙をもらって、私はいてもたってもおられず電話をかけたい衝動に駆られていた。しかし父親からは直接話してはいけないと言われている。滑稽に思えるかもしれないが、そこで私は、当時部署にいたデスクの女性スタッフに頼み、私のデスクから聖子に電話をかけてもらうことにした。しかも、もし両親が出たら、その時は学校の友達だと言ってくれと頼んで……。こちらも必死だったのだ。
いまも昔も変わらないことはただ一つ。大切な話はきちんと自分の口から言葉にして伝えるということ。それだけだった。
かくしてCBS・ソニー市ヶ谷ビルの片隅にて、私は、電話のすぐそばで固唾を呑んで待っていた。心なしか受話器を握るスタッフも緊張気味である。そして数回ベルの音がしたのちに誰かが受話器の向こうで出たのがわかった。
「本人です、ご本人ですよ!!」
すぐさま電話を代わると、私は少しうわずった声で「元気にしてましたか?」と言葉をかけた。
後日そのときの礼を手紙でもらっている。この前は折り返し電話をいただいて大変感激しましたといった言葉が丁寧に書かれていた。続けて、これからも誰にも負けない強い気持ちで頑張りますといった文面で、改めて歌手になる決意が綴られていた。消印は1978年12月16日。
このときも再び私は折り返し電話をかけている。そして「もう一度、東京に来てみませんか?」と提案していた。手紙だけではわからないこともある。久しぶりに顔を合わせて話した方が解決の道筋が見えるかもしれない。すると、今度の冬休みに東京の親戚の家に遊びに来るというではないか。私は聖子と会って話す約束をした。
大切な話は自分の口からきちんと言葉にして伝えるということ。それだけは、今も昔も変わらないことだったからだ。
モノレールで語った決意
年の瀬近い街にジングルベルが流れる頃、聖子と私は、麹町の日本テレビの近くにあった喫茶店で会っている。
聖子によると、東京の親戚宅に遊びに行くことについては、父親も賛成してくれたという。もしかしたら父親は、聖子がようやく歌のことを諦めて志望大学のキャンパス見学にでも行っていると思っていたのかもしれない。しかし実際に訪れていたのはCBS・ソニーのある市ヶ谷からもほど近い、小さな喫茶店だった。
しばらく話すと、聖子はせきを切ったように切々とデビューへの熱い思いを伝えてきた。私の決意は変わりません。どうしても歌手になりたいのです。
「法子ちゃん、もう一度心を込めてお父さんを説得するしかないよ」
彼女は、強い意志をたたえた瞳で真っ直ぐに私を見て頷いていた。
このとき私は聖子を、浜松町からモノレールで羽田まで見送っている。冬の夕陽が長い影とともに車内を赤く染めていた。湾岸方向に目をやると、次第に海が見えてくる。私と聖子は夕焼けに染まる東京湾やビル群を眺めながら、モノレールの座席に座っていた。すると夕映えの美しさを感じていたせいか、急に私の口からいつになくセンチメンタルな言葉がこぼれた。
「君はすごい才能を持っている。それは間違いない。だから僕は君の才能を信じて全てを賭けるつもりだ。その代わり法子ちゃんも覚悟を持って頑張ってほしい。しかしこの世界は、努力したから売れるものでもないし、どんなに曲が良くても歌がうまくても、必ずヒットが出るわけじゃない。運が大きく左右する。先が見えない日もあると思う。でも3年間はとにかく一生懸命頑張ってみよう。君ならきっと何かが掴めるはずだ。もしもそれでも夢が叶わなかったら、そのときは福岡に帰る日も来るかもしれない。それでも夢を信じて一緒に頑張ろう」
真剣な眼差しで聞いていた聖子は、小さく、でもしっかりとした意志を持って「はい」と頷いていた。まずは親の説得が先だが、既に私は彼女がスターになった日々のことを頭に描いていた。
プロデューサーとしてほとんど実績もない私に、不安がなかったと言えば嘘になる。けれど実績がないからこそ、真っ直ぐな気持ちで自分の直感を信じ情熱を注いだ。愚直だが、聖子の強い気持ちに応えるように、私も自分の人生を賭けるとそのとき決意を固めていたのだ。
冬の夕陽は羽田へと向かうモノレールの車内に熱いゆらめきを作っていた。
手紙に書かれた決意
それからすぐに1979年の新春を迎え、私は激動の予感をひしひしと感じていた。同時に英気をしっかり養い、その年の正月を過ごしたのを覚えている。
聖子からは新年の挨拶の意味も込めて3通目の手紙が届いていた。消印は1月6日。暮れに東京で会ったときのお礼や、歌手になったときのことも想像しながら、果たしてどれくらい頑張れるだろうかといった揺れ動く気持ちも綴られていた。東京へ来てみて、より現実のものとして歌手になる夢を捉え始めていたのだろう。
しかし最後には、これからも強い気持ちで頑張ります、と改めて決意がしっかりと書かれていた。
考えてみれば、手紙とは実にいいものである。自らのペンで気持ちを一文字一文字確認しながらしたためていく。その作業によって自分の思いと熱意がさらに固まっていくのだ。メールの気軽な楽しさもあるが、手紙は廃れてはならない文化だと思う。もしも夢を実現したいなら、手紙にして誰かに願いごとを送ってみるのもいいかもしれない。もちろん自分自身に送ったっていい。自筆の言葉が持つ力が時空を超えて倍増され、運を手繰り寄せていくからだ。聖子の手紙からは、そんな力さえ感じられた。
「娘がどうにもならないんだ」
すると仕事始めから間もない1月中旬頃、突如制作6部(注・若松さんの所属部署)へ福岡から電話がかかってきた。電話の主は聖子の父親であった。
「若松さん、すまない。ちょっと急ぎで久留米まで来てもらえないだろうか。娘がどうにもならないんだ」
電話越しの父親はいつになく動揺していた。いったいどうしたことか!? 暮れに聖子に会ってから何か蒲池家に起きたのだろうか。私はあわてて間に合うフライトで福岡へ飛んだ。久留米は当時空港から西鉄福岡駅へタクシーで移動し、急行で1時間ほど。夕方には駅前に到着していた。
会合場所に指定されたのは駅前のレストランだった。店のドアを開けて2階の個室へ行くと、聖子と両親が神妙な面持ちで待っていた。一瞬、まだ許しが出るわけではないのだろうかと怯んだものの、父親から告げられたのは、愛情深い親ならではの熱い言葉だった。
「娘が言うことをどうしても聞かない。家出をするとまで言っている。こうなると親としてはもう彼女の夢を叶えてやるしかない。若松さん、あなたに私の娘を預けます。他でもないあなたに預けますので、責任を持って預かってください。私はあなたを信じます」
心の奥底を覗き込むように真っ直ぐに私の目を見て話す父親の言葉に、私は身が引き締まる思いがした。ついに雪解けの日が来たのだ。聖子の想いにほだされて、父親も翻意するしか道がなかったのだという。
世の中ではあちこちで、私が聖子の父親を説得したという話になっている。確かにそれも真実だ。しかし同時に、本当の意味で父親を説得し強い気持ちで許しを勝ち得たのは聖子自身だったのだ。長かった。聖子の声を初めてテープで聴いてから既に半年が過ぎていた。西鉄グランドホテルで父親と会ったことも無駄ではなかった。あのときに誠意を持って長時間話したことで、父親は少なからず私を信頼してくれていたのである。ようやく許しが出て涙ぐむ聖子とそれを見守る母親。
父親の頭髪には以前に会ったときよりも明らかに白く光るものが増えていた。そこで私は初めてこの一件が随分と父親に心労をかけていたことに気づいた。そして、一人の歌手の卵の人生を預かる責任を改めてしっかりと受け止め、同時に、必ず聖子をスターに育てるという決意を新たにせずにはいられなかった。
***
1980年4月1日、松田聖子は「裸足の季節」でデビューを果たす。すぐにトップアイドルとなった彼女は40年以上たって、中央大学法学部通信教育課程を卒業した。進学を強く望んでいた父のことは脳裏に浮かんだだろうか。
※『松田聖子の誕生』から一部抜粋、再構成。
若松宗雄(わかまつ・むねお)
1940(昭和15)年生まれ。音楽プロデューサー。CBS・ソニーに在籍、一本のカセットテープから松田聖子を発掘した。80年代後期までのシングルとアルバムを全てプロデュース。ソニー・ミュージックアーティスツ社長、会長を経てエスプロレコーズ代表。『松田聖子の誕生』が初の著書。
デイリー新潮編集部








































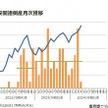

































































































![[重賞回顧]師弟で掴んだ王者の称号。長期休養を乗り越えたテーオーロイヤルが古馬最高の栄誉を獲得!〜2024年・天皇賞(春)〜](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33150.png)





