今クールのドラマで一番の盛り上がりを見せた「不適切にもほどがある!」(以下「不適切」)が、今夜最終回を迎える。【成馬零一/ドラマ評論家】
「話し合いましょう」と急に歌い出して…
金曜ドラマ(TBS系金曜夜10時枠)で放送されている本作は、昭和61年(1986年)から令和6年(2024年)にやってきた体育教師の小川市郎(阿部サダヲ)が巻き起こす意識低い系タイムスリップコメディだ。
脚本は宮藤官九郎、プロデュースは磯山晶。「池袋ウエストゲートパーク」(2000年、長瀬智也主演)、「木更津キャッツアイ」(2002年、岡田准一主演)、「俺の家の話」(2021年、長瀬智也主演)といったTBSの名作ドラマを多数手がけてきた2人が、本作では令和のテレビ局を舞台に、ハラスメントやSNSの炎上といった現代社会の問題を「笑い」によって浮き彫りにする痛烈な社会風刺ドラマとなっている。
劇中では、令和の日本に蔓延する様々な問題が描かれる。第1話では、アプリ開発会社で働く秋津真彦(磯村勇斗)が新人女性社員に対して「頑張ってね」と声を掛けたことが、パワハラだと上司から指摘される。
「さすがZ世代」と世代で括ればエイジハラスメント、「嫁さんにする男は幸せだね」と言えばセクシャルハラスメント。相手が不快になったら、それはもう「ハラ」なんだよと言われてしまう秋津。
彼らの会話を聞いた市郎は割って入り、「頑張って」と言った彼が責められるのは間違っている、じゃあどうすればよかったんだ? と問い返す。
その後、上司に反論する市郎の意見に興味を持った秋津が「話し合いましょう」と急に歌い出し、歌に乗せて自分の意見を主張するミュージカルシーンへと様変わりする。最終的にパワハラを訴えていた新人女性社員が登場して「叱って欲しかったんです」と歌い、オチがつく。
つまり、今の社会で問題となっているテーマについて意見が対立するもの同士がお互いの意見をぶつけ合う姿をミュージカルで見せていくドラマとして本作は始まったのだ。
中堅社員が抱えるジレンマ
次の第2話ではテレビ局のプロデューサーとして働きながら、子育てをする犬島渚(仲里依紗)が登場する。働き方改革の影響で、部下のAP(アシスタントプロデューサー)がシフト制で交代するので、渚はまともに仕事を教えることができずに疲弊。これなら1人で仕事をした方がラクだと思う場面が描かれる。そして第3話では、バラエティの帯番組の司会者の恋愛スキャンダルが起きて、ネットの炎上を恐れるあまり極端な自主規制に走る番組プロデューサーの姿が描かれる。
悩みの多くは、会社組織で働く中堅社員が直面するものだ。
コンプライアンスや多様性に対する意識が高まり、ブラック労働やセクハラ、パワハラといった問題を無くすために生まれた新しいルールによって表向きは健全化したように見える。しかし、その結果、後輩との意思疎通をうまく行えなくなり、上司と部下の間にいる中堅社員にそのしわ寄せがくる。
そうでありながら、正社員としてキャリアを積んで安定した立場にいるように見える彼らは、会社の後輩や社会的弱者からは、恵まれた立場にいる成功者だと思われている。そのため、どちらが悪いのかという議論になると、即座に加害者認定されてしまう。
だからこそ彼らはパワハラとなることを恐れて、当たり障りのないことしか言えないのだが、その結果、新人との人間関係を構築できず、さらには仕事を教えることもできず、後輩がどんどん辞めていってしまうというジレンマを抱えている。
それぞれの時代に馴染む市郎とサカエ
第9話では犬島渚が、妊活に励む後輩のAP(アシスタントプロデューサー)の杉山ひろ美(円井わん)から、社内報での発言がアウディングだと疑われる。そして、渚が妊活で仕事に入れない杉山を気遣って口にした「だったらその週は、いないものとしてシフトを組んどくから、来れたら顔出して」という言葉が“プレ・マタニティ・ハラスメント”に該当すると言われ、1ヶ月の謹慎処分を受けてしまう。
第2話では、「働き方改革」を意識した上辺だけの配慮の影響で、やりたいように仕事ができないことにブチ切れた渚が夫と上司に「お願い」をする場面が軽快なミュージカルに乗せて爽快に描かれた。そんな彼女が今度はハラスメントの加害者として訴えられてしまう。
この9話が皮肉なのは、セクハラにあたる不適切発言を杉山におこなった市郎ではなく、渚が処分を受けて、社内に居場所がなくなってしまうことだ。
そんな渚を心配した市郎は、1往復分の燃料しかないタイムマシンで、渚を連れて昭和に帰る。最終的に市郎が昭和に帰るのはある程度、予測していたが、ハラスメントでキャンセル(排除)されて令和で居場所を失うのが市郎ではなく渚だったのは意外だった。
当初は不適切な発言と言動で周囲を翻弄する昭和の市郎の存在は異物として描かれていたが、市郎自身はスマホを筆頭とする現代のテクノロジーに興味を持ち、令和の価値観にみるみる適応し、テレビ局のカウンセラーとして現代に馴染んでいく。
令和から昭和にやってきた社会学者でフェミニストの向坂サカエ(吉田羊)も気が付けば昭和という時代を満喫している。最初は異なる価値観で周囲を翻弄するトリックスター的存在だった市郎やサカエが、それぞれの時代の空気に馴染んでいくのが「不適切」の面白さだ。そこには人間の価値観はその時代の空気に簡単に染まってしまうもので、それくらい人の価値観なんて流動的なのだという、作り手の人間観が滲み出ている。
「ゆとりですが」でも描かれたハラスメント疑惑
市郎やサカエのような人は、環境が変わってもすぐに適応して馴染むことができる特別な存在だ。対して、労働環境やハラスメントに異を唱える人や、世間がうるさいからという建前上の理由だけで世間の価値観に合わせることができるテレビ局の上層部も、立場こそ真逆だが令和の価値観を生きているといえるだろう。
渚のような令和の価値観に表面上は合わせて適応しているが、違和感を抱えている。そんな上司と部下の間で板挟みになっている30代の中堅に皺寄せが向かっているというのが「不適切」が描く令和に対する現状認識だ。
渚は34歳で、世代で言うとゆとり世代にあたるのだが、2016年に宮藤は、1989年生まれのゆとり第一世代の3人の男性を主人公にした連続ドラマ「ゆとりですがなにか」(日本テレビ系、以下「ゆとり」)を手がけている。
「ゆとり」で、主人公の1人であるサラリーマンの坂間正和(岡田将生)が後輩の山岸ひろむ(仲野太賀)に、仕事中の発言を逆恨みされ、ハラスメントで訴えられる場面を、渚がハラスメントで訴えられるシーンを見て思い出した。劇中で「ゆとりモンスター」と呼ばれている山岸は、同じゆとり世代の坂間でも理解不能な得体の知れない怪物として当初は描かれた。
「不適切」の9話では杉山からパワハラで訴えられた渚が、杉山の弁護士と上司から聞き取りを受ける場面があるのだが、「ゆとり」にも坂間が山岸へのハラスメント疑惑について会議室で意見を聞かれるというそっくりな場面がある。
しかし、大きく違うのは「ゆとり」では、聞き取りに山岸も顧問弁護士と労働組合の代表と共に同席し自分の被害を訴えることだ。対して「不適切」では、被害を訴える杉山がその場にいない。
坂間を訴えるという主張は暴論で、上司も坂間の味方をしてその場で山岸を叱責する。その後、山岸は訴えを取り下げ会社に残り、坂間と山岸は対話を繰り返し、少しずつお互いを理解していくというドラマらしい展開になっていくのだが、2016年のドラマでは描くことができたクレーマー化した若手社員との対話が、2024年の「不適切」ではできなくなっていることが、この2作を比較するとよくわかる。
平成世代の渚は令和に戻ってくるのか?
昨年(2023年)劇場公開された「ゆとり」の続編映画「ゆとりですがなにか インターナショナル」では、かつての坂間と同じ中堅社員となった山岸がZ世代の新卒社員から訴えられる場面が序盤で描かれる。そして山岸も2ヶ月の謹慎を言い渡される。
かつて坂間を訴えたあの山岸が、下の世代からパワハラで訴えられるという因果応報的な展開は描写もコミカルなので笑ってしまうが、被害を訴えているZ世代の新卒社員の何人かは査問の席に直接姿を現さず、リモートで参加していることにも注目したい。まともな対話ができないことがすでに暗示されているのだ。
「ゆとり」は宮藤にとって転機となった作品である。本作以降、漫画、音楽、アイドル、テレビ番組といったポップカルチャーのあるあるネタと同じ頻度でハラスメント、LGBTQ、待機児童問題といった社会性のある話題が劇中で頻発するようになり、社会派コメディのテイストが強まっている。
「不適切」はそんな社会派コメディの極地と言える作品だが、ここで描かれる問題の萌芽は「ゆとり」の時点ですでに描かれていた。だから、平成の終わりに作られたドラマ版「ゆとり」と、働き方改革とコロナ禍を経た令和5年に作られた映画版「ゆとり」を比べると、わずか7年の間にこんなに社会は変わったのかと驚かされる。
「不適切」では昭和と令和の極端な違いが強調されているが、劇中で描かれている令和の問題は、平成の終わりに作られた「ゆとり」を間に挟むと、どのようなグラデーションで社会が変わっていったのかが、理解できる。
昭和と令和の比較で話が進むため、平成が描かれていないように見えてしまう「不適切」だが、世代で言うと現在30代のゆとり世代の中堅社員である渚たちの存在が、劇中で透明化されている平成という時代を象徴していると言えるだろう。そんな彼女が本作では一番疲弊している。
「話し合いましょう」という対話の可能性を模索する場面から始まった「不適切」だが、話が進むごとに露わになっているのが、話し合いが成立しない令和社会の構造的な問題で、それが決定的に露見したのが第9話だったのではないかと思う。
令和という時代に絶望を感じ、昭和に向かう市郎と渚だが、果たして彼女は再び令和に帰ってくるのだろうか?
どんな小さな理由でもいいので、渚が令和に戻るに値する希望のようなものが見える終わり方を期待している。
成馬零一(なりまれいいち)
1976年生まれ、ライター、ドラマ評論家。単著に『TVドラマは、ジャニーズものだけ見ろ!』(宝島社新書)、『キャラクタードラマの誕生 テレビドラマを更新する6人の脚本家』(河出書房新社)がある。
デイリー新潮編集部


































































































































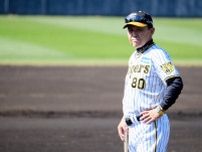
![[競馬エッセイ]関東の刺客と呼ばれたライスシャワーの歩み](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-31945.jpeg)






