「サッチー・ミッチー騒動」で世間の注目を集めてから早くも四半世紀がたちました。剣劇役者・浅香光代さん(1928〜2020)です。実力に裏付けられた確かな芸で、圧倒的な人気でした。気っ風が良くて義理堅く、「情の人」でもあった彼女の生き様とは――。朝日新聞の編集委員・小泉信一さんが様々なジャンルで活躍した人たちの人生の幕引きを前に抱いた諦念、無常観を探る連載「メメント・モリな人たち」。今回は無類の役者魂!を見せた、浅香さんの人生に迫ります。
「あたしゃ、許さないよ!」
遺言や葬儀などを準備し、「自分らしい最期」を飾ることを「終活」と呼ぶ。この人の場合は、昔の舞台衣装を早稲田大学演劇博物館に寄贈したことが終活だった。胸のすくような豪快な女剣劇で圧倒的な人気を得た女優の浅香光代(本名・北岡昭子)さんである。
「剣劇」という芸をよく知らなくても、元プロ野球選手・野村克也さん(1935〜2020)の妻・沙知代さん(1932〜2017)の言動を批判して論争となった、1999年の「サッチー・ミッチー騒動」で記憶している人も多いだろう。
「あたしゃ、許さないよ!」
と江戸っ子らしい歯切れのいい啖呵を切り、沙知代さんに向かっていった浅香さん。テレビキャスター、コメンテーター、リポーター……と舞台以外でも活動の幅は広かった。プロレスの試合に参戦したこともあった。
2019年10月、末期がんが判明したが、高齢だったこともあり手術はしなかった。そのあたりも江戸っ子らしい潔さを感じさせる。翌20年12月13日、膵臓がんのため92歳で亡くなった。
筆者が親しくなったきっかけは、2010年8月、肺がんのため65歳で亡くなった芸能リポーター・梨元勝さん(1944〜2010)の取材だった。マイクを手に「恐縮です!」を連発しながら直撃取材を敢行した梨元さん。実は、仕事の合間を縫って、浅草にあった浅香さんの稽古場に通っていたのである。
「私とはツーカーの仲で、浅草のお祭りにもよく来てくれましたが、最初は弟子にするつもりはまったくありませんでした」
と浅香さんは言った。踊りのことをよく知っているかのように話すので、「あなたね、ちょっと違うんじゃないの。きっちり勉強したら」。そう一喝したそうである。それがきっかけで「名取になるまで頑張る」と梨元さんは弟子入りを決意したという。
全国に3000人以上の門弟がいる「演劇舞踊浅香流」。梨元さんは浅草公会堂の舞台にも出演。会場では「梨元の瓦版」と題し、自らが編集した芸能ニュースを配布。演劇舞踊浅香流の「広報部長」としての活動にも尽力した。
「川の流れと同じ。逆らわない」
気っ風が良くて義理堅く、負けず嫌いで意地っ張り。細かな気遣いを見せる「情の人」でもあった浅香さん。経歴について簡単に触れてみよう。
1928(昭和3)年2月、東京・神田の生まれ。盆も正月も祭りもない侘しい暮らしだったという。父親が株で失敗。母親が働く料亭の常連客に紹介され、9歳のころ新興キネマの映画俳優だった浅香新八郎(1906〜1944)と森静子(1909〜2004)の内弟子となった。
14歳のとき独立。新生国民座の少女座長となり、師匠の「浅香」をもらって「浅香光代」とした。戦前戦後を通じて女剣劇の役者として活躍する。
ヤンヤ、ヤンヤの人気を呼んだのは、激しい立ち回りだった。着物の下から真っ白な太ももが見えてしまうことが何度もあった。男らしく勇ましい演技を見せても、ほんのわずか、もろ肌をチラリとのぞかせる姿が何とも悩ましかった。
「周りからは『品のない剣劇』と陰口をたたかれました。『女を武器に客を釣るのは邪道だ』とまで言われたんです。でも、格好なんかかまっちゃいられなかったわよ」
長かった戦争がようやく終わり、人々が娯楽に飢えていた時代でもあった。浅草松竹演芸場では、押すな押すなの人気に10カ月の続演になったこともあったという。
80年超の芸能生活。浅草寺の北側にあたる「奥浅草」と呼ばれるあたりに自宅兼事務所があった。下町情緒あふれる土地柄である。浅香さんは「昔、こんな話があったのよ」と前置きしたうえで、
「シャケ(鮭)2切れ、340円で買って、千円札を1枚出したら、7千円のお釣りがきた。『苦労してんだろ。祝儀だ。持ってけ』と言うんです」
貧乏のつらさは骨身にしみた。亡くなった母親の遺言は「カネがないと人生駄目だよ」。でも、浅香さん自身、金に執着する気持ちはさらさらなかった。株も手がけたが、「川の流れと同じよ、逆らわないの」。
恋多き女性だった浅香さん。大物政治家との間にできた子どももいた。大物政治家って誰なのか? 晩年、あれこれ臆測が飛び交ったが、本欄ではこのことについては触れないでおこう。ただ、生まれてきた子どもを立派に育てたことは忘れないでほしい。人間・浅香光代は、やはり義理堅い人でもあった。
「日本の男は女の抱き方が下手」
さて、女が男に扮してチャンバラをする女剣劇について、もう少し述べておきたい。戦火が拡大し言論統制が強まった1939(昭和14)年ごろから人気を呼んだ女剣劇は、男中心の社会に対する皮肉や風刺を感じさせた。浅草では大江美智子(1910〜1939)、不二洋子(1912〜1980)、中野弘子(1922〜1996)が人気を得ており、戦後の女剣劇を支えたのが浅香さんだった。
その浅香さんについて興味深い論考がある。浅草に育った作家や俳優、芸人、歌手たちの人生を情感豊かに綴ったエッセー集「浅草のひと 久保田万太郎から渥美清まで」(東京新聞出版局)の著者・鈴木としおさんが書いている。
《彼女(註・浅香光代)の鍛え上げた芸の力が彼女の人気を支えているのはいうまでもないが、いま一つ、見落とすことができないのは天性の朗質ともいうべき彼女の屈託のない人柄である。これは彼女の余人以上の生い立ちの苦労、血のにじむ思いの修業の積み重ね、それに反するもって生まれた陽性の芝居、容姿と素質があったればこそと思う》
そんな浅香さんが、地元の台東区から浅草芸能大賞を贈られたのは1987年だった。主な受賞理由は「女剣劇の第一人者で、浅草に生まれ育ち、身につけた芸境は天下一品。舞台の他テレビにも出演。さらに自己研鑽のため浅香ミニ劇場を主宰し、年2回の定期公演をするなど、常に前向きの一貫した姿勢をとっている」というものだった。
受賞の喜びを「浅草で育った私にとっては、ほかのどんな賞よりうれしい」と語った。その言葉に偽りはなかった。浅香さんは地元浅草では様々な活動に奉仕。本当にまめで、警察や消防の1日署長を務めたり、自分のミニ劇場にお年寄りを無料で招待したりするなどきめ細かい心遣いをした。
その一方、前述した野村沙知代さんとの「ミッチー・サッチー騒動」のときと同じように、ピリリと辛口や風刺を効かせたコメントは秀逸だった。「余白を語る」と題した朝日新聞のインタビューに、こんなことを言っていた。
《日本の男は女の抱き方がへたですね。私は舞台で男役をやっているからよくわかるんだね。この前、新幹線のホームで若い男女が抱き合ってキスしていた。それもうしろ手したままね。あんなんならキスするより、小指をおたがいにからませての愛情表現のほうがいいな。抱き方の美学がなっていませんよ、ただべたべたするだけじゃあね》(朝日新聞1991年4月5日夕刊文化面)
「年をとるほど恋愛をしていたい」とも言っていた浅香さん。「いくつになっても抱いてみたい女でありたいわ」とまで公言していた。
《80歳すぎたって、おかねがいくらかかってもきれいになりたいね。色気がなければ舞台もつとまりませんよ。恋愛や男友達はとしをとるほど必要なんじゃない。それがなければ人生つまらないじゃないの》(同上)
舞台ではジャズのリズムで立ち回りをしたこともあった。歌手の淡谷のり子さん(1907〜1999)が見て、「流行りのアイドル歌手よりうまい」と褒めてくれたらしい。
89年、当時の首相・宇野宗佑氏(1922〜1998)の愛人スキャンダルが世間を騒がせたとき、「女が悪い。影の女なら表へ出てくるな。だいたい政治家(男)はみんな嘘つきだ。浮気のできない男なんて駄目」と言っていた。もしも、いま同じような発言をしたら、あちこちから批判が噴出するに違いない。だが「あたしゃ、許さないよ!」と持論を展開するのが浅香さん。完全にアウトな発言でも、曲げることはしないだろう。
次回は、9年前、54歳で早世した女優・歌手の川島なお美さん(1960〜2015)。青山学院大学在学中に芸能界デビューし、女子大生タレントの先駆けとなった川島さんの生涯をたどる。
小泉信一(こいずみ・しんいち)
朝日新聞編集委員。1961年、神奈川県川崎市生まれ。新聞記者歴35年。一度も管理職に就かず現場を貫いた全国紙唯一の「大衆文化担当」記者。東京社会部の遊軍記者として活躍後は、編集委員として数々の連載やコラムを担当。『寅さんの伝言』(講談社)、『裏昭和史探検』(朝日新聞出版)、『絶滅危惧種記者 群馬を書く』(コトノハ)など著書も多い。
デイリー新潮編集部








































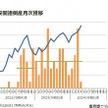

































































































![[重賞回顧]師弟で掴んだ王者の称号。長期休養を乗り越えたテーオーロイヤルが古馬最高の栄誉を獲得!〜2024年・天皇賞(春)〜](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33150.png)





