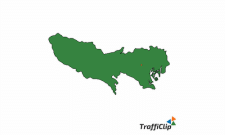知らなくても生きていけるが…
「ムナカタシコウってそれ、なんですか? 人の名前ですか?」
と初めて高校生から質問された時は頭の中が真っ白になったが、2回、3回、4回とさらには大学生からも質問が続くと、「面白い。この現実から私は逃げないぞ」と、どうやったら棟方志功が若者とリンクするのかの試行錯誤をするようになった。
「世界的に有名な版画家です」と言ったって、そんなことは自分の人生には関係ない。いかに自分の生き方に影響を与えてくるかが肝なのだ。
「ムナカタシコウ、知らなくったって生きてけます。でも棟方志功が心の中に住んでいると、生き方が変わってきます」
42歳で富山県に疎開
あまり知られていないが、現在唯一、棟方志功の暮らしていた家は富山県に残っている。青森に生まれて東京で活躍した棟方志功の家がなぜ富山にあるか、といえば疎開である。
棟方志功42歳はチヤ夫人と4人の子供たちと、東京から逃れて富山県福光町(現・南砺市福光)にやってきた。その福光にきた1カ月後に東京の借家は空襲で燃え、そして志功はこの疎開の地で生まれて初めての自分の家を持つことになる。
借家暮らしが長かった志功は、誰にも遠慮がいらない初めての自分の家が嬉しくてならず、家中の壁や天井、板戸に勢いよく筆を走らせた。「愛染苑」と名付けて5年間暮らしたこの家は今も歓喜ほとばしるままに、棟方志功記念館の一部として公開されている。
私は学芸員になる直前、この記念館に勤めたが、それはそれは至福の時であった。私の心は終始、棟方志功にときめいて仕方なかったのだ。棟方志功の作品もそうなのだが、そもそも人間・棟方志功が好きなのだ。
女性目線で語られた志功
志功の愛くるしいキャラクターと画業への真っ直ぐな情熱に魅了されて志功を語った人は多い。しかし、一つ大きく欠けたものがある。女性目線で語られた志功である。そもそも生涯志功と一緒に道を歩んだチヤ夫人がいかにして棟方志功に出会い、そして心を持っていかれたか。そんな文章に私は出会ったことがない。
しかしここにきて出会えたのだ。
原田マハの『板上に咲く』(幻冬舎)。
チヤが志功の心に吸い込まれていく瞬間を描いたヒラメの焼き魚のシーンは美しい。「……忘れね。ワ、この瞬間、一生、忘れね」と志功は小説の中で呟くが、私の中でも一生忘れられない景色となって焼き付いてゆく。
そこから紡がれる2人の物語は山越え谷越えやがて疎開の地「福光」にたどり着き、そしてクライマックスを迎える。チヤが志功と再会を果たすそのかたわらにポツンと立つ赤ポストは、代替わりしながらも今も福光の同じ場所に立っている。私にとって見慣れたポストのあの商店街にたちまちスポットライトが当てられて、私の中で特別な場所になった。
志功の人生に存在した3つのハンデ
志功は生きている間に「世界のムナカタ」として名を成し、たくさんの仲間や家族に愛されながら一生を終えていく、恵まれたアーティストだった。しかし、そんな志功の人生はハンデだらけの中で始まった。
まず第一に目が悪かった。画家になりたい人が目が悪い、なんてことは画家にとって致命的なハンデである。第二に、今よりずっと画壇が権威を持っていた100年前に、その枠からはみ出たところで頑張っていた。何をどう頑張ったら世の中に出ていけるのかイメージできない世界である。
そして第三に、文化の中心地である東京から離れて片田舎の富山に疎開しなければならなかったことである。戦後の物のない時代の疎開者は、生活するだけでも肩身の狭い立ち位置である。どこを切り取ってもハンデだらけなのだがしかし、志功はそれら全部をプラスに転じて生きていく。
第一と第二のハンデの転じ方はここでは割愛し、福光の地からは第三の疎開のハンデについて語ろうか。
肌身で学んだ浄土真宗の「他力」
志功が疎開していた今から約80年前、福光近辺は浄土真宗が非常に盛んだった。どのお寺でも毎朝ご門徒たちが集まり読経を上げ、法話を楽しんだ。仏教には様々宗派がありそれぞれに特徴があるのだが、浄土真宗が肝にしているのは「他力」である。
この「他力」こそ、志功が生涯追い求めていたものだった。「他力」とは、他人のおもわくに身を委ねる、ということではない。空気を読むでも流されるでもない。「人間の意識」が及ぶ程度のそんなちっぽけなものではない、もっともっと大きな仏様の力に身を委ねる、ということである。
志功は福光で何人かの住職と親しくなり、そのお寺に毎日のように通い、住職と語り合い、朝には地元の人たちと一緒にお経を唱えた。浄土真宗の「他力」を、肌身で学んで染み込ませていったのが福光の疎開時代であった。
「私は自分の作品に責任を持っていません」と志功は言う。
「私の手足を、仏様が動かすんです。棟方志功というこんなちっぽけな一人の人間の力で仕事をしていません。もっともっと大きな力で仕事をしているんです。私は、自分の仕事に責任を持っていません」
福光以降の作品にある「泳ぐような浮遊感」
志功の画風は福光で大きく変化していった。
記念館に勤めて毎日志功の作品を眺めていると、だんだん目が慣れてきて「あ、これは福光以前の作品。これは福光以降だね」と見えてくる。福光以降の作品は力が抜けて泳ぐような浮遊感があるのだ。
疎開を終えて東京に戻っていった志功はやがて世界で認められていくのだが、その第一歩となる初の国際展での受賞作は福光で生まれている(「女人観世音板画巻」)。
というと福光で志功の才能が開花したような誤解を生むのだが、実は「世界のムナカタ」として本格的に名を知らしめるきっかけの一つとなった作品は、福光に来る以前にすでに仕上がっていた。志功の代表作中の代表作「二菩薩釈迦十大弟子」である。
この作品の板木は本当であれば、東京の空襲で燃えて灰になっているはずだった。しかし志功の妻チヤが戦火に呑まれる直前に「釈迦十大弟子」の板木を東京から福光に危機一髪で疎開させた。
残念ながら「二菩薩」の板木は燃えてしまったが、助け出された「十大弟子」は、福光で彫り直された新しい「二菩薩」と共にベネチア・ビエンナーレに出品され、大賞を受賞し志功の名を世界に轟かせていったのだった(写真中の屏風「二菩薩釈迦十大弟子」の両脇には、板木が燃える以前に刷られた「二菩薩」が展示されている)。この奇跡のいきさつは『板上に咲く』でぜひお楽しみいただきたい。
制作中の志功が頭に巻いているモノは?
ところで、志功が無心に板画を彫っている姿を動画か写真でご覧になったことがあるだろうか。ちょっと注目していただきたいのは、その真っ最中の志功の頭である。
いつもぐるりと頭に「何か」が結ばれている。志功は汗、唾、涙、鼻水、興奮すれば何かしらを辺りに飛び散らせて分泌液が多い。だから私は最初、「これは汗どめのタオルだろう」と思っていた。ところがよく見ると、それはタオルでも手拭いでもなく、和紙をこよった「ヒモ」なのだ。
棟方志功を知らなくても生きていける。でも、棟方志功を知っていると、生き方が少し変わる。
志功は自分の中に宿る仏様を祀って生きた人である。
土居彩子(どい・さいこ)
1971年富山県生まれ。多摩美術大学芸術学科卒業。棟方志功記念館「愛染苑」管理人、南砺市立福光美術館学芸員を経て、現在フリーのアートディレクター。
デイリー新潮編集部