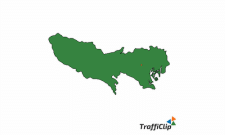満州国皇帝の姪・愛新覚羅 慧生(えいせい)と青森県八戸市出身の大久保武道。昭和31年に学習院大学で始まったふたりの恋は、翌年の末にピストル心中という最後を迎えた。その場所は静岡県の天城山。当時のマスコミが「天国に結ぶ恋」と大きく報道する一方、双方の家族は「無理心中」と「同意の上」をそれぞれ主張した。一体ふたりはなぜ永遠の旅立ちを選ぶに至ったのか。慧生の親友や武道の実弟の貴重な証言を交えて愛の軌跡をたどりつつ、いまだ明らかにならない真の動機に迫る。
(前後編記事の前編・「新潮45」2005年6月号掲載「昭和史 女と男の七大醜聞 『天城山心中』愛新覚羅慧生の女ごころ」をもとに再構成しました。文中の年代表記等は執筆当時のものです。 文中敬称略)
***
小綺麗な男女の服装
若い男女を乗せたハイヤーが、でこぼこの峠道を慎重に踏みながら天城トンネルに達したころには、日はとっぷりと暮れ、辺りは漆黒の闇が佇むばかりだった。
昭和32年12月4日、時刻は午後5時半を回っていた。修善寺駅からの客であった男女は、トンネル口で車を止め、運転手に2000円を手渡している。実際の料金は1380円――。
ふたりはトンネル脇から延びる急峻な登山道に、すぐに足を踏み入れようとした。小綺麗な男女の服装、足下を見た運転手に一抹の不安がよぎる。とても登山道の先、八丁池まで歩き着ける格好ではない。
運転手が、「いまお釣りがないので、降りてくるまで、ここで待ちましょう」と言うと、男性は「地理はよく知っているから、帰ってかまいません」と返した。そして少し登りかけて引き返し、運転手に訊いた。
「最終のバスは何時でしょう」
無理心中か合意の上か
それを確認した男女は、再び鬱蒼とした林間に向かったのである。いつからか、初冬の冷たい雨粒が、山肌を静かに洗いはじめていた。不審感を拭いきれなかった運転手は、そのまま湯ケ島の警察署にハンドルを回している。
のちに女性は、満州国最後の皇帝溥儀の姪、愛新覚羅慧生とわかる。学習院大学の2年生で19歳だった。交際相手の20歳の男性は、級友の大久保武道。その夜のうちに、ふたりは天城山中で拳銃自殺を遂げた。
死をめぐる見解は、両遺族間で行き違った。愛新覚羅家側は「連れ去りによる無理心中」とし、大久保家側は合意の上の死とした。誤解をとくため、数年後には、恩師や親友らの手を借り、ふたりの交わした書簡集が出版されるにいたる。
だが、別々の墓地に納まった遺骨が、一緒になることはついになかった。
ラストエンペラーの姪
愛新覚羅慧生は、昭和13年2月、満州国の首都新京(現長春)で生まれている。父は満州国皇帝溥儀(ふぎ)の実弟・溥傑(ふけつ)。母は、侯爵・嵯峨実勝(さが・さねとう)の長女・浩である。
日清友好の礎として、関東軍幹部からこの縁談が持ち上がった当時、溥傑は日本の陸軍士官学校を卒業し、千葉の歩兵学校に学んでいた。話の背景には、皇帝溥儀に嫡子がないという差し迫った事情があった。
6歳になった慧生は昭和18年、浩の母校・学習院で教育を受けるため嵯峨家に預けられた。その半年後、溥傑の陸軍大学校入学に伴い、母と乳飲み子の妹・嫮生(こせい)も来日したが、昭和20年2月に、在学中の慧生のみを残して一家は満州に戻っていった。そして8月の終戦である。ソ連に捉えられた父溥傑と、嫮生を連れて、過酷な逃亡生活を強いられた母の消息は、ぷっつりと途絶えてしまった。
浩と次女が、佐世保港に辿り着いたのは、1年半後の昭和22年1月だった。慧生が身を寄せる横浜市日吉の嵯峨家邸で、親子3人の暮らしがはじまっている。8年のち、溥傑は撫順(ぶじゅん)の戦犯管理所にいることが確認された。
同級生の野暮ったい青年
溥傑の釈放と家族再会を待ち望む母娘の暮らしが9年目を迎えた昭和31年春に、慧生は学習院大学文学部国文科に進んだ。母との話し合いで、東大の中国文学科への進学を諦めての、選択だった。
約30人の国文科の級友のなかに、八戸出身の大久保武道がいた。坊主頭に酷いニキビ顔、流行らない丸眼鏡。雨でもないのに長靴履きといった青年は、級友から浮いた存在だった。抜けきらない東北訛りが、野暮ったさに輪をかけた。だが慧生だけは、わだかまりなく彼と言葉を交わした。
就学して3カ月ほどが過ぎた。6月26日に、なにかのリサイタルにふたりで出かけたことが、武道の日記に記されている。
「目白の東京パン食堂部で食事し、慧子(慧生のこと)の身上話を聞かされた。慧子との交際の本格的な第一日であったのだ。品川経由で有楽町に出た。この日こそは生涯の一重大事の発端をなしたのだ。愛新覚羅慧生なる人の家も一応は知ったし、同情を禁じ得なかった」
一年半後に死を覚悟した武道は、毎日つけていた日記を処分したが、表紙だけとなったノートに、この一枚だけを残していた。
雰囲気が優雅で、華があった
慧生と武道、それと高校一年生から慧生の親友だった三好明子(旧姓・木下)の3人は、よく一緒の時間を過ごした。
天城山心中から50年近い歳月が流れたいまも、明子のなかで当時の思い出は、一向に風化していなかった。
「エコ(慧生のこと)ちゃんは、だれとでもよく話し、みんなから好かれていた。すごい美人でもないんだけど、体中からにじみ出る雰囲気が優雅で、華があった。だから、人が周りに集まってくる。でも、どういうわけか特定の友だちがいなかったの。彼女は、少し高所から人を突き放してみるようなところがあって、それが他人との親密な関係を阻んでいたような気がするんです」
名家の子女が集まり、ややもするとグループ間の垣根が高くなりがちな気風が学習院にはあった。高校1年生の春、病気のために、1年進学が遅れた明子は、この環境にやや戸惑った。そんなときに声をかけてきたのが慧生だった。
ふたりは学校で会うと毎日2、3時間おしゃべりし、高田馬場 の校舎から新宿駅まで、肩を並べて歩いて帰るようになる。長期休暇に入れば、慧生が毎日のように近況を伝える手紙を送ってきた。
旧侯爵家の複雑な内情
「手紙などを読むと、最初、大久保さんが一方的に彼女に夢中になったと思われますでしょ。でも、私はそうは思わないんです。彼女は気さくな人柄でしたが、真意はめったに他人に漏らしたりしない。ところが、大久保さんにはいきなり自分の身の上を、話して聞かせているでしょう。そんなこと、慎重な彼女にはまずあり得ないこと。大久保さんは、彼女の身の回りには、いなかったタイプ。あのあまりに木訥な誠実さに、最初から強く心を惹かれていたんだと思うのね」
もっとも慧生は、「身の上相談所長」と敬愛する明子だけには、自分が暮らす旧侯爵家の複雑な内情をよく語って聞かせていた。
あるときのそれは、高価な家財を切り売りして、家計をまかなう戦後華族の苦しい台所事情だった。排水溝から流れ出た麦粒をめぐる騒動もそのひとつ。麦飯を食べていることが世間に知れては恥ずかしいと、家中に厳重な注意が下された顛末を吐露した。
慧生に課せられた生き方
またあるときは、お手伝いさんも入り乱れた家庭内の歪んだ人間模様を、苦々しげに語った。名門同士が絶対の条件であった親族の結婚問題も、何度か話題となった。祝福されぬ恋愛を貫き、嵯峨家と疎遠になりながら、平凡だが平安な家庭に収まった人。身分的には申し分ない縁談だが、夫婦間に修羅場を抱える人など。いずれも名門なる仮面を尊ぶがゆえに生じる、皮肉な現実だった。
初めて武道とふたりだけでリサイタルに出かけた日から1カ月後の7月30日に、明子に送った手紙がある。
「あと四年つきあえば、どうなるかきまるでしょうけれど、やっぱり母は反対だと思います。それを押しきってまで結婚するということは、私はしたくないし、青森氏(編注:武道のこと)にも悪いと思います」
「青森には、けっしてネツなんかあげませんからご心配なく。いたって冷静に観察中。それでは、何らかのご意見おきかせ下されたく候」
家名と逼迫する生活の狭間で、慧生は成績優秀だった自分に課せられた生き方を、肌で感じ取っていた。いずれ良縁をもって名実ともに、再び家名を盛り立てることだ。
慧生の深奥に居座る索漠とした不安
明子には忘れられない慧生の口癖がある。
「私は、母から期待されている。だけど妹のように可愛がられてはいない」
それは慧生の深奥に、黒点のように居座る索漠とした不安だった。戦後、中国大陸で生死の境をともにした母と妹の間には特別な絆があり、自分はそこには入っていけないと、ずっと感じていたようなのだ。
明子は、その痛みと慧生独特の男性への接し方が、妙に重なるのだと私に語った。妙に大人びていた慧生には、男友だちに対する不安定な距離の取り方があった。気持ちを寄せる男性を、はぐらかすような態度で翻弄するのだ。
「彼女は、多感な時期に親と離れて他家で育ったでしょ。幼いとき、充分に親の愛情を受けられなかった子って、いつも真実の愛を探そうとするものなのね。だからかな、恋人ができると、何度も相手の気持ちを試すようなことをするの」
武道の目の前で、急にほかの男性と親しげにしだして、ぷいっと一緒に帰ってしまうことが幾度かあった。結果、相手の男性に気を持たせることになり、ふたりの関係はなかなか落ち着かないのだ。
決闘騒ぎ、絶縁宣言
だが、大久保武道は、彼女の優柔不断な立ち回りに見事に振り回されながらも、駆け引きなど出来ぬ、まったく無垢な男だった。それだけに、反応は大きい。武道が別の男性と決闘騒ぎをおこし、慧生と明子、武道の恩師らが必死に止めに入る一幕まであった。
なんでも真に受けて、真っ直ぐ行動する武道をキリキリ舞いさせると、しまいには慧生自身がはらはらさせられる。その都度、「あなたの悪い癖よ」と明子が慧生をたしなめると、彼女はわかっているとばかりに、自己嫌悪に陥るのだった。
武道との交際をうとましく思い出した慧生が、ただの友人に戻ることを申し出たこともあった。このとき、彼は思い詰めて絶縁を宣言した。手紙の日付は、11月27日である。
「貴姉の御手紙は全部焼却いたします。小生の手紙はお返しくださいとは申しませんが、焼却せられたく希望いたします。今日以降没交渉なることを只今宣言いたします。なにかと非礼の段心よりお詫びいたし、且つ従来の御厚誼深く感謝いたします」
武道は思いを断つべく頭を丸め、合気道場で断食と座禅の荒行に入った。
別れ話は過去にも何度かあったのだが、最後には慧生が踏み止まった。「そうね、途中からエコちゃんの方が、彼に夢中になっていたのはたしかでしょう」と明子は、微笑ましげに回想に耽った。
***
大久保武道が「同情を禁じ得なかった」と記した愛新覚羅家の事情。一方で慧生の親友は、恋人の気持ちを試すような慧生の振る舞いについて、「真実の愛」を探すがゆえだと指摘した。だが、武道の同情心だけが、山中での最期に至った理由ではないようだ。後編では、武道の実弟が後年に明かした「父への反抗心」や、武道が抱えていた深い苦悩などから当時の心理を推測する。
後編【こめかみを撃ち抜かれ、指にはエンゲージリングが…「ラストエンペラーの姪」が遂げた心中事件の真相 相手男性が悩んでいた“父親の問題”】へつづく
駒村吉重(こまむら・きちえ)
1968年長野県生まれ。地方新聞記者、建設現場作業員などいくつかの職を経て、1997年から1年半モンゴルに滞在。帰国後から取材・執筆活動に入る。月刊誌《新潮45》に作品を寄稿。2003年『ダッカに帰る日』(集英社)で第1回開高健ノンフィクション賞優秀賞を受賞。
デイリー新潮編集部