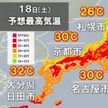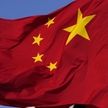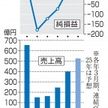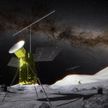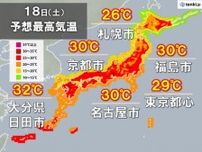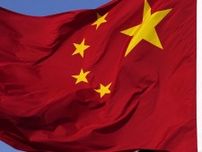前編【<東京裁判・開廷から78年>カネの問題、最も苦労したことは…速記者10人が語っていた裏話】からのつづき
第二次世界大戦後の1946年に開廷した「極東国際軍事裁判」、いわゆる「東京裁判」は、現在も様々な議論が存在する。研究本の類は現在も新刊が店頭に並び、4時間半を超えるドキュメンタリー映画「東京裁判」(1983年)は近年、終戦記念日に合わせた特別上映が定番化した。
いまだ関心が高いこの裁判は、日本の戦後を方向づけた歴史的出来事であり、多種多様な“登場人物”たちが織り成す人間ドラマでもあった。その両面を法廷の中央で見ていた者たちがいる。「人情のつれなさというものを身にしみて感じさせられた」――東京裁判から6年後、裁判記録の作成に従事した衆議院の速記者たちが語った言葉とは。
(前後編記事の後編・「新潮45」2010年12月号掲載「稀少資料入手! 国会速記者たちが語っていた『東京裁判』裏話」をもとに再構成しました。文中の年齢、役職、年代表記等は執筆当時のものです。文中敬称略)
***
パール判事は日本人トイレを使用
座談会の後半に入ると、出席者たちは、いよいよ裁判の登場人物の感想を述べ始める。
〈検察官ではフィリピンのロベス(原文ママ)というのがいましたね。あれが非常に威丈高になつて食つてかかるんだけれども、ああいう尋問の態度でもやつぱり大国民と小国民は違うんじやないかというような感じを持つたね。〉
〈毒舌を吐き、非常にゼスチュアを見せて、虚勢をはつているようなところが見えた。〉
「ロベス」とは、法廷で激しい対日批判を展開したことで知られるペドロ・ロペス検事と思われる。この直後、ロペスと対比させて、英国の検察官コミンズ・カーに触れている。
〈それと正反対なのがコミンズ・カーという検事です。イギリスの王室の法律顧問か何かしている偉い人らしいんだけれども、いつでも長身に黒つぽい古い洋服をまとうて、髪の毛はボサボサ(原文はくノ字点)にさして、地味に、淡々とやつていましたね。
真相は藪の中のゴシップも
続いて、A級戦犯を弁護した米国人の弁護人についても印象を述べている。
〈この間、日本で問題を起した弁護人がありましたね。女の人をだましたという――ブルックス。それからスミスというのがいたね。あれは裁判長に弁護人の資格を剥奪された。〉
「ブルックス」とは、元首相・陸軍大将の小磯国昭を担当したアルフレッド・ブルックスを指すとみられる。だが、なんとも興味深い「女をだました」事実については不明だ。
約30年前、米国で眠っていた東京裁判に関する機密文書を初めて研究、調査し、『東京裁判への道』(講談社)などの著書もある立教大学の粟屋憲太郎名誉教授に尋ねると、「その話は聞いたととがない。当時、出回っていたゴシップの類で話題になったのではないか」とのことだ。報道統制下だっただけに、真相は藪の中である。
「裁く側」に対する複雑な心情
一方の「スミス」とは、デービッド・スミス弁護士のことであり、豪州のウェッブ裁判長と対立して法廷から追放される憂き目に遭った人物として有名だ。ここで別の出席者たちがスミス、さらにウェッブについて語っている。
〈よく裁判長に食つてかかりましたね。〉
〈退廷するときの態度は、実にりつぱでしたよ。それに比べて、あの裁判長はどうです。〉
〈濠州自体、排日感情の盛んなところだが、その代表的人物という感じを受けたね。豪州では、五番目か六番目のえらい判事だというがね。結局濠州から裁判長を持つて来たというのは、アメリカの占領政策の一つですね。〉
「中立公正」が鉄則の速記者ではあるが、やはり「裁く側」には概して好印象を抱いていないようである。だからなのかどうか、有名な「被告全員無罪」を主張する意見書を出したインドのラーダ・ビノード・パール判事については、気さくな印象を抱いたようだ。
〈ただあのときの、インドの判事のパル氏ね。あれはいつ見ても、ニコニコしていたね。日本無罪論なんかも書いたし、実に堂々としていた。〉
〈あそこの二階の便所は、外人専用で日本人使用禁止なんだ。ところが彼はそとに行かずに、日本人の便所にやつて来て、用をたしていた。〉
日本人弁護団とウェッブの対立
日本人弁護団の副団長である清瀬一郎も登場する。“天敵”ウェッブとの対立ぶりをこう表現する。
〈日本人の弁護人で、あそこでよくしやべつたのは、清瀬一郎氏だ。〉
〈裁判長に、よくばかにされたようなことがあつたね、日本人の弁護人は。広田なんかは、証言のときに、歴代総理大臣中、かかる愚昧なる者は初めてであるなんて言われましたからね。〉
〈清瀬さんが、一度ちよつと英語でやつた。すると、裁判長が「あなたの英語はわからないから日本語で言ってくれ」(笑声)〉
粟屋名誉教授は次のように解説する。
「例えば、ウェッブは判事たちの間で半ば孤立し、食事も1人でとっていたそうだし、キーナンも同僚から嫌われていた。判事、検事、弁護団ともに一枚岩ではなく、そこにさまざまな人間模様があったのは事実」
人騒がせなラスト・エンペラー
裁判が進行する中で次々と登場する証人について座談会出席者は、「一番問題の多かつた」一人として、日本が建国した満州国の皇帝の溥儀(宣統帝)の名を挙げている。
〈傅儀(原文ママ)さんも、ずいぶんジェスチュアの多い人だった。(略)もつとおつとりし人柄かと思つていたら、そうでもないんだな。〉
〈あの人は、ロシヤ側からいろいろな制約も受けたところがあるのじやないかと思いますけれども、日本人としては(比較的単純な国民のせいかもしれないが)信じられないようなことを言つていた。〉
〈傅儀(原文ママ)さんの書いた、せんすの字の真偽が当時問題になりましたね。〉
〈強制されたとかなんとか、あすこで証言した。〉
溥儀は終戦後にソ連軍に逮捕され、東京裁判の証言台に立った。唐突に出てくる「せんすの字」については、粟屋名誉教授は「扇子については調べてみないと分からないが、満州国建国を推し進めた関東軍に無理に書かされたという自筆の証文を指しているのではないか」という。
実際、溥儀は法廷で、「関東軍によって、傀儡として帝位に就かされた」などと主張している。さらに言えば、後に自伝『我が半生』を世に出し、東京裁判では、自らの立場を守るために偽証したことを告白している。人騒がせな人物だったことには違いないのだ。
日本語について用意周到だった米国
通訳についてはあまり評価は高くなかったが、法廷記録業務を仕切る米国の言語担当者らの優れた日本語能力に感嘆したとの発言も見える。
〈向うでは、戦争中から将来日本を占領したときに備えて、相当日本語を教育していたようですね。日本版の英和や和英の辞書の複写版が配布されていたが、そういうところはなかなか(原文はくノ字点)手まわしがいいと感心しましたね。〉
〈ぼくは向うでできた日本人の姓氏の辞典の厖大なやつを見て驚いた。ローマ字で引くとカワイの所に川井、河井、河合、川合……と漢字で出ている。〉
〈向うの対日政策の一つの現われですね。言語将校といいますか、そういうものが完成されていたんですね。日本語学校で、林というあのときのモニターが教官をしていたわけです。そういうふうにして、戦時中から日本を統治する準備ができていたんです。〉
人情のつれなさを痛感
裁判は開廷から2年半後の23年11月12日、被告に対する判決言い渡しが終わり、ようやく終結した。判決では、ウェッブ裁判長が被告人全員を「有罪」とし、東條(条)英機、広田弘毅、土肥原賢二など計7人に絞首刑を言い渡している。座談会の終盤、出席者らは6年前の裁判をしみじみと振り返っている。
〈戦争中の東条は、われわれ(原文はくノ字点)が養成所に入つたころは首相で、さつそうと馬に乗つて来て、われわれ(原文はくノ字点)が養成所の前でおじぎすると、挙手の礼を返した。それを見ててまた法廷の東条を眼のあたりに見たということは、実に感慨無量というか何とも言えない気持でした。〉
〈肩書きや肩章をもぎとられた人間の姿というものがどんなものかということをあすこで見せつけられたこと、それから戦争中は大いに太鼓をたたいて、東条さんでなければ夜も日も明けなかつた人が、掌を反すがごとくに今度はその悪口を言う、その人情のつれなさというものを身にしみて感じさせられた。それが今日ではまた占領行政の悪口を言い、復古をとなえるというのだから、ますます(原文はくノ字点)もつて考えさせられますね。〉
速記者の努力の賜物である「極東国際軍事裁判速記録」は後に刊行され、東京裁判の一級資料となった。だが、速記者養成所は4年前の平成18年に最後の卒業生を送り出した後、閉所された。国会で録音機械やビデオを使用するようになり、速記者に頼らない方法が主流になったためだ。「衆友」も5年前、最後の号を630部ほど発行し休刊した。
「勝者の裁き」か「文明の裁き」か
東京裁判の最中の22年、衆院選に初当選した元首相の中曽根康弘氏はこう振り返る。
「あの裁判に対して痛切に感じていたのは、勝者が敗者を裁いているということだ。しかも、裁判手続や訴因を勝者が自分たちで決めてやっている裁判で、公正な国際裁判とはいえないと思っていた。実際に政治家としてそう主張していた」
前述の粟屋名誉教授は、「東京裁判は、海外の法学者による再検討など、最近になってやっと多角的に研究されるようになった」と話す。そして、次のように座談会記事を読んだ感想を述べた。
「今まで知られていなかった速記者の地道な黒子としての役割が見えた。講和条約が締結されて間もないころで、肩の荷が下りた時期だったからこそ、気軽に話しているのだろう。東京裁判での言語の問題は非常に複雑だった。モンゴル人が証言した際には、モンゴル語から中国語、中国語から英語や日本語に訳していたほどだ」
速記者が戸惑いながらも記録し続けた東京裁判とは結局、何だったのか。中曽根氏が指摘したように、勝者の裁きでしかなかったのか、それとも検察側が主張したように、「文明の裁き」だったのか。そもそも、戦争を裁くことができるのか――。
いまだ決着がついていない難題だが、少なくとも昭和16年12月8日の真珠湾攻撃に始まった太平洋戦争の残り火は、終戦後、東京裁判が始まってもなお、くすぶり続けていたのは確かである。
菊地正憲(きくちまさのり)
ジャーナリスト。1965年北海道生まれ。國學院大學文学部卒業。北海道新聞記者を経て、2003年にフリージャーナリストに。徹底した現場取材力で政治・経済から歴史、社会現象まで幅広いジャンルの記事を手がける。著書に『速記者たちの国会秘録』など。
デイリー新潮編集部