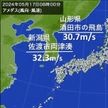昭和57年2月8日未明、東京のホテル・ニュージャパンで発生した大火災。地獄絵図と化した現場の様子はテレビで生中継され全国に衝撃を与えた。だが、悲劇は続く。翌9日朝、羽田沖で日航機がまさかの墜落事故。2つの事故現場には各機関から大量の人員が動員され、混乱状況のなかで対応を続けた。死体の検視や身元確認、遺族への遺体の引き継ぎ、現場検証などを行う警視庁の鑑識課もその1つだ。当時の鑑識課長を務め、後に作家・コメンテーターとして活躍した田宮榮一氏の証言とともに、当時の「呪われた48時間」を振り返る。
(前後編記事の前編・「新潮45」2009年7月号掲載「シリーズ『昭和』の謎に挑む 4・ホテル・ニュージャパン火災と羽田沖日航機墜落 警視庁が呪われた48時間」をもとに再構成しました。文中の年齢、役職、年代表記等は執筆当時のものです。文中敬称略)
***
未明の緊急電話
あの悪夢のような48時間の裏で一体、何があったのか。警視庁の刑事たちは捜査史上最悪のカタストロフィーにどう臨んだのか――。
昭和57年2月8日の未明、警視庁の鑑識課長だった田宮榮一は、一本の緊急電話に起された。鑑識課の当直員からで、「ホテル・ニュージャパンが大火災を起しています」という連絡だった。
「その当直員は、未明に鑑識課長を起すのは申しわけないと思ったのか、『ご参考までに』なんて言っている。なにが『ご参考まで』なんだと思いながら、すぐに公舎に車を回せと指示を出し、電話を切ると急いで外出する支度を始めたんです」(田宮、以下同)
公舎は笹塚にあった。赤坂の現場に着いた時は、まだホテルの窓から炎が噴き出していた。高層階の窓からは、炎と煙に押し出されるように人が飛び降りてくる。
窓枠にしがみついて手を振っている人の姿もある。部屋からシーツを垂らし、必死に階下への脱出を試みる人もいた。はしご車のはしごが届かず、地上からはただ見守るしかない。まさに地獄絵だった。
鑑識課員全員の招集を即断
鑑識課長としてまず頭にあったのは、現場検証のことだった。すでに鑑識課の現状班(事件の発生に備えている班)が現場に入っていたが、田宮は百数十名いる鑑識課員全員に招集をかけることを即断した。まずは人命救助、そして現場検証を迅速に進めるためだ。
昼ごろ、火災は鎮火の方向に向かう。炎がおさまるのを待って、田宮たちはホテルの中に入った。1階のロビーには、上階から避難してきた宿泊客が大勢いて、負傷者がソファや床の上で手当てを受けていた。
焼け焦げた臭いの中、放水で水浸しになったホテルの各階を歩き回り、逃げ遅れている宿泊客がいないか確かめた。上階に近づくと、死亡した宿泊客が廊下の両側に毛布やシーツをかけられたまま転がっていた。
ホテル・ニュージャパンの火災の火元は、9階の938号室である。後に行われた鑑定の結果、ベッドの上にこぼれたたばこの火が炎となり、壁沿いに立ち上って天井裏に達し、横に広がったことが明らかになった。
「炎はいったん天井裏に抜けたら、横に広がるのが速い。これをフラッシュオーバー現象といって、火災に多い事例です。アパート火災などでも、自分の部屋の天井裏に火が回っているのに気づかず、まだ大丈夫だと思っていて、逃げ遅れてしまうケースが多い」
名門ホテルとは名ばかりの粗雑な建物
大惨事になってしまった要因として、当初からホテル側の防災体制が疑問視されていた。
まず、非常ベルの電源が切られていた。設備はあったものの誤報が多く、その度に点検するには要員が足りないということで切られていたのだ。
また暖房設備の外気取り入れ口が閉鎖されていた。冷たい外気を取り入れると暖房費が余計にかかるというのがその理由である。ホテル内は汚れた空気が循環するだけで、カラカラに乾燥していた。火がついたらあっという間に燃え広がるのは必然だった。
さらにスプリンクラーが役目を果たしていなかった。消防からの再三の指摘でスプリンクラーの金具は付いていたが、天井裏にあるはずの配管がなく、まったくの見かけ倒しだったのだ。隣室との壁も粗雑だった。壁紙が焼け落ちた後には、いくつもの穴があいており、そこが火の通り道になっていた。名門ホテルとは名ばかりの、元来粗雑な建物だったのだ。
横井社長が用意したサンドイッチ
ホテルを経営していたのは、“乗っ取り屋”の異名をとる横井英樹。従業員から火事の一報を聞いた横井は、人命救助はさておき、「まず金目の物を持ち出せ」と指示したという話もある。その横井の姿を、田宮は鎮火後、1階のロビーで目撃している。
「蝶ネクタイをして、宿泊客や報道陣にハンドマイクで呼びかけていた。印象に残っているのは、そんな火急のときでも、調理場に指示を出して大皿にサンドイッチをたくさんつくって、『みなさんで召し上がってください』と捜査員に提供してきたこと。そんなことに気が回る男なんです。
われわれは腹が空いていたけれど、部下たちには『手を出すな』と命じました。後に彼は捜査の対象となるはずで、捜査する側が捜査される側に施しを受けたというのはまずい、と思ったからです」
翌日午前3時に帰宅
鑑識課の重要な仕事には、死体の検視と身元確認、遺族への遺体の引き継ぎがある。田宮は死体の検視を芝増上寺の葬祭場で行うことに決め、検視班、身元確認班、遺体引き継ぎ班などを編成する傍ら、ホテル・ニュージャパンにあった遺体を増上寺に搬送した。
「遺体の何体かを解剖したのですが、その中に外国人の女性がいて、遺族から猛烈に抗議されました。ここは日本なので、日本の法律に従ってほしいと説得したのですが、結果的にその女性は妊娠していることがわかり、お腹の子に対しても補償されることになった、そんなケースもありました」
田宮が一連の作業を終えて鑑識課に戻ったのは夜10時近くになっていた。翌日の検証作業の班編成について指示したあと、捜査本部が設置されている麹 町警察署に出向いた。それまでの経過と翌日の段取りを報告し、公舎に帰ったときは日付変わって9日の午前3時頃になっていた。
長い一日だったが、本格的な仕事はこれからである。そう心していた田宮だったが、その数時間後、検証作業の段取りを覆すことになる大事件が再び起こるのである。
早朝に「至急、至急」という無線が
2月9日の朝、田宮が数時間の睡眠をとり、公舎を出て迎えの車に乗り込んだのは、通常より早い午前8時前だった。
幡ヶ谷から高速4号線に乗り、霞が関ランプの近くまで来たとき、通信指令本部から「至急、至急」という無線が流れた。田宮が車を路肩に停めさせると、無線は続けて「警視庁から各局、羽田沖で日航機が墜落した模様」と緊迫した声で伝えた。
見上げると、上空に警視庁のヘリコプターの機影が見える。ホテル・ニュージャパンの俯瞰撮影をするよう指示を出した鑑識課員が搭乗しているはずである。田宮は無線機で上空のヘリコプターに「羽田に急行して墜落した飛行機を撮影しろ」と命じた。
それから指令本部に「鑑識20(鑑識課長のコールナンバー)から警視庁、これより羽田空港に急行する」と連絡、非常灯を点滅させ高速1号線で羽田に向かった。
風景は奇妙な静けさの中にあった
羽田空港に着いて、車のままC滑走路に行くと、見たこともないような光景が広がっていた。滑走路の先の海上に、銀色の航空機が浮かんでいたのだ。機体が前の方で折れ、先端のコックピットが後部の客室にめり込んでいる。
田宮が着いたとき、助かった乗客たちが、腰まで水につかりながら、じゃぶじゃぶと水をかき分けて岸に向かって歩いて来るところだった。空は晴れており、ちょうど引き潮の時間だった。墜落地点から滑走路までは、立って歩けるほどの水深しかなかったのだ。
乗客たちは岸にたどり着くと、這い上がってへたり込み、肩で「はぁはぁ」と息をしていた。まだ救助車輛の多くは到着しておらず、風景は奇妙な静けさの中にあった。
事故を目の当たりにした田宮の最初の印象は、“なんだ飛行機というのはワイヤーの塊なんだな”というものだった。ちぎれた機体の断面から、さまざまなワイヤーが飛び出し、糸のようにもつれていたからだ。
上空では鑑識課員を乗せたヘリコプターが旋回し、田宮の指示通りに写真を撮っていた。そのうちに報道のヘリコプターも数機現れて、現場は次第に騒がしくなった。消防車や救急車がサイレンを鳴らして到着し、負傷者を運び始めた。
海上では水上警察の船をはじめ何艘かのボートが航空機に向かって集まってきた。その救助のボートのひとつに、乗客に混じってK機長が乗り込んでいたことを、田宮はそのとき知らなかった。
***
大火災に続いて墜落事故。検視が終わった遺体の安置では、皮肉なことにホテル・ニュージャパンにおける遺体検視の経験が生かされたという。だが、2つの大惨事をほぼ同時に現場検証するという前代未聞の状況では、意外なものの“不足”にも悩まされた。そしてさらには、横井社長とK機長に関する捜査――。後編では、事件発生後も続いた激動の日々を伝える。
後編【入院中のK機長を目撃して「これは明らかにおかしい…」 羽田沖日航機墜落事故はなぜ1人も起訴できなかったのか】へつづく
上條昌史(かみじょうまさし)
ノンフィクション・ライター。1961年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部中退。編集プロダクションを経てフリーに。事件、政治、ビジネスなど幅広い分野で執筆活動を行う。共著に『殺人者はそこにいる』など。
デイリー新潮編集部