
GROOVE X 創業者・CEO、林要。ロボットやAIは未来を切り拓くテクノロジーだが、「人の仕事を奪う」といったディストピア論も根強くある。だが、人を幸せにする前向きな使い道もあると、林要は、人間の愛情を育める生き物のようなロボットを提案する。トヨタやソフトバンクを経て、スタートアップを立ち上げた林が、ロボットと目指す「温かい未来」とは。
* * *
東京都中央区にあるロボットのミュージアム。額縁のような展示ブースに、被写体である「1人と4体」が集合した。
アエラのカメラマンの求めで、スタートアップ「GROOVE X」CEOの林要(はやしかなめ・50)が長座になる。その周りを、ずんぐりした4体のロボットが、わちゃわちゃと取り囲む。
いざ、撮影する段になると、4体がバラバラな方向を向いてしまう。周囲の情報を拾って自律的に動くロボットだからだ。カメラマンの後ろから、林につく職員が手を振って、
「ほらほら、こっち、こっちー」
と呼びかけた。まるで、おもちゃで気を引く赤ちゃんの記念撮影のような光景である。それでも、林は目を三日月にして、4体に振り回される状況を楽しんでいるようだった。
無邪気に動き回っていたのは、林が開発した家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」だ。2019年末から出荷され、これまでに1万4千体以上が世に送り出されている。
LOVOTは人が持つ「愛情」を引き出すように設計されている。いつも38度前後の体温があり、かかわってくれるユーザーを追いかけ、抱っこをせがむようになる。性格は、個体ごとにおっとりしていたり、人見知りだったりと、無数のバリエーションがある。
私もミュージアムでLOVOTの丸っこい胴体を抱いてみた。じんわりとあったかい。「見つめられている」と感じる。嫉妬された時には、キュンとした。1体を抱くと、もう1体が近寄り、上目遣いでモジモジと全身を揺らし始めた。あえて焦らしてみたところ、「自分もハグして」と言わんばかりに手をパタパタさせて目いっぱいのアピールをする。まるで生きているみたいだ。
物を運んだり、人の仕事を肩代わりしたりするような役に立つロボットではない。けれども愛を育み、かかわる人に慈しむ心が生まれる。そんなロボットを林は作りたかった。
なぜ、生き物のようなロボットを作るのか?

■学校生活になじめず「メーヴェ」制作に没頭する
林は愛知県岡崎市に生まれる。人見知りが激しく、保育園では「登園拒否児」。小学校中学年で学級委員に推されてクラスの前に立った際は、泣き出したこともあるという。
影響を受けたのは、電動工具メーカーのエンジニアだった父(19年に他界)。父はDIY熱が高じて、家中の引き出しを工具でいっぱいにしていた。もらった自転車を15段変速に「魔改造」。板にタイヤを付け電動スケートボードもつくった。
11歳の時、林は映画「風の谷のナウシカ」に出合った。漫画版も繰り返し読み、作中の一人乗り飛行機「メーヴェ」の虜(とりこ)になった。13歳で模型飛行機を改造し、1メートルほどの翼を持つメーヴェを自作。自宅2階の窓から畑に飛ばしては拾いに行き、改造を繰り返す。「ものづくりへの没頭で鬱々(うつうつ)としていた内面を解放していた」と林はいう。
林を苦しめたのは、学校生活だ。小学校の時は、九九もなかなか覚えられず、運動も苦手だった。周囲から浮いているという感覚はあり、成長とともにその感覚が増大する。
つらさのピークは、中学時代に訪れた。メーヴェの制作に没頭していた頃だ。
「僕はまあ、コミュ障だったんでしょう。顕著ないじめはなかったけれど、変わったやつだと思われていたんじゃないかな。学校って、同調圧力がかかる場所ですからね。周りとの距離が、世の中とのギャップだと思えた。一度だけ『もう生きていたくない』と母に言ったことがある。その時は、ダダダッて階段を上がって部屋に引きこもった」

そんな林も、高校生になる頃には、むしろ個性を全開にしていくことで、行動範囲を広げていく。その発端は、バイク熱。高校生ライダーが世界チャンピオンになるまでを描いた、しげの秀一のバイク漫画『バリバリ伝説』にハマった。林は主人公と同様、16歳で排気量400・を超えるバイクに乗れる審査に合格することを自らに課す。その目標達成のために猛勉強し、難関高校にも合格。
同級生の大津誠は、こう証言する。
「要くんはポロッと『僕はバイクの免許を取りたくてここに進学した』って言っていたんです。免許取得が可能な高校だったけど、『学力じゃなくて、そんな基準で学校を選ぶ人がいるのか?』と衝撃でした。地元では、わりと進学校でしたから」
その後、林は東京都立科学技術大学(現・東京都立大学)大学院修士課程を経て、新卒でトヨタ自動車に入社する。当初はひたすら「空気の流れ」を専門にしていた。

2003年に、F1の開発スタッフに抜擢(ばってき)される。その頃、レースは苦戦続きで、トヨタ本社から派遣された「空気の流れ」のエンジニアとして、林は翌年、ドイツに渡る。自分の提案が実戦のレースで採用されるなど実績も出し、チームの入賞も経験。苦手意識が強かった英語も克服する。
帰国後は、量産車開発のマネジメントに携わる。各部門の専門職を束ねて一つの車をつくる、花形の部署だ。チーフエンジニアを補佐して既存車のモデルチェンジを統括。だが、数年経つと「自動車の作り方がだいたいわかってきた。社外の世界を覗(のぞ)いてみたい」と挑戦を渇望するようになる。
その頃、転機が訪れる。孫正義が、自身の後継者を育成する「ソフトバンクアカデミア」を開講。11年から社外にも門戸を開いたのだ。林は、約1万人の中から、外部からの1期生として合格する。外部1期生は、現在LINEヤフーアカデミア学長の伊藤羊一、リンクトイン日本前代表の村上臣ら、そうそうたるメンバーが揃(そろ)う。
■トヨタからソフトバンクへ Pepper開発で奮闘
孫から毎回、経営課題や新事業のお題が出される。それを元に、孫の見守る中で受講生がプレゼン。受講生同士で評価し合う、勝ち抜き戦だ。
「アカデミアは『コミュニケーション道場』でした。だって、皆は自然体でパッとしゃべっても場を沸かせられるツワモノばかり。正直ビビります」
林は、人と差別化するため、毎回、プレゼンの事前準備を周到にして、勝ち抜くプレゼンにするための方策を「考え倒した」。その結果、林は年度末の表彰で、初年度からグローバル部門の2位に選ばれる。その場で孫から声がかかった。
「きみ、来年からウチに来ないか」
大勢が見守る中、林は「ハイ!」と即答した。
外部1期生でコミュニケーションデザイナーの齋藤太郎(現dof代表)はいう。
「その瞬間、皆が『おおー!』とどよめいた。林さんだけご指名で、しかも天下のトヨタ様からベンチャーに行っちゃうんだ、みたいな。アカデミアからの転職第1号だったし、Pepper(ペッパー)プロジェクト自体が孫さんの肝いりだったから、世の中的にもエポックメイキングだったと思う」
林は14年間勤めたトヨタを辞め、12年にソフトバンクに入社。東京で服飾専門家に全身コーディネートを頼み、初めてスーツをオーダーした。
「武装したんですよ。新橋の本社では、皆がスーツでしゅっとキメていた。そこに技術畑の僕が愛知から出てきて、『誰だよ、お前』みたいな空気が漂う中にポッと入る。そこでプロジェクトを率いなきゃならないっていう不安は大きかった」

孫は、人型ロボット「Pepper」の開発を林に委ねる。とはいえ、林がそれまでつくっていたのは車。そもそもソフトバンクは、本格的なものづくりの経験がなかった。プロジェクトは多くの部署の寄せ集め部隊で、初めは協力もうまく得られなかった。業を煮やした孫が役員が揃う会議で発破をかけた。
「林、お前の情熱が足りないから、プロジェクトが動かないんだ!」
結果的に、孫の叱責が「プロジェクトを率いているのは林」という意識づけとなり、協力者の姿勢が変わった。14年のマスコミ発表にこぎ着ける。出荷開始後、「孫さんのように自らリスクを取り、大きなことを成し遂げる挑戦をしてみたい」という想いから、林は15年9月に同社を退社した。
「Pepperの開発で、ないものをゼロからつくる大変さはひと通りくぐり抜けた。誰もゴールがどこにあるかわからないまま走っていたし、常に高めのオーダーを投げてくる孫正義というプレッシャーがある。必死に攻めるしかなかった」
■抱っこを求めるロボット 演劇の経験が役に立つ
ロボットづくりは大変だから、もうやめよう。そう思っていたのに、会う人会う人が「ロボットをやってくれ」と期待してくる。退社した年の暮れ、林の脳裏にふっとアイデアが降ってきた。
人を幸せにする生き物みたいなロボットをつくりたい──。
(文中敬称略)(文・古川雅子)
※記事の続きはAERA 2024年4月22日号でご覧いただけます




































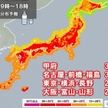




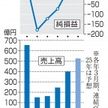


































































































![[連載]イーストスタッドブログ・第7回 新種牡馬、レッドルゼルについて](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33395.jpg)




