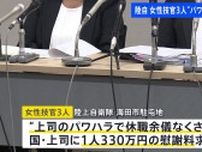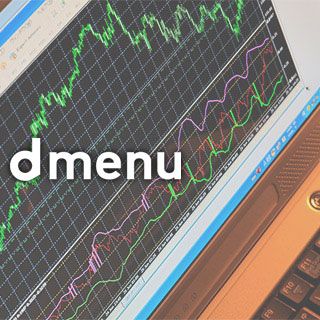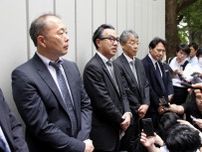大河ドラマ『光る君へ』で注目されている『源氏物語』。藤原道長は光源氏のモデルとされ、“平安時代最高の権力者”とまで言われるほどの全盛期を築き上げた。しかし、その歴史の裏には道長の被害者も……。平安文学研究者・山本淳子氏の著書『平安人の心で「源氏物語」を読む』(朝日選書)から一部を抜粋、再編集し紹介する。
* * *
■病を招く、平安ストレス社会
「病は気から」。まるでそのことわざをなぞるようだ。『源氏物語』の柏木(かしわぎ)は光源氏に「(意地の悪い)いけず」を言われたことがきっかけで病気となり、果ては亡くなった。単純に言えば、精神的ストレスによって命を落としてしまったのだ。現代人にとっても他人ごとではない。ストレスが実際に体に悪いことは、むしろ近年の科学でますます明らかになってきている。その実例らしきものは、平安時代の実在の人物についても、いくつも確認できる。
『栄華物語』(巻八)では、高階明順(たかしなのあきのぶ)なる人物が、藤原道長に叱責されて亡くなっている。寛弘六(一〇〇九)年のことだ。発端は呪詛(じゅそ)事件で、道長とその娘の中宮彰子(ちゅうぐうしょうし)、また彰子が前年に産んだ、一条(いちじょう)天皇(九八〇〜一〇一一)の次男・敦成親王(あつひらしんのう)の三人が標的とされた。天皇の長男で故中宮定子(ちゅうぐうていし)の産んだ敦康親王(あつやすしんのう)の皇太子擁立を図る一派の仕業とされ、捜査の結果、定子の母の一族、高階光子(こうし)らが逮捕された。明順は光子のきょうだいで、共犯を疑われた。道長に呼びつけられ、ねちねちと責められた挙げ句「天罰が下るぞ」との一言がきつかったのか。明順はそのまま発病し、五、六日で亡くなったという。ただし、これを裏付ける史料はなく、むしろ『栄華物語』が『源氏物語』の光源氏と柏木の場面にヒントを得たという説もある。
いっぽう、長年のストレスにじわじわ追い詰められた結果と思えるのが、『大鏡(おおかがみ)』「時平(ときひら)」が記す藤原保忠(やすただ)の例だ。彼は、陰謀により菅原道真(みちざね)を無実の罪に陥れたとされる左大臣・藤原時平の長男である。道真は大宰府に流され、二年後に配所で亡くなった。そこから、陰謀を企てた側の恐怖が始まる。当時は、恨みを抱いて亡くなった人間の魂は怨霊と化して祟ると考えられたからだ。実際、時平は三十九歳で早世。道真を流罪に処した醍醐(だいご)天皇(八八五〜九三〇)の皇太子・保明(やすあきら)親王は二十一歳、その子で親王に代わって皇太子に立てられた慶頼王(よしよりおう)は何と五歳で亡くなっている。保忠は常に「次は自分」という恐怖におびえていたのだろう。あるとき病気に罹り、枕もとで『薬師経(やくしきょう)』を読んでもらったのだが、その経の一節が耳についた。「所謂宮毘羅大将(しょいくびらたいしょう)」と、僧が大声で読み上げたのだ。「くびら」が「くびる」に聞こえ、それは「首を絞める」という意味。絞め殺される、と思ってそのまま、彼は恐ろしさに絶命してしまったという。時に承平六(九三六)年のこと、保忠は四十七歳。道真の亡くなった延喜三(九〇三)年からは三十年以上にもなる。その歳月の間、彼はおびえ続けてきたのだ。平素からストレスが体の抵抗力を低下させており、そのうえたまたま病気に罹って衰弱したところへ、さらに「くびら」の一撃が加わったことが、何らかの発作を惹き起こしたといえそうではないか。
驚くのは、一条天皇の例だ。側近・藤原行成(ゆきなり)が、天皇自身から聞いたこととして、日記『権記(ごんき)』に記している。寛弘八(一〇一一)年五月、天皇はまだ三十二歳の壮年だった。軽い病にかかったものの、それは快方に向かっていた。だがその矢先に、彼は自分の病状に関する易占の結果を聞いてしまう。「豊(ほう)の明夷(めいい)」。卦(け)自体は決して悪くないものだが、気味が悪いのは、村上天皇(九二六〜九六七)や醍醐天皇の崩御(ほうぎょ)の折にも出た卦だということである。実はこの占いは藤原道長が学者に命じて行わせたもので、本来は天皇の耳に入れるはずのものではなかった。だが、あまりの結果に道長は動揺、天皇が臥す夜御殿(よるのおとど)の隣の部屋で、僧とともに声を上げて泣いてしまった。帝は何事かと几帳(きちょう)のほころびから覗き、全てを知ることになった。その結果、病状は急変、一カ月後には本当に亡くなってしまうのだ。占いは当時、一種の科学と信じられており、天皇には死の宣告となった。死ぬと信じたことで彼は命を奪われたのだ。
もっと明確に現代の病名が充てられる例といえば、三条(さんじょう)天皇(九七六〜一〇一七)の眼病である。「炎症性緑内障(りょくないしょう)」。国文学者の山岸徳平氏の推測に、医学博士で医学史の研究者でもある服部敏良氏が太鼓判を押している。藤原実資(さねすけ)の日記『小右記(しょうゆうき)』によれば、三条天皇は即位から三年後の長和三(一〇一四)年春ごろから片目が見えなくなった。翌年には両眼ともほぼ失明。ところが瞳には濁りがなく、外見上は視力を失ったように見えない。また時には視力が戻ることさえある不可解さだ。同年五月七日の『小右記』は、賀静(がじょう)なる天狗僧の霊が現れて、帝の眼疾は自分が御前にいて時折翼を開き、御目を塞いでいるせいだと白状していると記す。当時の人々には、天狗や物(もの)の怪(け)のせいとしか考えられない症状だったのだろう。服部氏はこれを、ストレスによると診断する。炎症性緑内障は中年以降では精神過労により発症することがあり、心神の安定で一時的に視力が戻ることもあるという。確かに天皇は、道長に譲位(じょうい)を迫られるなどストレスの増した日には目が暗くなり、邪気祓いなどの後には明るくなっている。
今も昔もストレスは怖い。ところで今回紹介した四つの症例の内、三つにまで関わっている人物がいる。藤原道長だ。どの症例においても、彼が患者にストレスを与えている。彼が栄華を獲得する道とは、こうした道でもあったのだ。ストレスよりも怖いのは、人にストレスを与える人間である。