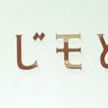「こちら、今日からウチに入社することになった増田花林さんだ」
毎朝のルーティーンである朝礼で、部長からの紹介を受けた若く快活そうな女性社員が深々と頭を下げた。
「よろしくお願いします」
ぱらぱらと拍手が鳴り、千帆も周囲に倣った。
「柳沢千帆さん、指導係としていろいろ教えてあげて」
朝礼終わりに、部長から声を掛けられた。千帆は中堅不動産会社で営業事務として働き出してから15年目を迎えるベテラン社員。新入社員、中途採用を問わず、指導係になったことは一度や二度ではない。
「初めまして、柳沢です」
「増田です」
千帆が自己紹介をすると、花林は笑顔で会釈をした。その勝ち気な表情に、ほんの少しの苦手意識と嫌な予感を感じたけれど、もうこのときの千帆にそのことをどうにかすることなんてできやしなかった。
「ああ言えばこう言う」新人
そのときの嫌な予感がかたちになるまでに、1週間と時間はいらなかった。
もちろん、前職でも営業事務を経験したことがある花林は仕事ができないわけではない。むしろ入力ミスなども少なく、かつ正確で、どちらかと言えば優秀と言ってもいいのかもしれない。
けれどそれを差し引いてもあまりある問題が、千帆の頭を悩ませていた。
「増田さん、物件や顧客情報の資料を整理してファイリングしてってお願いしてたのやってなかったみたいだけど…… 。 他の子がやってくれてたけど、私は増田さんにお願いしたよね?」
千帆が注意をすると、花林は小さくため息を吐いた。
「いや、柳沢さん、今どき紙の資料なんてまとめて何になるんですか? 全部電子化してPC管理が当たり前ですよ? ペーパーレスって知ってます?」
「それは、もちろん分かるけど、そんないきなり電子化できるわけじゃないから……」
「ほんと、遅れてますよね。頭を使って仕事をしてないから、こういうことに気付かないんですよ。私はそんな非効率で意味のない仕事したくないです」
「そんなこと言われても、増田さんがやってくれないとみんなが困るのよ……」
千帆が何を言っても、花林はあーだこーだと言って反論する。とにかく花林は我が強く、千帆は手を焼いていた。
噂をすれば
千帆にとっては昼休みだけが気を緩めて息をつける時間になっていた。いつものように声を掛けてくれた同僚の典子と一緒に社員食堂へ向かう。典子はコブサラダ、千帆は焼き魚定食の食券を買い、あいている席に腰を下ろす。
2人の話題になるのは、もちろん花林のことだ。
「千帆さん、やばくないですか? 増田さん」
「うん、ちょっとね……別に仕事ができないわけじゃないんだけど」
「いやいや、周りとちゃんとコミュニケーション取りながら仕事するのだって立派な能力ですからね。人事部、見る目なさすぎますよ」
典子の同意に気が緩み、千帆は深い深いため息を吐く。典子がこうして千帆の愚痴を聞き、代わりに怒ってくれるからこそ、千帆は花林の指導をなんとか続けていられるのだと真面目に思う。
典子は30歳になったばかりで、若手と千帆のようなベテラン、どちらとも接することのできる貴重な存在。だからこそ、多くの社員が典子と仲良いし、典子を中心に会話の輪が広がることが多い。
「はぁ〜典子ちゃん、ほんとに癒やしだよ〜」
「任せてくださいよ。千帆さんのことならいつでも癒やしますよ〜」
大根おろしにしょうゆをかけながら言う千帆に、典子がほほ笑みかける。しかし2人の気心知れた憩いの時間は、降りかかった一言であっけなく終わりを告げた。
「一緒にいいですか?」
どうぞ、とこちらが答えるまでもなく、花林が席に腰を下ろす。千帆たちが気まずく思っていることを気にするようなそぶりなどみじんもない。
自サバ女の珍走
「わ、出た。コブサラダ」
唐揚げを頰張りながら、花林が典子の前にあるコブサラダを指さした。
「典子さん、そんなご飯で午後も働けるんですか? 私だったら絶対無理〜。やっぱランチは肉じゃないと、肉」
花林はおしゃべりだが、千帆たちは苦笑いを浮かべるほかにない。
「女子って小食アピールしますよね。私そういうの全然分かんなくて。よく言われるんですよ、増田は男勝りだって。分かっちゃいるんですけどね〜。でも自分のこと飾らずに生きたほうがいいと思うんですよ〜」
そうだね、と千帆は苦笑い。典子は恥ずかしそうにうつむきながらコブサラダを食べていた。話題を変えなければと、千帆は思った。
「どう、仕事はもう慣れた?」
「んー、そうですね。でも何だか、こんなレベル低くていいのって感じで驚いています」
返す言葉が見当たらずに思わず固まった千帆たちの反応を見て、花林は勝ち誇ったように笑う。
「ああ、ごめんなさい。私ってサバサバしてるから、何でも思ったことを口にしちゃうんですよね〜」
まだ固まっている典子に構わず花林は続ける。
「でも、私が言ってることは間違ってないと思うんですよ。無駄が多いっていうか。それで皆さん残業してるわけですし、意味ないですよね」
「そ、そうかもねぇ……ははは……」
愛想笑いもとっくに限界で、白目をむきそうになったとき、食堂の入り口のほうへ向けて会釈をした典子に花林の意識が向けられる。典子の先には営業部の面々がいた。
「そういえば、なんか、作田くん、もうすぐ課長になるんじゃないかって言われてるよね?」
作田くんというのは営業部のエースのことで、若くてかっこいい上に営業事務の社員にも丁寧に接してくれるため、女子社員からの人気が厚かった。もちろん千帆からすれば10歳以上も年の離れた作田に色めくようなことはなく、男性アイドルを見て騒ぐような気分に近いのだけど。
「そうですね。まあ、この間も大きな商談をまとめたみたいですし、当然ちゃ当然なのかも」
「作田さんって、そんなに仕事ができるんですね!」
割り込んできた花林にあっけにとられながらも、典子が答える。
「そ、そうね。真面目だし、頼りがいがあるよね」
「へえ、イケメンで仕事もできるって最高じゃないですか⁉」
花林は今まで見たこともない顔で笑っている。
「……イケメン、確かにね。独身なのが不思議なくらいですよね。でも、そんな話聞いたことないし」
典子の言葉に花林は手を合わせて喜ぶ。
「うわぁ、女性関係が真面目って、完璧だなぁ。どんな子が好きなんでしょうね〜?」
「ああ、なんか、一緒にいて楽な子、気を遣わなくて済む子がいいですねって前に言ってたような気がするけど……」
典子の言葉を聞いて、花林はにやりと笑った。
「うわ〜、それって私ですよね〜?」
その質問は反応に困る。
しかし花林は千帆たちが何も言わなくても勝手に盛り上がる。
「なんか作田さんって、私のこと見てません? すごく視線を感じるんですよね〜。でも私って男友達が多いじゃないですか? そういうの作田さんは気にしないかな〜」
花林が独り言を言ってる最中、千帆と典子はわずかに目を合わせた。
どうやら、花林は作田のことを気に入っているらしい。千帆は、ご愁傷さまと心の中で作田に対して手を合わせた。
「そうだ。私の歓迎会ってことで、飲み会設定してくださいよ。もちろん作田さんも誘って」
「あ〜、ね……」
千帆と典子の声がそろう。ちなみに歓迎会は2日前くらいに一度、やろうという話が出た。そのときに断ったのが何を隠そう花林だったのだ。
「そ、そうね。それじゃあ、近くにおいしいイタリアンがあるから、そこで……」
「ええ〜、そんなの嫌ですよ。普通の居酒屋とかが絶対いいですって。ああいう店って、映えとかしか気にしてなくて、実際の味は大したことないっていうのが多いじゃないですか」
「そ、そうかな……?」
「店選びのセンスがなさすぎですよ〜。だからいつまでたっても結婚できないんじゃないですか〜」
花林の言葉に典子はうつむく。
「増田さん、そんなこと言っちゃダメでしょ」
千帆は思わず花林を注意するが、花林は悪びれる様子もなく、楽しげに笑った。
「ああ、ごめんなさい。あたし、サバサバしてるから、何でも口にしちゃうんですよね〜」
「居酒屋でいい店がないか探してみるね……」
典子は振り絞った笑顔で応えた。
「お願いしますよ。雰囲気と味、両方が兼ね備わっているところですよ。作田さん誘うの忘れないでくださいよ? じゃないと、私、行きませんから」
ワガママ放題な花林の要求に、千帆と典子は同時にため息をついた。
●花林に振り回される千帆と職場の面々、花林に灸を据えるような出来事は果たして起こるのか……? 後編にて、詳細をお届けします。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。