連続テレビ小説『虎に翼』(NHK総合ほか)がいろんな意味で話題を呼んでいる。シリーズ110作目となる本作は、日本初の女性弁護士のうちのひとりであり、戦後は女性で初めての判事・家庭裁判所長を務めた三淵嘉子さんをモデルに、主人公・猪爪寅子(伊藤沙莉)の半生を描く。
寅子が女性法律家として、道なき道を突き進むこのドラマにこめた思いを、制作統括・尾崎裕和さんに訊いた(取材・文/佐野華英)。
■『虎に翼』は「女性たちの物語」──『虎に翼』が各所で大きな話題となっていますが、まずはこの評判を受けての率直な感想をお聞かせください。
正直に言って、うれしいです。企画の段階から、脚本の吉田恵里香さんと一緒に準備してきて、いろんなことを考えながら作ってきた作品なので、テーマの深いところが視聴者のみなさんに届いているんだなと感じるリアクションをいただけて、とてもうれしいです。
──物語の序盤は、昭和初期の社会制度の中で法曹を志す女性・寅子が、目の前に立ちはだかる壁を打ち破って進んでいくというターン。ゆえに現在のところ、フェミニズム的な色調が濃く、それに対していろんな意味での「強い反応」もありますが。
脚本の吉田さんとは、「寅子の物語」というよりは寅子も含めた「女性たちの物語」であるということを最初から構想していました。三淵嘉子さんをモデルにすることに決めて、明治大学の女子部についていろいろと調べていくうちに、さまざまな境遇の女性たちがそこに在籍し、法律を学んでいたということを知りました。そこから「女性たちの群像劇」というか、さまざまな立場で、いろんなバックグラウンドを持つ女性たちが歩んでいく物語にしたい、というアウトラインができました。
半年という放送期間のなか、長いスパンで描かれていくので、寅子だけでなく、登場する女性たちがどんなふうに人生を歩んでくのかが、ドラマの「背骨」となっています。もちろん今後、男性をはじめ、さまざまな人たちが関わってくるので、いろいろな視点から見ることのできるドラマにもなっていると思います。
■「それぞれのバックグラウンドから出てくる意見」が重要──寅子が法曹という「力を持つ立場」になっていくだけに、いかにして「裁きを下してスカッとさせる」という方向ではなく描いていくのか、というところが気になります。今後、女性だけでなく「あらゆる弱者の立場になって考える」というドラマになっていくのでしょうか。
寅子はやがて弁護士になり裁判官になるので、「人を救える力を持つ存在」を目指すのですが、寅子も完全な人間ではない。虐げられた人々を救おうとするのだけれど、なかなかうまくいかない。絶えず打ち破らなきゃならないもの、乗り越えなければならいものが目の前に現れる。
「完全なる立場から人を救う」のではなく、弱く、虐げられた人たちと同じ目線に立って問題を解決したり、あるいは、なかなかすべてが解決するには至らないのだけれど、一歩進むことができたり。そんな物語が続いていきます。
寅子と同じ女子部の面々も、本科に進んでから出会う男子学生たちも、さまざまです。そんな彼女ら・彼らが議論を交わしたとき、「それぞれのバックグラウンドから出てくる意見」が重要であると考えます。「主人公だからといって、寅子だけが正しいというわけではない」というのが前提としてある。
いろんな意見があって当然で、ある回では「寅子の言うとおりだ」と思ったとしても、違う回では「いや、よね(土居志央梨)の意見のほうが共感できるな」と思えるように描いています。そして、それが吉田さんの作家性だと思います。
──第1回冒頭のシーンを見て「この作品は、あらゆる弱者の目線に立って描かれるドラマになるのではないか」という期待を抱きました。憲法第14条が読み上げられるなか、戦後の焼け跡に生きる、いろんな属性、いろんな立場の人たちが映し出されるシーンが見事で。『虎に翼』ではこうした、いわゆる「エキストラ」と呼ばれる役でも「それぞれの人生があり、そこに生きている」と感じさせてくれる演出が際立っていますね。
第1週は作品のテーマを打ち出す週ですので、チーフ演出の梛川善郎が、かなりこだわって周囲の人物たちを描きました。いわゆる「エキストラ」と言われるような存在の方々でも、それぞれがドラマを背負っている。それがこの作品のテーマなのだと、強く意識してやったところだと思います。
それに対する視聴者の方々の反応もうれしかったです。大きく映ることのない、画面の端のほうで存在している人物に至るまで、きちんと見ていただけているのだと知って、ありがたい思いです(後編へ続く)。






















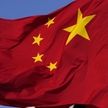












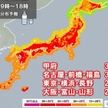


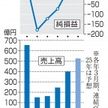















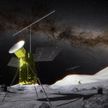





































































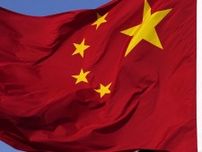














![[連載]イーストスタッドブログ・第7回 新種牡馬、レッドルゼルについて](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33395.jpg)


