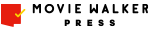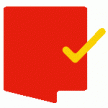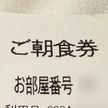「55年前に行方不明になった“イシナガキクエ”という女性を捜索する、特別公開捜索番組」という体裁をとり、4月29日深夜の初回放送から大きな反響を呼んできたテレビ東京の「TXQ FICTION/イシナガキクエを探しています」。過去3回放送され、X(旧Twitter)では一時日本トレンド1位になるなどのムーブメントを巻き起こしてきた本作が、TVerにて配信中の(4)をもって完結した。
「TXQ FICTION」で制作の中心となったのが、テレビ東京の大森時生プロデューサー、寺内康太郎、皆口大地、近藤亮太という4名のクリエイターだ。インターネット上に真偽不明の考察が飛び交い、新たな都市伝説になってしまった感すらある“イシナガキクエ”。多くの視聴者が彼女を探し回った1か月間が終わったいま、PRESS HORRORでは4名のクリエイターを2名ずつでインタビューし、配信後だからこそ明かせる本作の結末についてや、制作までのプロセスを振り返ってもらった。
前編となる今回は「境界カメラ」や「フェイクドキュメンタリー『Q』」を手掛けた寺内康太郎監督と、「ゾゾゾ」で知られ、寺内監督と共に「フェイクドキュメンタリー『Q』」を立ち上げた皆口大地による対談をお届けする。
■「『イシナガキクエ』がいい作品に仕上がっているなら、それはチームの関係性がいいからだと思います」(寺内)
――寺内監督と皆口さんといえば、「フェイクドキュメンタリー『Q』」でコラボレーションされていることがホラーファンにはお馴染みですが、それぞれに活動されてきたお2人がコラボされたきっかけをお聞かせください。
寺内「2020年に深夜ドラマの『心霊マスターテープ』を監督した時、ゲストで『ゾゾゾ』メンバーの皆さんに出演していただきました。それがきっかけになって、(『ゾゾゾ』メンバーによるYouTubeチャンネルの)『家賃の安い部屋』に僕も出たんです」
皆口「連絡先を交換して、お食事に行かせてもらいました。その時に、寺内監督から『YouTubeを始めたいので、「ゾゾゾ」での経験を聞かせてほしい』という相談を受けまして。自分自身が監督のファンなので、寺内監督がYouTubeをやるなら絶対おもしろいものじゃないといけないと思って、『こういうのが観たいんです!』みたいな思いをぶつけていくうちに『一緒に番組を作りましょう』となって、『Q』が発足したという感じですね」
寺内「僕自身、これまで通りのやり方では企画が通らなかったり、出資者に企画を止められてしまったりすることがあってフラストレーションが溜まっていたんです。そんな時に皆口さんも『台本があって、役者がいるようなコンテンツもやってみたい』と言ってらして。お互いのやりたいことがしっかりと合致したというのが『Q』を始めた理由であり、結果が出た理由だと思います」
――それまでのお二人の作品にはエネルギッシュなものも多かったですが、「Q」がソリッドに恐怖を追求する方向性になったのはなぜでしょう。
皆口「寺内監督が撮られるホラーって恐さをロジカルに突いてくる、教科書といえるような作品なんです。悪質なことをしなくてもおもしろくなると確信していたので、日常の隙間を突っつくような作品になった、という感じでしょうか」
――皆口さんに質問です。皆口さんと大森さんは、同じようにプロデューサーの立ち位置で作品を作られてきたかと思いますが、どのような点から「TXQ FICTION」の取り組みにつながったのでしょうか。
皆口「大人同士の難しいビジネスの話とかじゃなくて、ただ純粋に『こういうものをやれたらいいよね』みたいな雑談を楽しくした時に、『ああ、大森さんとなら本当におもしろいものができるんじゃないかな』って思ったのが最初でした。その時話していたのが『イシナガキクエを探しています』の基になるアイディアだったんです。そのあと、寺内さんにすぐお声がけして3人でワチャワチャお話をして、『Q』のスタッフである福井鶴さんにもっとおもしろくなるようにストーリーを書いていただいたりして…と、あっという間に進んでいきましたね」
寺内「作っていく過程で最終的にどんなものにするかを変えていくことができたというのは、このチームのスピード感と関係性ゆえだなと僕は思いました。『イシナガキクエ』がいい作品に仕上がっているとすれば、それは僕らの関係性がいいからだと思いますね」
■「“人が死んだこと”を扱うコンテンツだからこそ、『ボーダーラインはどこか』と考えます」(皆口)
――2人のプロデューサーとお仕事をされてきて、寺内監督は2人の共通点をどうお考えでしょうか。
寺内「ブリコラージュというすでにあるものを組み合わせる作り方と、エンジニアリングと言う目的を持って作るという作り方があります。料理で例えるなら、ブリコラージュは冷蔵庫にあるもので料理を作る。エンジニアリングは決めた料理を作るために必要なものを用意するというような感じです。僕はエンジニアリングのタイプなのですが、『Q』でいうと皆口さんが、『TXQ FICTION』では大森さんがブリコラージュの人でしたね。皆口さんと大森さんは視聴者がどう観るか、作品を観てどのような変化が起きるかまで考えるんです。二人とも最後まで責任を持って、結果が出るところまでを考えるという意識がすばらしいと感じました」
――「ゾゾゾ」はロケ地への許可取りが徹底されていたり、関わっている方にちゃんと理解を得られている点が珍しく、ホラーなのにハートフルな雰囲気が魅力だと感じています。また、大森さんも“常識の範囲”を出ないことを重んじてらっしゃるようにお見受けします。
皆口「ホラーってただでさえ怒られがちなジャンルだと思うんですよ。心霊系コンテンツって、言い方を変えれば人が死んだことをネタにしていることにもなってしまうので。だからこそ『ボーダーラインはどこなのか』ということはすごく考えますし、大森さんもホラーの不謹慎性については非常に考えられていると思います。『イシナガキクエ』を進めていくなかでも、大森さんは『これは大丈夫だと思います。でも、こういうことはやったらダメだと思います』という基準をはっきりと示していました。価値観をしっかりお持ちなので、刺激を受けますね。寺内監督はいかがですか?」
寺内「時代の流れというのは、やはり大きいなと感じます。映画業界にも、一昔前までは“おもしろければなんでもいい”という風潮がありましたが、いまとなっては、やってはいけないことをやってきた人たちがちゃんと怒られていますよね。ですがホラーっていうジャンルは、やっているだけで怒られてたわけで(笑)。だからこそ、ルールを守ったなかで表現しようとしてきたという歴史はあるかもしれません」
■「“イシナガキクエ”という都市伝説ができていく過程を見られたのは、すごく感動的でした」(皆口)
――寺内監督は「TXQ FICTION」以前にも、大森さんと共に「祓除」で三部作にわたる壮大な映像作品を作り上げられましたよね。
寺内「『祓除』はテレビ東京60周年のイベントをやるというのが大前提で、事前事後番組を含めて映像作品にすることはあくまでおまけだったんですね。背筋さん、梨さんという圧倒的個性のあるホラー作家の世界観を、なんとかしがみついて映像に落とし込みました。あの時は自律神経がおかしくなったぐらい、とにかく一生懸命でしたね」
――「祓除」に続いて、「TXQ FICTION」の制作へと移っていくと思うのですが、皆口さんにとっては、これまでと違う“テレビ”というフィールドでの番組作り。どのような違いがありましたか?
皆口「普段自分は、『ゾゾゾ』でも『フェイクドキュメンタリー「Q」』でも、視聴者の声に対して、ある種耳を貸さないようにしているんですよ。ただ、そんな自分でも今回はテレビの影響の大きさを思い知りました。それこそ“イシナガキクエ”という都市伝説ができていくような過程を見られたのは、すごく感動的でしたね。珍しく、『自分はいま、おもしろいものを作っているんだ』という自信が生まれました。(1)が放送された時点では、まだ(2)以降を作っている途中だったので、1回目の反響を2回目に取り入れたり、視聴者の方からいただいた情報提供のお電話も作品に取り入れたりしました。“声”に影響を受けて反映したというよりは、取り入れるという手法ではあるんですけど。でも、終わり方はたくさん議論しましたよね」
寺内「そうですね。終わり方は当然議論になりました。でも結局元々の台本に戻ったんです。僕は制作期間中にも議論が続いたことこそが、結末を簡単に変えられない映画と違う、テレビコンテンツならではのおもしろさだと思っています。途中で視聴者の反応を見ながら展開を変えていくというのは、それこそブリコラージュ的要素だと思っていて。やってみて楽しかったです」
■「本作は『絶対に共感はできないけれど、一生懸命に生きた男の物語』だと思います」(寺内)
――寺内監督は、演出家として「イシナガキクエを探しています」でたどり着いた結末を、どのような物語だと表現されますか。
寺内「元々の構想は、イシナガキクエと米原実次という2人の関係性がなんだったのか、というテーマにあたたかな要素を入れようというものでした。『祓除』のラストもですけど、ホラーってどうしても嫌な終わり方が多くて…もうああいうのに疲れたっていうか(笑)。僕なりに『イシナガキクエ』の結末を簡単に表現すると、『変な男のとんでもない衝動の物語。絶対に共感はできないけれど、一生懸命に生きた証』という感じでしょうか。僕は米原という男の物語だと思っています」
――ありがとうございます。最後にお2人が今後、映像で挑戦してみたい“恐怖”の伝え方を教えてください。
皆口「例えば大森さんとでしたら、彼の作品は変化球が多いので(笑)、ものすごいド真ん中の心霊物を一緒にやれたらおもしろそうですね。いまの時代新しいものを作っても、単品で置いておくと埋もれちゃうし見つけてもらえないと思うので、その際は『Q』や『TXQ FICTION』のように“場所”を作って、そこに作品を置いていきたいですね」
寺内「いま僕ら2人が作っている『Q』などの作品は“超リアリズム”と呼ばれているようなんですけど、『イシナガキクエ』は”超フィクション”のつもりで、フィクションであることのすばらしさを信じて作っています。現実的な痛みという表現もたまにはやりたくなるんですけど、やっぱり作っていても痛いし、観ている人はもっと痛かったりして辛い。ですから最近は、自分が子どものころに影響を受けた大好きなフィクションの世界に帰ってきています。今後も、“恐怖”を感じさせるフィクションを作っていきたいなと思いますね」
取材・文/小泉雄也
「イシナガキクエ」は“懸命に生きた男の物語”。寺内康太郎×皆口大地が語る、「Q」から「TXQ FICTION」への道のり

関連記事
おすすめ情報
MOVIE WALKER PRESSの他の記事もみるあわせて読む
-

イ・ジフンと妻のアヤネさん、まだ新婚みたいでも「30日後にはパパとママ」
WoW!Korea6/17(月)8:21
-

TOBE合流9か月…北山宏光、初単独コンサート完走で「皆さまがいないとステージに立てなかった」
ENCOUNT6/17(月)8:17
-

香音、“野々村夫妻の長女”からティーンが憧れるモデルへ 俳優としても“ガチ恋”女子大生役で見事なギャップ披露
WEBザテレビジョン6/17(月)7:10
-

テレ朝「耳の穴かっぽじって聞け!」演出語る(1) 「文章には人の本音が反映されやすい」
スポニチアネックス6/17(月)7:00
-

あのちゃん、「この組み合わせは最高すぎ」4人組バンドと集合ショット!「まじのまじでたのしみ!」なコラボを発表
スポーツ報知6/17(月)6:45
-

「うちの息子の嫁に!」の声が殺到も 高橋里華 ひと目ぼれで結婚して芸能界引退、直後に介護を迎えた怒涛の人生
CHANTO WEB6/17(月)6:30
-

フィギュアスケーター高橋大輔、銀幕デビュー「新しい自分を発見できるチャンス」 地元・倉敷舞台の『蔵のある街』
ORICON NEWS6/17(月)6:00
-

高橋大輔、映画初出演決定 MEGUMI・前野朋哉ら出演「蔵のある街」製作開始
モデルプレス6/17(月)6:00
-

フィギュアスケーター・高橋大輔が俳優に挑戦! 倉敷を舞台にした映画『蔵のある街』製作開始
クランクイン!6/17(月)6:00
-
-

衣類乾燥機やQUOカード1万円分のプレゼント企画も データ放送ではこんなことができる!【6/17〜23の実施企画一覧】
日テレTOPICS6/17(月)5:50
-

高橋大輔氏が映画デビュー、初の俳優挑戦 故郷の倉敷市舞台作で主人公に関わる美術館学芸員役
日刊スポーツ6/17(月)5:00
-

TWS、トップバッターで新曲「hey! hey!」披露 冒頭ダンスブレイクに会場釘付け【Weverse Con Festival】
モデルプレス6/17(月)0:31
-

「芥見下々『呪術廻戦』展」榎木淳弥&諏訪部順一が音声ガイドに登場! 渋谷ヒカリエコラボ情報も
アニメ!アニメ!6/17(月)0:00
-

榎木淳弥と諏訪部順一が『呪術廻戦』展の音声ガイドを担当 渋谷ヒカリエとのコラボも決定
SPICE6/17(月)0:00
-

『呪術廻戦』展の音声ガイドは榎木淳弥&諏訪部順一「見応え満点」 渋谷ヒカリエのコラボ実施
ORICON NEWS6/17(月)0:00
-

ENHYPEN、ステージ終了後に“意味深スポ”で会場ざわめき NI-KIソロダンスから開幕でファン熱狂【Weverse Con Festival】
モデルプレス6/16(日)22:52
-

“家ロケ”復活!芸能人の自宅で「桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜」をプレイ!:有吉ぃぃeeeee!
テレ東プラス6/16(日)22:45
-

長谷川博己主演「アンチヒーロー」、怒濤の後半CM無し最終回にトレンド1位急浮上「はぁ〜、スカッとした」の声
スポーツ報知6/16(日)22:17
-
エンタメ アクセスランキング
-
1

南果歩がおばあちゃんに!「息子が父になりました」 感激の初孫抱っこ「グランマというより…」
スポニチアネックス6/17(月)0:57
-
2

TBS渡部アナ 泥酔で放尿など 民家上がり通報 日曜「Nスタ」は出演見合わせ
スポニチアネックス6/17(月)4:50
-
3

最終回【アンチヒーロー】考察アタリ!ネット鳥肌「気がついた人すごい」“名前”に驚きの共通点「やばい」
スポーツ報知6/16(日)22:24
-
4

中居正広 「あれからドラマの話は一切来てない。あれが最後。あれ遺作です」にスタジオも驚き
スポニチアネックス6/16(日)21:57
-
5

『アンチヒーロー』怒涛の最終回 裏切り者&ライバルが“仲間”に「鳥肌」「胸熱展開すぎる」
ORICON NEWS6/16(日)22:17
-
6

有吉弘行、訪れたスーパーで芸人がロケ…“大はしゃぎ”する姿に「うちの奥さんが声かけちゃって」
スポニチアネックス6/16(日)21:00
-
7

カブス・鈴木誠也に次男誕生!妻・畠山愛理が出産報告「夫がちょうどシカゴにいるオフ日に陣痛が…」
スポニチアネックス6/17(月)0:58
-
8

有吉弘行 妻・夏目三久さんの想定外行動に仰天「何を思ったのか…」「腹立ってたんじゃない?」
東スポWEB6/16(日)22:29
-
9

河合優実 「家族から顔が似ていると言われる」人気芸人とは? 「自分でもそう思う」
スポニチアネックス6/16(日)22:46
-
10

『アンチヒーロー』最終回に“未解禁キャスト”が登場 ネット驚き「一瞬だけw」「サラッと出てきた」
ORICON NEWS6/16(日)22:17
エンタメ 新着ニュース
-

カブス鈴木誠也の妻・畠山愛理さん、第2子次男出産「益々賑やかな毎日」「メイクも眉毛あればいっか」
ENCOUNT6/17(月)8:25
-

TOBE合流9か月…北山宏光、初単独コンサート完走で「皆さまがいないとステージに立てなかった」
ENCOUNT6/17(月)8:17
-

池田エライザ、上も下も生肌露出…太ももあらわのスリットワンピ姿に「めっちゃスタイルいい」と反響
WEBザテレビジョン6/17(月)8:15
-

<明日の虎に翼>伊藤沙莉“寅子”、スリの少年・和田庵“道男”を追いかけていると土居志央梨“よね”に再開
WEBザテレビジョン6/17(月)8:15
-

『虎に翼』第57話 スリを追いかけた寅子、よねと再会する
ORICON NEWS6/17(月)8:15
-

「虎に翼」多岐川ふんどし一丁 寅子呼び出し年始滝行!冒頭3分ネット爆笑「月曜の朝から何をw」
スポニチアネックス6/17(月)8:15
-

「虎に翼」今日が最後…よね、寅子と6年ぶり再会も“拒絶”ネット心配「轟に救われる」「頑なすぎない?」
スポニチアネックス6/17(月)8:15
-

「虎に翼」寅子がよね&轟と再会「轟、相変わらずいいキャラ」ネットもホッ…胸なで下ろす
日刊スポーツ6/17(月)8:15
-

朝ドラ「虎に翼」6月18日第57話あらすじ 轟法律事務所で、多岐川(滝藤賢一)は子供たちに必ず手を差し伸べると約束する
iza!6/17(月)8:15
-

明日の「虎に翼」 よね(土居志央梨)たちと再会する寅子(伊藤沙莉)<6月18日放送>
産経新聞6/17(月)8:15
総合 アクセスランキング
-
1

南果歩がおばあちゃんに!「息子が父になりました」 感激の初孫抱っこ「グランマというより…」
スポニチアネックス6/17(月)0:57
-
2

沖縄県の玉城知事「選挙結果、真摯に受け止める」 辺野古反対の姿勢は「揺るがず」
産経新聞6/17(月)1:15
-
3

TBS渡部アナ 泥酔で放尿など 民家上がり通報 日曜「Nスタ」は出演見合わせ
スポニチアネックス6/17(月)4:50
-
4

「父の日」に大暴れ!大谷翔平が今季2度目の1試合2発で球場大興奮 19号でついにリーグトップに1本差
スポニチアネックス6/17(月)6:29
-
5

最終回【アンチヒーロー】考察アタリ!ネット鳥肌「気がついた人すごい」“名前”に驚きの共通点「やばい」
スポーツ報知6/16(日)22:24
-
6

中居正広 「あれからドラマの話は一切来てない。あれが最後。あれ遺作です」にスタジオも驚き
スポニチアネックス6/16(日)21:57
-
7

『アンチヒーロー』怒涛の最終回 裏切り者&ライバルが“仲間”に「鳥肌」「胸熱展開すぎる」
ORICON NEWS6/16(日)22:17
-
8

大谷翔平、特大18号&19号のマルチHR トップに1本差…由伸&ベッツ離脱危機に奮闘
Full-Count6/17(月)7:17
-
9

「オヤジ狩りをするか」男子高校生4人が60代男性に暴行し財布など奪い逮捕 東京・あきる野市
TBS NEWS DIG6/17(月)1:23
-
10

ド軍激震、ベッツが死球で左手骨折…長期離脱、大谷翔平「タフな瞬間」
中日スポーツ6/17(月)7:07
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-
![[重賞回顧]自分らしくありのままに。絶妙なペース配分で美しく逃げ切ったアリスヴェリテが重賞初制覇〜2024年・マーメイドS〜](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33680.jpeg)
[重賞回顧]自分らしくありのままに。絶妙なペース配分で美しく逃げ切ったアリスヴェリテが重賞初制覇〜2024年・マーメイドS〜
ウマフリ6/17(月)8:00
-

長谷川唯、冨安健洋からロンドンの日本人美容師を紹介してもらった話を明かす 「トミくんから…」
Qoly6/17(月)7:45
-

メッシ、サウジアラビアの2300億円オファーを拒否!その理由をアル・ヒラル会長が暴露 「金より大事な…」
Qoly6/17(月)7:30
-

イングランド代表ベリンガム、EUROのゴールセレブレーションは「人狼ゲーム」だと説明!
Qoly6/17(月)7:13
-

青年海外協力隊、スポーツ隊員の知られざる仕事とは?
パラサポWEB6/17(月)7:00
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) MOVIE WALKER Co., Ltd.