1983年から85年にかけて5季連続で甲子園に出場し、優勝2回、準優勝2回と圧倒的な戦績を誇ったPL学園。その中心にいたのは1年生からエースと4番として活躍した桑田真澄と清原和博の“KKコンビ”だった。高校野球史に残る“伝説の3年間”の軌跡をたどる。
阿部珠樹氏のスポーツノンフィクション傑作選『神様は返事を書かない』(文藝春秋)より「KK、戦慄の記憶」の項を紹介します。<全3回の2回目/第1回、第3回へ>
PL学園は、特別なチームに
翌'84年の大会は、前年の池田のポジションにPLが腰を下ろしていた。春の選抜大会は決勝で岩倉高校に敗れてはいた。勝者の岩倉はみごとだったが、大会5試合で清原は3本、桑田は2本の本塁打を打ち、投げても桑田は決勝で14個の三振を奪っていた。実力は群を抜き、負けさえも野球のむずかしさを示す教材になるような、特別なチームになっていた。
だが、2度目の夏は油断ならない相手との顔合わせがスタートだった。愛知代表の享栄高校は東邦、愛工大名電、中京などと覇を競うレベルの高い愛知県の名門で、特にこの年は強打が注目を集めていた。
「藤王二世」
それが安田秀之につけられた呼び名だった。藤王康晴は前の年の選抜で3本の本塁打を放ち、享栄のベスト8進出の原動力になっていた。超高校級の打力と評価され、ドラフトでは地元ドラゴンズに1位で指名されて入団し、大きな注目を集めていた。その藤王に並ぶような素質の持ち主というのが、2年生の安田に対する評価だった。PLに清原がいるなら、享栄には安田がいる。安田なら桑田を打ち砕くかもしれない。
「高校では通算で47本、本塁打を打ちました。藤王さんが49本だったから、数だけなら近かったですね」
安田は現在、ドラゴンズでスコアラーを務めている。
「藤王さんたちの代が終わって新チームになった1年の秋からぼくは4番を任されました。しっかり当たれば、かなり飛んでいくという自信はありましたね。夏の大会は県予選の決勝で東邦と当たり、接戦になりました。4対3で勝ったんですが、その試合で得点に 絡む活躍ができて」
甲子園に乗り込んだときの安田は、口には出さなかったが相当な自信を秘めていた。抽選で1回戦がPLと決まり、喜ぶ者はいなかったが、うつむく者もいなかったという。
「勝てば勢いがついてぐんと上がっていける。そう思っていました」
桑田、清原との対戦経験はなかったが、テレビでは何度も見ていた。テレビで見る限り、桑田は高校生としては、球も速いし、コントロールもいいが、まとまっている分、打てない相手ではないように思われた。
「ぼくは清原君より少しだけ背が高いんです」
高校生らしからぬパワーといわれる清原よりも体格では上回っている。それも安田の支えになっていた。
「なんなんだ、こいつら。そう思いました」
だが、安田と享栄のひそかな自信は、甲子園の現場に来るとたちまち場外に弾き飛ばされてしまった。まず最初に衝撃を受けたのはエースの村田忍だった。清原や安田よりも1歳上の3年生で、ストレートの球速はさほどでもないが、大きな落差のあるカーブとスライダー、シュートの揺さぶりは定評があった。その村田は試合前の練習で、見てはいけないものを見てしまう。
「なんなんだ、こいつら。そう思いました。清原もすごかったけど、桑田の打撃が特にすごかった。よく打つぞ、気をつけろっていい合った」
1回表、いきなり清原のタイムリーを浴びて先制を許す。2回には2点。そして3回には4点。前年の高知商とよく似た失点パターンでたちまち苦境に陥る。とりわけ3回に清原に打たれた2点本塁打の衝撃が大きかった。
「第1打席でタイムリーを打たれて、うまい打者だなとは思っていました。だからここは外角中心でフライを打たせる組み立てを選びました。でも全部外角というわけには行かないので1球内角に投げた。それを引っ張られてアルプススタンドの照明の近くまで運ばれた。大ファウルでした」
「落ちてこない飛球は…あのときだけですね」
恐怖がコントロールを狂わせた。勝負球の変化球がやや高めに。清原は見逃さなかった。ライトに飛んだ打球を村田が目で追う。
「ライトは安田が守っていたんですが、彼がバックしてラッキーゾーンに付いた。取れるかと思ったら、打球はいつまでも落ちてこないで、そのままラッキーゾーンの中まで行った。落ちてこない飛球というのはあとにも先にもあのときだけですね」
ラッキーゾーンにしがみつくように頭上の清原の打球を見送った安田は、打席では桑田の投球に呆然となった。
「ここまで速いか。そう思いましたね。ぼくには全部ストレート。なめてんのかと思いましたが、打てませんでした。あっという間に終わりましたね」
享栄は桑田に3安打に抑えられた。喫した三振は11個。清原は3回の2ランを皮切りに、 レフト、センターと本塁打を3本叩き込んだ。プロでもできない芸当である。
安田から都市伝説めいた逸話を聞いた。
「桑田に二塁ゴロに打ち取られた先輩が戻ってくると、金属バットがへこんでて、縫い目の跡がはっきりついていました」
桑田の切れのあるストレートは金属バットをへこませ、刻印をつけていた。強豪の享栄に14対1と圧勝したPLの連覇を疑うものはこの時点でほとんどいなかったろう。
勝負になると思っていた…
だが、'84年夏は決勝まで進んだものの、延長で取手二高に敗れ、連覇を逃す。翌'85年春は準決勝で、伊野商・渡辺智男の速球に屈する。'83年夏の優勝以来、つねに他を圧倒したように見えた清原、桑田たち3年生には、優勝の機会は'85年夏しか残っていなかった。
その夏、期間中に、日航機の墜落事故が起こり、騒然とした空気の中で大会が進んでいく。PL学園は最初の東海大山形戦で29対7と大勝する。32安打を放ち、毎回得点という勝利は、優勝への備えが万全であることを見せつけた。つづく3回戦は桑田が津久見高校を完封した。
そして準々決勝。相手は2年前と同じ高知商業である。高知商にとってもPLは因縁の相手だった。全国制覇まであと1イニングと迫った'78年夏の大会では土壇場で追いつかれ、サヨナラ負けを喫している。2年前は8点差を1点差まで詰めながら、最後の一線が越えられなかった。
監督の谷脇一夫は2年前の対戦よりも自信を持っていた。あの時は1年生中心のチームということで軽く見た嫌いがあった。今度は違う。自分たちの戦力も整っている。特にエースの中山裕章は桑田に引けを取らない力があると信じていた。
「私は中学の有望選手だといわれても、自分で見たりはしないんですが、彼だけは見に行って、ぜひウチにということで入学してもらった。それだけの素材でした。打つほうも、選抜で優勝した伊野商の渡辺君を打ち崩して予選を勝ってきたので勝負になると思っていましたね」
2年前には8点リードされて追い上げたが及ばなかった。なんとしても先制を。期待通りにチームは2回表、桑田から2点を奪う。早いカウントからストレートをねらう作戦が功を奏した。
「あの本塁打は大きかった」
しかし、この2点がかえってPLを目覚めさせてしまった。3回裏、連続四球とバスター、二塁打などがからむPLの硬軟取り混ぜた攻めは、中山から4点を奪った。だが、それ以上に決定的なダメージになったのは5回裏の2本の本塁打だった。
「あの本塁打は試合の上でも大きかったし、当たりとしても大きかった。特に清原。レフトスタンドの中段まで飛んだんじゃなかったか」
150kmを超えるストレートで押す中山の投球がそこまで運ばれたのははじめてだった。一方、桑田の方はライナーで一直線に飛び込む一打だった。かつて8点差を追いかけ たことを考えれば、4点差でひるんではいられない。だが清原、桑田の強烈な2本は、高知商の意欲を消すには十分なものだった。
<続く>
文=阿部珠樹
photograph by Katsuro Okazawa/AFLO

















































































































![[天皇賞・春]キタサンブラックにマヤノトップガン…。レコードタイムで淀の2マイルを駆け抜けていった名ステイヤーたち](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33018.jpeg)



















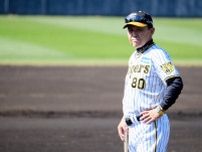

![[競馬エッセイ]関東の刺客と呼ばれたライスシャワーの歩み](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-31945.jpeg)



