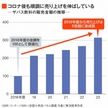青山学院大学を一躍、箱根駅伝の強豪校へと導き、今年の箱根駅伝でも総合優勝を成し遂げた原晋監督。就任当初、徐々にチームの実力を上げてきた原は関東学連選抜監督を務めることになる。今や伝説となった学連選抜での「4位」はどのように成し遂げられたのか。初出:『箱根駅伝 ナイン・ストーリーズ』(文春文庫、2015年12月刊)。肩書はすべて当時のもの(全3回の第3回/初回は#1へ)
就任4年目の2007年には、生活力の徹底によって予選会で次点まで這い上がった。そうなると、選手たちの間にも「みんなで箱根を目指そう」という意識が高まり、チームカがみるみるうちに上がっていった。
この予選会で次点となったことで、原にはひとつのチャンスが転がり込んだ。関東学連選抜チームの監督を務めることになったのだ。
原は学連選抜というチームに、情熱があった
学連選抜は知名度も高いが、チームを預かる監督にとっては「罰ゲーム」と評されることもある。箱根を走れない自分のチームの面倒を見るだけでも気がかりなのに、寄せ集めの選手たちでチームを作らなければならない。実際、選抜メンバーの5000mのタイムを足し上げると、本戦でも十分に上位に食い込むだけの力があるのに、シード権外でのレース展開となってしまうことが多かった。
原にとっては、初めて箱根駅伝で采配を振るチャンスがやってきた。学連選抜というチームに、情熱があった。
「預かったからにはしっかりやらないといけないと思いました。原という人間を陸上界で認めてもらうチャンスだとも思いました」
成功に必要な3つの力、生活力、チームカ、競技力のうち、「チームカ」を高める必要性を感じていた。
その集団で戦う理由がないなら、作ればいい
「学連選抜が弱い理由は簡単だった。その集団で戦う理由がないから。だったらその理由を作ればいい」
例年、学連選抜の最初の集合では、選手、スタッフが自己紹介をしてユニフォームの採寸、そしてマスコミヘのインタビュー対応で解散する。しかし原はいきなり、メンバー全員での長時間のミーティングを行った。
君たち、学連選抜で何をしたいの?
「君たち、学連選抜で何をしたいの? と問いかけたんです。記念? お祭り? 戦いたいのか、走りたいだけなのか。話し合ってもらうために、ふたつにグループ分けして目標を設定しました。そのなかでシード権だとか、3位を目指すという意見もありました。よし、君たちの情熱はわかった。だったら私も本気でやるから、練習をしっかり積んで欲しいと言い渡したんです」
寄せ集めのチームだから、一緒に寝起きをして生活力を高めるというわけにはいかない。全員が集まっての合宿は2回しか予定されていなかった。原は各大学の監督にマメに連絡を取り、「練習を本気でやらせてください。お願いします」と懇願した。
クリスマスイブに「もう一度、合宿をやりたい」
原が情熱を注いだことで、選手たちはたった一度のチームに対して「忠誠心」を醸成しつつあった。12月、千葉・富津で2度目の合宿をおこなう頃にはチームとしての力が増してきた。そこで原は、メンバーに「チーム名を決めよう」と提案し、再びミーティングを開いた。
「学生たちから出てきたのが、『JKH SMART』という名前でした。ジャパンのJ、関東学連のK、箱根のH。それに集まった大学の頭文字を取ったのがこのチーム名だったんです」
さらには12月24日、クリスマスイブの日に、学生たちから「もう一度、箱根の前に合宿をやりたいんです」という提案を受けた。原は「こりゃ、みんな本気になってきたぞ」とうれしかった。選手たちは学連選抜で走る意味を探る機会を原によって与えられたのだ。
「どうしてウチの選手を使わないのか?」に対し…
暮れの12月29日には、本戦での区間エントリーを行う。実は、学連選抜の監督を務める場合、学閥などによってしがらみが発生する場合がある。原のところにも、「どうしてウチの選手を使わないのか?」という質問が大学の指導者から寄せられた。
「僕は中京大の出身ですから、他の関東の監督さんたちと上下の関係がないのも結果的に良かった。だから、そうしたことを言われても『本当に強い選手を使いますから』とハッキリと伝えました」
私は走りたいと思った選手を手助けしただけ
そして、原の作ったチームは力を発揮した。特に5区を走った福山真魚(まお)(上武大)が区間3位の走りを見せると先行する大学を5人も抜き、4位で往路を終えた。復路に入っても勢いが止まらない。佐藤雄治(平成国際大)が区間2位の走りで3位に順位を上げた。7区で5位と番手を下げたものの、8区の井村光孝(関東学院大)も区間2位と大健闘を見せ、再び3位へ。9区には中村嘉孝(立大)が起用され、ふだんは陸上とは無縁の大学だけに、大きな話題を呼んだ。このあたりのプロデュース能力はもともと優れていたのだ。
学連選抜は粘って粘って4位で大手町に戻ってきた。大成功だった。
「私は走りたいと思った選手を手助けしただけです。私が他の大学の学生に走れ、と怒鳴ったところで誰も走りやしません。最初のミーティングでみんなが目標を設定して、それでやる気になっただけなんですよ」
この学連選抜での成功体験は、原に自信を与えた。自分の「チーム・ビルディング」の方法は間違っていない。この路線で強化を進めていけば、箱根には絶対に出場できる。
青学が強くなりそうだ
そして2008年10月、青山学院大は箱根駅伝の予選会を突破する。箱根出場は実に33年ぶりのことだった。
「関係者のみなさんは喜んでくれましたが、私に嫌がらせをしたOBが握手を求めてきた時、私は手を差し出しませんでした(笑)」
2009年の正月、第85回の箱根駅伝に出場した青山学院大は23チーム中、22位に終わった。
それでも、構わなかったのだ。
箱根出場はひとつのお祭りであり、ここが原と青山学院大にとって本当のスタートと言ってよかった。すでに予選会で次点になった時から、高校生たちの間では「青学が強くなりそうだ」という噂が広まり始め、超一線級とまではいわないが、成長の余地を残した選手が入学を検討するようになっていた。
ずいぶんと大きなフォームで走る子。その名は…
2010年には、前年22位のチームが一気に8位へと駆け上がり、シード権を獲得する。このメンバーで強くなっていこう。チーム全体が目標を共有し始めたのだ。ようやく原がイメージしていたような個性あふれる学生の集団へと変化が始まった。
「人間的な魅力のある選手たちが集まってくるには、組織というものの『土壌』を耕さなければいけないとつくづく感じました。組織のカラーが確立されれば、自然とその色に近い人間が集まってくる。いきなり、2、3年目にこんな雰囲気を作ろうとしても不可能でした。功を焦って、全体が見えていなかったんです」
そしてこの年の夏、原は合宿地でひとりの高校生に目を留める。
「ずいぶんと大きなフォームで走る子がいるなあ」
体重は40キロに満たないその少年は、愛知県の中京大中京高校の2年生で、名前を神野大地といった。
神野が2015年の箱根駅伝の5区で、駒澤大を抜き去り、青山学院大学が優勝するための必要なピースになるとは、このときはまだ誰も知る由もなかった。
まさに、青山学院大は頂点まで一気に駆け上がったのだ。
<「現役時代」編とあわせてお読みください>
文=生島淳
photograph by Takashi Shimizu