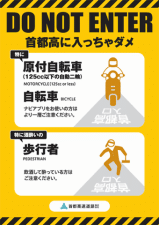ミットを叩く音が心地良い。
宜野湾春季キャンプの第2クール初日だった2月6日、ライブBP(実戦形式の打撃練習)にトップで初登板した小園健太は、先頭打者だった松尾汐恩から空振り三振を奪い、その後、林琢真、牧秀悟ら計6人の打者をストレートで押し、無安打に抑える投球を披露した。
「変化球を確かめたいというのもあったんですけれど、投げる前にキャッチャーの方とストレートで押していこうと話をしていて、基本的にストレートで押していけました。
コントロール自体はアバウトでしたけれど、ゾーンの中にはしっかりとコントロールできていたと思います。バッターの反応を見ても、ボールの下を振っていた感じがありました。ゾーンの中に強い真っすぐを投げることをテーマにしていたので、その点は良かったです。いい時のファウルの取り方もできていたと思います」
投じた球数は24球。「そのうち思い通りの球は1/3くらいだった」と本人は振り返るが、この日計測した最速144kmのスピード以上に球の走りを含め全体的に感触は悪くなかったように映った。
「今日は2球いい球を続けて投げられても、次の球が上ずったり引っ掛けていたりしました。その辺りは課題です。再現性をもっと上げていかないといけないですね。しっかり思った通りのリリースができた時は、バッターも予想通りの反応をしているというか、いい球がいっているので、その割合をもっと増やしていかないといけないと思いました」
時には自分を戒め、時には自分を称えるように少し笑みをこぼしながら小園はそう口にした。
2年前のドラ1に感じた「覚醒の予感」
21年ドラフト1位で入団。この日、春季キャンプの実戦の初期段階での第一歩をまずまずの格好で踏み出せたことに、ベイスターズファンからも“ようやく今年は来るか”という明るい声が、かすかに聞こえてくるように感じる。
この2年間、小園はもがき苦しんできた。高卒ながら背番号18を託されたように、入団当時から期待値は高かった。1年目から一軍キャンプに帯同するも実戦登板はなく、その後、身体作りに徹し、トレーニングの日々を重ねた。8月にイースタン・リーグで初登板。短いイニングとはいえ3試合連続で無失点ピッチングを続けたが、体調不良のため戦線を離脱し、その後のリーグ戦での登板はなかった。
市和歌山高校では1年春からベンチ入りし、マウンドにも立った。早い段階から実戦に立って感覚を磨いてきた小園は、投げながら成長するスタンスだ。
1年夏の和歌山大会準々決勝・南部戦で決勝打を浴びた試合から高校野球を本格スタートさせ、県内屈指のライバル・智弁和歌山と相対するたびに、分厚い壁をどう打ち破ればいいのか、研究熱心な性格も手伝って、球質向上や新球習得に時間を費やしたことも多かった。
高校2年の冬、小園はこんな練習方法を教えてくれた。
「ボールにどうやったらうまく力が伝わるのか、あれこれ握り方を変えてもうまくいかなくて。(通院している)整骨院の先生にそのことを相談したんです。そうしたら、指先を鍛えるためにサンドボールを使うのもいいって聞いて、それから練習でサンドボールを握って、リリースに力を集約する練習もしていました」
硬球3個分の重さのサンドボールは、予想以上に指に負荷がかかる。それでもあれこれ握り方を工夫し、最良のリリースポイントを探究した。ブルペンでもコーチに投球フォームの動画撮影をお願いしながら、身体の軸を意識したフォームを何度も研究した。高校野球界では秋は週末ごとに試合があったが、その投球成績を1試合ごとに○回、○球、○奪三振など細かいデータを携帯電話のメモ機能に残すことも当時の小園の日課だった。
だが、プロ1年目はそれすらできなかった。
「(1年目は)本当に自分は何もしていないので……。ずっと投げていなくてフォームもおかしくなっていて、正直、投げ方すらままならない感じでした」
そんな小園に、さらに追い打ちをかけるような出来事も1年目のシーズンにはあった。高校時代、バッテリーを組んでいた松川虎生(ロッテ)の躍動だった。
高校時代の“親友”が突如、スターダムに
とは言っても、松川の活躍が喜ばしくなかったのではない。正捕手の田村龍弘が負傷した影響もあったとはいえ、高卒ながら開幕戦でいきなりスタメン出場を果たすと、4月10日には剛腕・佐々木朗希の史上16人目の完全試合をアシストし「20歳と18歳の最年少バッテリーの快挙」と大きくメディアで報じられた。この試合も含め1年目に一軍で76試合に出場した松川が活躍するたびに「高卒新人捕手では○年ぶり」という見出しが何度も紙面を賑わせた。
松川の存在を、小園はバッテリーを組んでいた間柄以上に「親友」と明かしてきた。中学時代、貝塚ヤングからバッテリーを組み、お互いの家を行き来するほどの仲で、高校時代から互いの誕生日にプレゼントを贈り合うほど強い絆で結ばれている。プロになった今も、オフが合えば一緒に出掛けることも多いという。
「素直にすごいですよね。だって、19歳でいきなり開幕スタメンですよ。世間で言えば思春期ですよ(笑)。ほんまにすごいなって。でも自分は……あの頃はスタートラインにすら立てていなかったですからね」
悪気はなくとも…「早く一軍で」という言葉が苦しかった
何より苦しかったのは周りの反応だった。
「一番刺さったのは、悪気がないのは分かっていても周りからよく言われた“健太も早く一軍で(投げろよ)”というのが……。ありがたい言葉ですし、応援してもらえているのは嬉しいことですけれど、あの頃の僕からすればすごく傷つくというか、心がえぐられるような感じはありました」
投げて自信をつけるはずが、それができていない。身体作りも大事だが、まだ何もできていない。それどころか、投げ方を模索している最中の自分にとっては酷な言葉だった。
「何もできていなくて、あの時の自分はメンタルが弱くなっていたところもありましたけれど……。全く投げていないのに“一軍は?”とか“いつ投げるん?”って言われても……。そもそも自分もいつ投げさせてもらえるのか分からないですし(苦笑)。今はもう何を聞かれても大丈夫ですけれど、あの頃は辛かったですね」
2年目だった昨季は二軍でチーム最多の16試合に先発するなど83回1/3を投げ、2勝5敗の数字を残した。39与四球とコントロールに課題は残ったものの、マウンド経験を積み重ねられたことは間違いなく“第一歩”だったと言える。
11月中旬からは約1か月間、台湾で行われたウインターリーグに参加した。
「台湾の応援が凄いアウェイの雰囲気でしたけれど、中6日で自分に課せられたイニング数を投げられましたし、真っすぐで三振が取れたのは大きかったです。2戦目からはフォークも安定していて低めに投げられて三振も取れましたし、良い状態で投げることができました」
CPBL(台湾選抜チーム)との試合では、7回を投げ8奪三振をマークするなど、4試合で19回を投げ13奪三振、2勝0敗。防御率1.42とまずまずの成績を残した。
「7割以上が真っすぐで、変化球はフォークと……少しだけカーブを投げたくらいです」
やはりこだわるのはストレート。そのストレートを軸に勝負できたことは、何より大きな自信になった。
最近は、かつて高校時代に握り方を工夫しながら“自己流”で変化球をマスターしたように、カットボールの握り方を変えながら球質を磨くことにも時間をかけている。
「自分のイメージするカットボールはどんなボールだろうと思った時、バッターがバットを振ってから気づくというか、『今、何のボールだったの?』って後で気づくようなボールがいいなと思ったんです。目に見えて分かるのではなく、キャッチャーとバッターだけが分かるようなボールです。
真っすぐに限りなく近い握り方で、少し重心をずらすようにストレートを投げるイメージですね。捻ろうとするとスライダーになってしまうので、そこに気をつけながら……マッスラのような感じですね」
昨年は12月中旬までウインターリーグに参加していた影響もあったが、意識的にオフを短くしたという。帰国してすぐに大阪の実家に戻ると、年末は母校で約1週間、練習を重ね、4日の地元での野球教室から徐々に体を動かし始めた。8日からはDeNAの1年先輩の松本隆之介投手を介して涌井秀章投手(中日)の自主トレに参加。今季でプロ20年目のベテラン右腕の一挙一動も目に焼きつけた。
「ウインターリーグで保てた良い状態を年末年始のオフを挟んでも維持したかったので、オフを短くしたんです。一昨年のオフは自分では準備できていたつもりでも、まだ浅かったと思いました。今年、こうやってチームで最初にライブBPに入れていただいたのも、しっかり投げて走れているのも、自主トレに向けて自分で準備してこられたからだと思います」
「ひと皮剥けました。心が一番成長できたかなと」
すっきりした表情は充実感の表れなのだろうか。「取材は苦手」と自ら明かすも、小園は今の自分を、時には笑いも交えて饒舌にこう続けた。
「ひと皮剥けました。身体もそうですが、心が一番成長できたかなと。何を言われても動じなくなりましたし、何かを言われているうちが華なのかなと。もう、4月で僕21歳ですよ(笑)」
今キャンプでは、いい球をいかに確率高く投げられるかにこだわっていくつもりだ。その先に、実戦形式でのピッチング、紅白戦、そしてオープン戦と繋がっていく。
「まず一軍で初勝利を挙げることは大前提で、直近の目標は開幕ローテーションに入ること。厳しい競争になると思いますが、オープン戦からローテーションの一角を守れるようになれたらと思います。先発ローテーションは狙っていきたいというより狙っていかないといけない立場。どん欲に狙うのはもちろん、そこでしっかり結果を残したいです」
2年間の“重み”があるからこそ、強くなれた。並々ならぬ思いで臨む2024年のシーズン。ハマの18番が輝きを放つ瞬間は、今季、必ず来る。
最後に見せた小園の毅然とした表情が、そんな予感を確信に変えた気がした。
文=沢井史
photograph by Fumi Sawai