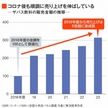人生の中で岐路に立つことは何度あるだろうか。広島2年目の益田武尚は1年目のシーズンを終えたばかりの昨秋、プロ野球人生で大きな運命の分かれ道に立った。
「右腕を下げてみないか」
1年目のシーズンを駆け抜けて臨んだ秋季キャンプ、黒田博樹球団アドバイザーからフォームの変更を提案された。迷いがなかったわけではない。野球をはじめた小学4年から、ずっと右腕を上から振り下ろしてきた。その投げ方で高校、大学、社会人と結果を残し、プロの扉をこじ開けた。だからこそ抵抗感があった。
だが、この世界で生き抜いていくために、何かを変えなければいけない必要性をどこかで感じていた。夏場に初昇格を果たした1年目は8試合に登板。初登板から7試合連続無失点、150km超の力強い直球などは可能性を感じさせたが、本人は危機感を強くしていた。
「数字で言ったら“0点”だと思います。1年間、一軍で戦い抜けなかったですし、CS(メンバー)に残れなかった。技術が足りないのか、経験が浅いからなのか、まだまだ信頼が薄い。来年も同じことをしていたら、再来年には終わりだなと思っている」
シーズン終了後に語っていた自分自身へのふがいなさや悔恨の念が、フォーム変更を決断させた。
覚悟の先に見えた景色
着手したばかりの秋季キャンプ中は戸惑いも違和感もあった。リリース時に感じる指のかかり具合に強さを感じられず、変化球の軌道も変わった。プレートを踏む位置を極端に一塁側に変えたことで景色が大きく変わり、打者に対して描くラインも変わった。
「ちょっとモヤモヤする気持ちもあるけど、これで自分のポジションをつくってしまえばいい。オフシーズンいろいろ考えながらやって、ポジションをつかみ取れれば」
腹をくくって覚悟を決めた。益田にオフはなかった。秋季キャンプ打ち上げ後、12月も、1月も新フォームで投げ続けた。常に投げてきたことで、迎えた春季キャンプ初日からブルペンで150kmを計測。フォーム変更によって目立つ存在感が、仕上がりの良さを際立たせた。
腕を下げたことによって、益田という投手の個性が色濃くなった。昨季一軍打者を押し込んだ直球の速度も回転数も維持したまま、フォークがスライダーのように曲がりながら落ちるように変わった。シンカーのように変化しながら落ちるフォークを投げる右投手はいるが、広島に同じような軌道を描くフォークを投げられる投手はいない。腕を下げたことで心配された左打者との対戦でも大きな武器となる。
キャンプ、オープン戦では先発でも起用された益田を中継ぎとすることを、新井貴浩監督が3月6日に明言した。開幕一軍当確を示唆するような言葉に、期待感が感じられる。
「先発と中継ぎ。両にらみで調整してきたけど、『中継ぎで行くぞ』と伝えて、本人もわかりましたと。先発が早めに降板する形になったらロングもできるし、同点の場面ももちろん、1点ビハインドでも。仮に先発争いさせるとして、(ニ軍スタートとなって)ファームで並走させておくのは、ちょっともったいない。いい球を投げているし、いいものを見せてくれているので」
監督就任1年目の昨季は先発陣の安定もあり、ロングリリーバーの起用はあまりなかったが、シーズンを通した先発投手のマネジメントの必要性を感じている。先発の負担を減らす意味でも、試合を立て直す役割としても、益田が担う役割はブルペンに欠かせないピースだと言える。
三度諦めたプロへの道
「プロを諦めた瞬間が3回あったけど、それが何とか転がって、今がある。投げさせてもらえるだけで感謝しかない」
野球界でいうエリート街道を歩んできたわけではない。益田は文武両道でプロへの道を拓いてきた。
福岡県内で進学校として知られる嘉穂高で145kmを計測し、プロから注目されるようになった。同校のグラウンドにスカウトが訪れる光景に学校関係者は色めき、調整というよりも品評会のようなブルペン投球となって、夏の大会を前に体が悲鳴をあげた。同校から初のプロ入りは幻となった。
東京六大学や東都リーグ所属の大学からも推薦をもらったが、「地元の公務員として働けばいい」と北九州市立大へ進んだ。4年後もプロからの指名はなし。就職に向けて勉強を始めていたときに、たまたま枠が残っていた東京ガスから誘いを受けた。
2022年ドラフト会議で指名されなければ、野球を辞めるつもりだった。周囲からは「1位指名あるぞ」と言われていただけに、1位指名が終わり2位指名でも名前が読み上げられず、会見のために締めたネクタイを緩めていたところ、広島から3位指名を受けた。
諦めるという選択肢もあった分岐点を経て、今がある。すべてが好転しているように感じられるのは、自身の選択を信じて突き進んできた結果だ。腕を下げるという投手人生で最も大きな選択が正しかったことを、今季の益田は証明できるだろうか。
文=前原淳
photograph by NIKKAN SPORTS