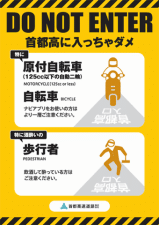慶應義塾高校、107年ぶりの甲子園優勝の陰には、11名の大学生の献身があった。現役時代の悔いや憧れを胸に、指導者の道を歩み、高校生たちと真摯に向き合い続ける良き兄貴分たちには、約40年受け継がれし若き血のDNAが流れている。
(初出:発売中のNumber1092号[優勝校の独自システム]慶應義塾高校「学生コーチの対話力」より)
慶應高校11人の学生コーチ
夏の甲子園に響き渡った「若き血」。
慶應義塾高校、107年ぶりの全国優勝は既存の高校野球のイメージを変えた。それでも、十分に語りつくされていないこともある。高校生たちに適切な目標設定を促し、成長へと導いた学生コーチの存在だ。
2月20日午後2時、日吉にあるグラウンドを訪ねる。森林貴彦監督は慶應幼稚舎での教務のため、グラウンドに到着するのは夕方。平日の練習の実施は大学生たちに任されている。
現在、慶應高には11名の学生コーチがいる。全員、高校時代はこのグラウンドで白球を追い、大学進学を機に母校のコーチになった。
この日、話を聞いたのは投手担当の松平康稔(法3)、内野担当の片山朝陽(経3)、外野担当の松浦廉(商3)の3人。
投球練習のあとは必ず話し、選手が考えていることを把握
慶應高の特色は学生コーチが戦略、戦術の立案に深く関与していることだ。投手コーチは激戦の神奈川を勝ち抜き、甲子園で勝てる投手陣の構築を進め、野手コーチたちは「チーム能力の最大化」(松浦)を図る。学生コーチたちは日々の練習の中で選手個人の目標を聞き出し、その実現に向け手助けする。
投手担当の松平は選手との対話を重視している。
「各学年に10人前後、投手がいます。投手というポジションは、生きる道がたくさんあります。140kmを超えるストレートで勝負したい。あるいは右のサイドスローから特殊球を投げて相手を幻惑する。面談という改まった機会ではなく、ブルペンでの投球練習のあとには、必ず話す機会を作り、選手が考えていることを把握するようにします」
甲子園の優勝投手である小宅雅己とは、昨年のセンバツが終わって「変化球で空振りを取っていこう」と目標を立てた。
「春の段階ではスライダーが中間球のようになってしまい、空振りが取れずにバットに当てられることが多々ありました。夏の甲子園で勝つためには、スライダーの質を上げたい。練習試合で試し、結果を話し合い、それをまた試す。その繰り返しでした」
実現のためにラプソード(ボールの軌道を分析する機器)を用い、速球とスライダーの見極めを難しくするよう「ピッチトンネル」を意識させた。すると夏になって質が向上し、小宅は甲子園で5試合に登板、28回を投げ奪三振15、与四球は広陵戦の2つだけと安定した投球を見せた。松平は対話を通して小宅のピッチングをデザインし、成功を収めたのである。
また、松平は投手だけでなく、ウェイトトレーニングのコーディネートも担当している。大学2年の春から、慶應義塾大学体育研究所の稲見崇孝研究室でウェイトトレーニングの理論を学び、それを高校生のトレーニングへと応用した。数値目標を提示できるので、選手たちの反応は上々だった。
「選手たちの体組成などを計測し、『パワー』『スピード』『バランス』の3つのタイプに分類して、各々のメニューを立案しました。僕たちが高校生の頃は漠然と取り組んでいましたが、今は数値目標を示せるので、選手たちもやりがいを感じてくれたはずです。去年の例でいえば、県大会決勝の横浜戦で逆転スリーランを打った渡邉千之亮はスピードタイプだったので、トレーニングではパワーを重視したことが結果につながったと思います」
高校生は数字を信奉する。成長が実感できるからだ。その一方で松平は、野球において必要な繊細な感覚を言語化することも目標にして欲しいと話す。
「数値目標と言語目標、どちらも大切です。数値は分かりやすく、裏切りません。実際に筋肉量が増えたことでスイングスピードが上がり、春のセンバツでは歯が立たなかった仙台育英の投手陣の速球に、夏は振り負けませんでしたからね。ただ、言葉も大事です。再現性が高まるので」
数字とともに現代の高校生たちが好むのは映像による確認だ。しかし、映像に頼ると言語化が疎かになる。
文=生島淳
photograph by Yuki Suenaga