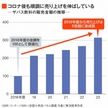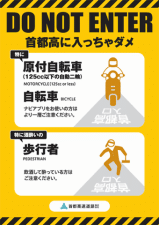2018年、多くを語らず、ひたすらに岩壁で理想の登攀を追求し続けた稀代のクライマーが高峰に散った。一村文隆、享年41。自由な思想で日本のアルパインクライミングを旧習から解放した男の生涯を追う。
(初出:発売中のNumber1092号[ノンフィクション]「ギリギリの彼方。クライマー・一村文隆の生と死」より)
ミステリアスな存在「イッチー」
「暗いやつだな」
それが横山勝丘の一村文隆への第一印象だった。仲間内で「ジャンボ」の愛称で親しまれる横山は、岩肌を想起させるような骨格と風貌の持ち主だ。横山は2つ年上の一村を「イッチー」と呼んでいた。
「イッチーの名前は聞いてたんです。すごい気合いの入ったやつがいる、って。アルパインクライミングを真面目にやってる人って、すごく少ない。だから、そういう情報はすぐ入ってくる。話には聞いていたんですけど、すごく人見知りする感じでしたね」
写真の中の一村は、目が小さいせいもあるのだろう、表情が読みづらく、確かに内向的に見えた。
私の中で一村は長くミステリアスな存在だった。トップクライマーたちの話の中にたびたび登場するのだが、どんな人物で、何をなし遂げたのかもわからない。
ピオレドール賞という、賛否両論あるものの、世界の山岳界においてもっとも権威のある賞がある。一村は2008年に同賞を受賞したほどの実力者であるにもかかわらず、極端に情報が少なかった。
彼はメディアに露出することをひどく嫌悪していたという。山で価値の高い成果を挙げると山岳雑誌等にレポートの提出を求められるのだが、パートナーが書くことはあっても一村が書くことはまずなかった。
登山界に突如現れた「ギリギリボーイズ」
アルパインクライミング――。この言葉を簡単に説明すると、標高6000m以上クラスの山で、年中、氷と雪が張り付いているような壁を2本のアックス(鎌のような登山具)を使いながら登る登山のことだ。乱暴な書き方をすれば、さまざまな種類の登山の中で、もっとも死が身近にある。
日本で一時期、この登山スタイルによる成果が「狂い咲いた」時期がある。狂い咲きという表現を使ったのは山岳ライター兼編集者の森山憲一だ。
「日本のアルパインクライミングって、'90年代はずっと停滞していたんです。凝り固まったタイプの登山家たちばっかりで。その状況で『ギリギリボーイズ』という20代のやつらが現れた。彼らは山を舐めるなと威張っていた古い気質の登山家たちがとても登れないような壁をバッコバッコ落としていったんです。'05年あたりから始まって、'12年、'13年ぐらいまでがピークだったかな。それは鮮烈でしたよ。最初の頃、彼らの中心にいたのが一村君と横山君だったんです」
ギリギリボーイズとは、彼らが使っていた遠征隊の名称だ。複数人で登山申請を行う際、団体名を記入しなければならない。従来の遠征隊なら大学山岳部や山岳会の名称を使うところだが、彼らはそうした大組織には属さず、遠征ごとに2人から3人程度の小さなチームを組んで行動していた。その際、便宜的に使っていたのがこの名前だった。ひと昔前、ちょっとしたブームを巻き起こしたギリギリガールズというセクシー女性アイドルの名称をもじったのだという。この軽いノリが彼らの気分と勢いを象徴してもいた。
「こいつと一緒に登らなければダメだ」
横山が一村に初めて会ったのは2004年夏のことだ。場所は「小川山」と呼ばれる長野県川上村の岩場が乱立するエリアだった。
「約束をして会ったんじゃなくて、たまたま知り合ったんです。僕は明るいやつの方が好きなんですけど、山に対するモチベーション、向いてる方向は彼と一緒だった。イッチーはすでに海外経験も豊富で、組んだら海外の大きな山に行けそうだな、というのがわかった。だから、こいつと一緒に登らなければダメだって。会った翌日には、もう来年どっかに行こうぜ、という話になっていたと思います」
その前年から、横山は「冬壁」に取り組み始めていた。彼らが出てくる以前、クライミングと言えば、岩肌にいくつものボルトを打ち込み、ただ、真っ直ぐに登るというのが主流だった。後続する者も、そのルートを踏襲する。そこには横山が求めていたものはなかった。
「夏に登ったらそんなにたいしたこともない壁も、冬になると雪とか氷でデロデロになる。下から壁を見上げたとき、氷と雪とクラック(岩の割れ目)をどうやってつなげば登れるかを考えるんですけど、僕にとってそれはパズル感覚に近い。年によって氷や雪が付く場所が変わるので、正解は毎年変わる。難しいし、怖いけど、それが楽しいんですよね」
年が明けると、一村と横山は海外遠征に向けて、さっそく冬壁でのトレーニングを開始した。登攀の際、彼らは原則的にナチュラルプロテクションと呼ばれる回収可能な固定器具のみを用い、回収不能なボルトは使わない。壁を傷つけないのが流儀だった。
横山にとってテクニックはもちろんだがそれ以上に刺激を受けたのは一村の山への向き合い方だった。
一村の代名詞でもあった「残置無視」の哲学
「山に入って、それからどこの壁を登るか決める。それがイッチー流。予習はほとんどしていかない。不確定要素が多ければ多いほど楽しいという考えなんです。あと、それまでは残置(のボルト)があったら僕も使っていたんですよ。けど、一村はボソッと『そんなの使わねーよ』って。あれは目から鱗でしたね。彼は本能的にこうすれば登山がもっとおもしろくなるということがわかっていたと思う」
「残置無視」。これは一村の代名詞でもあった。一村が書き残した数少ない署名記事、『ROCK&SNOW』の2006年6月号に掲載されたエッセイにはこんな言葉が記されていた。
〈ボルトラダー(ボルトが階段のように連なっているルート)をたどる行為ほどむなしいことはない。これはすでにクライミングではない〉
シンプルだが刃物のような切れ味を感じさせる文章である。横山が思い出す。
「残置の支点がすぐそばにあるのに使わないって、すっごいシュールだなと思った。でも、その方が精神的強さも身につくし、山を見る目も養われる。残置無視で冬壁を登ったことで、そのあと誰も登っていないような海外の壁にも対応できたんだと思います」
「あと何年あったら、下からちゃんと登れてた?」
倉上慶大もまた、そんな一村から大きな影響を受けたクライマーのうちの1人だ。倉上は2014年から2019年まで登山用具の輸入代理店、ロストアローで働いていた。一村は会社の先輩であり、山の師でもあった。仕事が終わると、同じ敷地内の人工壁が設置されたジムで夜の6時から規定の10時までともにトレーニングに励んだ。冬は隙間風が吹くため、ストーブの前で山の話をすることの方が多かったという。
倉上は今、素手で自然の壁を登るフリークライミングの世界で頭一つ抜けた存在である。2015年、国内最難度の壁で、まだ誰も成功者のいなかった「千日の瑠璃」という大岩壁を登り切った。日本山岳史に残るビッグクライミングだった。だが、一村に会社のジムでそのことを報告すると「おめでとう」と言われた後、何気ない口調でこう言われた。
このクラスの難壁に挑むとき、クライマーは通常、事前に上からロープでぶら下がり、岩の形状等をチェックする。だが、倉上はそれを自らに禁じていた。ただ、このときは悩んだ末に下見をした。それをしなければ太刀打ちできない壁だと判断したのだ。
一村が言った「下からちゃんと」とは「上からぶら下がることなく」という意味だった。倉上が話す。
「一村節ですよね。実力をつけて、下から登った方がよかったんじゃない? と。つまり、おまえは何のために登ってるんだよっていうことですよね。あの言葉は今もある種の呪縛のようになっているんです」
山と対等でありたい。一村のその志向は、もはや宗教に近いものがあった。
酒席で仲間が不甲斐ない発言をすると、一村は…
冬の間、みっちりトレーニングを積んだ一村と横山は4月、いよいよ海外遠征に打って出た。そしてアラスカを拠点に2つの新ルートを開拓する等、次々とビッグクライミングを成功させた。一村と横山は初登となったルートにそれぞれ「志士」「武士道」と名付けた。いずれもそのとき一村が読んでいた本がヒントになっている。横山が回想する。
「イッチーは侍ものが好きなんですよ。『志士』って付けたときは、イッチーが『竜馬がゆく』を読んでいたのかな。『志士は溝壑に在るを忘れず……』という言葉があった。武士たるもの、いつ殺されて、そこらへんの溝に転がってるかわからないっていうことですよね。アラスカの大岩壁を目の前にして、こういう心境じゃなきゃ登れないと思ったんです」
一村は酒席などで仲間が不甲斐ない発言をすると、腹の前で両拳を重ね、横に引くポーズをすることが度々あった。つまり、切腹である。
横山は一村と組んだことで、2段、3段抜かしで階段を上がっているかのような感覚になっていた。
「ここまでできるんだ、ここまでやっていいんだということに気づかせてくれた。自分が解放されましたね。あれが僕のブレイクスルーでした」
ここから若手クライマーたちの解放の連鎖が始まる。狂い咲きの季節がやってきたのだ。
ただし、花の命は永遠ではない。咲いた花はいつか枯れる。あるいは、散る運命にあった。
文=中村計
photograph by Yusuke Sato