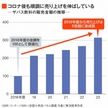野球界注目のスラッガー・花巻東高の佐々木麟太郎が、米スタンフォード大への進学を決めたことが話題となった。実はこの秋、陸上界から高校女子No.1中距離ランナーも海を渡る。1500mで高校歴代2位の記録を持つ浜松市立高3年の澤田結弥(ゆや)が、MLBやNFL選手も多く輩出する超名門・ルイジアナ州立大への進学を決めた。これまで女子のトップランナーが海外大へ進学を決めたケースはほぼない。なぜ彼女はその決断に至ったのだろうか。本人にその真意を聞いた。《NumberWebインタビュー第2回/前編から読む》
本格的に陸上競技をはじめて、わずか1年半――。
そんなキャリアで高校2年生の8月に出場したU-20世界選手権1500m6位入賞という結果を残した静岡・浜松市立高の澤田結弥。大舞台の後も、彼女の好調は続いた。
世界大会での結果を受けて、日本陸連からは次世代の育成強化選手であるダイヤモンドアスリートにも選ばれた。また、10月のとちぎ国体では3000mで日本人トップとなる2位。12月の世界クロカン選考会では、高校生ではあまり走る機会のない5000mでいきなり15分台をマークし、世界クロカン日本代表にも選出された。
マルチな種目で活躍する才能を見せ、ここまではまさに順風満帆の陸上生活だった。
年が明けた2023年3月には、世界大会の走りを評価されスカウトを受けたルイジアナ州立大の施設見学にも趣き、アメリカ進学へも前向きな思いが出てきていた。
故障に端を発した高3時の「スランプ」
ところが、年度が替わり3年生に進級した頃から、その好調さに影が差しはじめる。
腸脛靭帯の痛みに端を発したシンスプリント、それが悪化しての疲労骨折など、故障を連発した。なんとか春の県大会、東海大会は突破したものの、満足にトレーニングが積めないなかで高校生活最大の目標にしていた夏のインターハイは欠場することになった。
「やっぱり高校で本格的に陸上をはじめてからはインターハイを一番の目標にやってきていました。そこに出られないということが分かって、一度自分の目標を見失ってしまった感じがあったんです」
まだ10代の高校生だ。しかも、それまでは長期の不調など経験したこともなかった。競技の結果は、如実にメンタル面にも影響した。
こんな調子でアメリカなんて、本当に行けるんだろうか。弱気になった。前向きになりかけていた世界への扉が、少しずつ閉まろうとしていた。
そんな中でインターハイが終わった8月、テレビで見ていたブダペスト世界陸上でやり投げの北口榛花(JAL)が金メダルを獲得したシーンに目を奪われた。チェコ人のコーチと喜びを分かち合い、流暢なチェコ語で現地のインタビューに答える北口の姿は、目標を見失っていた澤田の心にもう一度、火をつけた。
「とにかく世界の舞台で輝いていた北口さんがカッコよかったんです。ダイヤモンドアスリート向けの講演で『早いうちから海外に出たほうがいい』とご本人が言っていたことも思い出して。
U-20世界選手権こそ入賞できましたけど、私、国内でも“1番”になったことがないんです。だからこそ北口さんを見て、なんというか――世界とか、もっと高いところを目指してみたいなと、素直にそう思えたんです」
海外への進学…背中を押した先輩たちの言葉
その後は、アメリカの大学への進学を選んだ男子800mの元日本王者であるクレイアーロン竜波(相洋高→テキサス農工大→ペンシルベニア州立大)や、100mハードルの高校記録保持者で、現在筑波大からテキサス大サンアントニオ校に編入した小林歩未、独自の進路を歩み続ける女子中長距離の第一人者である田中希実(New Balance)らにも相談したという。
「田中さんに言われたのは、競技の面では『必ずしも海外に行くことだけが正解とは限らない』ということでした。でも、その上で皆さんが共通して言っていたのが『(海外へ進学するという)挑戦をすることはとても価値があることだし、その選択自体は全く後悔していない』と。それですごく背中を押してもらえた気がします」
故障が癒えた9月以降は、少しずつ練習を再開した。
駅伝シーズンには母校2度目となる全国大会出場の立役者にもなり、12月には都大路でエース区間の1区を駆けた。年明け2月の福岡クロカンでは、シニアのランナーを相手に2km部門で憧れの田中に次ぐ2位に入り、再びセルビアで行われる世界クロカンの代表にも選ばれた。
3月頭にはルイジアナ州立大の語学試験に無事、合格。今後は9月の入学までは地元・浜松を拠点に英語の勉強に力を入れつつ、日本選手権などの大会を目指していくという。
「ダイヤモンドアスリートのカリキュラムにたまたまオンライン英会話が入っていて、それがとても助かりました。学校の授業が終わってからは1日5時間〜6時間とか勉強して、少しは話も理解できるようになったと思います」
最大の強みは「いい意味での“陸上素人”感」
澤田を指導する杉井将彦監督は、彼女の最大の強みを「いい意味での“陸上素人”感」と分析する。
「いまだに全部のレースで自己ベストを出す気で走っているんです。このレベルの選手では普通、考えられないでしょう(笑)。でも、それを心から信じられる強さがある。それが実はすごく大事なことだと思っています」
元110mハードルの日本王者で、現在は日本陸連の強化育成担当も務める杉井はこう言葉を繋ぐ。
「いまの日本の育成年代の選手は、インターハイであれ全中であれ、短中距離であれば予選、準決勝、決勝の3本、長距離であれば予選と決勝の2本のレースをいかに高いレベルで“まとめるか”で結果につながっています。でも、世界に出たら1本のレースでいかに120%を出せるかの勝負になってくるんです」
ユース、ジュニアの年代ならば、従来のやり方でもなんとか通用する。
だが、前半からハイペースで突っ込んで、その結果“落ちてくる”選手を抜いて着順を上げるレーススタイルでは、シニアになって力が付き、高出力で複数本のレースを走れるようになった海外勢に太刀打ちができなくなってしまう。
杉井は、強化委員としてそんなシーンを何度も目の当たりにした。だからこそ、澤田の持つ気質の貴重さを肌で感じているのかもしれない。
そしてそれは、彼女の育成環境による影響も大きい。
澤田の通う浜松市立高は、学年の半数以上が国公立大に進学する静岡有数の公立進学校だ。いわゆる駅伝強豪校の私学のように、スポーツにフルコミットできる環境とは異なる。
多くの強豪校では当たり前の朝練習も「自由参加」で、メニューも個々人の裁量による部分が大きい。澤田自身は「入学当初は朝練で走り込んだりもしたんですが、急に練習量が増えたからか小さなケガが多くなって。まずは体幹など含めたフィジカル面の強化が必要だと感じて、いまは朝練では補強しかしていないんです」と語る。また、テスト期間中は部活動そのものがなく、赤点を取れば部活参加もできなくなる。
「普通の高校の部活動」だから得られたもの
普段の練習も16時半の授業終了後からはじまり19時には完全撤収で、日曜日は完全オフ。まさによくある「普通の高校」の部活動の姿だ。だからこそその環境で成長するには、自分自身でどんな練習が効果的なのかを自問自答し、考え続ける必要がある。もちろん中長距離パートでも走行距離にこだわることもなく、澤田本人もいまだに「適性距離がよくわからないんです」と苦笑する。
「中距離ランナーと言われることが多いですが、800mは一度も走ったことがないですし、5000mとかも走ることがあるので……」
ただ、その未知数な部分こそが、杉井の言う「強み」そのものなのだろう。
「上半身の腕振りはまだ“バスケ走り”ですが、裏を返せばそれも伸びしろでしょう。また、高3のシーズンを故障で苦しんだこともかえって良かったと思います。上手く行かないときでも出口があることがわかったでしょうし、それこそ海外に行けば一筋縄ではいかないケースも増えるでしょうから」
誰も歩んだことのない道を行くのは決して簡単なことではない。それでも、未踏のルートを進んだからこそ見える風景があるのもまた事実だろう。
弱冠18歳――いまでもまだ競技歴は3年足らずだ。
そんな“未完の大器”が示す新しい道は、ひょっとしたら見たことのない頂へと繋がっているのかもしれない。
文=山崎ダイ
photograph by (L)AFLO、(R)Hideki Sugiyama