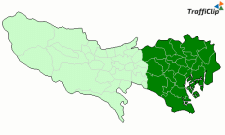現在、タレントとしてテレビを中心に活躍する元衆議院議員の杉村太蔵さん。高校時代はテニス部に所属し、国体で優勝するほどの腕前を持つ杉村さんは推薦で筑波大に入学も、テニスを続けることはなかった。将来を期待された「高校日本一」の選手は、なぜコートを去ったのか。(Number Web「私の部活時代」インタビュー全3回の第2回/初回はこちら)
「監督以上に、太蔵が怖かった」
高校3年生となった杉村は、札幌藻岩高校テニス部のキャプテンに就任。名実ともに同校の大黒柱となり、「日本一」の悲願に向けてさらに練習に力を注いでいく。
杉村の掲げる「日本一」とは個人ではなく、あくまで団体優勝のこと。だから、自分だけでなく仲間のレベルも引き上げなければいけない。杉村の勝利への執着はチームメイトにも向けられ、厳しく接し、時には容赦ない叱責を浴びせた。
「あまり練習に身の入っていないヤツを見ると、正直ムカついていましたよ。『練習イヤだなぁ』などとつぶやいているヤツがいたら『何いってんだよ!』と怒鳴ったり。今も当時の仲間たちと集まると『監督以上に太蔵が怖かったよ』って言われます(笑)」
なんでそんな簡単なこともできないんだよ
それに、テニス一家に生まれ、幼少期からラケットを握っていた杉村はいわゆる天才肌の選手。周りのできない選手を見ても、そのできない理由がわからない。それもまた彼の苛立ちを募らせた。
「サーブが苦手なヤツに『もっと肩の力を抜けよ』と言うのですが、そもそも彼はその力の抜き方がわからなくて悩んでいるんですよね。でも、当時の僕は『なんでそんな簡単なこともできないんだよ』と思っていました。僕みたいな人間には一生コーチは務まりませんね(笑)」
それにしても、高校時代の話を聞けば聞くほど、お茶の間で見る「杉村太蔵」のイメージとはかけ離れた意外な一面に驚かされる。当時の杉村はただ純粋に、「北海道から日本一へ」という頂点だけを見つめ、自分に、そして仲間に厳しく接していたのだ。
ダブルスのペア相手に「プレッシャーをかけすぎた」
1997年8月、杉村はキャプテンとして最後のインターハイに臨む。最大の目標に掲げていた団体戦は、残念ながら前年の優勝校にベスト8で敗れ、「柳川を倒して日本一に」の悲願はかなわず涙をのんだ。
一方、後輩選手と組んで臨んだ個人戦のダブルスでは第1シードを撃破するなど快進撃を見せ、準決勝まで勝ち進む。東京の私立強豪校ペアとの一戦はファイナルセットまでもつれ、5-5で杉村の後輩のサービスゲームを迎える。タイトルへの執念に燃える杉村は、鬼の形相で後輩をにらみつけた。
「いいか、1ポイント目が大事だぞ。絶対にファースト(サーブ)を入れろよ。絶対だぞ!」
はたして、前衛で構える杉村の後ろから飛んできたのは、ハエが止まるようなひょろひょろサーブ。相手選手の強烈なリターンを食らい、そのサービスゲームを落としてしまう。結果、5-7で敗れて決勝進出を逃してしまった。
「バッコーンと打ち込まれて……後輩にプレッシャーをかけすぎてガチガチにしちゃった僕のせいです。高校生なので、まぁ若気の至りですかね……」
反省が活かされた国体「のびのびやれ」
杉村は当時を振り返り、苦笑いを浮かべる。しかし、このインターハイでの“失敗”が、その1カ月後に大阪で開催された「なみはや国体」で活かされる。
北海道代表として、インターハイと同じ後輩選手とともに国体に出場した杉村。反省を活かし、今度は後輩に「思い切ってのびのびやれ」と語りかけ、プレッシャーから解放させた。そのかいもあって、見事に優勝を果たすのだ。
杉村のプロフィールでは「国体ダブルス優勝」と書かれていることが多いが、正確にいうと国体はシングルス2本、1勝1敗の場合はダブルス決戦という「団体戦」だ。監督の緒方も含め「オール札幌藻岩」で国体に臨んだ杉村は、15歳から抱き続けてきた「北海道から日本一に」の悲願をついに果たしたのだ。
なぜあんな大学生活になってしまったんだろう
高校最後の大会で山頂にたどり着いた杉村。この先もテニスでの輝かしいキャリアが待っている、と周りの誰もが思っていたし、自分もそう信じて疑わなかったはずだ。
しかし、その後の彼を待ち受けているのはあまりに数奇な、そして過酷な運命だった。
「僕の人生で、大学での6年間というのは何ひとついい思い出がないんです。自分でも、なぜあんな大学生活になってしまったんだろう、と……」
大学時代のことに話題を向けると、杉村はそう言ってしばし言葉を詰まらせた。
高校時代の栄光から一転、何が起こったのか。思い出したくもない6年間を、杉村は重い口を開いて少しずつ語り始めた。
歯科医一家も「継ぐつもりはなかった」
祖父の代から歯科医の杉村家にとって、長男である太蔵は“家業”の歯科医を継ぐべき存在として家族の期待を一身に受けてきた。両親は「浪人してでも歯科大学に」と諭したが、18歳の杉村はそれをかたくなに拒んだ。
「人の口の中にまったく興味がないんです。絶対に歯医者を継ぐつもりはありませんでした」
一方で、国体優勝のタイトルを手にした杉村のもとには、関東、関西の強豪大学から多くのスカウトが舞い込んだ。その中から彼が選んだのは関東の強豪校、筑波大学だった。
大学入学時にはラケットを握る気力すらなくなり……
大学への進学も決まり、部を引退後もしばしばコートで汗を流していた杉村。しかし、自身の心身面でのある「異変」に気づく。
「まず、すごく疲れるんです。それに、テニスしていても楽しくない。いくらいいショットを決めてもちっとも嬉しくないんです」
引退したばかりだし、少し休めば大学に入学する頃にはまた意欲も戻るだろう――そんな淡い期待を抱いていたが、逆に大学に入学した頃にはラケットを握る気力すら残っていなかった。
「バーンアウト(燃え尽き症候群)」に陥ってしまったのだ。
大学ではテニスをやらなかった
テニスでスカウトされ、推薦を受けて大学に入っているのだから、本来は大学のテニス部に入部するのが既定路線だ。しかし、高校で「日本一」の目標を達成した杉村には、次に目指す目標が見つからず、もはやテニスを続ける意味を完全に見失っていた。テニス部から何度も声をかけられるが、ひたすら無視し続けた。
「入部しないにしても、本来は自分から断りの連絡を入れなければいけませんよね。でも、そうわかっていても電話をしようとする気力すらわかない。それほどの精神状態だったんです」
不調を言語化できないもどかしさ
自ら望んで進んだ大学ではないから、授業を聴いてもまったく面白くない。キャンパスを歩いてラケットバッグを持ったテニス部員とすれ違ったら、冷たい目で睨まれる――次第にキャンパスから足が遠のき、下宿先に引きこもるようになっていく。
「昼過ぎに起きて、食べて、また寝て……今考えたら想像もできないような堕落した生活をしていました」
1998年当時は、「バーンアウト」の言葉もそれほど浸透しておらず、主だった研究もない時代。だから杉村自身、自分の置かれている状況をうまく言語化できず、もどかしさを抱えたままでいた。
何にも興味が起こらず、頑張る気力もない。この状態は、いったい何だろう……?
24歳で退学「僕の過去にはそういう時代がある」
「スポーツの最高学府」でもある筑波大学だからメンタルトレーニングの研究も進んでいるのでは、と杉村は学内のさまざまな研究論文を調べてみた。しかし、試合中にパフォーマンスを最大化するための研究はあっても、バーンアウトに関する研究はほとんどなかった。
やる気の出ない自分をなんとか変えたいと、法学部への転部も試みた。司法試験の勉強にもチャレンジした。それでも状況を打開できないまま、大学6年目、24歳の杉村は大学からの退学を余儀なくされる。
「18歳から24歳の、人生でいちばん輝かしいはずの時期を、僕はそうして過ごしてきました。普段はテレビに出て、明るく元気よく振る舞っているように見えると思いますが、僕の過去にはそういう時代があるんです」
テニスとともに歩み、栄光を手にした人生から一転、テニスとは無縁どころか、世間からも隔絶された光の見えないトンネルを、杉村はさまよい続けていた。
実家からは「働かないなら死ね!」
ほぼ引きこもり状態の6年間を過ごし、筑波大学からの退学を余儀なくされた杉村。実家からの仕送りも途絶え、困り果てて父に電話で「旭川に帰ろうと思う」と相談したところ、強烈な“リターン”を見舞われる。
「働かないなら死ね!」
その一言で目が覚め、「このままじゃいかん」とあわてて就職活動を始める。しかし、2000年代初頭の当時は「超」がつく就職氷河期。大学に6年も在籍した挙句に追い出された24歳の若者を相手にしてくれる企業などなかった。
そして、杉村は国会議員になる
藁にもすがる思いで派遣会社に登録し、なんとか清掃会社での職を得た杉村。当時住んでいた千葉県市川市から始発の総武線に乗り、東京・赤坂の山王パークタワーで6時半から清掃員として働いた。
「毎朝、総理官邸の裏の坂道を降りて出勤していました。ここに小泉(純一郎・元首相)さんがいるんだな、と思いながら……まさか2年後、この小泉さんにあいさつに行くとは夢にも思わないですよね(笑)」
その後、ビル清掃の仕事で外資系証券会社の社員と出会ったのをきっかけに同社で雑用の仕事を始める。その時期に自民党の衆院選候補者の公募に合格し、2005年の衆院選で自民党の圧勝を受け35位の比例名簿からまさかのタナボタ当選で、知名度もまさに全国区になっていく。
そして、政治家となった杉村は約6年ぶりに再びラケットを握ることになる。
<つづく>
文=堀尾大悟
photograph by Yuki Suenaga