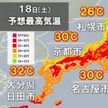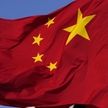多くのアスリートの語学面をサポートするタカサカモト氏に、その過程とレッスンから垣間見えた素顔を訊いた。前編は、“世界最高峰”と評されるプレミアリーグの舞台に30歳でたどり着いた遠藤航(リバプール/31歳)のエピソード。日本代表キャプテンが英語習得のために使った意外なトレーニング法とは?【NumberWebインタビュー全2回の1回目/後編に続く】
2017年、24歳の遠藤航は歌い続けていた。何を? エド・シーランの「Thinking Out Loud」を。
老いてもなお変わることのない愛――結婚式でも定番のラブソングであり、愛妻家として知られる遠藤にピッタリの選曲だ。とはいえ、リリックのテーマはさして重要ではない。のちに日本代表のキャプテンとなる男は、海外移籍の可能性を模索しながら、ある講師のもとで一風変わった英語のトレーニングに励んでいたのだった。
“エド・シーラン熱唱指令”の真相
「自分自身が受験生のとき、単語帳って苦手だったんですよ。語学学習的にも、日常生活で単語だけ発するというのはありえないので、文脈で覚えたほうがいい。文を丸ごと呑み込んでもらうという意味で、最初は英語の歌や英文を暗唱するという方法を採用しました」
そう振り返るのは、“エド・シーラン熱唱指令”を出した語学講師のタカサカモトだ。英語、ポルトガル語、スペイン語を巧みに操り、語学面からアスリートの海外挑戦をサポートする事業「フットリンガル」の代表を務めるサカモトは、浦和レッズで遠藤の同僚だった李忠成の紹介によって、2017年から語学のレッスンを担当することになった。
もちろん、ただ漫然とエド・シーランを歌わせていたわけではない。歌詞の英文を完璧に理解し、正確な発音をマスターさせるために、5分にも満たない「Thinking Out Loud」の完成に1カ月ほどの時間を費やしたという。付け加えるなら、いざ海外移籍が実現したときに“エンドー・シーラン”としてロッカールームで華々しいデビューを飾るところまでをイメージしての選曲でもあった。
「レッスンを始めた時点で遠藤選手はすでに3児の父(現在は3男1女の4人)で、送り迎えをしたりお風呂に入れたり、子育てにもしっかりコミットしていた。レッスンはリモートなんですけど、『ボクも見る〜!』ってお子さんが画面に入ってきちゃったり(笑)。そういった意味であまり時間がなかったので、アウェイ戦の前泊と代表活動中に集中してやることが多かったですね」
東京大学文学部卒のサカモトから見ても、遠藤の学習意欲と“強度の高いメニュー”への耐性は群を抜いていた。歌を通じて耳と舌の素地を固め、そこから単語帳や参考書を用いてのリスニングとリーディング、暗唱へと移行しても、モチベーションが萎えることはなかった。中学レベルから徐々に負荷を上げていく過程で、「宿題を出せば必ずこなしてくる」のが遠藤という人間だった。
「(クライアントの1人である)原口元気選手に聞いたんですけど、代表メンバーのお喋りのなかで『日本代表で一番サッカー選手っぽくないのは誰?』という投票をしたら、遠藤選手が1位だったそうです。なんというか、いい意味でアスリートっぽくないんですよね。スポーツクラスのなかに、1人だけ特進クラスの生徒が交ざっている、みたいな(笑)。ロシアW杯の直前に課題として出したドイツ語の文法ドリルを、W杯期間中に最後まで終えていたこともありました。教える側としてはむしろ、遠藤選手でうまくいったからといって成功体験にしてはいけないな、と」
子どもたちに交ざってフランス語を学ぶ!?
2018年のシント・トロイデン移籍後、遠藤は自ら現地の「公文」に子どもたちに交ざって通っていた。フランス語を母語とするチームメイトが複数いたことが主な理由だった。さらに、翌年シュツットガルトに移籍する前からドイツ語の学習も開始。語学学習の専門家としてドリル選びなどドイツ語の勉強法もサポートしていたサカモトだが、「いまでは彼の方がちゃんと喋れますね」と苦笑する。
「頭のよさって、学力だったり人間観察力だったり、いろいろな種類があるじゃないですか。遠藤選手の場合は、効率へのこだわりがすごいんですよ。思考が本当にロジカルで、徹底的に考えて答えを導き出す素養を持っている。彼の著書のタイトルにもありますが、まさに『最適解』マンですね(笑)」
2023年夏にプレミアリーグの名門リバプールへと加入すると、遠藤の語学力の高さは現地でも注目を集めた。「Yeah」といった相槌を交えながら、インタビュアーの質問に流暢な英語で答えていく――短期間で“適応”を果たしリバプールの中盤の要となった日本代表キャプテンも、数年前までは中学レベルの教材と向き合っていたのだ。
ここで簡単に、サカモトの経歴を紹介したい。
東京大学在学中に留学先のメキシコでタコス屋として働き、卒業後は飛び込みのプレゼンを経てブラジルの名門・サントスFCで広報の仕事に就くなど、東大文学部の先輩である小田実もかくやの「何でも見てやろう精神」を発揮。その行動力と語学力を駆使して、ネイマール来日時の通訳やガイナーレ鳥取の通訳をはじめサッカー界で活動の幅を広げ、2017年に「フットリンガル」を創業した。上京時は鳥取弁しか喋れなかった青年が国際派のマルチリンガルに至るまでの足跡は、サカモトの著書『東大8年生 自分時間の歩き方』(徳間書店)に詳しい。
「フットリンガル」の事業としての性格上、クライアントには海外挑戦を視野に入れた選手、つまるところ日本代表クラスの選手も少なくない。具体的には、原口元気、鈴木武蔵、室屋成、伊藤涼太郎といった選手たちがサカモトのもとで語学を学んでいる。
向上心も代表クラスだった原口元気
遠藤とは異なり「サッカー選手らしいキャラクター」だという原口だが、その向上心は語学学習においても“代表クラス”だった。サカモトは「自分に足りないものが何か、納得がいくまで突き詰めるタイプ」と分析する。
「根がすごく真面目だし、こういう考え方だから選手としてこのレベルまで到達できているんだろうな、というのが接していてよくわかります。個人的に嬉しかったのが、原口選手が『ベルリンの歴史を知りたい』と言ってきてくれたこと。語学だけでなく、自分が暮らす土地のことを理解したいと。語学は社会への見識を深めて、人生を豊かにするリベラルアーツの入口でもある。哲学に興味を持った遠藤選手に、東大でお世話になった小松美彦先生(科学史・生命倫理学)を紹介して、オンラインで座談会を開いたこともありました」
室屋についても、こんなエピソードを明かしてくれた。
「彼も最初は『今までちゃんと勉強してこなかった』『学び方そのものが分からない』と言っていたんですけど、レッスンを続けていくうちに”覚醒”して、700ページもある文法の本を1カ月で全部読んでしまいました。さすがにびっくりしましたけど(笑)。彼が独特なのは映画がすごく好きで、作品というよりも“監督の名前”で話ができるタイプだったこと。ドキュメンタリーとかミニシアター系もおさえている。そこをレッスンでも活かすことにしました」
かつて好きな俳優にナタリー・ポートマンとイーサン・ホークの名前をあげ、『パルプ・フィクション』をフェイバリット・ムービーとしていた室屋は、「作家主義的な映画の見方ができるサッカー選手」だという。そういったパーソナリティや個々の状況に応じて、ときに雑談も交えながら最適なカリキュラムを組むことができるのがサカモトの強みだ。
「海外での生活に適応するにあたって、おおまかに人種、言語、文化という3つの壁があると思っていて。このうち人種は変えられないし、お互いを尊重できていればその“壁”をあえて超える必要はない。一方で、言語の壁は努力でなんとかできる部分ですよね。そしてもうひとつ、『言葉だけできても……』というところで文化への理解が必要になってくる。僕は言葉と文化の壁をなるべく薄めて、取り払ってあげたい。純粋にサッカーで評価されたければ、競技以外のマイナスは消した方がいいですから」
そんなサカモトが新たに取り組んだミッションが、メジャーリーグのサンディエゴ・パドレスに加入した松井裕樹への“特別レッスン”だった。日本語、英語、スペイン語、韓国語の4カ国語を駆使した異例のメディア対応には、一体どんな創意工夫が隠されていたのか。現地で絶賛された入団スピーチのウラ側を掘り下げていく。
(後編に続く)
文=曹宇鉉
photograph by ProSports Images/AFLO