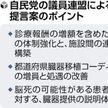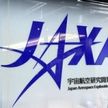パリ五輪出場をあと一歩のところで逃した女子マラソンの加世田梨花(25歳)。成田高校から名城大学、そしてダイハツへと進み、「増田明美2世」とも言われた“陸上エリート”の加世田だが、他人に嫉妬し、葛藤した過去があった。《NumberWebインタビュー全3回の2回目》
陸上を始めたのは中学生のころ。足が速いことを褒められたのがきっかけだった。
それまではバスケットをやっていたが、背が低いこともありなかなか試合では使ってもらえなかった。ただし、走ることは得意で、校内のマラソン大会で優勝したこともある。「やっぱり褒めてほしいので」という理由で、中学では陸上部に入った。
しかし、女子校で部員数も少なく、指導者も専門の知識を持ち合わせていなかった。先輩が残していったメニューに自分でアレンジを加え、練習はほぼ単独で行っていたという。
それでも県大会の1500mで決勝に残り、入賞するまでになると、こんな欲が出てきた。もっと強い学校で陸上を続けたい。仲間たちと一緒に切磋琢磨したい。高校は陸上の名門である千葉の成田高に進学。才能はそこで開花した。
「強くなりたい」加世田が決意した日
高1まではケガが多くて思うような結果を残せなかったが、2年生になると高校総体の3000mで5位入賞。アジアクロカンの日本代表に選ばれ、中東バーレーンで初の海外レースに挑んだ。さらにU20の世界選手権(ポーランド)にも出場。5000mにエントリーし、8位入賞を果たしている。
加世田はその頃から強く世界を意識するようになったと話す。
「私、高2で初めてインターハイに出て、自分でもびっくりしたんですけど決勝に進んで5位に入賞したんです。でも、促されるままインタビューエリアに行ったら、記者の方が誰も私に声をかけてくれなくて……。それがすごく悔しかったんですね。
アジアクロカンの時は、周りを見たら遠藤日向くん(学法石川高)とか、のんちゃん(田中希実・西脇工高)とか顔も名前も知っている選手ばかりで、コミュニケーションが取れたのがすごく楽しかった。私もこういう人たちと肩を並べられるようになりたいって思ったし、強くなりたいモチベーションがそこで一段上がりました」
悔しさと喜びを糧に、高校生活を陸上に捧げた。家から学校までが遠く、朝練に出るためには6時過ぎの電車に乗らなければならなかったが、3年間早起きの生活を繰り返した。
「『増田2世』は恐れ多かったですけど…」
実績が伴ってくると、やがて「増田2世」と呼ばれるようになる。ロサンゼルスオリンピックの日本代表で、現在は解説者としてお馴染みの増田明美さんは同校の先輩だ。ガッツある走りが増田さんを彷彿とさせ、走りがマラソン向きと言われることも多かった。
この頃からすでに本人も、漠然とだが将来はマラソンをやりたいと思うようになっていた。
「逆に私で良いんですかって思うくらい、『増田2世』と呼ばれることは恐れ多かったですけどね。でも、ざっくりと将来は増田さんみたいに実業団へ進んでマラソンをやるんだって。正直、頑張るのは実業団へ行ってからで、大学で燃え尽きることだけは絶対に避けようって思ってました」
高校卒業時、多くの大学や実業団から入部の誘いを受けたが、その中から土地勘のない愛知の名城大を選んだ。その理由が振るっている。
「まだ実業団でやるには自分が未熟だとわかっていたので、強い大学で駅伝を勝ちたいなって。それで当時一番強かった『立命館が気になってます』って話を松澤(誠)先生(高校の顧問)にしたんです。そしたら、『すでに日本一の大学に行ってもつまらんだろう。どうせならお前が行って強くしろ。その方が楽しいぞ』って。それで、確かに!って思ったんですね(笑)」
大学時代に“嫉妬した”2人の選手「練習が怖くなったことも」
名城大ではルーキーイヤーからトラックや駅伝で活躍。全日本大学女子駅伝では1年生ながらエース区間の5区を任され、区間記録を持つ立命大の選手を抜いて首位に順位を押し上げた。区間2位ながら、有言実行の走りでチームを12年振りの優勝に導く。
加世田が在学中に、名城大は同駅伝を4連覇。まさにチームを常勝軍団へと導いた主役の一人だった。
だが、こうした活躍のかげで、人知れず悩んだ時期もあったようだ。大学時代の挫折体験についてこう打ち明ける。
「周りからしたら順風満帆に思われていたかもしれないですけど、いま思うと意識が低かったです。とくに2年生の時に強い後輩、高松智美(ムセンビ)だったり、和田有菜が入ってきて、二人の強さに嫉妬したんですね。練習では当たり前のように最後ちぎられるし、今まで一人勝ちみたいにやっていたのが、そうじゃなくなったときにすごく動揺してしまって。負けるのが嫌だから、練習するのが怖くなったこともありました」
もしケガをしたら、この状況から逃げられるかもしれない。そんな思いでいたら、本当に足を疲労骨折してしまった。ストレスから体重も増加し、メンタルもひどく落ち込んだ。
常勝軍団のキャプテンとして
立ち直るきっかけになったのが、くしくもその休養期間だった。
「いつも二人は楽しそうに練習していて、こっちは一生懸命やっているのに勝てない。でも、外側から眺めたら、二人がちゃんと努力しているところがよく見えたんです。明るく、みんなに分け隔てなく接して、一緒に強くなろうとしているんだなって。私は自分のことだけを考えて卑屈になって、周りがよく見えていなかった。それはケガをしているときにすごく思って。なんで今、千葉から遠く離れて名古屋で寮生活をしているのか。一度初心に戻って考えるようにしたんです」
大学には結果だけを求めてきたのではない。仲間と切磋琢磨し合う環境で人間力を高め、実業団で飛躍するための土台作りをするつもりだった。
そう気づいて自分を変える努力をしたからこそ、4年時にはキャプテンを任され、コロナ禍で大変な時期にうまくチームをまとめあげることができたのだろう。《インタビュー第3回に続く》
(撮影=杉山拓也)
文=小堀隆司
photograph by L)AFLO、R)Takuya Sugiyama