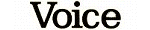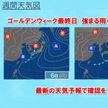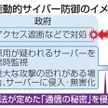中国・習近平政権の強権的な国内政策や「戦狼外交」の背景には何があるのか。中国の内政や軍事に詳しい阿南友亮氏が、「中国共産党の論理」について分析する。
※本稿は、『Voice』(2024年2月号)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
習近平の個人独裁は、共産党内のアレルギー反応の産物
日本国内では、中国の習近平政権の強権的な国内統治と「戦狼外交」と呼ばれる強硬な外交を「自信の発露」と解釈する人が少なくない。しかし、実態はまったく逆であり、柔軟性を欠いた内政と外交は、習政権の余裕のなさに起因している。
1970年代末から今日まで続く「改革・開放」路線のもとでは、中国共産党が政治と経済に対する特権的な地位を保持したまま中国に市場経済の論理を導入することが試みられてきた(「社会主義市場経済」)。
このため、経済が発展すればするほど、共産党の高級幹部を中心とする特権的既得権益集団に富が集中し、アメリカよりも深刻な貧富の格差が出現した。
中国の場合、収入・資産の格差が権力との距離によって決まる傾向が強いため、格差拡大は政権への不満に直結し、いわゆる「官民対立」の先鋭化を招いた。
その象徴的事例が1989年の天安門事件であるが、それ以降も全国各地で民衆による集団騒乱事件(デモや暴動)が頻発し、習近平が共産党の総書記に就任した2012年頃は、そうした事件が年間20万件以上発生しているような世相だった。
そうした「官民対立」の深刻化と並行する形で、政権内部の分裂も顕在化した。
習近平に総書記の座を譲った胡錦濤(こきんとう)および胡の前任者だった江沢民(こうたくみん)はいずれも、「改革・開放」路線の「総設計士」と呼ばれた鄧小平(とうしょうへい)の意向により党の総書記および国家主席に就任した。すなわち、胡錦濤までは誰が党のトップに立つかは争う余地があまりない事柄だったのである。
ところが、ポスト胡錦濤の指導体制は、鄧というカリスマ的指導者の「神託」がないなかで決めなければならなかったため、後継者争いが激化した。
この争いは、もともと胡錦濤派が推す李克強(りこっきょう)と江沢民派の庇護を受けて出世を重ねた習近平との一騎打ちと見られていたが、そこに習と同じく太子党(高級幹部の子弟グループ)に属する薄煕来(はくきらい)も参戦したため、三つ巴の様相を呈した。
後継者をめぐって党内が3つに割れたことは、共産党の空中分解を予感させるものだった。このため、共産党内では、暴走気味の薄煕来を排除し、後継者争いで優位に立った習近平を「核心」に据えて結束を強めようとする気運が高まった。
こうして約10年間(2013〜23年)、習近平のライバルだった李克強が国務院総理(党内序列三位)として習を補佐する共闘体制が続いたのだが、その間、習とその取り巻きたちは、党内の結束を重視する気運を巧妙に利用して習に多くの権限が集中する体制を整備した。
これは「改革・開放」路線で重視された集団指導体制の骨抜きと個人独裁への傾斜をもたらした。
このような習近平への権力集中を背景に、習近平派は、「改革・開放」路線のもとで慣例化した定年制(68歳定年)や任期制(1期5年で2期まで)を恣意的に運用し、李克強を引退させる一方で、68歳を過ぎた習が党の総書記と国家主席を3期目も務めるというシナリオを実現させた。
要するに、習近平の個人独裁体制は、党と社会の関係悪化ならびに党内の結束の乱れに対する共産党内のアレルギー反応、あるいは防衛本能の産物と捉えることができるのである。
このため、習の個人独裁体制は、必然的に政権に対する不満や異議申し立てに対する寛容性を失い、政権を脅かしかねない不安因子をヒステリックとも言えるほど躍起になって取り除こうとするようになった。
「反腐敗」という名目での党内不穏分子の排除、大学やマス・メディアを含む言論界に対する締めつけの大幅な強化、「反スパイ法」に依拠した密告の奨励と「疑わしき外国人」の拘束、キリスト教・イスラム教・仏教などの宗教界へのさらなる干渉、新疆ウイグル自治区のウイグル民族に対する「ジェノサイド」とも呼ばれるような容赦なき抑圧、そして、露骨な政治介入による香港における民主化の阻止ならびに言論の弾圧などがその代表例と言える。
習近平の乱暴な振る舞いで中国から遠ざかる台湾
2019年の香港騒乱を惹起した習政権による香港の立法と行政への介入は、香港に適用されていた「一国二制度」、すなわち共産党政権が中国本土とは異なる香港独自の政治・社会体制の存続を尊重するという枠組みの形骸化と実質的な終焉を意味した。
1997年に香港が中国に返還されてから50年間「一国二制度」を尊重するという中国の国際公約(1984年の中英合意)は、習政権によってあっけなく反故にされてしまったのである。
習政権は、香港に対するグリップの強化を通じて、中国国内における政権批判と自由・民主主義の最後の砦を弱体化させることに成功した。しかし、それは台湾を中国から一段と遠ざけるという副作用の引き金となった。
中華人民共和国の建国当初からの国家目標とされてきた「台湾の解放」(台湾平定)を実現するために、共産党政権は武力行使も辞さないという姿勢を堅持する一方で、台湾問題の平和的解決の選択肢も提示してきた。
それは、香港に適用されてきた「一国二制度」を台湾にも適用する形で中台の統合を果たすという選択肢だった。
しかし、「一国二制度」に守られていたはずの香港の自由な社会空間を習政権が極めて乱暴な形で再起不能なまでに蹂躙したため、台湾社会の約90%が「一国二制度」による中台統一に反対するようになった。香港の悲劇は、習政権が民主主義とは根本的に相容れない存在であることを台湾社会にあらためて広く実感させた。
また、この時期露呈した新型コロナ・ウイルス問題をめぐる習政権の隠蔽体質も中国への不信感と違和感を助長した。
こうした中国に対するイメージの悪化は、「中国には過度に接近・依存せず、距離を置いて付き合う」という方針を2016年以来掲げていた民進党の蔡英文政権の再評価につながり、2020年1月の総統選挙における蔡英文の再選に寄与した。
習政権は、もともと台湾に経済的恩恵を与えながら浸透工作を推進し、蔡英文を総統の座から追い落とそうとしていた。ところが、そうした努力も空しく、蔡英文の続投が決まると、習政権は方針を一変させ、台湾周辺における解放軍の活動の活発化による軍事的威圧を通じて、台湾の政局に影響を及ぼそうとする姿勢を強めた。
こうして2020年以降、台湾は慢性的な軍事的緊張状態のもとに置かれることとなったのである。